「人間ってのはね、じぶんの知らなかったことを知る、わからなかったことがわかる、そういうときに喜びば感じるようにできているとよ」
荻平地区歴史民俗博物館の“センセイ”の言葉。
小学6年の夏休みに東京から九州の山奥にやってきた少年が見つけた、隠された海賊船の秘密とは?
『銀河乞食軍団黎明篇』や『でたまか』の鷹見一幸初のジュブナイル小説です。いや、油断ならないぞ。
話としてはオーソドックスなジュブナイル小説。子供が元気なのはもちろん、登場する大人も一見怪しげにみえても根っこのところは良識ある社会人なので、安心して子供たちの冒険を追いかけられます。結果的に命令無視の独断専行がベターな選択だったとしても、最初から無謀ありきな話ではがっかりしてしまいますから。
【飛べ!ぼくらの海賊船】【鷹見一幸】【岸和田ロビン】【そなえよつねに】【来島十傑衆】【村上水軍】【安宅船】【ワンピース】
荻平地区歴史民俗博物館の“センセイ”の言葉。
小学6年の夏休みに東京から九州の山奥にやってきた少年が見つけた、隠された海賊船の秘密とは?
『銀河乞食軍団黎明篇』や『でたまか』の鷹見一幸初のジュブナイル小説です。いや、油断ならないぞ。
話としてはオーソドックスなジュブナイル小説。子供が元気なのはもちろん、登場する大人も一見怪しげにみえても根っこのところは良識ある社会人なので、安心して子供たちの冒険を追いかけられます。結果的に命令無視の独断専行がベターな選択だったとしても、最初から無謀ありきな話ではがっかりしてしまいますから。
【飛べ!ぼくらの海賊船】【鷹見一幸】【岸和田ロビン】【そなえよつねに】【来島十傑衆】【村上水軍】【安宅船】【ワンピース】
















 「人類の歴史はそもそも最初から、実践的な知能と哲学的な知能の二つながらを示す例で満ちている。僕たちが昔の人たちより優れていると考えていつも怪しまないのは、おそらく僕らの最大の誤りなのだ」
「人類の歴史はそもそも最初から、実践的な知能と哲学的な知能の二つながらを示す例で満ちている。僕たちが昔の人たちより優れていると考えていつも怪しまないのは、おそらく僕らの最大の誤りなのだ」




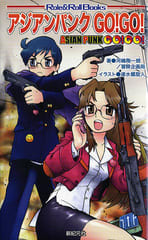
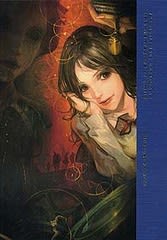

 結局、下巻分は500円の中古で最初の新潮社版ハードカバー1巻本を買ってしまいました。著者に印税が入らないから新刊で手に入るものは出来る限り新刊で買ってますが、今月はそろそろ金穴。上巻は新刊で買ったということで勘弁してください。(20/07/24)
結局、下巻分は500円の中古で最初の新潮社版ハードカバー1巻本を買ってしまいました。著者に印税が入らないから新刊で手に入るものは出来る限り新刊で買ってますが、今月はそろそろ金穴。上巻は新刊で買ったということで勘弁してください。(20/07/24)



