2019/03/06(水)京都市東山区の東福寺を散策する。
今回は、歴史を散策するグループ8名と東福寺と京の冬の旅(文化財特別公開)光明宝殿(東福寺)で30年ぶりの公開と境内を散策の目的とした。
✿大本山東福寺(臨済宗東福寺派)
創建は鎌倉時代で、ときの摂政関白の藤原道家(九條道家)が東大寺と興福寺から「東」よ「福」の二字をとり、九條家の菩提寺として造営したと云う。
開山は円爾弁円(えんにべんねん)で天皇より初めて国師号(聖一国師)を贈られた禅僧である。
三門、本堂(仏殿兼法堂)、方丈と庫裡、開山堂などからなる伽藍を中心に周辺には25の塔頭寺院がある。境内の中心には洗玉澗(せんぎょくかん)という渓谷があり、上流から偃月橋、通天橋、臥雲橋という3橋(東福寺三名橋)が架かる。通天橋から眺める新緑と紅葉は絶景の名所であると伝え、今回は空想の絶景を感じた。
〇三門(国宝)
応永年間(1394-1428)の造営と云われ、楼上には足利義持の筆による扁額「玅雲閣」が掲げている、大きさは約畳三枚と云われ、上層階に釈迦如来と十六羅漢を安置(非公開)する。現存する禅寺の三門としては日本最古のものであると伝える。


三門(手前は恩遠池) 扁額「玅雲閣」
〇本堂(仏殿兼法堂)
明治14年(1881)に仏殿と法堂が焼けた後、昭和9年(1934)に完成した。高さ25.5m、間口41.4mの大規模な建物で、昭和期の木造建築としては最大級のものである。天井の画龍は堂本印象の力作である。また、ここには像高が約7mある本尊釈迦仏像が祀られていた。火災の際に奇跡的に燃え残った大仏の左手(約2m)が祀られていると云うが今回は観る事ができなかった。


本堂 扁額 天井の龍
〇庫裡
切妻を正面とする禅宗式寺院の典型的な建物である。
庫裡
〇方丈
明治23年(1890)の再建。正面前庭にある方丈唐門は明治42年(1909)に造営され、昭憲皇太后(明治天皇皇后)の恩賜建築である。
方丈を囲んで四方に配される庭は「八相の庭」と命名されている。庭園は昭和の名作庭家、重森三玲(しげもりみれい)によって昭和14年(1939)に作庭され、鎌倉時代庭園の風格を基調に現代芸術の構成美を取り入れた枯山水の「万丈八相庭園」である。
・南庭(八海) 荒海の砂紋の中に四仙島(蓬莱、方丈、瀛洲、壺梁)の表現した巨石を配し、渦巻く砂紋で八海を表し、芝で五山を表現されていた。また、正面には唐破風の唐門は恩賜門とも呼ばれる。
・西庭(井田市松) さつきの刈込みと砂地とをかずら石で方形に組んで大きく市松模様に表現し、井田市松を表現している。
・北庭(小市松) 苔と恩賜門内にあった敷石を利用し、市松模様に配している。
・東庭(北斗七星) 雲文様地割に東司の柱石の余石を利用して北斗七星を表現しいる。

方丈入口 恩賜門



方丈(庭の中央「恩賜門」) 
西庭(井田市松)

北庭(小市松)
東庭(北斗七星)
〇開山堂・常楽庵(重文)
開山の円爾弁円(えんにべんねん)像を祀る。上層の「伝衣閣」(でんねかく)にある「三国伝来の布袋」像は伏見人形の元祖と云われる。

開山堂
〇東司(とうす)(重文)
室町時代前期で唯一の日本最大最古の禅宗式東司(便所)の遺構である、通称は用を足す百雪隠(ひゃくせっちん)とも呼ばれる。内部は中央通路をはさんで左右両側に円筒の壺を埋める形です。


東司 内部
〇浴室(重文)
長禄3年(1459)に建てた京都最古の浴室建築の遺構と云う。
浴室
〇禅堂(重文)
貞和3年(1347)に再建された、中世期より唯一現存するわが国最大最古の坐禅道場である。
禅堂
〇龍吟庵

龍吟庵(閉門中)
〇月下(華)門(重文)
月下門
〇日下門


日下門
〇偃月橋(えんげつきょう)(重文)


偃月橋
〇通天橋
仏殿から開山堂(常楽庵)に至る渓谷・洗玉澗に架けられた橋廊で中央に切妻造の張り出しがある。



通天橋
〇光明宝殿(特別公開)
塔頭寺院の文化財を収蔵する文化財収蔵施設で通年は非公開である。
拝観当日は第53回「京の冬の旅」の非公開文化財特別公開期間中で30年ぶりの公開の日で拝観できました。
狩野派の絵師・渡辺了慶(わたなべりょうけい)筆と伝わる「柳松遊禽(ゆうきん)図」「桜梅遊禽図」「籬(まがき)秋草図」(いずれも重文)など、円山応挙、久保田米僊(べいせん)の画が展示される。また、かつて三門(国宝)に安置されていた像高約3.4mの巨大「二天王立像」(重文)、万寿寺の伝運慶作の金剛力士立像(重文)、丈六阿弥陀如来坐像(重文)など、東福寺に伝わる仏像の数々も特別公開された。
〇愛染堂(重文)
南北朝時代の建築で、昭和12年(1937)万寿寺より移し、愛染明王を祀った。
愛染堂
〇経蔵
経蔵
〇六波羅門(重文)
六波羅門
〇勅使門
勅使門
〇龍雲橋


龍雲橋 龍雲橋から観る切妻造の張り出し
以上
2019/02/26岐阜県東濃地方にある小里城跡、明智城(長山城)跡をめぐる。
✿✿小里(おり)城跡(岐阜県史跡)✿✿
岐阜県瑞浪市の城山の山頂(標高約405m)に有り、城下から約150m登った地点にある。その築城時期については、天文3年(1534)に小里光忠によって築城され、以後小里氏の居城となったと伝える。また天正8年(1511)生まれの光忠が22歳の時に居住を小里に定めた記載が「小里家普」にあることから、天文元年(1532)とも考えられる。
戦国時代の天正2年(1574)には織田信長が改修を命じ池田恒興を置いて対武田戦の最前線として重要な役割を担った。小里氏は一時期小里城を撤去するものの、慶長5年(1600)の関ヶ原合戦後、再び小里城を居城とした。<パンフレットより>


県道33号沿いの石標 県道20号の登口

小里城跡全体図

大手門跡手前の石垣

大手門跡手前の堀切リ

大手門跡




御殿場跡
大手道

岩


急な登り道の石組み

曲輪跡

本丸前の休憩場 城下を眺める
案内板














本丸の天守台の周囲石垣(東南西北)


天守台入口


天守台の内部
✿✿可児明智(長山)城跡✿✿
美濃の守護、土岐頼清の次男である頼兼が、康永元年(1342)頃に築城と伝える。
諸説ある中、二つの明智城がこの近くに存在する、恵那明智城は宝治元年(1247)に築城とか。


明智址跡案内板 大手門跡
大手口 

桔梗坂(入口) 桔梗坂(城近く)

明智城址碑

本丸跡

馬坊柵 馬場跡

二の丸跡


七ツ塚
本丸跡から眺める
✿✿明智氏歴代之墓所✿✿
大手口跡の近くにある青雲山天龍寺の敷地内で鐘楼近くに墓所はある。

天龍寺参道 山門と本堂
明智家の案内板

明智氏歴代之墓所 標柱の後方にある宝篋院塔は明徳時代(1390)頃と云う。
✿太元神社(だいげんじんじゃ)
祭神は国常立尊と応神天皇


鳥居 拝殿
✿✿八坂入彦命の墓(宮内庁管理)✿✿
八坂入彦命は崇神天皇皇子と云う。宮内庁の看板に「崇神天皇皇子 八坂入彦命」と記載がある。
第12代景行天皇(日本武尊の父)は泳宮(可児市久々利)に長期に滞在し、八坂入彦命の女、八坂入媛命と結婚しその子は第13代成武天皇となる。
(場所は可児市の県道84号とMAGロードの立体交差近く)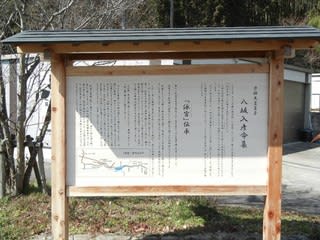

案内板 宮内庁の注意案内

◎後日、可児明智(長山)城跡の六親眷属幽魂塔と産湯の井戸に行って来ました。
✿六親眷属幽魂塔(ろくしんけんぞくゆうこんとう)
昭和48年(1973)明智城址発掘調査で六親眷属幽魂塔が発掘された。発掘の折り地中から人骨や武具が発見されたが戦いの時代とは断言できない。

標柱 案内板

自然石の表に「六親・・・」の刻印がある。 祠の破風部分にある明智家の家紋「桔梗」
幽魂塔に向う山道脇にある古い弥勒菩薩で文化財級と云う。
✿明智光秀公の産湯の井戸
田んぼの中央部分に井戸が有ったと云う。井戸は耕地整理で無くなったがこの付近で古い土器が出土されたと伝える。
井戸が有った田んぼ
✿明智光秀公の位牌
日本一高い184cmで「長在寺殿明窓智禅定門」と戒名が記されている。

天龍寺の山門 明智光秀公の位牌
以上















