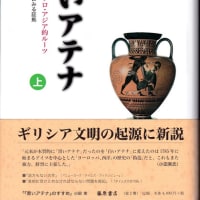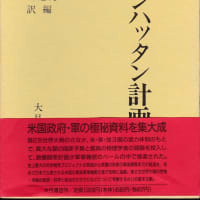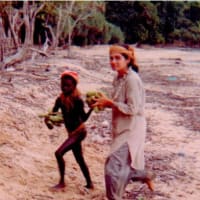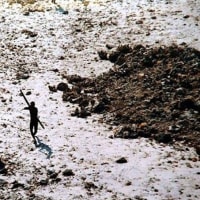▲ 竹内芳郎 著作 講演・論文掲載の雑誌、著作、共著の岩波講座など
竹内芳郎さん 追悼
竹内芳郎さん追悼
2016年11月21日 に竹内さんの訃報記事が朝日のインターネットに載っていた。11月19日に亡くなっていたのだが、長い業績紹介もなく、淋しい記事だった。どうしてなのだろうと思った。60年代末の大学闘争時代には、学生支援のエールを送り、大学を退官した後は、各種の講演や、私塾を開いていたそうなのだが、それにしても、メディアが竹内芳郎に冷たかったのはなぜなのだろうか。
ひょっとしたことから、高校時代の時に偶然求めた文芸雑誌の中で、鶴見俊輔・高橋和巳・いいだもも らとの座談会が載っていたことが、竹内芳郎を知り、読み出すきっかけとなった。座談会のテーマは、「暴力考」
1968年 『文芸』 8月号に掲載されていたのだが、 この年ベトナム戦争の泥沼が続き、和平交渉も不調に終わり、マーチン・ルーサー・キング牧師、ロバート・ケネディが暗殺された頃の状況を受けての対談だった。この座談を読んだ時代状況とともに記憶が強烈で、未だに反復して読むことがあった。
1969年5月の『展望』 には竹内芳郎が、北沢方邦の「管理社会と革命」、松田道雄の「永久暴力の論理」などとならんで、「大学闘争をどう受け止めるか」を書き、1969年の日本現代史の一断面を記録する雑誌となっていた。
私が読み始めていたころは、フランス現代哲学専門の哲学者というイメージがあった。サルトルや、メルロ・ポンティの訳書にはお世話になったという記憶がある。
我が家にある竹内芳郎の著作は、1981年に出版した『文化の理論のために』 岩波書店 を最後に見あたらない。講座ものでは、『新岩波講座哲学』12 「文化のダイナミックス」 1986年 に収載した、「文化の変革」が最後のようだ。
その後の竹内芳郎の著作や論文を読んでいないのは、哲学周辺の動きがより精緻化して、専門業者のような職人芸というか、哲学の細分化が進んだのか、たまに読む日曜哲学では追いつけないほど変容を遂げているからなのだった。
その頃、竹内芳郎は、学問・メディアの中の哲学者であることを止め、「討議の哲学者」に変貌していたらしい。

▲竹内芳郎 『文化の理論のために』 1981年 岩波書店
▼ 目次

▲▼ 『文化の理論のために』 目次

▲『文化の理論のために』 目次
11月19日の死とはいえ、後期の竹内芳郎の著作、晩年の著作を読み解かないことには、追悼のしようもない。
以下、竹内芳郎が、通常の哲学者であることを止め、討論熟での活動を始めてから、竹内芳郎に出会うチャンスも、記憶もない人が多くなる中、私自身への叱咤激励とも受け止め、竹内芳郎の著作歴を記す。
竹内芳郎 たけうち・よしろう
以下の 著書目録は、岩波書店刊の『文化の理論のために』1981年のカバー裏の著者案内、三元社のホームページ 、閏月社のホームページ wikiを参照して作成。記して感謝します。
1924年岐阜県生まれ。 1943年東京大学法学部入学、1952年同文学部卒業。哲学者。討論塾主宰。
著書
『サルトル哲学序説』(河出書房、1956、盛田書店、1966、筑摩書房、1972)、
『実存的自由の冒険』(現代思潮社、1963、季節社、1975)、
『サルトルとマルクス主義』(紀伊國屋書店、1965)、
『イデオロギーの復興』(筑摩書房、1967)『文化と革命』(盛田書店、1969、第三文明社、1979)、『国家の原理と反戦の論理』(現代評論社、1969)、
『言語・その解体と創造』(筑摩書房、1972、増補版1985)、
『国家と民主主義』(現代評論社、1975)、『国家と文明』(岩波書店、1975)、
『課題としての〈文化革命〉』(筑摩書房、1976)、
『現代革命と直接民主制』(第三文明社、1976)、
『マルクス主義の運命』(第三文明社、1980)、
『文化の理論のために』(岩波書店、1981)、
『具体的経験の哲学』(岩波書店、1986)、
『意味への渇き』(筑摩書房、1988)、
『ポスト=モダンと天皇教の現在』(筑摩書房、1989)。
『天皇教的精神風土との対決』(三元社、1999)
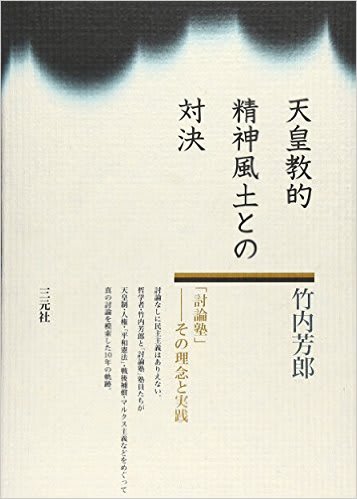
▲『天皇教的精神風土との対決』 1999年 三元社
編著
『サルトルの全体像』(ぺりかん社、1966、新泉社、1969)、
『高度資本主義国の革命』(筑摩書房、1972)、
『文化と革命』(筑摩書房、1974) 。
『討論 野望と実践』編著 閏月社 2013
訳書
ベルグソン『夢について』『時間と自由』(河出書房、1954、1955)、
サルトル『哲学論文集』『弁証法的理性批判1』(人文書院、1957、1962)、
メルロー=ポンティ『知覚の現象学』1・2、
『シーニュ』1・2(みすず書房、1967、1974、1969、1970)。
最近編著
『天皇教的精神風土との対決 「討論塾」―その理念と実践』 閏月社 2013年
討論なしに民主主義はありえない。哲学者・竹内芳郎と「討論塾」塾員たちが天皇制・人権・「平和憲法」・戦後補償・マルクス主義などをめぐって真の討論を模索した 年の軌跡。
定価=本体 3,800円+税
1999年7月22日/A5判並製/472頁/ISBN978-4-88303-059-0
[目次]
はしがき
I 理念とその実践 013
A 討論塾開設に向けて 014
B 討論塾・塾則 020
C 塾報からの断章 027
II 挫折とその教訓 085
A 第一次事務局を担ったXA氏らの場合 087
B 第二次事務局を担ったXG氏の場合 106
C 第四次事務局を担ったYB氏の場合 138
III 主題とその深化 145
A 天皇制(教)論 146
B 「平和憲法」再考 184
C マルクス主義論 239
D 「戦後補償」論 276
E 人権論 303
IV 時代認識 395
A 現代民主主義をめぐって 397
B 沖縄問題について 424
C 比較文明論から見た現代文明の課題 427
D オウム教団・賢治boom・司馬boom 449
E 「自由主義史観」なるものについて 456
討論塾年譜 465

▲竹内芳郎 『ポストモダンと天皇教の現在』 1989 筑摩書房
この『ポストモダンと天皇教の現在』 が出版された1989年以降、竹内芳郎は、メディア批判の鋭さを増し、それとともに、メディア界・出版界の天皇制(教)的精神風土から、竹内芳郎排除の憂き目に会っていくようだ。
つづく