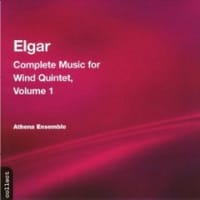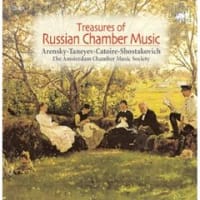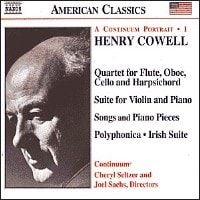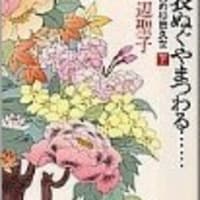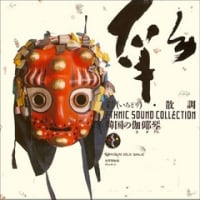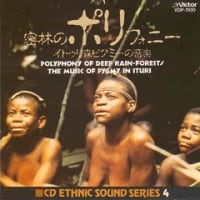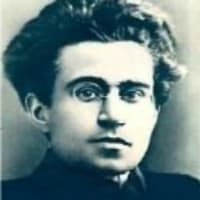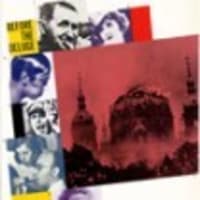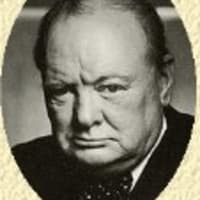官僚も(一例、前防衛省事務次官)、企業も(一例、赤福)、そして個人も(例は多数)、倫理観がどこかおかしくなっている、と指摘する人が多いようです。
中には、戦後社会の動き自体にその原因を求める向きもあり(GHQの陰謀論あり、日教組原因説あり?!)、こういった人は往々にして「教育勅語」の復権や、道徳教育の復活を求めたりするのね。
しかし、戦後社会総体に原因ありとしても(小生、そうは思わないけれど)、
次のような考え方もあるんです。
けれども、責任のあり方が変容した契機となったのは、むしろ明治維新だったんじゃないかしら(その点で、小生は、福沢諭吉の『痩我慢の説』とも問題意識を共有する)。
そもそも、明治維新時に、幕臣で敗戦責任なり失政責任なりを取った人は幾許ありや、ということになりますが、明らかに責任を取った「高級官僚」は、江戸城開城の報を聞いて自死した、川路聖謨(かわじ・としあきら、1801 - 68) くらいなものじゃあないか。
こうして見ると、明治維新時、アジア・太平洋戦争敗戦時とも、大多数の人びとは責任を取らずに、「今日は〈勤王〉、明日は〈佐幕〉」、とコロコロとあり様を変えていったようです。
その一例として、前に引用した『東京セブンローズ』の一節を、再度引いておきましょうか。
ごく悲観的に言えば、そのような存在が、われわれ「日本人」なのかもしれません。
中には、戦後社会の動き自体にその原因を求める向きもあり(GHQの陰謀論あり、日教組原因説あり?!)、こういった人は往々にして「教育勅語」の復権や、道徳教育の復活を求めたりするのね。
しかし、戦後社会総体に原因ありとしても(小生、そうは思わないけれど)、
次のような考え方もあるんです。
「かの戦争が敗戦におわったとき、明らかに責任をとるべき者が曖昧に身を処して生き残った。そのけっかが、一億総無責任時代の頽廃を現出している。」(八尋舜右「人間の責任のあり方」)
けれども、責任のあり方が変容した契機となったのは、むしろ明治維新だったんじゃないかしら(その点で、小生は、福沢諭吉の『痩我慢の説』とも問題意識を共有する)。
そもそも、明治維新時に、幕臣で敗戦責任なり失政責任なりを取った人は幾許ありや、ということになりますが、明らかに責任を取った「高級官僚」は、江戸城開城の報を聞いて自死した、川路聖謨(かわじ・としあきら、1801 - 68) くらいなものじゃあないか。
「三月十四日、江戸城もきょうで官軍に引渡しとなった――と根岸御行の松の彼の屋敷に、人が知らせてくれた翌十五日朝。一度厠へ入り、出てくると居間に坐り、『白湯を持て』と妻の佐登子に命じた。
彼女が何気なく、台所へ白湯をとりに行っていると、突然、短銃の音がしたので、おどろいて引返してみると、半身付随の体で端坐し、わずかに動かし得る右手を使って引き金をひき、咽喉を射抜いて、すでに絶命していた。やがて納棺のため湯灌をすることになって、衣類をぬがせると、真新しい木綿で幾重にも腹を巻いてあるのを発見した。
これを解くと、浅く一文字に切ってあった。かたわらに短刀を置いてあった。厠の中で切ったものである。
この短刀は、かつて勘定組頭格として、仙石騒動を裁断したとき、自分をその地位にまで抜擢してくれた恩人、脇坂中務大輔からもらったものだったいう。
(中略)
『官軍箱根よりかなた、いづ方まで参候と申すことさえ区々の咄なり。しかるに老拙、精神はかわらず、されども腰いよいよ立たず、一寸も動かされず、よりて何の御用も出来ず……。
述懐 生替り死かはりて幾度も身を致さなむ君の御為に
二荒山神もあはれとみそなはせ
露の此身のつくす真こころ
おもひ決して、三月十一日記之。日記を合わせみれば、わが側にあると同じかるべし』」
(徳永真一郎『幕末閣僚伝』「川路聖謨」)
こうして見ると、明治維新時、アジア・太平洋戦争敗戦時とも、大多数の人びとは責任を取らずに、「今日は〈勤王〉、明日は〈佐幕〉」、とコロコロとあり様を変えていったようです。
その一例として、前に引用した『東京セブンローズ』の一節を、再度引いておきましょうか。
「つい、この間まで神と崇め奉っていた超絶的な存在を、そう簡単に下がかった冗談の種にしていいのだろうか。そうしていいのは、あの時代にも、天皇は神ではないと主張していた者だけではないのか。天皇を現人神(あらひとがみ)と思い、他人(ひと)にもそう思えと強制してきた者が、どんな動機があったにせよ、そば屋で天丼でも誂えるかのようにあっさりと簡単に、天皇かマッカーサーに宗旨を変えて、その上、かつての神を笑いを誘うための小道具にしてしまっていいのだろうか。ひょっとすると日本人は何も本気で信じていないのではないか。そのときそのときの強者に尻尾を振ってすり寄って行くおべっか使いに過ぎないのではないか。」
ごく悲観的に言えば、そのような存在が、われわれ「日本人」なのかもしれません。