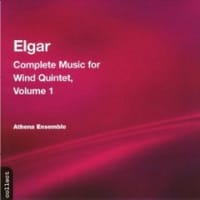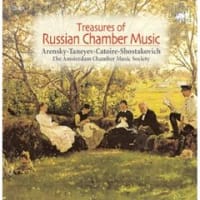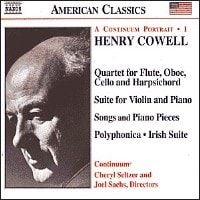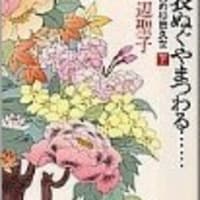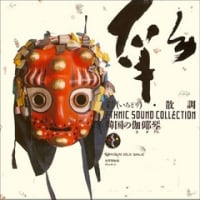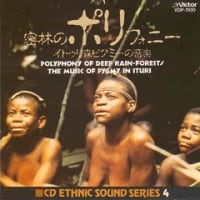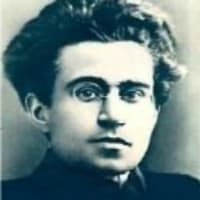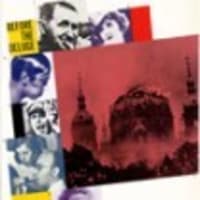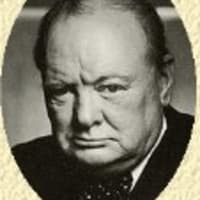伽耶琴(カヤグム)という楽器があります。
韓国の伝統楽器で、その名のとおり、朝鮮半島の最南端「伽耶」の国(現在の慶尚南道金海周辺にあり、532年に新羅に降伏し滅んでいる)に起源を持つ撥弦楽器です。
形は、日本で普通に見られる「箏(そう/こと)」と同じようなのですが、12弦であること(「箏」は13弦)や、膝の上に載せて弾く、などの違いがあります。
「音」という面では、この解説書にもあるように、「弄弦」という演奏技法による装飾音(初めて聴くと、ヴィブラートが不思議な効果を上げていることに気付く)が、大きな特徴です。
「筝」や「琴」系統の楽器の通例なのですが、音量では、西欧の楽器(ヴァイオリンやハープなど)に比べると、けっして大きいとは言えません。
また音階も、日本での「都節(みやこぶし)」と同じような短調系統ですので、はかなさを感じることもあるかもしれない。
けれども、打楽器とともに演奏されると、そこには特有のリズムが出てきて、
このような特徴を持った伽耶琴の音色を、「伽耶」が亡国の憂き目に会ったことから、「滅亡の美」として捉える人がいるようです(隆慶一郎『一夢庵風流記』の記述など)。
しかし、これは、民藝運動の創始者・柳宗悦(やなぎ・そうえつ/むねよし、1889 - 1961)が、朝鮮民族の美を「悲哀の美」と捉え、彼らの白色好きを「色を楽しむ心の余裕を失ったから」であると論じているのと同じような、偏見に過ぎないでしょう。
――柳を全否定しているのではない。1919年の「三一独立運動」の際に「朝鮮人を想う」という文章を書き、日本による植民地支配を正当化する人びとに対し、
それだからこそ、美術における「偏見」を惜しむ。
虚心坦懐に、伽耶琴による音楽を聴いてみると、前に引用した文章のように、むしろ「ダイナミックな」「極めて自由な響き」があることに気付くことでしょう。
どうも、異文化の音楽(固有美術の場合も同様)は聴き慣れないために、既にある知識による先入観で捉えがちです(あるいは、拒否感が先に立っての「食わず嫌い」)。
そのような点に注意なさって、伽耶琴の演奏を、ぜひ一度お聴きください。
彩(いろどり)・散調
ETHNIC SOUND COLLECTION
韓国の伽耶琴
(SEVEN SEAS/KING K30Y 5123)
韓国の伝統楽器で、その名のとおり、朝鮮半島の最南端「伽耶」の国(現在の慶尚南道金海周辺にあり、532年に新羅に降伏し滅んでいる)に起源を持つ撥弦楽器です。
形は、日本で普通に見られる「箏(そう/こと)」と同じようなのですが、12弦であること(「箏」は13弦)や、膝の上に載せて弾く、などの違いがあります。
「楽器の構え方も日本の箏は、楽器を体の前に置き、右手の親指、人差し指、中指に義爪をはめて弾くが、伽耶琴は、胡座(あぐら)をかくような形で床の上に座り、膝の上に楽器の頭部をのせ、素手の指で弾く。左手は、弾いた弦の響きに陰影を与え、弄弦(ノンヒャン)と呼ぶ種々の装飾音を醸し出す。そのため、まず音色演奏技法の幅も日本の箏とは違った広がりを作り、ある時は柔らかく、ある時はダイナミックに、そしてある時は揺れ動き、極めて自由な響きを展開している。」(草野妙子「CD解説書」より)
「音」という面では、この解説書にもあるように、「弄弦」という演奏技法による装飾音(初めて聴くと、ヴィブラートが不思議な効果を上げていることに気付く)が、大きな特徴です。
「筝」や「琴」系統の楽器の通例なのですが、音量では、西欧の楽器(ヴァイオリンやハープなど)に比べると、けっして大きいとは言えません。
また音階も、日本での「都節(みやこぶし)」と同じような短調系統ですので、はかなさを感じることもあるかもしれない。
けれども、打楽器とともに演奏されると、そこには特有のリズムが出てきて、
「ある時は柔らかく、ある時はダイナミックに、そしてある時は揺れ動き、極めて自由な響き」を感じ取ることができます。
このような特徴を持った伽耶琴の音色を、「伽耶」が亡国の憂き目に会ったことから、「滅亡の美」として捉える人がいるようです(隆慶一郎『一夢庵風流記』の記述など)。
しかし、これは、民藝運動の創始者・柳宗悦(やなぎ・そうえつ/むねよし、1889 - 1961)が、朝鮮民族の美を「悲哀の美」と捉え、彼らの白色好きを「色を楽しむ心の余裕を失ったから」であると論じているのと同じような、偏見に過ぎないでしょう。
――柳を全否定しているのではない。1919年の「三一独立運動」の際に「朝鮮人を想う」という文章を書き、日本による植民地支配を正当化する人びとに対し、
「ほとんどなんらの賢さも深みもなく、また温かみもないのを知って、余は朝鮮人のためにしばしば涙ぐんだ」
「我々日本人が今朝鮮人の立場にいると仮定してみたい。おそらく義憤好きな我々日本人こそ最も多く暴動を企てる仲間であろう」と、彼が書いたことを忘れてはならないだろう。
それだからこそ、美術における「偏見」を惜しむ。
虚心坦懐に、伽耶琴による音楽を聴いてみると、前に引用した文章のように、むしろ「ダイナミックな」「極めて自由な響き」があることに気付くことでしょう。
どうも、異文化の音楽(固有美術の場合も同様)は聴き慣れないために、既にある知識による先入観で捉えがちです(あるいは、拒否感が先に立っての「食わず嫌い」)。
そのような点に注意なさって、伽耶琴の演奏を、ぜひ一度お聴きください。
彩(いろどり)・散調
ETHNIC SOUND COLLECTION
韓国の伽耶琴
(SEVEN SEAS/KING K30Y 5123)