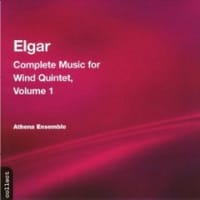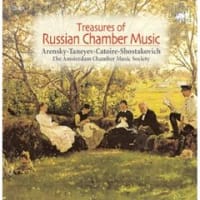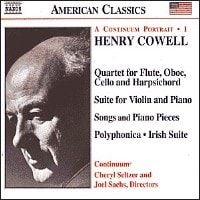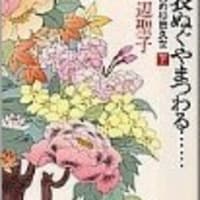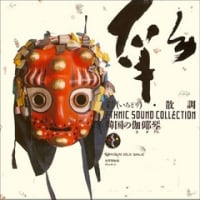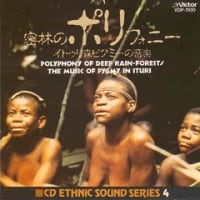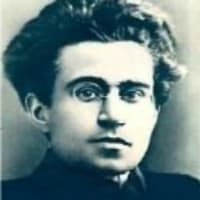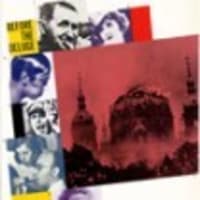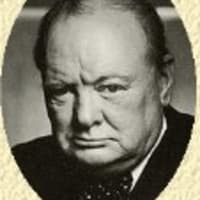梅雨明け宣言も出されていないというのに、もう本格的な夏が来てしまったような暑さです。
こう蒸し暑いと、皮膚がじめついて、どんな音楽を聴いてもさっぱりしない状態。
それならば、いっそのことということで耳にしたのが、
『密林のポリフォニー』(ビクター)
という、アフリカの熱帯雨林に暮らすピグミーの音楽。
19世紀的な意識からすれば、〈野蛮→未開→文明〉とヨーロッパをモデルとして、人類の文化は、一直線の進化を遂げるということになるでしょう。
そのような考え方で言えば、ピグミーの音楽は「未開」そのものと捉えられてしまう。
けれども、現代音楽におけるさまざまな試みを知っている20~21世紀的な「耳」からすると、実に新鮮に聴くことができ、その音楽秩序も、ヨーロッパ的なモデルと違っているだけで、かなり高い達成度を示している。
そのことは、別のアルバム『アフリカン・リズム』を聴けば、よく分かるでしょう。
このCDは、中央アフリカに住むピグミー、アカ族の合唱と、ジョルジ・リゲティ(1923 - )とスティーヴン・ライヒ(1936 - )の作品とを、ほぼ交互に収録したアルバムなのですが、ピグミーの『ボッソベ』という合唱と、ライヒの『クラッピング・ミュージック』という手拍子によるミニマル音楽
とを比較すると、
しかし、幸いにも、「音」を聴く手段に恵まれている今日では、現代に生きる音楽として、世界各地また各時代の音楽をも、横並びにして比較することも可能です。
そうした場合、「耳」は保守的だとは、必ずしもいえないのではないでしょうか。
この辺り、小生のようなクラシカル系の音楽を好んで聴く人間だけではなく、ロックやポップス、ジャズなどを良く聴く方は、どのようにお感じなのでしょうか。
こう蒸し暑いと、皮膚がじめついて、どんな音楽を聴いてもさっぱりしない状態。
それならば、いっそのことということで耳にしたのが、
『密林のポリフォニー』(ビクター)
という、アフリカの熱帯雨林に暮らすピグミーの音楽。
19世紀的な意識からすれば、〈野蛮→未開→文明〉とヨーロッパをモデルとして、人類の文化は、一直線の進化を遂げるということになるでしょう。
そのような考え方で言えば、ピグミーの音楽は「未開」そのものと捉えられてしまう。
けれども、現代音楽におけるさまざまな試みを知っている20~21世紀的な「耳」からすると、実に新鮮に聴くことができ、その音楽秩序も、ヨーロッパ的なモデルと違っているだけで、かなり高い達成度を示している。
そのことは、別のアルバム『アフリカン・リズム』を聴けば、よく分かるでしょう。
このCDは、中央アフリカに住むピグミー、アカ族の合唱と、ジョルジ・リゲティ(1923 - )とスティーヴン・ライヒ(1936 - )の作品とを、ほぼ交互に収録したアルバムなのですが、ピグミーの『ボッソベ』という合唱と、ライヒの『クラッピング・ミュージック』という手拍子によるミニマル音楽
とを比較すると、
「むしろ、アカ族の音楽の方が高度な達成を遂げていると感じられ」さえする。
「音は、見ることよりもはるかに文化的保守性が強い。好悪がはっきりと現われるのだ。」(内藤高『明治の音』)といわれます。
しかし、幸いにも、「音」を聴く手段に恵まれている今日では、現代に生きる音楽として、世界各地また各時代の音楽をも、横並びにして比較することも可能です。
そうした場合、「耳」は保守的だとは、必ずしもいえないのではないでしょうか。
この辺り、小生のようなクラシカル系の音楽を好んで聴く人間だけではなく、ロックやポップス、ジャズなどを良く聴く方は、どのようにお感じなのでしょうか。