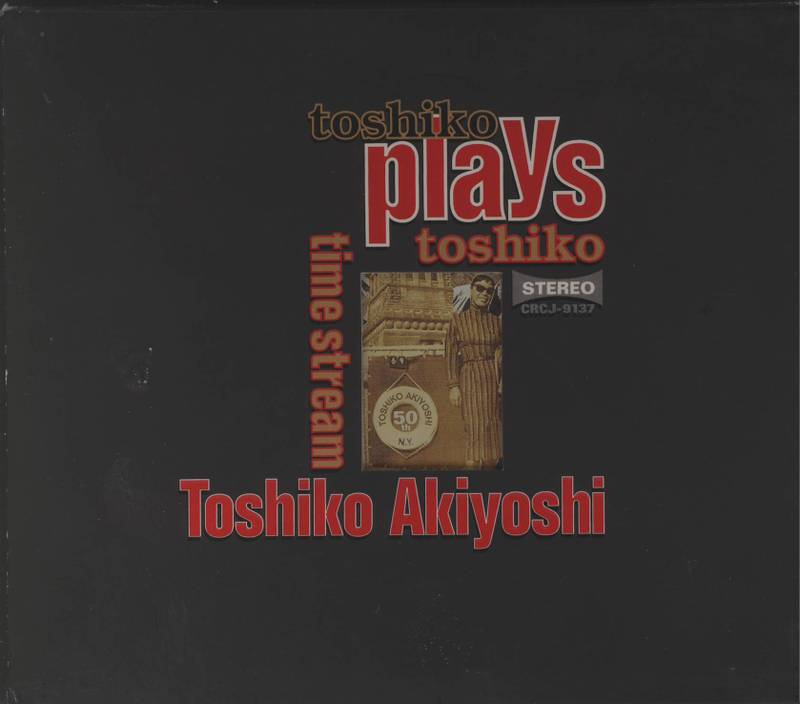●今日の一枚 114●
Bruce Springsteen The River

若い頃、ブルース・スプリングスティーンを聴いてこなかった。ロック好きだった私にしては、今思えば不思議なことだ。1970年代後半から80年代初頭、ラジオからは毎日のようにスプリングスティーンが流れていた。もしかしたら、リアルタイムで彼の音楽にのめり込んだのかもしれないが、意識的に聴いてこなかったのだ。
今思えば、原因はつまらないことだった。山川健一の「八月のトライアングル」(『壜の中のメッセージ』角川文庫所収)という作品に出てくる次の文章によってである。
ボブ・ディランはカントリーを歩いている、だけどスプリングスティーンは都会の底を走っている……
ボブ・ディランが好きだった私は、その言葉に反発と嫉妬ををおぼえたのだった。ボブ・ディランを軽く見やがって・・・。新参者のスプリングスティーンなど簡単に受け入れてたまるか、といった感じだ。
また、大ヒットした「ボーン・イン・ザ・USA」に対する誤解もそれに輪をかけた。「ボーン・イン・ザ・USA」は、レーガンが大統領選挙で利用したこともあり、単純なアメリカ讃歌として広まったのだ。私自身、スプリングスティーンに対して、単細胞でタカ派的な低脳ロックシンガーというイメージを抱いていた。ちゃんと音楽を聴きもせずにだ……。
ところで、作家の村上春樹氏は、その著書『意味がなければスウィングはない』(文芸春秋)所収の文章の中で、スプリングスティーンの音楽について共感を込めつつ論じているが、それによれば、「ボーン・イン・ザ・USA」の歌詞はこうだ。
救いのない町に生れ落ちて
物心ついたときから蹴飛ばされてきた。
殴りつけられた犬みたいに、一生を終えるしかない。
身を守ることに、ただ汲々としながら。
俺はアメリカに生まれたんだ。
それがアメリカに生まれるということなんだ。
何ということだろう。私の長年勝手に抱いていたイメージはまったくの誤解だった。正反対だったといってもいい。スプリングスティーンは、アメリカのワーキングクラスの閉塞感を代弁する歌を歌っていたのだ。村上氏は前掲書で次のように語っている。
ブルース・スプリングスティーンが『俺はアメリカに生まれたんだ』と叫ぶとき、そこにはいうまでもなく怒りがあり、懐疑があり、哀しみがある。俺が生まれたアメリカはこんな国じゃなかったはずだ、こんな国であるべきではないのだ、という痛切な思いが彼の中にはある。
最近、ブルース・スプリングスティーンをよく聴く。まるで、過去の空白を埋めるかのように、あるいは失ってしまった大切な何かを取り戻そうとするかのようにだ。今聴いているのは、1980年作品の『ザ・リバー』。私が高校3年生の頃の作品だ。ロックはずっと昔に卒業してしまったはずだが、なぜだか心に沁みる。当時のアメリカの抱える、おそらくは現実の風景をスプリングスティーンは淡々と歌っていく。
「ボブ・ディランはカントリーを歩いている、だけどスプリングスティーンは都会の底を走っている……」 そう語った山川健一の小説の登場人物に、今なら「そうかもしれないね」といえるかもしれない。
ドクサ……。人間は色眼鏡でものごとをみる。
 ヨーロピアン・ジャズ・トリオの2000年録音盤。当時新進気鋭のギタリスト、ジェシ・ヴァン・ルーラーがゲストとして4曲に参加しており、なぜか、スウィング・ジャーナル選定ゴールド・ディスクのマークがはいっている。
ヨーロピアン・ジャズ・トリオの2000年録音盤。当時新進気鋭のギタリスト、ジェシ・ヴァン・ルーラーがゲストとして4曲に参加しており、なぜか、スウィング・ジャーナル選定ゴールド・ディスクのマークがはいっている。