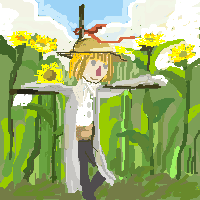西湖があるかと思われるが、杭州は恋の天国だとよく言われる。しかし、「東南仏国」とは僕にとって初耳であった。西湖風景区の一部として、霊隠寺が杭州を旅する時足を運ばなければならぬ所であろう。


寺のすぐ傍に飛来峰という小さな山があり、その山裾と山腹の所に古代から石の造像が数多作られた。中では阿弥陀仏もあれば、唐の三蔵法師(中国で名高き唐僧のこと)の物語もある。それに、狭くて暗い洞窟の中で来世・今世・前世を代表する三座の仏の像もある(下、左の右上)。其々家族のご健勝や自分の未来の安否などを意味するから、一つずつ拝むと良かろう。洞窟の造像の中でもっとも人気のあるのが財の神なる趙公明様、中に入る人々なら、誰でも拝む。其れに一人の案内人(よその方が雇った者、説明した時、私がちょうどその傍にいたから、耳を済ませて聞いた)の話によって、趙の手を触るともっと大金をもうけるという。妙な話だった。私は腹の太き弥勒仏が大好きであるから、それの写真を沢山撮ったものである(右の真ん中のは中の一枚)。


年代があまりにも長いのか、或は長年で風雨にさらされたのか、一部の造像は破損が大きいである。それがゆえに、体や下半身などしか見られなかった。しかしそれでも、今の様子から昔の風姿が想像できる。おっとりと立ったのもあれば、心優しく微笑しながら遠くを眺めたのもあろう。また顔などが完璧な者は落ち着いて下のこの自分をじっと見るのも・・・・・・頭をあげて仏とじっと見合ったその一瞬に、僕は嘗てもないほど初めて仏という不思議な力に心から実感できる(仏教の信者でないけれど)・・・言葉や身振りなどが要らない、ただ胸の中に敬虔を持つだけで、お互いに心の交流が出来るのであろう。一つの拈華微笑から、心の奥まで一つの声や音が聞こえるのであろう。たぶんその音はある明るい午後、一枚の葉っぱの裏、一筋の渓谷でもあろう。
南無大慈大悲觀世音,願我速畢學業。
南無大慈大悲觀世音,願我早得真愛。
南無大慈大悲觀世音,願我親朋平安。
南無大慈大悲觀世音,願我家人安泰。


寺のすぐ傍に飛来峰という小さな山があり、その山裾と山腹の所に古代から石の造像が数多作られた。中では阿弥陀仏もあれば、唐の三蔵法師(中国で名高き唐僧のこと)の物語もある。それに、狭くて暗い洞窟の中で来世・今世・前世を代表する三座の仏の像もある(下、左の右上)。其々家族のご健勝や自分の未来の安否などを意味するから、一つずつ拝むと良かろう。洞窟の造像の中でもっとも人気のあるのが財の神なる趙公明様、中に入る人々なら、誰でも拝む。其れに一人の案内人(よその方が雇った者、説明した時、私がちょうどその傍にいたから、耳を済ませて聞いた)の話によって、趙の手を触るともっと大金をもうけるという。妙な話だった。私は腹の太き弥勒仏が大好きであるから、それの写真を沢山撮ったものである(右の真ん中のは中の一枚)。


年代があまりにも長いのか、或は長年で風雨にさらされたのか、一部の造像は破損が大きいである。それがゆえに、体や下半身などしか見られなかった。しかしそれでも、今の様子から昔の風姿が想像できる。おっとりと立ったのもあれば、心優しく微笑しながら遠くを眺めたのもあろう。また顔などが完璧な者は落ち着いて下のこの自分をじっと見るのも・・・・・・頭をあげて仏とじっと見合ったその一瞬に、僕は嘗てもないほど初めて仏という不思議な力に心から実感できる(仏教の信者でないけれど)・・・言葉や身振りなどが要らない、ただ胸の中に敬虔を持つだけで、お互いに心の交流が出来るのであろう。一つの拈華微笑から、心の奥まで一つの声や音が聞こえるのであろう。たぶんその音はある明るい午後、一枚の葉っぱの裏、一筋の渓谷でもあろう。
南無大慈大悲觀世音,願我速畢學業。
南無大慈大悲觀世音,願我早得真愛。
南無大慈大悲觀世音,願我親朋平安。
南無大慈大悲觀世音,願我家人安泰。
「江南憶,最憶是杭州。山寺月中尋桂子,郡亭枕上看潮頭。何日更重游?」また白楽天『江南好』の一部。今日は杭州。


杭州をいえば、西湖を言わなければならぬ。まずは西湖の呼び方なんであるが、いったい「せいこ」か或は「さいこ」か、これは時々困ることになるであろう。しかし、中国では「せいこ」が一般的な読み方で、確かに入力する時は「さいこ」を使わないと出来ないが、以下で「さいこ」と読んでほしい。
《水龍吟》
辛弃疾
楚天千里清秋,水隨天去秋無際。遙岑遠目,獻愁供恨,玉簪螺髻。落日樓頭,斷鴻聲裏,江南游子,把吳鈎看了,欄杆拍遍,無人會、登臨意。
ちょっと最近は「欄干コン」になるかも知れぬが、あちこちに行ってみる時、よく欄干を探してとても熱意に満ちていた。なぜ以上のものを引用するか、それが「江南游子,把吳鈎看了,欄杆拍遍,無人會、登臨意。」という所が好きだからである。「欄杆拍遍」を直訳すれば、「手で江南のすべての欄干をたたく」となるが、やはり「たたく」より「触る、撫でる、摩る」のほうがもっと的確であろう。僕の場合は「欄干を撮る」、中国語で「撮る」を言う時、よく「拍」を使うから、これも面白い表現である。
灰色の欄干に長き蔓が付き纏う。
西湖を欄干の背景にして、ロングショットをするのも一種の感動。
丸いもの。方形物。獅子頭もの。色んな形の欄干。杭州の欄干。


地図を見ると、西湖は杭州の西南部に位置、都市全体からすれば、四の一を占めるであろう。湖畔を歩いてみたら、九月の西湖は柳の糸が春と同じで、柔らかくて美人の眉まで連想させる。これも俳人守武の「青柳の眉かく岸の額かな」という句にぴったりする光景である。西湖は好い所だなあ!

僕は写真専門ではないけれど、写真を撮る時、出来るだけいろいろ工夫して考えた。ショットの遠近や色、光など。その東屋もそうなのであった。所謂「黄金分割点」の所に置いて撮ったものである。それに天や山に近き、蓮の葉っぱ。九月は蓮の花がもう季節ズレで見えないが、幸いに葉っぱはまだであった。それに初めて新鮮な蓮の実を食った。

蓮の実と杭菊のお茶。見事に調和する。


西湖天地、一茶一坐。
禅意・たっぷり……


『愛たちの後ろ姿』。流石の「恋の天国」。年齢問わず、場所問わず。時問わず。愛は何処でも存在する!杭州、愛してる!

天地は万物のはたご屋で,光陰は百代の過客である.一人の旅人にとって、こんな風景はもう十分……


杭州をいえば、西湖を言わなければならぬ。まずは西湖の呼び方なんであるが、いったい「せいこ」か或は「さいこ」か、これは時々困ることになるであろう。しかし、中国では「せいこ」が一般的な読み方で、確かに入力する時は「さいこ」を使わないと出来ないが、以下で「さいこ」と読んでほしい。
《水龍吟》
辛弃疾
楚天千里清秋,水隨天去秋無際。遙岑遠目,獻愁供恨,玉簪螺髻。落日樓頭,斷鴻聲裏,江南游子,把吳鈎看了,欄杆拍遍,無人會、登臨意。
ちょっと最近は「欄干コン」になるかも知れぬが、あちこちに行ってみる時、よく欄干を探してとても熱意に満ちていた。なぜ以上のものを引用するか、それが「江南游子,把吳鈎看了,欄杆拍遍,無人會、登臨意。」という所が好きだからである。「欄杆拍遍」を直訳すれば、「手で江南のすべての欄干をたたく」となるが、やはり「たたく」より「触る、撫でる、摩る」のほうがもっと的確であろう。僕の場合は「欄干を撮る」、中国語で「撮る」を言う時、よく「拍」を使うから、これも面白い表現である。
灰色の欄干に長き蔓が付き纏う。
西湖を欄干の背景にして、ロングショットをするのも一種の感動。
丸いもの。方形物。獅子頭もの。色んな形の欄干。杭州の欄干。


地図を見ると、西湖は杭州の西南部に位置、都市全体からすれば、四の一を占めるであろう。湖畔を歩いてみたら、九月の西湖は柳の糸が春と同じで、柔らかくて美人の眉まで連想させる。これも俳人守武の「青柳の眉かく岸の額かな」という句にぴったりする光景である。西湖は好い所だなあ!

僕は写真専門ではないけれど、写真を撮る時、出来るだけいろいろ工夫して考えた。ショットの遠近や色、光など。その東屋もそうなのであった。所謂「黄金分割点」の所に置いて撮ったものである。それに天や山に近き、蓮の葉っぱ。九月は蓮の花がもう季節ズレで見えないが、幸いに葉っぱはまだであった。それに初めて新鮮な蓮の実を食った。

蓮の実と杭菊のお茶。見事に調和する。


西湖天地、一茶一坐。
禅意・たっぷり……


『愛たちの後ろ姿』。流石の「恋の天国」。年齢問わず、場所問わず。時問わず。愛は何処でも存在する!杭州、愛してる!

天地は万物のはたご屋で,光陰は百代の過客である.一人の旅人にとって、こんな風景はもう十分……
日出江花紅勝火、春来江水緑如藍。能不憶江南?白楽天『憶江南』の一部。江南地区の風景や季節感を生き生きと描き出す秀作だと、薦めである。
僕は先月11日から21日までの十日間で、南京、杭州、上海を旅していた。


左:南京の中山陵、中国民主革命の先駆なる孫文先生のお墓なのである。
右:明孝陵の一部、明代開国皇帝・朱元しょう(王辺に章)と奥さんの馬皇后との合葬(がっそう)墓である。
南京は六朝の古都なり、西安と同じ、世界でもかなり有名な町なのである。僕は二日間(週末)滞在して、人気のある中山・明孝両陵だけに行った。中山より明孝が勧めである。特に日本の方ならば、ぜひ明孝のほうへ行ってみて、中では顔真卿碑林というのがあり、中日両国書道家の作が多く立ってある。あとは、僕は余裕あまりないから、総統府へ行かなかった。


左:杭州の岳王廟にある岳飛のお墓。その右に立ってあるのは王の長男・岳雲のお墓である。南宋有名な英雄として中国で人気がある。墓の両側及びその下に石の翁仲や獣(馬、羊、虎)が墓を鎮護する。これらは一般的に帝王の陵墓しかないものなので、そこからすれば、岳王の地位がどれほど高いのが分かるであろう。
右:岳飛を陥れる秦檜、王氏(下)、張俊、万俟卨(上)四人の鉄製像。四人とも罪人だから、同じ姿勢で跪いている。実はこれについて、ある日本人の友から聞いたことがある。中日生死観の問題だったが、我々二人でかなり深く話し合ったものである。一般論にして話すならば、やはり「日本人は死を尊敬する、中国人は死を恐れる」など、また「日本では良し悪しに関わらず、死んだら誰でも神や仏になれるから尊敬すべきだ。中国では輪廻や業などの考え方があってから、今世で悪いことばかりすると、きっと来世には報いがある」というような結論が出てくる。この死生観の問題も中日関係を改善し向上させるに一定の意義があるではないか。
僕は先月11日から21日までの十日間で、南京、杭州、上海を旅していた。


左:南京の中山陵、中国民主革命の先駆なる孫文先生のお墓なのである。
右:明孝陵の一部、明代開国皇帝・朱元しょう(王辺に章)と奥さんの馬皇后との合葬(がっそう)墓である。
南京は六朝の古都なり、西安と同じ、世界でもかなり有名な町なのである。僕は二日間(週末)滞在して、人気のある中山・明孝両陵だけに行った。中山より明孝が勧めである。特に日本の方ならば、ぜひ明孝のほうへ行ってみて、中では顔真卿碑林というのがあり、中日両国書道家の作が多く立ってある。あとは、僕は余裕あまりないから、総統府へ行かなかった。


左:杭州の岳王廟にある岳飛のお墓。その右に立ってあるのは王の長男・岳雲のお墓である。南宋有名な英雄として中国で人気がある。墓の両側及びその下に石の翁仲や獣(馬、羊、虎)が墓を鎮護する。これらは一般的に帝王の陵墓しかないものなので、そこからすれば、岳王の地位がどれほど高いのが分かるであろう。
右:岳飛を陥れる秦檜、王氏(下)、張俊、万俟卨(上)四人の鉄製像。四人とも罪人だから、同じ姿勢で跪いている。実はこれについて、ある日本人の友から聞いたことがある。中日生死観の問題だったが、我々二人でかなり深く話し合ったものである。一般論にして話すならば、やはり「日本人は死を尊敬する、中国人は死を恐れる」など、また「日本では良し悪しに関わらず、死んだら誰でも神や仏になれるから尊敬すべきだ。中国では輪廻や業などの考え方があってから、今世で悪いことばかりすると、きっと来世には報いがある」というような結論が出てくる。この死生観の問題も中日関係を改善し向上させるに一定の意義があるではないか。


東風吹くや 国境一歩超えの旅


左:中越(ベトナム)辺境にある小さい市。香水(「ベトナム式フランスシリーズ」だっといって、本場かどうか?さあ!)や櫛など、ベトナムの特産を売っている。ここは所謂「緩衝地帯」なので、暫くベトナムの国土に滞在した(外国への旅!へへ~~!)。写真になかったが、ベトナム側の山の頂に歩哨所(東屋のように見えるが~~)が隠蔽している。
右:木棉の木(キワタノキ.インドワタノキ)。
川は帰春河という。向こうの岸はもうベトナムの国土である。
ガイドさんによって、所謂「川の国境線」。


左:通霊大峡谷(地球の傷あとだと言われる)の底にて。
右:噂の無花果(イチジク)。
実は直に幹や枝にそのまま実っている。


左:通霊滝。落差は約185mだという。
右:帰春河。中国側にて。向こうは同じ、ベトナム。


徳天の大滝。
中越の国境線に横なる滝。
今頃(3~6月)はちょうど渇水期なので、そんなに壮大ではなかった。
午後四時。外国語学院の八階。窓を通して、雨の中を眺めていた。
青い池、緑の茂み、木々の緑。世界が雨の白い煙に濛濛としている。緑に囲まれていた外国風講堂。白い柱、赤煉瓦の屋根。詩的な一切。
雨の斜めな糸が風とともに力強く窓から吹き込んだ。裸の壁と接吻するようだった。
「早く早く」ある赤傘の下から、女子学生の甲高い声が聞こえるようだった。それに、移動する丸い赤傘。
青い池、緑の茂み、木々の緑。世界が雨の白い煙に濛濛としている。緑に囲まれていた外国風講堂。白い柱、赤煉瓦の屋根。詩的な一切。
雨の斜めな糸が風とともに力強く窓から吹き込んだ。裸の壁と接吻するようだった。
「早く早く」ある赤傘の下から、女子学生の甲高い声が聞こえるようだった。それに、移動する丸い赤傘。
今日は「案山子」という児童的短編を書きました。案山子は僕の好きな田舎のものです。それを主人公にするのも面白かったです。
案山子
案山子が寂しく向日葵畑に立っている。身元の向日葵らより背が高いが、彼はとても己の醜い格好にコンプレックスを感じていた。それが原因で毎日ため息ばかりをついた。
ある初夏の朝である。太陽に向かってにこにこと笑っている向日葵らの顔を見ながら、案山子はおずおずと傍の向日葵に話をしてみた。
「お、お、おはよう御座います。」
「ああ、君ですか。おはよう御座います。君はどうして毎日ため息ばかりをつきますのか。何か悲しいことや不幸な遭遇があるのでしょうか。」と向日葵は問いました。
「い、いや、別にありませんが、」
「なければ、なぜ悲しそうな顔をしていますのか。」と向日葵はまた聞きました。
「それは、それは、僕の格好のせいです。」
「格好!どうして、君は立派ではありませんか。我々向日葵はみんな君の格好に羨ましいですよ。」
「本当ですか。」
「ええ、本当ですよ。毎日立派な格好で畑に立ってて、それで威風堂々ではありませんか。雀らが凄いでしょう。あれで君の事を恐れますよ。」
「本当ですか。全然知りませんでした。良いことを言ってくれて、ありがとう御座いました。」と案山子は今楽しそうに向日葵にお礼をした。
「僕って、そんなに格好いいのでしょうか。この前全然知りませんでした。良かったです。良かったです。」と夜になると、案山子はひとりで呟いていた。
秋は実りの多い季節である。毎日沢山の雀らが向日葵畑の上を飛びまわっていた。ある日のことである。
「この前、向日葵さんは僕の格好、とても良いって言いましたが、今日それを雀らに確かめてみよう。」と案山子は一人で呟いた。
「雀さん!雀さん!ちょっと僕の肩に留まってくださいませんか。恐れるな、恐れるな。僕です。案山子です」と案山子は大声で空中を飛んでいた雀の群に叫んだ。
雀らは案山子の叫び声を聞くと、ジージーと一斉に彼の肩に留まった。
「こんにちは。誰かと思ったら、何だ君でしたのか。何かご用がございませんか。」
「ちょっと君らに確かめたいことがありますが、僕が案山子って知る前に、恐れたことがありますか。」
案山子の質問を耳にすると、雀らはみんな笑いながら、
「恐れるわ!とても恐れるわ!案山子様は立派で、凄いですわ。」とおばさんらしい雀が狡猾そうに案山子に言いかけた。
「本当ですか。どうもありがとうございます。いいこと言ってくれてうれしいです。」
「では、またね。食事をしに行きますから!」と雀らは、にたりと笑いながら向日葵畑へ飛びに行った。
「ちょっと!君たち!嘘! やめてください。やめてください。やめてください。」と案山子はいくら叫んでも、雀らは今度やめていなかった。
翌日。向日葵畑がメチャメチャになってしまった。それに、主人が怒って案山子を取り去った。
案山子
案山子が寂しく向日葵畑に立っている。身元の向日葵らより背が高いが、彼はとても己の醜い格好にコンプレックスを感じていた。それが原因で毎日ため息ばかりをついた。
ある初夏の朝である。太陽に向かってにこにこと笑っている向日葵らの顔を見ながら、案山子はおずおずと傍の向日葵に話をしてみた。
「お、お、おはよう御座います。」
「ああ、君ですか。おはよう御座います。君はどうして毎日ため息ばかりをつきますのか。何か悲しいことや不幸な遭遇があるのでしょうか。」と向日葵は問いました。
「い、いや、別にありませんが、」
「なければ、なぜ悲しそうな顔をしていますのか。」と向日葵はまた聞きました。
「それは、それは、僕の格好のせいです。」
「格好!どうして、君は立派ではありませんか。我々向日葵はみんな君の格好に羨ましいですよ。」
「本当ですか。」
「ええ、本当ですよ。毎日立派な格好で畑に立ってて、それで威風堂々ではありませんか。雀らが凄いでしょう。あれで君の事を恐れますよ。」
「本当ですか。全然知りませんでした。良いことを言ってくれて、ありがとう御座いました。」と案山子は今楽しそうに向日葵にお礼をした。
「僕って、そんなに格好いいのでしょうか。この前全然知りませんでした。良かったです。良かったです。」と夜になると、案山子はひとりで呟いていた。
秋は実りの多い季節である。毎日沢山の雀らが向日葵畑の上を飛びまわっていた。ある日のことである。
「この前、向日葵さんは僕の格好、とても良いって言いましたが、今日それを雀らに確かめてみよう。」と案山子は一人で呟いた。
「雀さん!雀さん!ちょっと僕の肩に留まってくださいませんか。恐れるな、恐れるな。僕です。案山子です」と案山子は大声で空中を飛んでいた雀の群に叫んだ。
雀らは案山子の叫び声を聞くと、ジージーと一斉に彼の肩に留まった。
「こんにちは。誰かと思ったら、何だ君でしたのか。何かご用がございませんか。」
「ちょっと君らに確かめたいことがありますが、僕が案山子って知る前に、恐れたことがありますか。」
案山子の質問を耳にすると、雀らはみんな笑いながら、
「恐れるわ!とても恐れるわ!案山子様は立派で、凄いですわ。」とおばさんらしい雀が狡猾そうに案山子に言いかけた。
「本当ですか。どうもありがとうございます。いいこと言ってくれてうれしいです。」
「では、またね。食事をしに行きますから!」と雀らは、にたりと笑いながら向日葵畑へ飛びに行った。
「ちょっと!君たち!嘘! やめてください。やめてください。やめてください。」と案山子はいくら叫んでも、雀らは今度やめていなかった。
翌日。向日葵畑がメチャメチャになってしまった。それに、主人が怒って案山子を取り去った。
昨日の昼間、隣組のK君は「天気が良い」と言って遠足を誘ってくれた。
二人で春の暖かい日差しに南のほうへ行った。路傍の養鶏場から「じーじー」と、無数の肉鶏が鳴いていた。もっと南へ行くと、一面の麦畑が目の前に蔓延した。久しぶりに新鮮な緑を見ていたので、気持ちがすごく良くなってきた。
近いところに、一人の老婆は、麦の苗で羊を飼っていた。僕はK君に「なぜ羊が麦の苗を食うのか」と聞くと、彼は「まあ、羊は麦の根まで食わなくて、葉だけを食うよ」と教えてくれた。その母羊の傍にとても可愛い羊の子がいた。「ただ生まれた20日の羊の子」と飼い主の老婆が教えた。
麦畑の中で、どこかから冬眠終わりの蛙の鳴き声が聞こえた。野生の鳩の姿をも眺められた。遠方の木々の間、名の知らない野鳥の鳴き声が日差しの中に伝えてきた。とても自然な農村風景だった。
麦畑から出て、郭杜村の大通りに沿って帰るつもりだが、K君から「この近くに古刹がある」と教えた。二人は近所の村人に尋ねながら、そのお寺の所在を探し始めた。塔の姿を見ていた時、目標先は遠くないと僕は判断した。途中で小さなダムがあり、その下に二人の釣り人がいた。川水の質はあまり良くないから、魚がいるのか——僕は疑った。
お寺の正門まで着かなかったが、路傍の電信柱に「香積寺117号」という文字が見えてきた。古刹の名が香積寺だろうと、僕は思った。
正門で少し休憩したから、階段を上り始めた。僕はわざと数えていたが、ちょうど31級だった。Kから「仏教の多くの建築、たとえば、塔の層数や階段の級数などが奇数である」と教えた。一人五元でお寺の中に入った。大雄宝殿の前のその殿に、K君と仏参りした。僕は小さな願望を祈った。大雄宝殿は入殿禁止だったが、門の前に立って檀香の香りがした。私たちが昼の時訪ねてきたので、朝鐘暮鼓が聞こえなかった。僕はさっき眺めた塔の後ろを見に行って、普通の古塔だった。ほかの名所の塔と同じように、塔の身の青石に観光客の名前や記念言葉が所々刻まれた。たぶん僕と同じような仏への無心者だろう。
もし本当の善男善女なら、仏門の地でこんな悪事をするはずがないだろう。
寺の境内には松柏のほか、名の知らない草木が所々植えられてあった。塔の後ろに小さな野菜園がある。僕は「なんて今お寺には女子の姿が見えるのか」と責めていたが、K君は「さっき見た普通衣装を着ている婦人らはこの近くに住む仏教の信者のはずだ。暇の時、境内の掃除などをするよ」と教えた。
塔の少し前に高大の古松が立っていた。私たちが昼間の時訪ねてきたか、樹下には一人の和尚さんが居眠りをしていた。とても意味のある風景だろう。古代なら、だれそれの画伯がこの風景を見たら、たぶん「松下周公夢」という名画が残っているだろう 。
二人で春の暖かい日差しに南のほうへ行った。路傍の養鶏場から「じーじー」と、無数の肉鶏が鳴いていた。もっと南へ行くと、一面の麦畑が目の前に蔓延した。久しぶりに新鮮な緑を見ていたので、気持ちがすごく良くなってきた。
近いところに、一人の老婆は、麦の苗で羊を飼っていた。僕はK君に「なぜ羊が麦の苗を食うのか」と聞くと、彼は「まあ、羊は麦の根まで食わなくて、葉だけを食うよ」と教えてくれた。その母羊の傍にとても可愛い羊の子がいた。「ただ生まれた20日の羊の子」と飼い主の老婆が教えた。
麦畑の中で、どこかから冬眠終わりの蛙の鳴き声が聞こえた。野生の鳩の姿をも眺められた。遠方の木々の間、名の知らない野鳥の鳴き声が日差しの中に伝えてきた。とても自然な農村風景だった。
麦畑から出て、郭杜村の大通りに沿って帰るつもりだが、K君から「この近くに古刹がある」と教えた。二人は近所の村人に尋ねながら、そのお寺の所在を探し始めた。塔の姿を見ていた時、目標先は遠くないと僕は判断した。途中で小さなダムがあり、その下に二人の釣り人がいた。川水の質はあまり良くないから、魚がいるのか——僕は疑った。
お寺の正門まで着かなかったが、路傍の電信柱に「香積寺117号」という文字が見えてきた。古刹の名が香積寺だろうと、僕は思った。
正門で少し休憩したから、階段を上り始めた。僕はわざと数えていたが、ちょうど31級だった。Kから「仏教の多くの建築、たとえば、塔の層数や階段の級数などが奇数である」と教えた。一人五元でお寺の中に入った。大雄宝殿の前のその殿に、K君と仏参りした。僕は小さな願望を祈った。大雄宝殿は入殿禁止だったが、門の前に立って檀香の香りがした。私たちが昼の時訪ねてきたので、朝鐘暮鼓が聞こえなかった。僕はさっき眺めた塔の後ろを見に行って、普通の古塔だった。ほかの名所の塔と同じように、塔の身の青石に観光客の名前や記念言葉が所々刻まれた。たぶん僕と同じような仏への無心者だろう。
もし本当の善男善女なら、仏門の地でこんな悪事をするはずがないだろう。
寺の境内には松柏のほか、名の知らない草木が所々植えられてあった。塔の後ろに小さな野菜園がある。僕は「なんて今お寺には女子の姿が見えるのか」と責めていたが、K君は「さっき見た普通衣装を着ている婦人らはこの近くに住む仏教の信者のはずだ。暇の時、境内の掃除などをするよ」と教えた。
塔の少し前に高大の古松が立っていた。私たちが昼間の時訪ねてきたか、樹下には一人の和尚さんが居眠りをしていた。とても意味のある風景だろう。古代なら、だれそれの画伯がこの風景を見たら、たぶん「松下周公夢」という名画が残っているだろう 。