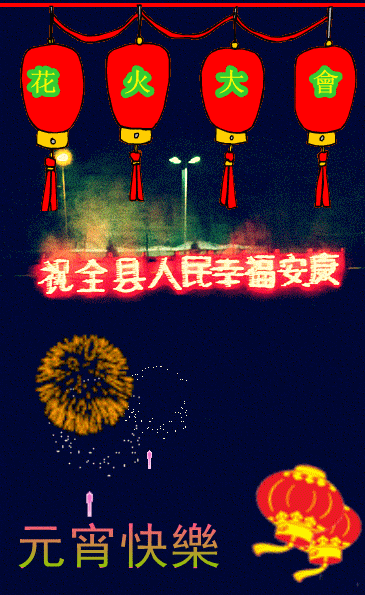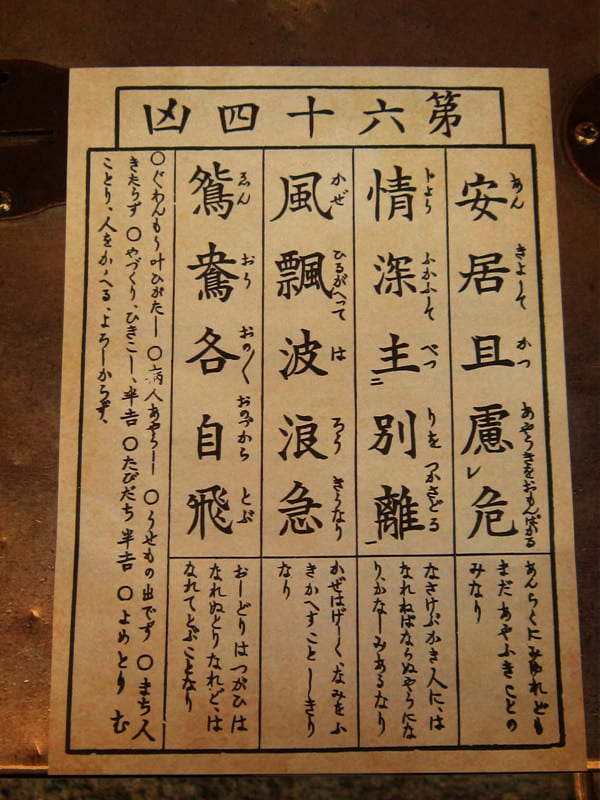蟋蟀の宇宙は狭き甕にあり 原豊
蟋蟀の世ではなく、宇宙である。宇宙は無限かつ広大である。その宇宙はただ狭き甕にありとは、妙な組み合わせだと思う。無限広大な空間と狭き甕の空間は一体になる。この間、ニッチ論という理論を読んだ。まさに、その甕は蟋蟀の宇宙であり、ニッチでもあるのだろう。甕からみれば、人間の飼う、闘蟀であろう。昔、北京で闘蟀が盛んだったが、高価の飼い甕もあれば、普通の甕もあった。今も骨董屋などで昔の甕がよく見られ、珍しい蟋蟀が甕で宝のように飼われた。その狭き甕に生まれ、生きて、闘い合い、死ぬ。狭き甕は宇宙そのものとなる。下五を「瓦礫かな」に添削してみると、自然の中の蟋蟀が思われるのだろうか。蟋蟀も我々もニッチを探しながら、一生を送るのであろう。
蟋蟀の世ではなく、宇宙である。宇宙は無限かつ広大である。その宇宙はただ狭き甕にありとは、妙な組み合わせだと思う。無限広大な空間と狭き甕の空間は一体になる。この間、ニッチ論という理論を読んだ。まさに、その甕は蟋蟀の宇宙であり、ニッチでもあるのだろう。甕からみれば、人間の飼う、闘蟀であろう。昔、北京で闘蟀が盛んだったが、高価の飼い甕もあれば、普通の甕もあった。今も骨董屋などで昔の甕がよく見られ、珍しい蟋蟀が甕で宝のように飼われた。その狭き甕に生まれ、生きて、闘い合い、死ぬ。狭き甕は宇宙そのものとなる。下五を「瓦礫かな」に添削してみると、自然の中の蟋蟀が思われるのだろうか。蟋蟀も我々もニッチを探しながら、一生を送るのであろう。