TITLE: 銅鐸の謎(その3)
書籍名;「銅鐸の秘密」 [1986]
著者;臼田篤伸 発行所;新人物往来社
発行日;2005.3.10
初回作成年月日;H30.8.16 最終改定日;H30.8.24
引用先;文化の文明化のプロセス Implementing
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
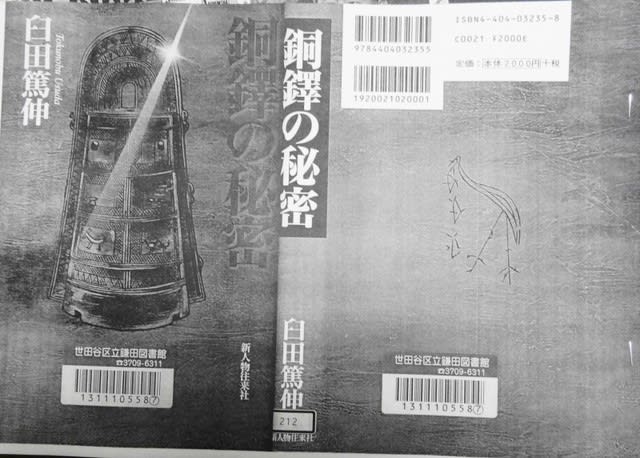
著者は、歯科医師で風邪に関する何冊かの著書があるが、銅鐸民族に深い興味を持っており,他にも「銅鐸民族の謎」がある。全体を通して、二つのことを強調している。銅鐸は銅矛とともに、戦争用具であることと、埋められたのではなく、長い年月によって埋まってしまった、というわけである。北九州を支配していた銅鐸民族が、天孫族により滅ぼされて、次第に東へ移動し、その都度銅鐸の様式も少しずつ進化してきたという説である。
また、関連する多くの著書の中身を紹介して、賛成、反対を明確にしている。そして、歯科医師らしく、その根拠を示している。このような手法は、メタエンジニアリング的と言えるのではないかと思う。
著者は、自らの手法を「ゲリラ考古学」と称して、常識的な目を通して、出土品を調べてゆくとしている。銅戈と銅鐸は情報伝達を含む武器であり、出土地は民族紛争の結果として、敗者がその地に放置したものだったというわけである。その経路を次のように説明している。
・銅鐸民族玉砕の地
著者は、弥生時代の初期に、青銅器の鋳造技術を持った「銅鐸族(国津神族)」が北九州に定住し、紀元前後から「天孫族(天津神族)」により、東に追われたと仮定している。
『わが国に銅鐸民族が最初に侵入した地域には、主として福田型銅鐸が存在していたことが明らかとなっています。ところが、この銅鐸は天孫族の北部九州侵略で紀元前後にはすでに断絶してしまいました。この戦乱とは、「天孫降臨」から「倭国の乱」に至る過程に起きたものです。弥生初期に製作されたこの銅鐸は、高度先進技術だったがゆえに、天孫族によって徹底的に破壊されました。北部九州からは銅鐸本体はほとんど出土していません。しかし、石製の鋳型が六カ所から、それもバラバラに壊れた状態で見つかるのは、そのためでです』(pp.114)
さらに続けて、『出雲から東の地方で出土した銅鐸群は形や文様が福田型とはつきり違っています。右の戦乱のあと、銅鐸民族は共同体国家を守るため、新たな製造体制を整える必要に迫られたものという 推察ができるのです。』(pp.115)
そして、最終的には、『信州では、大型の二遠式銅鐸が塩尻市と松本市の二か所から出上しました。この銅鐸は銅鐸勢力の中心とおぼしい諏訪湖周辺地域からの出土です。近畿式銅鐸と同様に製造技術発達の最終段階とでもいうべき派なものです。このあたり一帯が銅鐸民族の東の司令部が存在した地域と推察されるのです。』(pp.115)
天孫族に追われて東へ逃げ延びるたびに、新たな銅鐸技法を創り出し、農耕民としての定住を図ろうとした。そして、諏訪大社に祀られる大国主の息子のタケミナカタは、銅鐸民族の最後の拠り所の首領だったというわけである。
後半は、様々な著書の紹介が続いている。
・古田武彦説については、
長く九州王朝を主張している古田説については、
『古田さんの判断は、次のようになったのです。「九州王朝は、銅矛圏の王朝。だから、その歴史に銅鐸が出てこなくても、何の不思議はない。その歴史の多くを、天武王朝がそっくり盗用したとすれば、『記・紀』に銅鐸が出てこないのは、むしろ自然なことである」 筆者も、この説を採りたいと思います。』(pp.119)
著者の説によれば、天孫族は銅鐸を壊す理由はあったが、銅矛を破壊する必要はなかったということなのだろう。
そして、特に彼の法隆寺の歴史説に賛同している。
『正倉院の財宝……九州王朝のもの(推測)。
法隆寺の釈迦三尊像・・…九州王朝のもの(三尊像は鋳造。当時の鋳造技術は九州が断然上)。
法隆寺の心柱……観世音寺の五重塔心柱(右に述べた測定)。
近畿王朝の神話……九州王朝のもの(かなり裏づけのある推論)』(pp.120)
つまり、すべては青銅器鋳造技術民族の遺産というわけである。
・森浩一説については、
「温厚な感じの人」とだけ記している。
・原田大六説については、
彼の、大国主の銅鐸説に賛同して、文字を使用しなかった銅鐸民族が,後世天孫族により、勝手に差別的名称を付けられたとしている。
『原田さんは「大穴」の穴とは銅鐸の空洞であること、としています。この説と大国主を表す巨大銅鐸、この二点から銅鐸そのものがご神体と説いたのです。原田さんが着目したのは『古事 記』にある大穴牟遅を『日本書紀』では「大己貴」読ませていることです。本来なら大穴貴(おほあなむち)でしょう。この大穴こそが神の正体を知る手がかりになるというのです。大穴のある青銅器は何かと問えば、 むろん答えは銅鐸です。この穴が大穴であれば、巨大銅鐸そのものということができるというわけです。』(pp.142)
・藤森栄一説については、
『精力的にフイールドワークをこなし、 鋭い直観力で銅鐸の謎への入り口を見つけ出した、ということです。既存の説や見解に疑間を投げかけたこの本がーつのきっかけで、常々埋納一辺倒に疑問を抱いていた筆名も、銅鐸の世界に足を踏み入れることになったのでした。』(pp.143)として、著者の「自然に埋まってしまった」説の元となったポイントを列挙している。
・大羽弘道説については、
『「銅鐸の謎」(光文社)は一九七四年に出版されました。この本は一年で四〇余刷りを重ねるヒット作でした。銅鐸絵画に対し、絵文字説を初めて具体的に述べたことが、強いインパクトを与えました。これはーつの足跡です。』(pp.145)
私も、愛読した一人なのだが、文字と解釈しての読み方に「歴史認識の甘さが目立つ」として、否定的になっている。しかし、しこから「原田大六説」が生まれたようにも思ってしまう。
・他に4名の著書も挙げている。
・銅鐸の用途については、
『通常は集落に面した山腹から一~二個の出土というケースが大半です。この出土状況から察し、筆者は銅鐸の主な使途を、平和時は集落内部や集落間の連絡用、そして戦闘の際には戦術のコミュニケーションの具として使われた、と考えます。』(pp.188)
として、現代の「火の見櫓」の原型としているのだが、そうだとするならば、置いてある場所が全く異なっている。山影では、見通しがきかない。
最後に、『文字をベースにした天孫族と総合的な総力戦を戦うには、銅鐸は無力に近かったのです。戦略のない戦術は、しょせん、戦略を持った相手には勝てなかったのです。 別の表現をすれば、銅鐸は、アコースティック的、瞬間的、その場的、再聴不能です。』(pp.193)として締めくくっている。ここにも、メタエンジニアリング的な視点を感じる。
書籍名;「銅鐸の秘密」 [1986]
著者;臼田篤伸 発行所;新人物往来社
発行日;2005.3.10
初回作成年月日;H30.8.16 最終改定日;H30.8.24
引用先;文化の文明化のプロセス Implementing
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
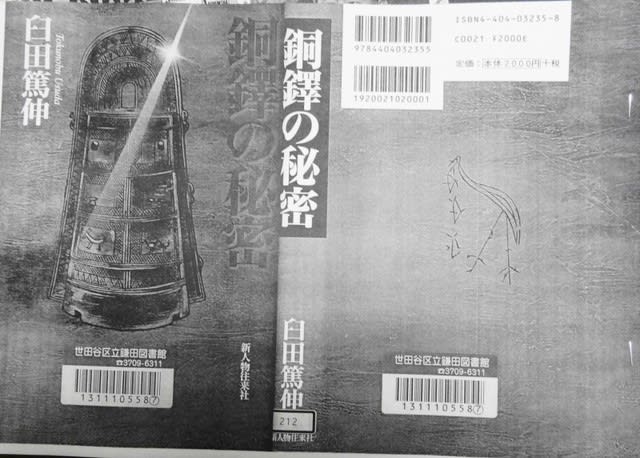
著者は、歯科医師で風邪に関する何冊かの著書があるが、銅鐸民族に深い興味を持っており,他にも「銅鐸民族の謎」がある。全体を通して、二つのことを強調している。銅鐸は銅矛とともに、戦争用具であることと、埋められたのではなく、長い年月によって埋まってしまった、というわけである。北九州を支配していた銅鐸民族が、天孫族により滅ぼされて、次第に東へ移動し、その都度銅鐸の様式も少しずつ進化してきたという説である。
また、関連する多くの著書の中身を紹介して、賛成、反対を明確にしている。そして、歯科医師らしく、その根拠を示している。このような手法は、メタエンジニアリング的と言えるのではないかと思う。
著者は、自らの手法を「ゲリラ考古学」と称して、常識的な目を通して、出土品を調べてゆくとしている。銅戈と銅鐸は情報伝達を含む武器であり、出土地は民族紛争の結果として、敗者がその地に放置したものだったというわけである。その経路を次のように説明している。
・銅鐸民族玉砕の地
著者は、弥生時代の初期に、青銅器の鋳造技術を持った「銅鐸族(国津神族)」が北九州に定住し、紀元前後から「天孫族(天津神族)」により、東に追われたと仮定している。
『わが国に銅鐸民族が最初に侵入した地域には、主として福田型銅鐸が存在していたことが明らかとなっています。ところが、この銅鐸は天孫族の北部九州侵略で紀元前後にはすでに断絶してしまいました。この戦乱とは、「天孫降臨」から「倭国の乱」に至る過程に起きたものです。弥生初期に製作されたこの銅鐸は、高度先進技術だったがゆえに、天孫族によって徹底的に破壊されました。北部九州からは銅鐸本体はほとんど出土していません。しかし、石製の鋳型が六カ所から、それもバラバラに壊れた状態で見つかるのは、そのためでです』(pp.114)
さらに続けて、『出雲から東の地方で出土した銅鐸群は形や文様が福田型とはつきり違っています。右の戦乱のあと、銅鐸民族は共同体国家を守るため、新たな製造体制を整える必要に迫られたものという 推察ができるのです。』(pp.115)
そして、最終的には、『信州では、大型の二遠式銅鐸が塩尻市と松本市の二か所から出上しました。この銅鐸は銅鐸勢力の中心とおぼしい諏訪湖周辺地域からの出土です。近畿式銅鐸と同様に製造技術発達の最終段階とでもいうべき派なものです。このあたり一帯が銅鐸民族の東の司令部が存在した地域と推察されるのです。』(pp.115)
天孫族に追われて東へ逃げ延びるたびに、新たな銅鐸技法を創り出し、農耕民としての定住を図ろうとした。そして、諏訪大社に祀られる大国主の息子のタケミナカタは、銅鐸民族の最後の拠り所の首領だったというわけである。
後半は、様々な著書の紹介が続いている。
・古田武彦説については、
長く九州王朝を主張している古田説については、
『古田さんの判断は、次のようになったのです。「九州王朝は、銅矛圏の王朝。だから、その歴史に銅鐸が出てこなくても、何の不思議はない。その歴史の多くを、天武王朝がそっくり盗用したとすれば、『記・紀』に銅鐸が出てこないのは、むしろ自然なことである」 筆者も、この説を採りたいと思います。』(pp.119)
著者の説によれば、天孫族は銅鐸を壊す理由はあったが、銅矛を破壊する必要はなかったということなのだろう。
そして、特に彼の法隆寺の歴史説に賛同している。
『正倉院の財宝……九州王朝のもの(推測)。
法隆寺の釈迦三尊像・・…九州王朝のもの(三尊像は鋳造。当時の鋳造技術は九州が断然上)。
法隆寺の心柱……観世音寺の五重塔心柱(右に述べた測定)。
近畿王朝の神話……九州王朝のもの(かなり裏づけのある推論)』(pp.120)
つまり、すべては青銅器鋳造技術民族の遺産というわけである。
・森浩一説については、
「温厚な感じの人」とだけ記している。
・原田大六説については、
彼の、大国主の銅鐸説に賛同して、文字を使用しなかった銅鐸民族が,後世天孫族により、勝手に差別的名称を付けられたとしている。
『原田さんは「大穴」の穴とは銅鐸の空洞であること、としています。この説と大国主を表す巨大銅鐸、この二点から銅鐸そのものがご神体と説いたのです。原田さんが着目したのは『古事 記』にある大穴牟遅を『日本書紀』では「大己貴」読ませていることです。本来なら大穴貴(おほあなむち)でしょう。この大穴こそが神の正体を知る手がかりになるというのです。大穴のある青銅器は何かと問えば、 むろん答えは銅鐸です。この穴が大穴であれば、巨大銅鐸そのものということができるというわけです。』(pp.142)
・藤森栄一説については、
『精力的にフイールドワークをこなし、 鋭い直観力で銅鐸の謎への入り口を見つけ出した、ということです。既存の説や見解に疑間を投げかけたこの本がーつのきっかけで、常々埋納一辺倒に疑問を抱いていた筆名も、銅鐸の世界に足を踏み入れることになったのでした。』(pp.143)として、著者の「自然に埋まってしまった」説の元となったポイントを列挙している。
・大羽弘道説については、
『「銅鐸の謎」(光文社)は一九七四年に出版されました。この本は一年で四〇余刷りを重ねるヒット作でした。銅鐸絵画に対し、絵文字説を初めて具体的に述べたことが、強いインパクトを与えました。これはーつの足跡です。』(pp.145)
私も、愛読した一人なのだが、文字と解釈しての読み方に「歴史認識の甘さが目立つ」として、否定的になっている。しかし、しこから「原田大六説」が生まれたようにも思ってしまう。
・他に4名の著書も挙げている。
・銅鐸の用途については、
『通常は集落に面した山腹から一~二個の出土というケースが大半です。この出土状況から察し、筆者は銅鐸の主な使途を、平和時は集落内部や集落間の連絡用、そして戦闘の際には戦術のコミュニケーションの具として使われた、と考えます。』(pp.188)
として、現代の「火の見櫓」の原型としているのだが、そうだとするならば、置いてある場所が全く異なっている。山影では、見通しがきかない。
最後に、『文字をベースにした天孫族と総合的な総力戦を戦うには、銅鐸は無力に近かったのです。戦略のない戦術は、しょせん、戦略を持った相手には勝てなかったのです。 別の表現をすれば、銅鐸は、アコースティック的、瞬間的、その場的、再聴不能です。』(pp.193)として締めくくっている。ここにも、メタエンジニアリング的な視点を感じる。









