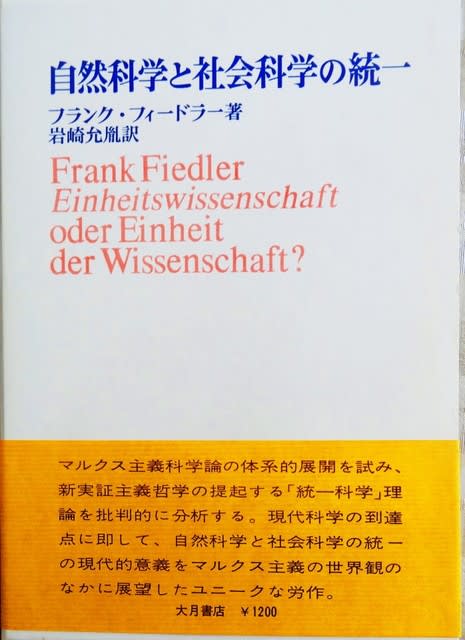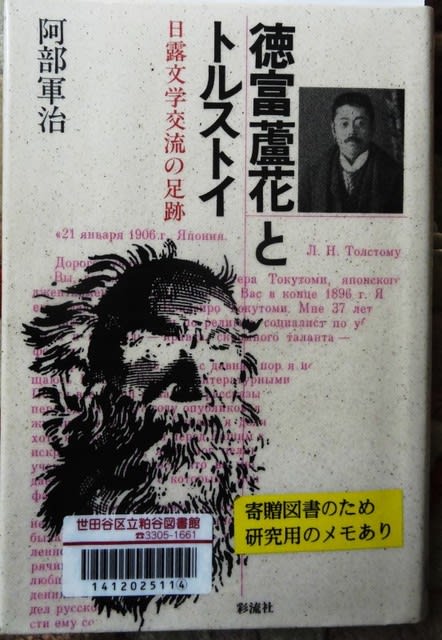その場考学との徘徊(52) 題名;トルストイと徳富蘆花の関係
場所;東京都 年月日;H30.12.25
テーマ;ロシアと日本 作成日;H30.12.25 アップロード日;H30.12.27
TITLE: トルストイと徳富蘆花
第46回「都立公園の事情」では、このように書いた。『我が家の500メートルほど南に都立芦花公園がある。徳富蘆花夫妻が晩年を過ごした茅葺屋根の建物と記念館、そしてお墓がある。しかし、それらはごく一部で、全体は公園になっている。
ちなみに、今年は蘆花の生誕150年で、トルストイとの面談直後に、晴耕雨読に目覚めて、39歳で都心からこの地に移った。』

先日、この中の記念館に立ち寄った。二部屋に遺物や著作本、原稿などが並んでいるだけで、いつもざっと歩くだけで、じっくりと中身を読んだことはなかった。今回は、たまたまヴィデオがかかっており、トルストイの画像が出ていた。蘆花の本は読んだことがないのだが、当時とてつもないベストセラーになり、年間に数十回も増刷されているとの事実を知って、俄かに興味がわいた。しかし、そこには同時に、彼の著作を今は読む人はいなくなった、とも書いてある。不思議な作家なのだ。そこで、今回の徘徊は、トルストイとの関連を含む彼の著作を渡り歩くことにする。
① 阿部軍治著「徳富蘆花とトルストイ」彩流社、1989
② 徳富蘆花集 第15巻 「日本から日本へ 西の巻」日本図書センター、1999
③ 徳富蘆花集 第14巻 「日本から日本へ 東の巻」日本図書センター、1999
④ 徳富蘆花集 第8巻 「順礼紀行」日本図書センター、1999
⑤ ジェイ・パリーニ著「終着駅 トルストイ死の謎」品文社、1996
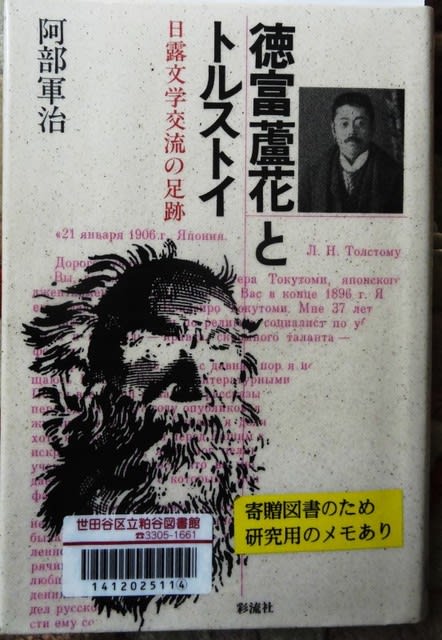
なお、②~④は復刻版であり、原本は明治39年から大正10年にかけて
金尾文淵堂から出版されている。
先ずは、①により彼らの関係を具体的に知ることができる。例えば、次のように書かれている。
『「順礼紀行の「ヤスナヤ・ポリャナの五日」によれば、トルストイと蔵花は顔を合せるが早いか、さっそく真剣な問題に関して語り合ったのであった。トルストイはほとんど開口一番、薦花の手紙は信じられないほど嬉しかったが、手紙に書いてあることは本当か、と質したという。いままで見てきたように、トルストイは薦花が真に自分に共鳴しているかどうか若干疑っていたので、当然の質間ではあるが、それにしてもいかにもトルストイらしい対応の仕方ではある。あれこれ話があってから、トルストイは、「土を耕し他の力に頼らずして生活する者が国の力也」、とその持論を述べ、「君は農業によって生活するを得ざるや」、と問うた。それに対し蔵花は、「農業は最も好む所に候。今は尺寸の土も有たざれども、行々は少なくも半農の生活をする心算に候」、と答えたのだった。(第七巻五〇〇頁)。』(pp.131)
トルストイの当時の心情としては次のように書かれている。
『はるか遠方の国からわざわざ彼に会いに来るということに、よほど感動したのであろう。この日からトルストイは、薦花の到着をじりじりして待っていたらしい。この二週間後にこういう覚え書きがある。「六月十三日 食卓で。 L ・N ・あの日本人はいったいいつ来るのかね。彼に日本や中国のことをあれこれ聞いてみたいんだが。わざわざ来るのだから、しばらく滞在してもらおう」(同巻」六二頁)。』(pp.130)
「あれこれ」とは、宗教的人生観、習慣、性質、家族、婦人への態度、などが挙げられている。
二人の会話は多岐にわたっているが、宗教論が真剣で面白い。
『話が信仰問題に及んで、トルストイにクリスチャンだというが、と問われて、薦花はこう答えている。「余は最広義最真義に於ての基督教徒也と自信す、余は人類の最大恩人として三人を数ふ、 基督、釈迦、孔子也、而して此内尤も高く昇れるを基督とす、基督によつて神顕はれぬ、基督を信ずるとは基督に顕はれたる神を信ずる也、神を信ずるとは神の聖旨を純粋に行ふ事也、儀文空礼 他を排して、独り主よ主よと呼ぶ所謂基督教は生の知らざる所也(後略)」。蔵花はトルストイとほとんど同じようなキリスト教理解を語ったわけであるが、それに対し相手は、「基督教徒多く基督を神化(神に祭り上ぐ)、基督の偶像化は余の好まざる所也(五〇七夏)、と答えたという。』(pp.132)
トルストイは、敬虔なキリスト教信者だったが、教会の権威や偶像化は嫌っていた。自身での愛の実践を好んで進めていた。
文学論や芸術論についても、毅然としたことを述べあっている。「濫りに書かずに、言いたいことがあるときのみ、四方八方から見て自分特有の発見があったときのみ書くべき。自身の作では、宗教、哲学、社会的な著作のみに意味があった」と、トルストイは言っている。
トルストイと過ごした5日間は、蘆花にとって衝撃的だった。一緒に水遊びをした川での経験を「自分にとっては、洗礼だった」と述べ、帰還については、理由をはっきりと述べている。
『大人まで加わりトルストイ家はいわば家族総がかりで引き留めたのに、彼は半ば意固地になったように辞去しているのである。予定を早めての帰国の主たる理由は、それよりは、トルストイに会って、目から鱗が落ちたようなところがあり、いわば開眼し進むべき道が見えたためであったろうと思われるのである。』(pp.146)
さらに続けて、『彼はこの帰朝時のインタビューにおいて、「私は数日の間翁の家に止まつて非常に楽しい生活を送り、大変留めて呉れたけれど、一年居ても同じことだと思いましたから、名残を惜んで六「七」月五日に翁の家を辞して帰りました」、こう語っているのである。また、後年「ヤスナヤ・ポリヤナの回顧」には
何よりも聖書の「爾は我に従へ」の一句に触発され、「然だ、何程真面目でも、模倣では駄目。人間は自己を創作しなければならぬ。トルストイをしてトルストイの行く道を行かしめよ。私には私の道がなければならぬ。私の帰意はここに決した。」』(pp.146)
蘆花の旅行は1906年の3月から8月だった。そして、その年の12月には、④を発行した。トルストイとの邂逅だけについて475ページを費やしている。
蘆花は、2年後のトルストイ生誕80周年祭りに長文を寄稿、更にトルストイ没後に夫人宛に長文を送った。
粕谷(つまり、現在の芦花公園の地)での半農生活については、次のように書かれている。
『薦花は帰朝して間もなく、明治三十九年八月に、青山高樹町に居を定めたが、十二月に『順礼紀行』を出し、翌四十年二月に、千歳村粕谷へ移り住み、彼の言う「半農」、「美的百姓」の生活へ入っている。トルストイを訪問したとき彼はほとんど開口一番農業を勧められ、また別れに際してのトルストイの最後の言葉も、最適境遇は「農的生活」であったし、いわば耳にたこができるほど営農を説かれたので、さっそくその実行に、本格的なトルストイ主義の実践に入ったのであった。』(pp.150)
この生活については「みみずのたはこと」に詳しいが、当時の粕谷については次のようにある。
『現在の粕谷町は家々がびっしり立ち並び、都心まで電車で四、五十分と交通の便利な町であるが、当時は東京の郊外の全くの田舎で、まだ新宿から電車も通っていない、戸数二十五にすぎないごく小さい不便なだったのである。そこに彼は、一反五畝の土地と、壊れかけた十五坪の草葺きのあばら屋を買い求め、それまでの借家住まいを清算して、はじめて地主的生活に入ったのだった。』(pp.191)
これで概要が分かったので、各論に移る前に、トルストイの晩年について⑤を振り返る。

本のカバーには、その全容が短く示されている。
『月あかりもない闇の夜、前庭に立った老トルストイは、生まれ育った屋敷を長いこと見上げていた。やがて身をかがめて土に口づける と、彼は立ちあがった。いっさいを棄てて、 いまこそ旅立つのだ一一。
1910年11月、トルストイは旅の途次、寒村の駅長官舎で息絶えた。82歳の文豪を流浪へと駆りたてたものは何だったのか。 最晩年の謎にみちた日々を、トルストイ夫妻、娘、高弟、秘書、主治医、それぞれの視 点から浮かびあがらせる。』(カバーの内面)
秘書や主治医や友人の書簡が主だが、トルストイ自身のものが数通示されている。1910年には、いち労働者宛に、このように書き出している。
『どうやら二つの問題があなたの心を悩ましているようですね。神ー神とは何か?ーということ、人間の魂の本質についてです。あなたはまた、神と人間との関係について間い、死後の生命についてあれこわ考えていられるらしい。
最初の疑間を取りあげてみましょう。神とは何か、そして神はどのように人間と関わっているのか?
聖書には、いかに神が天地を創造し、いかに神の民と関わって、報償と罰を配分されるかについて、たくさんのことが書いてあります 。これはばかげたことです 。そんなものはぜんぶ忘れておしまいなさい。神は万物の始原、 われわれの存在の原質であり、われわれのなかの生命と考えられるもの、〈愛〉によってわれわれに明らかにされるものです。(だから、われわれは「神は愛なり」というのです)。
しか し、もう一度言いますが、神が世界と人類とを創り、誰であろうと神に従わぬ者を罰する、な どというお説教はどうか忘れてください。あなた自身の生命を新しく考えなおすためには、そのことを頭から拭い去らなければなりません。』(pp.33)
これは、彼のキリスト教に対する基本的な態度なのだが、このことが、更に延々と長文でつづられている。
そして、この手紙の終盤には死について、このように書かれている。
『あなたはまた―誰もがそうであるように―死後の生命について知りたがっていられる。 私の言うことを理解するためには、以下のことによくよく注意してください。 死すべき人間にとっては(つまり、肉体にとってのみ)時間は存在する。すなわち時刻、日、月、 年は過ぎてゆくのです。また、肉体にとってのみ、物質界―見ることができ、手で触ることができるもの―も存在するのです。大小、硬軟、永続的あるいは非永続的、といった性質のものです。しかし霊魂には時間はありません。それはたんに人間の体内に住んでいるだけです。七十年前に〈私〉と呼んだものは、現在私が〈私〉と呼ぶものと同じです。また、霊魂は物質的な属性を持ちません。 私がどこにいようとも、私の霊魂に何が起ころうとも、私が言う〈私〉は同じものであり、つねに非物質的です。このょうに、時間は肉体にとってのみ存在します。霊魂にとっては、時間も場所も物質界も実体を持ちません。』(pp.34)
さらに続けて、『われわれのなかの霊魂は肉体が死んでも死なない、しかし、霊魂は死ぬはずがないことはわかっていても、それが将来どうなるか、またどこへ行くのかについては、われわれは知ることができない、というのが私の考えです。』(pp.35)
④については、すでに①の中で概要は述べた。トルストイに会いに行くためだけの旅行記になっている。この書には、多くの写真が添付されている。圧巻は、当時のエルサレムの360度のパノラマ写真だ。(pp.65)多くの記念物の位置関係が分かるのだが、遠景なので詳細の形は分からない。
冒頭の文章(まえがきにあたる)、次のように始まっている。
『今年三月の初、ある日伊香保の山に雲を踏みて赤城のタ藁を眺めし時、不図基督の足跡を聖地に踏みて見たく、且トルストイ翁の顔見たくなり、山を下りて、用意も勿々順膿の途に上りぬ。
四月四日横演を出で、八月四日敦賀に帰る。百二十日、舟車六千里、電光と往き、石火と復へって、行程を顧れば茫として夢のごとく、すでに印象の六七分を失ひぬ。』(pp.1)
更に、世界地図で旅程を示してから、本文が始まっている。
本文の冒頭は「門出」で、次のように始めている。
『まつはる吾子を縁より蹴落として出家せし昔人さへあるを、さりとは贅沢なる巡礼の門出よ。父、母、姉、妻、甥、姪と共に「主の祈」をなし、賛美歌「朝日はのぼりて世を照らせり」を歌ひて、・・・』(pp.1)
トルストイ家訪問については、『風采は写真版にて見飽き、思想は数多き著書にて大要を領す。別に用事はなけれども、唯何となく顔見たくてはるばる東より旅し来りし余は、今トルストイ翁の清居を驚かさむどす。』(pp.282)
肝心の農業生活につては、あまり詳しくは書かれていない。
『日本の政況、農と商工の比例を問い、「土を耕し他の力に頼らずして生活する者が国の力なり」とその持論を、・・・(中略)終に余に向かひて「君は農業によって生活するを得ざるや」、と問ひぬ。余は、「農業は最も好む所に候。今は尺寸の土も有ざれども、行々は少なくも半農の生活をする心算に候」と答ふ。』(pp.302)
蘆花が「自らの洗礼」とした川での水浴については、何度も繰り返し、詳しく述べている。一人だけのこともあり、夫人が参加したこともあるようだ。トルストイは当時78歳、夏とはいえ寒そうだ。

最後に、②と③について記す。
当初は、これがトルストイ訪問記だと思い読んでしまった。しかし、エルサレムまでの旅程は同じでも、それからイタリア(ナポリが主)経由でロンドンに行っている。気が付いたのは、2巻を読み終えた後で、トルストイ訪問は1906年で、この夫婦での旅行は1919年だった。間には13年間あり、間には第1次世界大戦があった。トルストイが亡くなったのは1910年で、その中間だった。
西廻りの世界一周なのだが、前半が「東の巻」で後半が「西の巻」。全部で1400ページ以上の大作で、旧仮名遣いなので読みにくい。
大正8年当時、蘆花は、50歳、妻の愛は44歳。第一次世界大戦で荒廃した世界を 「暖めたい」 というのが、彼らの旅の動機とある。香港、インド洋、エジプト、エルサレム、イタリア、フランス、スイス、ドイツ、ベルギー、イギリス、アメリカ合衆国を廻っている。 トルストイの思いを引きずっている。
③の冒頭には、旅の目的が書かれている。
『何為に世界を周る7
不得要領を本領とする私でも,世間の常軌に籍らねば身動きは出来ぬ。 何為に世界を周る? 族券出願書の ‘目的、の条下に,私は‘職後の慰問と人情覗察、と書いた。火事見舞ですと口上を添へた。私の慰問は雨刃だし,人情覗察も月並だが嘘ではない。然しそれでは何となくぎごちない。』(pp.14)
云うわけである。気楽そうでもあり、重荷をしょってでもあるような表現になっている。
どこの土地についても詳しく述べているのだが、「エルサレム」は特別だった。題名からして「屋上日記」とある。「耶蘇」の言葉を引用しているのだ。冒頭はこうであり、戦争の記憶が生々しい。
東の巻はここまでで、イタリアからは西の巻になっている。どうやら彼の間隔では、世界はエルサレムが中心らしい。(そのようなことは、どこにも書かれていないと思う)
②の「西の巻」は、内容的には面白かった。
私が、熟読したのは「ナポリ」そこだけでも30ページ近くある。最初の文章は、こうなっている。
『七月十四日。私共が落ちついたHotel Continentalは, 日本人泊りつけの宿であつた。日本人泊りつけの宿には,日本人 馴染の案丙者があつて,私共が泊ると翌朝早連やつて来た。 Antonioと云ふ五十男。出した信用帖には,多くの日本字が書かれてある。皆好い肝判を輿へて居る。私共は,四五日休息し て後,案内を頼む事にする。』(pp.638)
彼らは余裕綽綽なのだが、戦争直後なのに、なぜこうも落ち着いているのかが疑問になる。
『私共のバルコニイから、下の往来が さまざまの見物を私共に與へる。朝早く馬糞などちらばつてる下の通りをよく女が箒で掃き済めて居る。戦地の羅災者に生活の便を得さす為に 政府が各地に分けて. かかる仕事をもさすと云ふ事を後で聞いた。下が海水浴揚なので,それ等を黨に朝からパン売り菓子売がダマスコのパン売りを思はせて立売りする。何とか、フレスコオ、ト云ふ。‘焼き立てのパン、と謂ふのだ。』(pp.641)
そういえば、現在でもスペインでは都市の掃除に多くのひとを国費で雇っている。100年たっても変わらない風景なのか。
1週間後にカプリ島に渡っている。私は、国際会議でカプリ島に1週間滞在したので、おおいに懐かしい。
『力ブリの島は人口約八千,漁と葡萄つくり,それからお客相手で喜らして居る。 私共は上陸すると,Cable carに乗って,葡萄や柑橋の茂 つた傾斜をずうとCapri の本邑に上った。店があり,ホテルがあり,別蟹がある。 Aは私共をーの静かなホテルに導いた。其慮で午餐を食 べる。江の島あたりに遊んで居る気もち。特に魚を注文したら, 力サゴ見たやうなものの一皿をつけた。此慮の白,赤葡萄酒は名高いもの ものさうな。二重の酔を恐れて,私共は飲まなかった。』(pp.659)
私が滞在したほぼ100年後も、全く同じような雰囲気に思える。観光地としての管理が行き届いているのだろう。しかし、江ノ島を引き合いに出すとは、恐れ入る。当時の日本人は、今よりはよほど高慢だったのだろう。日本は、当時は戦勝国であり、現在は敗戦国という違いなのだろうか。
『日ざかりの日は熟し、直く,其慮のやに眼には見えても可なりの上りになるので, 私共はTiberiusの別荘跡も見に往く事をやめた。Aは別荘の間の狭い路を先に立って,私共を Augustus Villの公園に導いた。それは濁逸人の有であつたらしく崖の端近く腰掛があって,其慮からcapri 島の 南面の海が望まれた。遙か下の崖に白い波が寄せて居る。海は眼がさめるやうな純縁の色をして居る 。』(pp.660)
日帰りで、滞在時間が短く、多くが語られていないのは残念だが、雰囲気は伝わってくる。
ロンドンの記述も興味をそそった。書き出しはこうなっている。
『英吉利が私共に提供した住居は,私共の心に適ふものであつた。倫敦の西山の手,Hyde ParkやKensington Garden の南側を通るKensington Roadの片側町の一Blockの頭を占めたKensington Palace Mansions Hotelは,Hotelよりも Mansion即下宿で,決して所謂Fashionableでも乃至備はつ た意味に於ての所謂Comfortable なHtote!でもないが,矢張私共には一番好い家であった。第一に位置が好い。』(pp.1053)
また、エジンバラにも出かけている。ここの描写も、私の経験と大差はない。
『十二月十六日。十時頃からEdinburgh見物に出かける。 Edinburgh は好い。典雅な都だ。丘と平地の按排も面白く,倫敦あたりに見るを得ない高い建築,雅致ある建築が見る眼を悦ばしめる。私共のホテルの前通り、Princes Streetは欧州一の美しい街と誇称される。一方Edinburgh Castle を見上げて,公園ー帯を前に,此慮は電車も通さぬ片側街のまことに 気もちの好い街である。』(pp.1149)
最後の日本帰着の様子は、奥さんの感謝の文章で終わっている。