メタエンジニアの眼シリーズ(75) 銅鐸の謎(その1)
書籍名;「消えた銅鐸族」 [1986]
著者;邦光史郎 発行所;光文社
発行日;1986.4.30
初回作成年月日;H30.8.12 最終改定日;H30.8.21
引用先;文化の文明化のプロセス Implementing
人類最長の歴史を誇った「縄文文明」が、終焉を迎えて金属器の時代に入った。青銅器文化がそれなのだが、日本では銅鐸圏と銅鉾圏が明確に分かれている。銅鉾は使用目的が明らかで、特に文様などもない。しかし、銅鐸には文様があり、使用目的も諸説あり特定されていない。そこで、「銅鐸の謎」に関する多くの歴史著書がある。銅鉾文化は文明化しないが、銅鐸文化は文明化する要素を含んでいる。それを読み進めてみる。
先ずは、気楽なものから始めることにした。著者の邦光史郎氏は、著名な推理作家なのだが歴史推理小説が多い。1986年の発行は微妙であり、副題も「ここまで明らかになった古代史の謎」
とある。要点のみを箇条書きにする
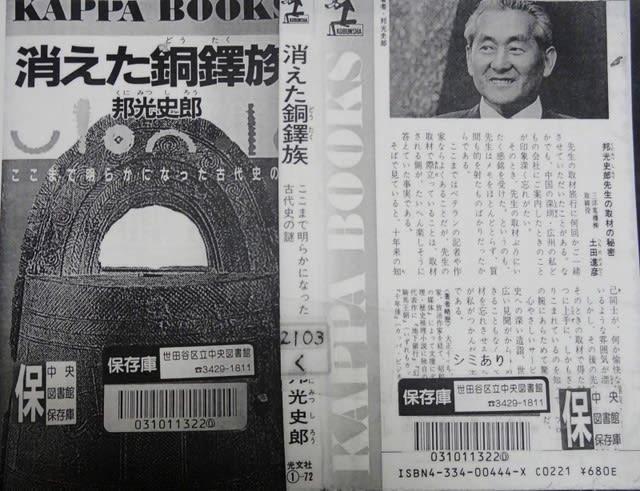
・史書によって隠された敗者の歴史を修復する。
・歴史の欠けた部分、いわば月の裏側を浮かび上がらせる。
・騎馬民族と銅鐸族、海人族は、共通語を持っていなかった。
・日本列島は、各種の種族と文化の吹き溜まりで、ここから先へは太平洋があるので、進めない。
・神武天皇の大和入りに、土蜘蛛と会話ができたのは、おかしい。
・「日本書紀」の世界は、やはり天武王朝を中心としたもの。
・推古女帝以前のことは、人物も事件も定かではない。
・越と出雲は、ツングース族が支配していた。
・赤い眼の大蛇や、體に蔦や檜が生えていたのは、体毛が豊かな北方民族を指す。
・鉄器文化のスキタイに追われて、青銅器文化のツング族が、裏日本に移住した。
・阿倍比羅夫は、斉明4年(658)に越の国の国司になり、津軽半島まで進出した。
・小銅鐸が、朝鮮から北九州に入り、近畿地方に入ってから大型化した。
・銅鐸は、紀元前300年から、紀元後200年まで500年間使われた。
・トンボやチョウの文様は、南方系の文化を表している。
・中国の「編鐘」とは、音色が異なり、全く違う目的の物。
・銅鐸の絵文字を呪文として、何を祈ろうとしたのか。
・文様のある区画だけ打ち抜いたものは、かつて祭祀に使われたことを示すのか。
・銅鐸には、中国の饕餮文のような怪獣は描かれない。
・温厚な、農耕民の文様に限られている。
・銅剣や銅鉾は死者とともに埋葬されるが、銅鐸はそうなっていない。
・なぜ一か所に纏めて埋められたか、非常事態に慌てて隠したのではないだろうか。
・銅鐸は、日本書紀には一切登場しない。
・銅鐸は、彼らの史書であり生活記録であり、タイムカプセルなのかもしれない。(結言)
書籍名;「消えた銅鐸族」 [1986]
著者;邦光史郎 発行所;光文社
発行日;1986.4.30
初回作成年月日;H30.8.12 最終改定日;H30.8.21
引用先;文化の文明化のプロセス Implementing
人類最長の歴史を誇った「縄文文明」が、終焉を迎えて金属器の時代に入った。青銅器文化がそれなのだが、日本では銅鐸圏と銅鉾圏が明確に分かれている。銅鉾は使用目的が明らかで、特に文様などもない。しかし、銅鐸には文様があり、使用目的も諸説あり特定されていない。そこで、「銅鐸の謎」に関する多くの歴史著書がある。銅鉾文化は文明化しないが、銅鐸文化は文明化する要素を含んでいる。それを読み進めてみる。
先ずは、気楽なものから始めることにした。著者の邦光史郎氏は、著名な推理作家なのだが歴史推理小説が多い。1986年の発行は微妙であり、副題も「ここまで明らかになった古代史の謎」
とある。要点のみを箇条書きにする
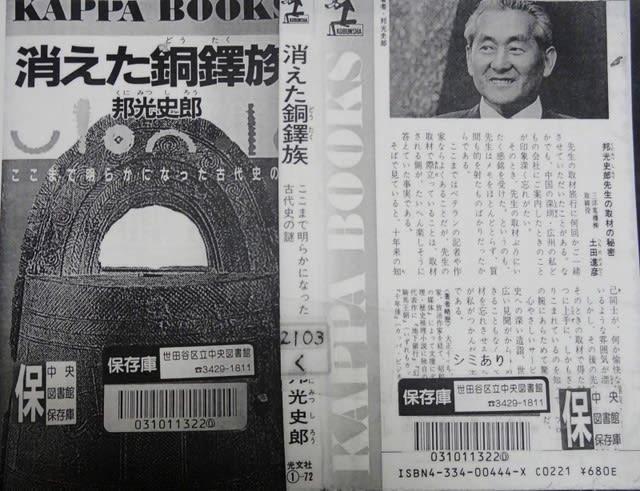
・史書によって隠された敗者の歴史を修復する。
・歴史の欠けた部分、いわば月の裏側を浮かび上がらせる。
・騎馬民族と銅鐸族、海人族は、共通語を持っていなかった。
・日本列島は、各種の種族と文化の吹き溜まりで、ここから先へは太平洋があるので、進めない。
・神武天皇の大和入りに、土蜘蛛と会話ができたのは、おかしい。
・「日本書紀」の世界は、やはり天武王朝を中心としたもの。
・推古女帝以前のことは、人物も事件も定かではない。
・越と出雲は、ツングース族が支配していた。
・赤い眼の大蛇や、體に蔦や檜が生えていたのは、体毛が豊かな北方民族を指す。
・鉄器文化のスキタイに追われて、青銅器文化のツング族が、裏日本に移住した。
・阿倍比羅夫は、斉明4年(658)に越の国の国司になり、津軽半島まで進出した。
・小銅鐸が、朝鮮から北九州に入り、近畿地方に入ってから大型化した。
・銅鐸は、紀元前300年から、紀元後200年まで500年間使われた。
・トンボやチョウの文様は、南方系の文化を表している。
・中国の「編鐘」とは、音色が異なり、全く違う目的の物。
・銅鐸の絵文字を呪文として、何を祈ろうとしたのか。
・文様のある区画だけ打ち抜いたものは、かつて祭祀に使われたことを示すのか。
・銅鐸には、中国の饕餮文のような怪獣は描かれない。
・温厚な、農耕民の文様に限られている。
・銅剣や銅鉾は死者とともに埋葬されるが、銅鐸はそうなっていない。
・なぜ一か所に纏めて埋められたか、非常事態に慌てて隠したのではないだろうか。
・銅鐸は、日本書紀には一切登場しない。
・銅鐸は、彼らの史書であり生活記録であり、タイムカプセルなのかもしれない。(結言)
















