その場考学研究所 メタエンジニアの眼シリーズ(70)
TITLE: 「イギリス精神の源流」 KMB3465
書籍名;イギリス精神の源流[1980]
著者; バジル・ウイリー 発行所;創元社
発行日;1980.5.10
初回作成年月日;H30.7.18 最終改定日;H30.8.1
引用先;文化の文明化のプロセス Implementing
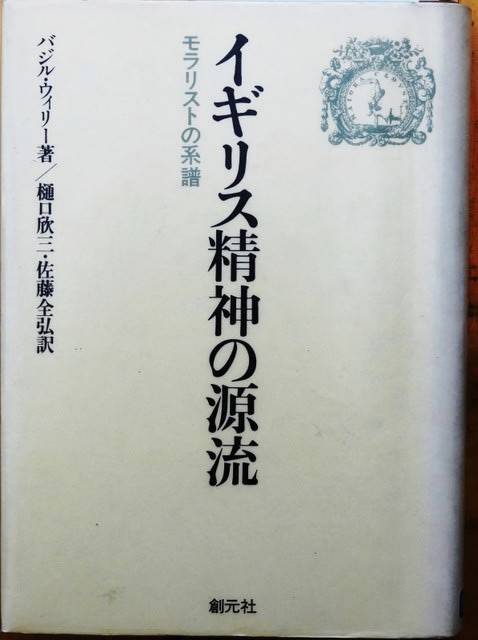
このシリーズはメタエンジニアリングによる、文化の文明化を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
副題は、「モラリストの系譜」とある。著者は、ケンケンブリッジで教鞭をとっていた人で、1964年の退職を前にこれを纏めたと述べている。中身については、
『私はこの本で、いささかも完壁を期してはいないからである。この表題をつかう理由はほかでもない。それがここ約30年間、ケンブリッジ大学英文科優等卒業試験論文の題であり、また、その年月の間、私が当試験について行ってきた講義の題目でもあるからにすぎない。イギリスのモラリストで有名な人たちも、相当多く省かれている。ー講義概要には含まれていた人でさえ、多数抜けている。これらの人たちをいま省いてあるのは、 彼らについては、すでにほかの本で書いたからである。』(pp.ⅰ)としている。巻末には、おびただしい数の「人名索引」が付けられている。
彼は、文学を通じてこの研究を纏めようとしており、『世界のさまざまの出来事や、心理学、経済史、社会学の新しい発見のおかげで、私たちは文学を成長と変化の独自の内面的法則を持つ孤立した現象とは考えないで、人間の生活と思考のほかのすべてのものを養いつちかってきた土壌と風土の産物と考えるのに、慣れてきている。モラリストとは、自分の時代の道徳的価値や態度を明瞭にしようとした著作家、あるいは、当代に行われている価値評価を批判した著作家のことである。』(pp.ⅲ)と、書いている。
いかにもシェークスピアの国といった感じを受ける。彼は、このためには「哲学者の思考は必要ない、文豪の作品をつぶさに調べれば十分に知ることができる」としているのだが、しかし中身を読めば、プラトンもアリストテレスもその著述を表した文筆家としているようであり、まさに彼自身が哲学者のように思えてくる。
『この種の研究に味方する考慮すべき点がいま1 つある。それは、三十年前には今ほど適切ではなかった点である。“自然科学”と同様、“人文系の学問″においても、専門化、部門化、断片化のプロセスは、いまや当時夢想だにもせぬ高度に達している。そこで前にもまして精神の鏡が必要なのである。すなわち、知的世界の全体を一望に収める見渡し、あるいは海図の必要が増してきているのであって、これによって、”全体“を全体としてつかむある感覚が達成され、保持されるのである。』(pp.ⅳ)としている。このことは、メタエンジニアリングに通じるところがある。
全体が19章に分かれており、プラトン、アリストテレスから始まり、十数名の著作から多くの言葉を引用して、彼の批判を加えている。しかし、結論は見当たらない。それは教育者である彼が、キリスト教的観念から抜け出せずに、人間の教育から得られる知識や知恵に疑問を持っているからのように思えた。そのことは、、中半の次の部分で明らかとなった。
『「“自然”に従え」ということを、宗教的ないし倫理的命令として使おうとすれば、重大な困難と暖昧さがつきまとうのであって、その理由は、(ここまでの議論を要約すれば)もし「自 然」という言葉を、人間が介入しなくても自然界で進行している一切事象、という意味にとれば、そんな自然には、 愛、慈愛、正義等々についての教訓はいっさい見出せない―じじつ、いやしくも人間的な意味での道徳性はいっさい見出せぬからである。そしてもし「自然」とは 、人間の本性のことだとするなら、理性に従うべきか、本能に従うべきか、それとも思考・意志・情念の複合全体に従うべきか、が不確かである。理性は迷うし、本能は無秩序となるし、複合全体(「人間本性」一般)は、神学的意味で「堕落して」いないとしても、邪悪であるかもしれないからである。』(pp.85)
ここでの、「「自 然」という言葉を、人間が介入しなくても自然界で進行している一切事象」というとらえ方は、東洋的な思想の中にはない。著者は、人間も自然の一部であるとは、片時も思わないのだろうか。彼は、人間は神が自然を支配するために創造したものであるとの、キリスト教の教義に忠実になっている。
「序」の最後には、こう述べている。『私たちの道徳的伝統で、ギリシア的起源とキリスト教的起源を無視することは、(中略)およそ理にかなったことではない』と。
このことから、彼のプラトンやアリストテレスの主張と、キリスト教の預言者の言葉の間での葛藤が始まっているように思う。彼は、知的活動から得られる一切をとことん信じることができない。かといって、教育者の立場から、それを否定しきることもできない。そして、それは近代文明への懐疑の念に繋がっているように思える。その個所を、いくつか引用する。
『「善」と「正」との関係はどうなのか。“善いということ” と“正しいということ”とは、黒や白と同じように、事物の本性についたものなのか。それとも、それらは、私たち自身の主観的欲求・欲望・偏見とか、私たち自身の属する社会集団や私たちの生きている国家の欲求等とかに相関しているのか。道徳的標準は、絶対的根拠に立って(たとえば、その標準が正しいがゆえに)私たちの忠誠を要求するのか。それとも、道徳性というのは行為の結果の計算のことであって、快または苦の量でかぞえられるのか。』(pp.4)
少なくとも、「道徳的標準」は、歴史上時代や地域で大きく異なるので、絶対的ではありえない。その時々の社会が、適当に都合よく決めているように思う。主な宗教であっても、そのように思う。
『思うに、キリスト教は三つの「神学的」徳(信仰、希望、愛)を、ギリシァ人のいう四つの「元徳」 (知恵、節制、勇気、正義)に付け加えはしたが、また、キリスト教の下す制裁は超自然的であり、その 勧奨はいっそうはげしいけれども、キリスト信徒もギリシア人もともに、聖アウグスチヌスがヴァロについて述べた 評言の感情をわかちもっている。すなわち「彼は〔人間の〕本性のなかに、身体と霊魂の二つのものを見出す。そのうち霊魂のほうがはるかに優秀な部分だと、彼は言いきっている。」じっさい、この通り簡単なことである。人間は 二つのものからなる存在であって、目にみえない世界と目にみえる世界の両方に親近性をもち、二組の衝動のあいだに引きさかれている。その一方は、人間を上なる事物の探求へと促すし、他方は人間を肉の餌や魅力で誘う。道徳的であるとは、私たちの「より高き」自己、「最善の」自己の促しに従うことであり、いいかえると、私たちの本性のうちで身体的部分と対立する理性的・霊的部分に属し、肉よりはむしろ知性に、生成の世界よりはむしろ抽象的な不変の存在界に、変化し過ぎ行く“多”よりはむしろ常住な“一”に属するすべてのものに従うことである。』(pp.8)
『ジュリアン・バンダ氏が述べたように(『聖職者の裏切り』のなかで―この本は三十五年前、T ・S・エリオット氏が私たちみなに読むように言っていた本だが)、「聖職者たち」のおかげで「人類は二千年問悪を行ったが、またよき誉も得たのであって、この矛盾は人類にとって名誉
であり、文明が世界へすべりこんでいった割目をなしたのである。』(pp.8)
過去のキリスト教会の活動を思えば、聖職者が道徳的であるとは、とても思えないのだが。
『現代の聖職者たちはソクラテスに対する有罪判決を是認する。バンダ氏の書いたところによると、「プラトンにとっては、道徳が政治を決定した。マキァヴェリにとっては、政治は道徳から独立していた。モーラス氏にとっては、政治が道徳を決定する。」』(pp.9)
つまり、人類の歴史においては、「道徳」は次第に世俗化していったという事なのだろう。
『ユダヤ人は奇跡を求め、ギリシァ人は知恵を求める。しかし、私たちはキリストを宣べ伝える―しかり、十字架に釘つけられたキリストを。これはユダヤ人にとっては躓きの石であり、ギリシア人にとっては愚かであるが、しかもキリストの召しを耳にした人々にとっては、ユダヤ人にもギリシァ人にもひとしく、キリストは神の力であり、神の知恵である。』(pp.11)
『キリスト教の教えは神学に依拠するに対し、ギリシァ人の知恵は純道徳的だ、という意見はどうだろうか。プラトンにもアリストテレスにも、その道徳の教えは、究めていけば神の観念
を中心としていることを示す個所がみつかる。』(pp.12)
本当にそうなのだろうか、具体例は示されていない。
『『エウデモス倫理学』においては(この本は「ニコマコス倫理学」より古いとイエーガーからわかるが)、神は宇宙における第一起動者であるばかりでなく、魂においても第一起動者である。神は人間の一切の道徳的欣求精進の目的である。』(pp.14)
著者は、キリスト教の教えとギリシア人の知恵の間で葛藤して、何とか共通性を見出そうとしているように思われる。
『教育の目的、あらゆる高貴なる生の目標は、プラトンにとっては、変化し移りゆく現象の影を超え出て、魂が実在を直接しかと見る、永遠の燦然たる白光に入ることである。周知の例は、『国家』の第七巻にある“洞窟"の比喰である―人々は洞窟に住んでいて、光に背を向けており、壁にうつる影の動きを見て、それを本物とまちがえている。』(pp.17)
『プラトンの高き精神性、アリストテレスの謹厳な知恵―これらのものは神の眼には愚かなのであろうか。聖パウロは(フッカーの句をつかえば)「信仰において熟達する道は、知恵・分別において未熟なることである」と教えているのか。ラグビーのトマス・アーノルド が言ったことがある、「ラグビー校の少年たちは、大学者になる必要はない、しかし、キリスト教的紳士になることは、おおいに必要である。」しかも、アーノルドは最善をつくして学者を育てたし、またケンブリッジでは―学問をするところならどこでも同じだが―文化教養の追求、すなわち何らかの形でのこの世の知恵の探求こそ、私たちの努力の理念であり、存在理由であると思われる。それなら、聖パウロの評価では、私たちは誤った道についているのか。』(pp.19)
『聖パウロは、その回心の新しい洞察にとらえられ、熱意にあふれで、アリストテレスができそこないだとしてあきらめたまさにその人に対する救済を語るのである。』(pp.23)
『特定の時代に特定な人によって、歴史の中でなされた啓示というキリスト教的観念と、「適当な訓練をうけた個人には、つねに開かれている」無時間的な不変の真理というギリシア的観念の違いである。』(pp.27)
『アリストテレスは、知性の徳と道徳の徳のあいだの区別を提示している。道徳的生を神的なイデアの把握として表し、この把握はその必然的結果として、イデアへ近づこうとする努力を伴うと述べるかわりに、今やアリストテレスは―後述のように、それまでの立場をすっかり放棄することはしないで―私たちが「性格」とよぶ思考、意志、情念の複合体に注意を向ける。そして、人間が人間本性の内的形相原理を実現することが道徳性だと考える。こうして アリストテレスは、道徳性を宇宙の運動全体と調和させるのである。』(pp.36)
『“徳”を“知性的”と“道徳的”とに分ける区分に出くわす。この区分は、さきに私が論じた他の区分、すなわち「理論的」知識と「実践的」知識とのあいだの区分と合致している。道徳的な徳は、「性格」の徳である。だから、「人の性格について語るにあたっては、彼は賢いとか、理解力があるとか〔知的な徳〕とはいわずに、彼はやさしい、穏和だとかいうのである。』(pp.60)
『人間が文明技術によって“自然"を十分に馴致し、もはやまったく自然の言いなりにならぬと感じるようになると古い迷信的恐怖のかわりに、新たにいっそう情緒的な態度が生じる―失われた楽園、失われた家郷、失われた親に対するノスタルジアの感情が。文明があまりにも都市的となり、あまりにもその土に下した根から離れると、いつでもきまって、「原始主義」の祭儀があらわれてくる。』(pp.90)
『十九世紀には、産業主義の恐怖から起るその反動として、おおいに権威を増し加えたし、D・H・ ローレンスにおいて、新しい力を得た。ローレンスは近代文明を目して、純粋で美しい世界の顔に人間がつけた見るも無惨な汚れと見て、一切の不幸と禍の根源は、知的精神の異常発達にあるとした。―精神も、妖婦と同様、命の生血を貧り吸ったのだった。』(pp.90)
これらの文章から「イギリス人の精神の源流」をたどると、道徳性はキリスト教とも、ギリシャ哲学ともい一致せず、ましてや近代文明とは相いれないという結論に達してしまったように思える。そこには、キリスト教という一神教の影響下にある西欧的な考え方の行き詰まりを感じる。東洋的な自然観と多神教の考え方からは、このような葛藤は生まれて来ない。
TITLE: 「イギリス精神の源流」 KMB3465
書籍名;イギリス精神の源流[1980]
著者; バジル・ウイリー 発行所;創元社
発行日;1980.5.10
初回作成年月日;H30.7.18 最終改定日;H30.8.1
引用先;文化の文明化のプロセス Implementing
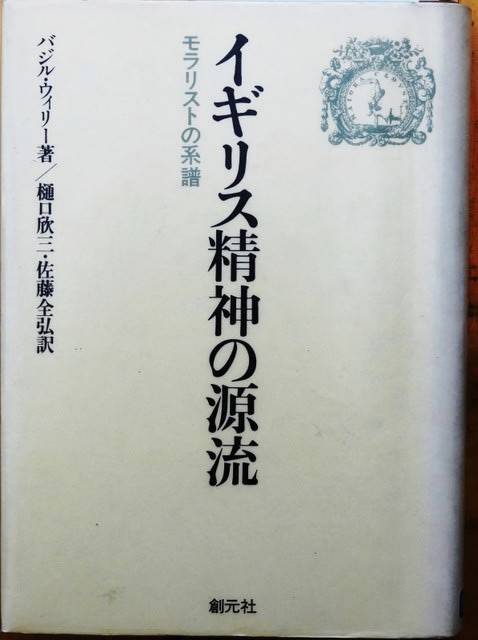
このシリーズはメタエンジニアリングによる、文化の文明化を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
副題は、「モラリストの系譜」とある。著者は、ケンケンブリッジで教鞭をとっていた人で、1964年の退職を前にこれを纏めたと述べている。中身については、
『私はこの本で、いささかも完壁を期してはいないからである。この表題をつかう理由はほかでもない。それがここ約30年間、ケンブリッジ大学英文科優等卒業試験論文の題であり、また、その年月の間、私が当試験について行ってきた講義の題目でもあるからにすぎない。イギリスのモラリストで有名な人たちも、相当多く省かれている。ー講義概要には含まれていた人でさえ、多数抜けている。これらの人たちをいま省いてあるのは、 彼らについては、すでにほかの本で書いたからである。』(pp.ⅰ)としている。巻末には、おびただしい数の「人名索引」が付けられている。
彼は、文学を通じてこの研究を纏めようとしており、『世界のさまざまの出来事や、心理学、経済史、社会学の新しい発見のおかげで、私たちは文学を成長と変化の独自の内面的法則を持つ孤立した現象とは考えないで、人間の生活と思考のほかのすべてのものを養いつちかってきた土壌と風土の産物と考えるのに、慣れてきている。モラリストとは、自分の時代の道徳的価値や態度を明瞭にしようとした著作家、あるいは、当代に行われている価値評価を批判した著作家のことである。』(pp.ⅲ)と、書いている。
いかにもシェークスピアの国といった感じを受ける。彼は、このためには「哲学者の思考は必要ない、文豪の作品をつぶさに調べれば十分に知ることができる」としているのだが、しかし中身を読めば、プラトンもアリストテレスもその著述を表した文筆家としているようであり、まさに彼自身が哲学者のように思えてくる。
『この種の研究に味方する考慮すべき点がいま1 つある。それは、三十年前には今ほど適切ではなかった点である。“自然科学”と同様、“人文系の学問″においても、専門化、部門化、断片化のプロセスは、いまや当時夢想だにもせぬ高度に達している。そこで前にもまして精神の鏡が必要なのである。すなわち、知的世界の全体を一望に収める見渡し、あるいは海図の必要が増してきているのであって、これによって、”全体“を全体としてつかむある感覚が達成され、保持されるのである。』(pp.ⅳ)としている。このことは、メタエンジニアリングに通じるところがある。
全体が19章に分かれており、プラトン、アリストテレスから始まり、十数名の著作から多くの言葉を引用して、彼の批判を加えている。しかし、結論は見当たらない。それは教育者である彼が、キリスト教的観念から抜け出せずに、人間の教育から得られる知識や知恵に疑問を持っているからのように思えた。そのことは、、中半の次の部分で明らかとなった。
『「“自然”に従え」ということを、宗教的ないし倫理的命令として使おうとすれば、重大な困難と暖昧さがつきまとうのであって、その理由は、(ここまでの議論を要約すれば)もし「自 然」という言葉を、人間が介入しなくても自然界で進行している一切事象、という意味にとれば、そんな自然には、 愛、慈愛、正義等々についての教訓はいっさい見出せない―じじつ、いやしくも人間的な意味での道徳性はいっさい見出せぬからである。そしてもし「自然」とは 、人間の本性のことだとするなら、理性に従うべきか、本能に従うべきか、それとも思考・意志・情念の複合全体に従うべきか、が不確かである。理性は迷うし、本能は無秩序となるし、複合全体(「人間本性」一般)は、神学的意味で「堕落して」いないとしても、邪悪であるかもしれないからである。』(pp.85)
ここでの、「「自 然」という言葉を、人間が介入しなくても自然界で進行している一切事象」というとらえ方は、東洋的な思想の中にはない。著者は、人間も自然の一部であるとは、片時も思わないのだろうか。彼は、人間は神が自然を支配するために創造したものであるとの、キリスト教の教義に忠実になっている。
「序」の最後には、こう述べている。『私たちの道徳的伝統で、ギリシア的起源とキリスト教的起源を無視することは、(中略)およそ理にかなったことではない』と。
このことから、彼のプラトンやアリストテレスの主張と、キリスト教の預言者の言葉の間での葛藤が始まっているように思う。彼は、知的活動から得られる一切をとことん信じることができない。かといって、教育者の立場から、それを否定しきることもできない。そして、それは近代文明への懐疑の念に繋がっているように思える。その個所を、いくつか引用する。
『「善」と「正」との関係はどうなのか。“善いということ” と“正しいということ”とは、黒や白と同じように、事物の本性についたものなのか。それとも、それらは、私たち自身の主観的欲求・欲望・偏見とか、私たち自身の属する社会集団や私たちの生きている国家の欲求等とかに相関しているのか。道徳的標準は、絶対的根拠に立って(たとえば、その標準が正しいがゆえに)私たちの忠誠を要求するのか。それとも、道徳性というのは行為の結果の計算のことであって、快または苦の量でかぞえられるのか。』(pp.4)
少なくとも、「道徳的標準」は、歴史上時代や地域で大きく異なるので、絶対的ではありえない。その時々の社会が、適当に都合よく決めているように思う。主な宗教であっても、そのように思う。
『思うに、キリスト教は三つの「神学的」徳(信仰、希望、愛)を、ギリシァ人のいう四つの「元徳」 (知恵、節制、勇気、正義)に付け加えはしたが、また、キリスト教の下す制裁は超自然的であり、その 勧奨はいっそうはげしいけれども、キリスト信徒もギリシア人もともに、聖アウグスチヌスがヴァロについて述べた 評言の感情をわかちもっている。すなわち「彼は〔人間の〕本性のなかに、身体と霊魂の二つのものを見出す。そのうち霊魂のほうがはるかに優秀な部分だと、彼は言いきっている。」じっさい、この通り簡単なことである。人間は 二つのものからなる存在であって、目にみえない世界と目にみえる世界の両方に親近性をもち、二組の衝動のあいだに引きさかれている。その一方は、人間を上なる事物の探求へと促すし、他方は人間を肉の餌や魅力で誘う。道徳的であるとは、私たちの「より高き」自己、「最善の」自己の促しに従うことであり、いいかえると、私たちの本性のうちで身体的部分と対立する理性的・霊的部分に属し、肉よりはむしろ知性に、生成の世界よりはむしろ抽象的な不変の存在界に、変化し過ぎ行く“多”よりはむしろ常住な“一”に属するすべてのものに従うことである。』(pp.8)
『ジュリアン・バンダ氏が述べたように(『聖職者の裏切り』のなかで―この本は三十五年前、T ・S・エリオット氏が私たちみなに読むように言っていた本だが)、「聖職者たち」のおかげで「人類は二千年問悪を行ったが、またよき誉も得たのであって、この矛盾は人類にとって名誉
であり、文明が世界へすべりこんでいった割目をなしたのである。』(pp.8)
過去のキリスト教会の活動を思えば、聖職者が道徳的であるとは、とても思えないのだが。
『現代の聖職者たちはソクラテスに対する有罪判決を是認する。バンダ氏の書いたところによると、「プラトンにとっては、道徳が政治を決定した。マキァヴェリにとっては、政治は道徳から独立していた。モーラス氏にとっては、政治が道徳を決定する。」』(pp.9)
つまり、人類の歴史においては、「道徳」は次第に世俗化していったという事なのだろう。
『ユダヤ人は奇跡を求め、ギリシァ人は知恵を求める。しかし、私たちはキリストを宣べ伝える―しかり、十字架に釘つけられたキリストを。これはユダヤ人にとっては躓きの石であり、ギリシア人にとっては愚かであるが、しかもキリストの召しを耳にした人々にとっては、ユダヤ人にもギリシァ人にもひとしく、キリストは神の力であり、神の知恵である。』(pp.11)
『キリスト教の教えは神学に依拠するに対し、ギリシァ人の知恵は純道徳的だ、という意見はどうだろうか。プラトンにもアリストテレスにも、その道徳の教えは、究めていけば神の観念
を中心としていることを示す個所がみつかる。』(pp.12)
本当にそうなのだろうか、具体例は示されていない。
『『エウデモス倫理学』においては(この本は「ニコマコス倫理学」より古いとイエーガーからわかるが)、神は宇宙における第一起動者であるばかりでなく、魂においても第一起動者である。神は人間の一切の道徳的欣求精進の目的である。』(pp.14)
著者は、キリスト教の教えとギリシア人の知恵の間で葛藤して、何とか共通性を見出そうとしているように思われる。
『教育の目的、あらゆる高貴なる生の目標は、プラトンにとっては、変化し移りゆく現象の影を超え出て、魂が実在を直接しかと見る、永遠の燦然たる白光に入ることである。周知の例は、『国家』の第七巻にある“洞窟"の比喰である―人々は洞窟に住んでいて、光に背を向けており、壁にうつる影の動きを見て、それを本物とまちがえている。』(pp.17)
『プラトンの高き精神性、アリストテレスの謹厳な知恵―これらのものは神の眼には愚かなのであろうか。聖パウロは(フッカーの句をつかえば)「信仰において熟達する道は、知恵・分別において未熟なることである」と教えているのか。ラグビーのトマス・アーノルド が言ったことがある、「ラグビー校の少年たちは、大学者になる必要はない、しかし、キリスト教的紳士になることは、おおいに必要である。」しかも、アーノルドは最善をつくして学者を育てたし、またケンブリッジでは―学問をするところならどこでも同じだが―文化教養の追求、すなわち何らかの形でのこの世の知恵の探求こそ、私たちの努力の理念であり、存在理由であると思われる。それなら、聖パウロの評価では、私たちは誤った道についているのか。』(pp.19)
『聖パウロは、その回心の新しい洞察にとらえられ、熱意にあふれで、アリストテレスができそこないだとしてあきらめたまさにその人に対する救済を語るのである。』(pp.23)
『特定の時代に特定な人によって、歴史の中でなされた啓示というキリスト教的観念と、「適当な訓練をうけた個人には、つねに開かれている」無時間的な不変の真理というギリシア的観念の違いである。』(pp.27)
『アリストテレスは、知性の徳と道徳の徳のあいだの区別を提示している。道徳的生を神的なイデアの把握として表し、この把握はその必然的結果として、イデアへ近づこうとする努力を伴うと述べるかわりに、今やアリストテレスは―後述のように、それまでの立場をすっかり放棄することはしないで―私たちが「性格」とよぶ思考、意志、情念の複合体に注意を向ける。そして、人間が人間本性の内的形相原理を実現することが道徳性だと考える。こうして アリストテレスは、道徳性を宇宙の運動全体と調和させるのである。』(pp.36)
『“徳”を“知性的”と“道徳的”とに分ける区分に出くわす。この区分は、さきに私が論じた他の区分、すなわち「理論的」知識と「実践的」知識とのあいだの区分と合致している。道徳的な徳は、「性格」の徳である。だから、「人の性格について語るにあたっては、彼は賢いとか、理解力があるとか〔知的な徳〕とはいわずに、彼はやさしい、穏和だとかいうのである。』(pp.60)
『人間が文明技術によって“自然"を十分に馴致し、もはやまったく自然の言いなりにならぬと感じるようになると古い迷信的恐怖のかわりに、新たにいっそう情緒的な態度が生じる―失われた楽園、失われた家郷、失われた親に対するノスタルジアの感情が。文明があまりにも都市的となり、あまりにもその土に下した根から離れると、いつでもきまって、「原始主義」の祭儀があらわれてくる。』(pp.90)
『十九世紀には、産業主義の恐怖から起るその反動として、おおいに権威を増し加えたし、D・H・ ローレンスにおいて、新しい力を得た。ローレンスは近代文明を目して、純粋で美しい世界の顔に人間がつけた見るも無惨な汚れと見て、一切の不幸と禍の根源は、知的精神の異常発達にあるとした。―精神も、妖婦と同様、命の生血を貧り吸ったのだった。』(pp.90)
これらの文章から「イギリス人の精神の源流」をたどると、道徳性はキリスト教とも、ギリシャ哲学ともい一致せず、ましてや近代文明とは相いれないという結論に達してしまったように思える。そこには、キリスト教という一神教の影響下にある西欧的な考え方の行き詰まりを感じる。東洋的な自然観と多神教の考え方からは、このような葛藤は生まれて来ない。









