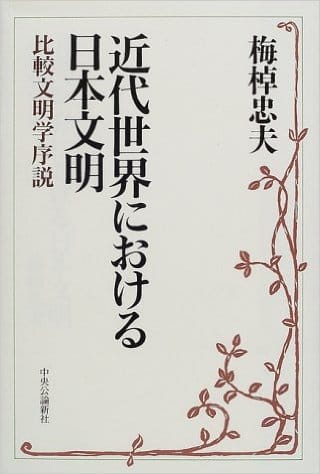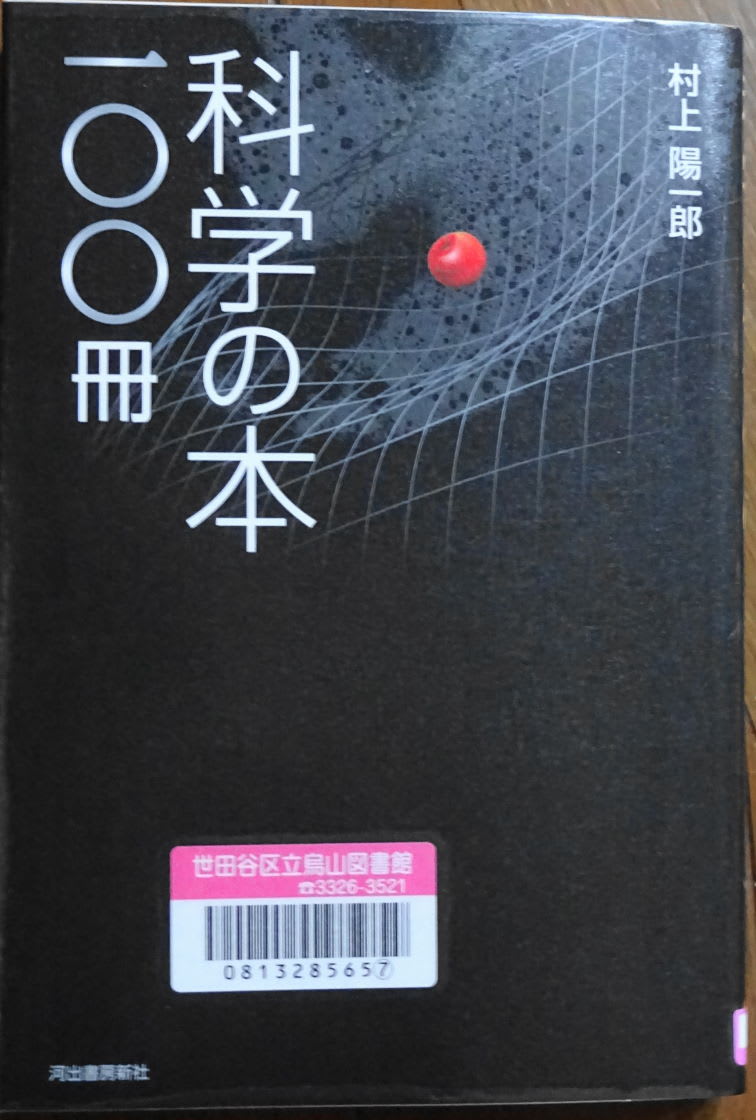ここでは、かつてメタエンジニアリング研究所で行われた研究の一部を紹介してゆきます。
4.懐古(メタヒストリーとしてのアジール)
Wikipediaには「アジール」という項目に次のようにある。
『アジールあるいはアサイラム(独: Asyl、仏: asile、英: asylum)は、歴史的・社会的な概念で、「聖域」「自由領域」「避難所」「無縁所」などとも呼ばれる特殊なエリアのことを意味する。ギリシャ語の「ἄσυλον(侵すことのできない、神聖な場所の意)」を語源とする。具体的には、おおむね「統治権力が及ばない地域」ということになる。現代の法制度の中で近いものを探せば在外公館の内部など「治外法権(が認められた場所)」のようなものである。』
『アジールとされた地域には、教会、神社、仏閣などの宗教的聖地の要素を持つ場所や、市場など複数の権力が入り混じる自由領域・交易場所などがあった。商業都市も、武力を背景とした統治権力に対抗する「自治都市」として強いアジール性が認められた場合がある。単に「統治権力が及ばない地域」というだけではなく、「大きな統治権力と小さな統治権力がせめぎあった結果、大きな統治権力の実効支配が否定されている地域」と理解することもでき、統治権力が大きく統合されていく過程で生じた過渡的な現象ということもできる。』
日本におけるアジール研究は、歴史学者の平泉澄が先鞭をつけた。それを具体的に説明した著書として、網野善彦著「無縁・公界・楽」(藤原書店[1978])がある。
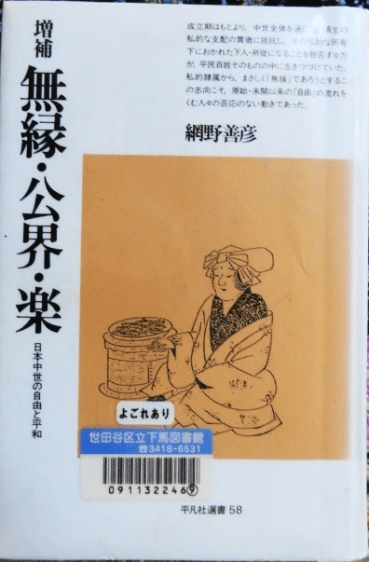
著者の網野善彦は、「無主」「無縁」の原理を担った人々の力こそ、真に歴史を動かしてきた弱者の力であると主張している。通常の歴史が、支配者、支配階級の地縁、血縁などで語られるのとは正反対の見方なのだが、少し考えれば、原始時代から続いているこの集団については、現代のSNSとメタバースやクラウド、仮想通貨などの流行を目にするにつけ、こちらに歴史の力が戻りつつあるようにも思えてくる。
本文は、昔の子供の二つの遊びから始まっている。私も、小学校時代の一時期、この二つの遊びを経験した。書かれているルールは全く同じものだったと記憶している。
『子供のころ、「エンガチヨ」という遊びがあった。突然みんなが私に向かって「エーンガチヨ、エンガチヨ」とはやしたてはじめる。なにかきたないものにさわったか、踏んだかしてしまったと思うが、自分では気がつかない。しかし友だちはみな私から逃げてしまう。私は「エンガチヨ」でめり、私には決して触れてはいけなくなったのだ。だれかに「エンガチヨ」をつけなければ、永久に孤独になってしまいそうなおそれにかりたてられて、私は友だちを追いかけまわす。あとは「鬼ごっこ」と同じである。足の遅いものにおいついて手をふれる。これで私はたすかる。「エンガチヨ」は、その子に移ったのだ。
ところが、この遊びには不思議なおまじないがある。両手の親指と人差指でくさりの輪をつくり、誰かに「エンきーった」といって、そのくさりを切ってもらうと、もう「エンガチヨ」はつかなくなる。みなにそのおまじないをされてどうにもならなくなり、全く困り切った記憶も、私には鮮やかに残っている。』(pp.11-12)
ここで、「エンガチヨ」の「エン」には、二種類の解釈が成り立つ。「縁」と「穢」である。「縁」は魔力に通じている。いずれにせよ、『人間の心と社会の深奥にふれる意味を持っているように思われるのである。』(p.14)とある。
もう一つの遊びは、以下である。これも経験がある。
『もうーつ、私の子供のころ、「スイライカンチヨー」という遊びがさかんであった。これが多分「水雷・艦長」のなまりで、同じ遊びを「海戦」といっている子供たちもいたことは、中学生になってからはじめて知った。ひさしのある帽子を前にかぶるか、赤い帽子をかぶった戦艦(艦長とも大将ともいった)は一人だけで、水雷(帽子を後にかぶるか、白い帽子をかぶる)に負け、駆逐(帽子を横にかぶるか、バンドにハソカチをぶらさげた)に勝つ。駆逐は水雷に勝つ。二手にわかれ「カイセーン」の合図で勝負がはじまる。戦艦は多くの駆逐と一、二の水雷を従え、戦隊を組んで出動する。水雷はたいがい足の速い子がなり、多くは散らばって身をかくし、戦艦のくるのを待ちぶせる。戦艦がつかまれば、これは一人しか いないから、まずは敗北である。海軍にあこがれる子供たちの多かった戦前の遊びであり、ほとんど組中の子供たちが加わって二手に分れ、校庭いっぱいかけまわったのは、いまでも楽しい思い出であるが、この遊びには、双方に「陣」(基地ともいったかもしれない) があった。たいてい大きな木そのもの、あるいはそのまわりに円を画いた場所が「陣」になった。』(p.14)
全く、正確な描写で、当時の小学校の校庭までが思い出される。
さらに続けて、『その木にふれるか、円内にとびこめば、外の勝負には関係なくなり、味方は安全であるが、つかまった敵は捕虜になって、この「陣」につれこまれる。これをたすけるには、外から木につかまっている捕虜にふれればよい。だから捕虜たちは手をつなぎ、なるべく長い列をつくって、必死にたすけを求めた。 また、面白いことに、同じ「艦種」(?)のもの同志がぶつかると「アイチーン」(あいこのなまりか)などといい、敵味方とも勝負に加わる力を失うが 、「陣」に手をふれるか、「大将」(戦艦)その人の身体にさわると、再び戦闘力を回復することができるのである 。』(p.15)
私の記憶でも、帽子の被り方まで含めて寸分たがわないのは、むしろ不思議なくらいだ。もっとも、子供の頃は駆逐艦というものを知らずに「クチク」ではなく「キチク」と云っていたように記憶している。
「外の勝負や戦闘に関係ない場所の存在」、「何かに触れると、戦闘力が復活する」など、このような「縁」や「アジール」に関する遊びは、他の遊びと違って、変わり様がないのかもしれない。これも歴史の不思議だ。著書では、『人間の社会、その歴史に奥底深い根を持っているに違いない。』(p.16)としている。
その後は本論に移り、アジールそのものの具体例が続く。戦国時代の「公界所」は、江の島や各地の寺院に多くあった。信長の「楽市、楽座」も同じ意味を持つ。
「楽」は、仏教用語の「十楽」による。聖衆来迎楽、蓮華初開楽など10種の楽があり極楽浄土を讃えている。
「公界(くかい)」も仏教用語で、道元の「雲堂公界の座禅」と云われるそうだ。「太平記」のなかにも書かれている。
「無縁」も勿論仏教用語で、「原因、条件、対策の無いこと」を意味している。
いずれも「アジール」に繋がり、そして「自由・平和・平等」に通じている。しかし、日本におけるこの種の「自由・平和・平等」は、西欧のそれとは異なっているという。欧州のそれは、王権との闘いによって勝ち取ったものだが、日本の歴史では、『日本の社会の中に、脈々と流れる原始以来の無主、無所有の原思想(原無縁)を、精一杯自覚的・積極的にあらわした「日本的」な表現にほかならない。』(p.129)として、安土桃山時代の堺の街を例に挙げている。
しかし、この様なものは、明治維新以来の西欧化で「寂しく暗い世界」の印象に変わっていった。「公界」は「苦界」に、「無縁」は「無縁仏」になり、江戸文化とは離れていった。だが歴史は巡って、現代で再びSNSなどのより、こちらに歴史の力が戻りつつあるようにも思えてくる。
さらに思いを広げれば、S.ハンチントンの究極の文明の世界、フランシス・フクヤマの歴史の終わりの次、猿の惑星などは、皆この方向に向かっていることを示しているのではないだろうか。
江戸末期に日本を訪れた西欧人の多くは、当時の庶民の生活を見て、その文化的な高さに感銘したという話は多く存在する。その中でも、パリスの通訳として滞在したオランダ人のヒュースケンの言葉は、まさに日本的なアジールを成立させた縄文文化を懐古させるものだ。
『いまや私がいとしさを覚えはじめている国よ。この進歩はほんとうにお前のための文明なのか。この国の人々の質撲な習俗とともに、その飾りけのなさを私は賛美する。この国土のゆたかさを見、いたるところに満ちている子供たちの愉しい笑声を聞き、 そしてどこにも悲惨なものを見いだすことができなかった私は、おお、神よ、この幸福
な情景がいまや終わりを迎えようとしており、西洋の人々が彼らの重大な悪徳をもちこもうとしているように思われてならない』(「ヒュースケン日本日記」青木枝朗訳 岩波文庫)
メタヒストリーという言葉には、色々な解釈が可能になる。小学校の校庭を走り廻った単純な遊びが、縄文文化から伝わる日本独特の文化の一つの表れだったことに、メタ思考の面白さを感じる。
子供時代の、この二つの遊びについて、私の記憶は鮮明なのだが、同世代の友人に聞いたところでは、あまり一般的ではなかったようだ。次ページに結果を示した。
〇 遊んだ経験がある
× 知らなかった
? よく覚えていない
スイライカンチヨー 育った場所 エンガチヨ
X 仙台市 X
O 板橋区 O
O 杉並区 O
X 江東区 O
O 渋谷区 O
O 東京都府中市 O
X 横浜市 X
X 名古屋市 X
X 京都市 ?
X 奈良市 X
X 広島市 ?
なお、エンガチヨは、昔ドリフターズがネタに使っていたので、名前だけの記憶にある人はいたが、実際に遊んだ経験のある人は少なかった。
いずれにしても、かなり地域も時期も限定的だったと思われる。
4.懐古(メタヒストリーとしてのアジール)
Wikipediaには「アジール」という項目に次のようにある。
『アジールあるいはアサイラム(独: Asyl、仏: asile、英: asylum)は、歴史的・社会的な概念で、「聖域」「自由領域」「避難所」「無縁所」などとも呼ばれる特殊なエリアのことを意味する。ギリシャ語の「ἄσυλον(侵すことのできない、神聖な場所の意)」を語源とする。具体的には、おおむね「統治権力が及ばない地域」ということになる。現代の法制度の中で近いものを探せば在外公館の内部など「治外法権(が認められた場所)」のようなものである。』
『アジールとされた地域には、教会、神社、仏閣などの宗教的聖地の要素を持つ場所や、市場など複数の権力が入り混じる自由領域・交易場所などがあった。商業都市も、武力を背景とした統治権力に対抗する「自治都市」として強いアジール性が認められた場合がある。単に「統治権力が及ばない地域」というだけではなく、「大きな統治権力と小さな統治権力がせめぎあった結果、大きな統治権力の実効支配が否定されている地域」と理解することもでき、統治権力が大きく統合されていく過程で生じた過渡的な現象ということもできる。』
日本におけるアジール研究は、歴史学者の平泉澄が先鞭をつけた。それを具体的に説明した著書として、網野善彦著「無縁・公界・楽」(藤原書店[1978])がある。
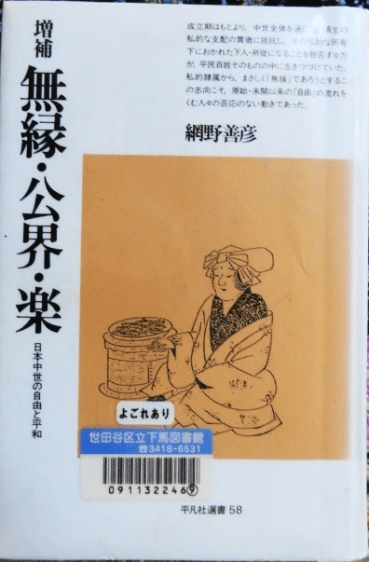
著者の網野善彦は、「無主」「無縁」の原理を担った人々の力こそ、真に歴史を動かしてきた弱者の力であると主張している。通常の歴史が、支配者、支配階級の地縁、血縁などで語られるのとは正反対の見方なのだが、少し考えれば、原始時代から続いているこの集団については、現代のSNSとメタバースやクラウド、仮想通貨などの流行を目にするにつけ、こちらに歴史の力が戻りつつあるようにも思えてくる。
本文は、昔の子供の二つの遊びから始まっている。私も、小学校時代の一時期、この二つの遊びを経験した。書かれているルールは全く同じものだったと記憶している。
『子供のころ、「エンガチヨ」という遊びがあった。突然みんなが私に向かって「エーンガチヨ、エンガチヨ」とはやしたてはじめる。なにかきたないものにさわったか、踏んだかしてしまったと思うが、自分では気がつかない。しかし友だちはみな私から逃げてしまう。私は「エンガチヨ」でめり、私には決して触れてはいけなくなったのだ。だれかに「エンガチヨ」をつけなければ、永久に孤独になってしまいそうなおそれにかりたてられて、私は友だちを追いかけまわす。あとは「鬼ごっこ」と同じである。足の遅いものにおいついて手をふれる。これで私はたすかる。「エンガチヨ」は、その子に移ったのだ。
ところが、この遊びには不思議なおまじないがある。両手の親指と人差指でくさりの輪をつくり、誰かに「エンきーった」といって、そのくさりを切ってもらうと、もう「エンガチヨ」はつかなくなる。みなにそのおまじないをされてどうにもならなくなり、全く困り切った記憶も、私には鮮やかに残っている。』(pp.11-12)
ここで、「エンガチヨ」の「エン」には、二種類の解釈が成り立つ。「縁」と「穢」である。「縁」は魔力に通じている。いずれにせよ、『人間の心と社会の深奥にふれる意味を持っているように思われるのである。』(p.14)とある。
もう一つの遊びは、以下である。これも経験がある。
『もうーつ、私の子供のころ、「スイライカンチヨー」という遊びがさかんであった。これが多分「水雷・艦長」のなまりで、同じ遊びを「海戦」といっている子供たちもいたことは、中学生になってからはじめて知った。ひさしのある帽子を前にかぶるか、赤い帽子をかぶった戦艦(艦長とも大将ともいった)は一人だけで、水雷(帽子を後にかぶるか、白い帽子をかぶる)に負け、駆逐(帽子を横にかぶるか、バンドにハソカチをぶらさげた)に勝つ。駆逐は水雷に勝つ。二手にわかれ「カイセーン」の合図で勝負がはじまる。戦艦は多くの駆逐と一、二の水雷を従え、戦隊を組んで出動する。水雷はたいがい足の速い子がなり、多くは散らばって身をかくし、戦艦のくるのを待ちぶせる。戦艦がつかまれば、これは一人しか いないから、まずは敗北である。海軍にあこがれる子供たちの多かった戦前の遊びであり、ほとんど組中の子供たちが加わって二手に分れ、校庭いっぱいかけまわったのは、いまでも楽しい思い出であるが、この遊びには、双方に「陣」(基地ともいったかもしれない) があった。たいてい大きな木そのもの、あるいはそのまわりに円を画いた場所が「陣」になった。』(p.14)
全く、正確な描写で、当時の小学校の校庭までが思い出される。
さらに続けて、『その木にふれるか、円内にとびこめば、外の勝負には関係なくなり、味方は安全であるが、つかまった敵は捕虜になって、この「陣」につれこまれる。これをたすけるには、外から木につかまっている捕虜にふれればよい。だから捕虜たちは手をつなぎ、なるべく長い列をつくって、必死にたすけを求めた。 また、面白いことに、同じ「艦種」(?)のもの同志がぶつかると「アイチーン」(あいこのなまりか)などといい、敵味方とも勝負に加わる力を失うが 、「陣」に手をふれるか、「大将」(戦艦)その人の身体にさわると、再び戦闘力を回復することができるのである 。』(p.15)
私の記憶でも、帽子の被り方まで含めて寸分たがわないのは、むしろ不思議なくらいだ。もっとも、子供の頃は駆逐艦というものを知らずに「クチク」ではなく「キチク」と云っていたように記憶している。
「外の勝負や戦闘に関係ない場所の存在」、「何かに触れると、戦闘力が復活する」など、このような「縁」や「アジール」に関する遊びは、他の遊びと違って、変わり様がないのかもしれない。これも歴史の不思議だ。著書では、『人間の社会、その歴史に奥底深い根を持っているに違いない。』(p.16)としている。
その後は本論に移り、アジールそのものの具体例が続く。戦国時代の「公界所」は、江の島や各地の寺院に多くあった。信長の「楽市、楽座」も同じ意味を持つ。
「楽」は、仏教用語の「十楽」による。聖衆来迎楽、蓮華初開楽など10種の楽があり極楽浄土を讃えている。
「公界(くかい)」も仏教用語で、道元の「雲堂公界の座禅」と云われるそうだ。「太平記」のなかにも書かれている。
「無縁」も勿論仏教用語で、「原因、条件、対策の無いこと」を意味している。
いずれも「アジール」に繋がり、そして「自由・平和・平等」に通じている。しかし、日本におけるこの種の「自由・平和・平等」は、西欧のそれとは異なっているという。欧州のそれは、王権との闘いによって勝ち取ったものだが、日本の歴史では、『日本の社会の中に、脈々と流れる原始以来の無主、無所有の原思想(原無縁)を、精一杯自覚的・積極的にあらわした「日本的」な表現にほかならない。』(p.129)として、安土桃山時代の堺の街を例に挙げている。
しかし、この様なものは、明治維新以来の西欧化で「寂しく暗い世界」の印象に変わっていった。「公界」は「苦界」に、「無縁」は「無縁仏」になり、江戸文化とは離れていった。だが歴史は巡って、現代で再びSNSなどのより、こちらに歴史の力が戻りつつあるようにも思えてくる。
さらに思いを広げれば、S.ハンチントンの究極の文明の世界、フランシス・フクヤマの歴史の終わりの次、猿の惑星などは、皆この方向に向かっていることを示しているのではないだろうか。
江戸末期に日本を訪れた西欧人の多くは、当時の庶民の生活を見て、その文化的な高さに感銘したという話は多く存在する。その中でも、パリスの通訳として滞在したオランダ人のヒュースケンの言葉は、まさに日本的なアジールを成立させた縄文文化を懐古させるものだ。
『いまや私がいとしさを覚えはじめている国よ。この進歩はほんとうにお前のための文明なのか。この国の人々の質撲な習俗とともに、その飾りけのなさを私は賛美する。この国土のゆたかさを見、いたるところに満ちている子供たちの愉しい笑声を聞き、 そしてどこにも悲惨なものを見いだすことができなかった私は、おお、神よ、この幸福
な情景がいまや終わりを迎えようとしており、西洋の人々が彼らの重大な悪徳をもちこもうとしているように思われてならない』(「ヒュースケン日本日記」青木枝朗訳 岩波文庫)
メタヒストリーという言葉には、色々な解釈が可能になる。小学校の校庭を走り廻った単純な遊びが、縄文文化から伝わる日本独特の文化の一つの表れだったことに、メタ思考の面白さを感じる。
子供時代の、この二つの遊びについて、私の記憶は鮮明なのだが、同世代の友人に聞いたところでは、あまり一般的ではなかったようだ。次ページに結果を示した。
〇 遊んだ経験がある
× 知らなかった
? よく覚えていない
スイライカンチヨー 育った場所 エンガチヨ
X 仙台市 X
O 板橋区 O
O 杉並区 O
X 江東区 O
O 渋谷区 O
O 東京都府中市 O
X 横浜市 X
X 名古屋市 X
X 京都市 ?
X 奈良市 X
X 広島市 ?
なお、エンガチヨは、昔ドリフターズがネタに使っていたので、名前だけの記憶にある人はいたが、実際に遊んだ経験のある人は少なかった。
いずれにしても、かなり地域も時期も限定的だったと思われる。