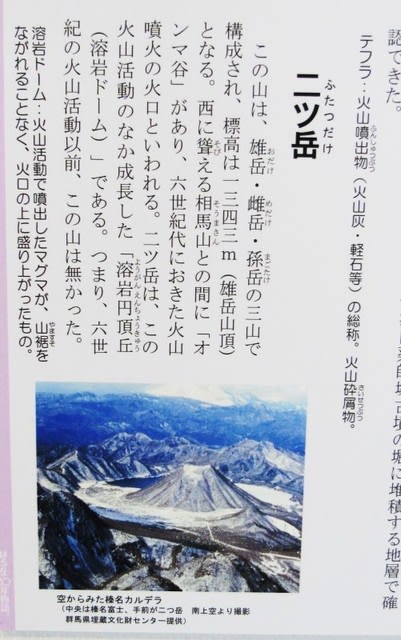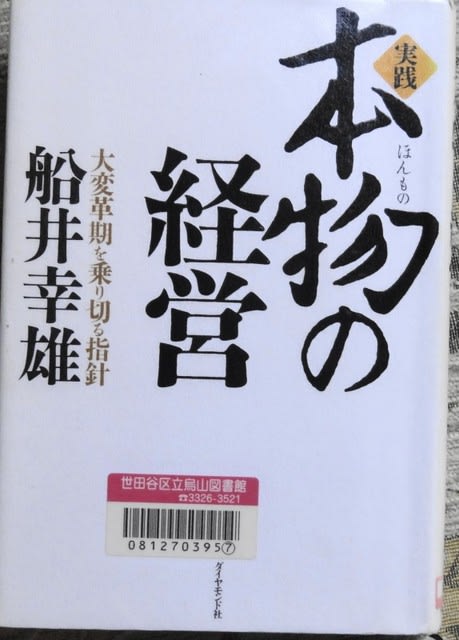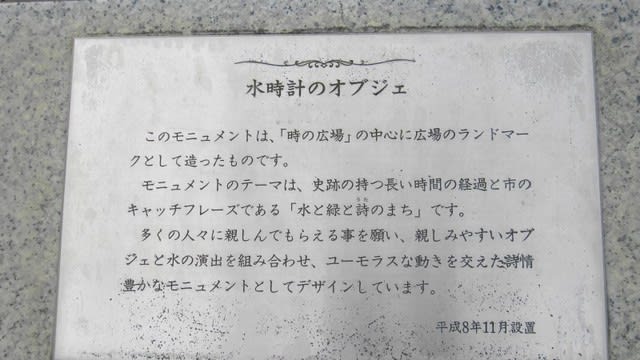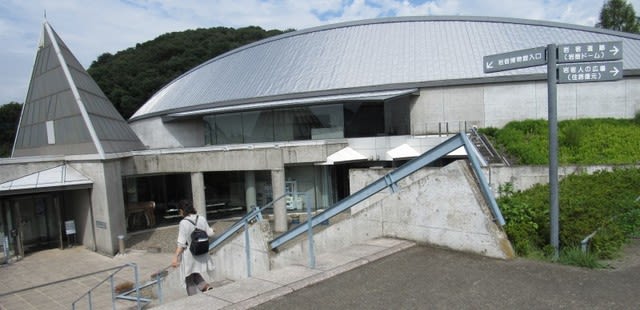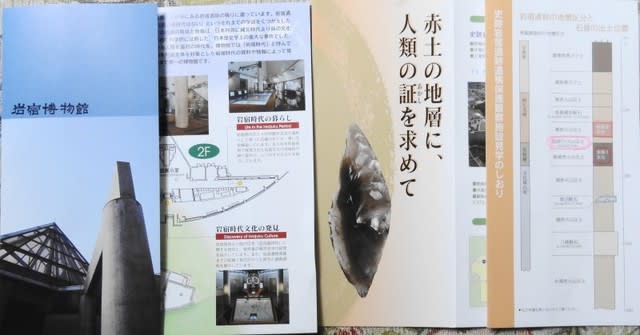メタエンジニアの眼シリーズ(95)
TITLE: 縄文革命と日本人の未来
書名; 「縄文文化が日本人の未来を拓く」 [2018]
著者;小林達雄 発行所;徳間書店
発行日;2018.4.30
初回作成日;H30.10.29 最終改定日;H30.
引用先;文化の文明化のプロセス Implementing
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
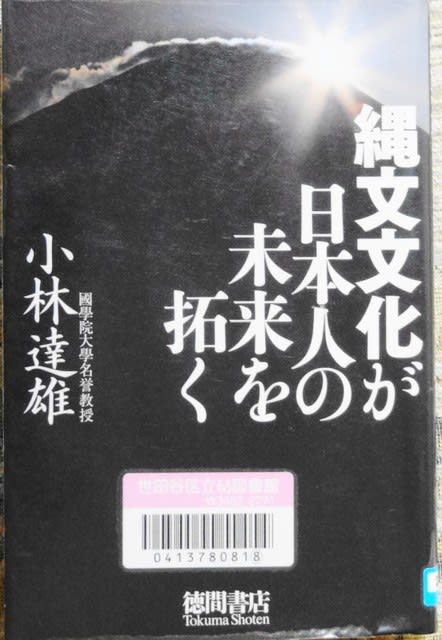
縄文文化が、西欧的な文明の次の文明に寄与することになるであろうとの著作は、近年多発している。その中でも、本書の著者は抜きんでているのかもしれない。著者紹介には、「國學院大學名誉教授」、「縄文文化研究者の第1人者」とあり、多くの著作がある。また、「縄文土器大観 全4巻(小学館)」、「縄文文化の研究 全10巻(雄山閣出版)」の編者になっている。
「はじめに」では、日本文化がその特殊性ゆえに、世界的に注目されていることを述べた後で、
『新石器革命で農耕とともに定住するようになった大陸側の人々は、自然と共生しないで 自然を征服しようとしてきました。人工的なムラの外側には人工的な機能を持つ耕作地(ノラ)があり、ムラの周りの自然は、開墾すべき対象だったのです。一方の縄文は、「狩猟、漁労、採集」によって定住を果たしていたため、ムラの周りに自然(ハラ)を温存してきました。自然の秩序を保ちながら、自然の恵みをそのまま利用するという作戦を実践しつづけてきたわけです。それが1000年、2000年ではなくて1万年以上続くのです。そういう歴史を欧米や大陸は持っていません。歴史の流れの先っぽにそれがないのです・』(pp.3)
さらに続けて、「文化は遺伝する、文化的遺伝子をミームという」とし、それは言葉だと思いついたとし、「やまとことば」を介して現代に繋がっている、としている。
目次は、異常にながい。その中で、第2章、第1節の目次は次のようにある。ここに、縄文土器とそれを維持し続けた文化のすべてがある。
『第2章 縄文火焔士器は器を超え物語を伝えている
(1)縄文土器は日本オリジナル
縄文土器が世界で一番古い
最初から完成形をイメージしていた
縄文文化を象徴する縄文土器
容器の機能を捨ててまで自らの世界観を表現した
縄文デザインの面白さ
沖縄、対馬に行った縄文人も朝鮮半島には行っていない
縄文土器の価値は弥生土器とは桁違い
縄文土器の文様は 、世界観を表している
縄文土器はメッセージをつたえている』(目次より)
新石器時代の世界の状況を述べた後で、
『そして約1万5000年前、最初にして 最大級の歴史的画期が日本列島に訪れました。
それまで絶えて見ることのなかった土器の製作、使用が始まったのです。
土器の製作は、まずは ①適当な粘土を見つけ出し、②精選して素地を整え、③加える水を調節しながらこねて、④ねかす。 次いで、⑤ひとかたまりの素地で底部を作って器壁を立ち上げて、全体を成形する。そして⑥器面にデザイン(文様)を施し、⑦十分に乾燥。⑧燃料の薪を集めて着火し、⑨焼き上げる。
これらの作業に要する時日と労力は並大抵のものではありません。』(pp.17)
つまり、土器の大量生産は、近代工業にも似て、石器の製作とは革命的な差があるというわけである。この技術を、縄文人は世界のどの民族よりも、数千年前に確立した。しかも、完成品に対する、独特の高度なデザイン感覚をも盛り込んでいる。
さらに、土偶についても新たな見解を示している。
『縄文世界に初めて登場した最古の土偶が、ヒトには不可欠な頭や顔のない形態から出発
して頑なに中期まで維持し続けた不思議な理由もここに潜んでいます。 もし縄文人が、己が姿形を本気で表現したいのであれば、あの縄文土器の優れた作品を創造した造形力をもってすれば、全く造作ないはずです。しかし実際には、圧倒的多数の土偶にそれだけの潜在カの片鱗すら見せないのは特別な理由があったからにほかなりません。』(pp.121)
数千年にわたってつくられた土器も土偶も、本来の目的は初期のものに存在するはずである。
『縄文人が表現したかった精霊
ところで各種の動物像には頭から尻尾の先までの全体の形態によって初めて種類を特定できるという性格があります。それと人像は明らかに違います。
岡本太郎が喝破するように、ヒトを表現する場合には、頭のてっぺんから足のつま先までの全体形を必要とせず、目鼻口で顔を描きさえすれば、たちまち誰しもヒトと判断できるという妙味があります。その肝心要の顔を最初の土偶につけなかったことは、極めて重要です。そこにこそ、土偶はヒトなのではないことの積極的な主張を見るのです。』(pp.122)
最後には、「はじめに」で述べられた言語、すなわち古代から伝わる日本語について、かなり詳しく述べられている。
『日本語はいろいろな点で興味深い特徴を持っていますが、その中で注目すべきものが、オノマトぺ 。擬音語・擬声語・擬態語のことです。
じいつと見つめると、川が 「さらさら」流れる。風が「そよそよ」吹く。これらはみんな擬音語です。擬声語というのは「テッペンカケタカ」(ホトトギス)とか「ツクツクホウシ」(ツクツクボウシ)とか「ブッポウソウ」(コノハズク)とか、鳥や昆虫の声とを重ねて表現しているものです。擬態語というのは「じいつと」見るとか、そういうものです。』(pp.132)
『本当にもう「日本語はものすごくバラエティに富んでいます。またそれを、いくらでも変化させることができるのです。「もの悲しい」「うら寂しい」と言って、みんなちゃんと、その情感が分かるのです。それは自然との共感共鳴の中から生み出されてきたものです。』(pp.135)
この書のように、縄文文化に関して、土偶の目的を明示し、そこから「やまとことば」に言及した著作はないと思う。そのことが、第1人者によって書かれたことは、喜ばしいことに思える。
自然の恵みをそのまま利用するという作戦を1万年以上も実践しつづけてきた歴史の事実は、これからの地球が最優先で取り組まなければならないことを示唆している。
TITLE: 縄文革命と日本人の未来
書名; 「縄文文化が日本人の未来を拓く」 [2018]
著者;小林達雄 発行所;徳間書店
発行日;2018.4.30
初回作成日;H30.10.29 最終改定日;H30.
引用先;文化の文明化のプロセス Implementing
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
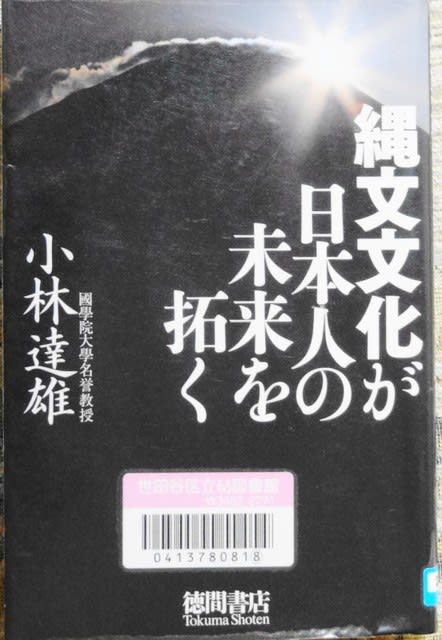
縄文文化が、西欧的な文明の次の文明に寄与することになるであろうとの著作は、近年多発している。その中でも、本書の著者は抜きんでているのかもしれない。著者紹介には、「國學院大學名誉教授」、「縄文文化研究者の第1人者」とあり、多くの著作がある。また、「縄文土器大観 全4巻(小学館)」、「縄文文化の研究 全10巻(雄山閣出版)」の編者になっている。
「はじめに」では、日本文化がその特殊性ゆえに、世界的に注目されていることを述べた後で、
『新石器革命で農耕とともに定住するようになった大陸側の人々は、自然と共生しないで 自然を征服しようとしてきました。人工的なムラの外側には人工的な機能を持つ耕作地(ノラ)があり、ムラの周りの自然は、開墾すべき対象だったのです。一方の縄文は、「狩猟、漁労、採集」によって定住を果たしていたため、ムラの周りに自然(ハラ)を温存してきました。自然の秩序を保ちながら、自然の恵みをそのまま利用するという作戦を実践しつづけてきたわけです。それが1000年、2000年ではなくて1万年以上続くのです。そういう歴史を欧米や大陸は持っていません。歴史の流れの先っぽにそれがないのです・』(pp.3)
さらに続けて、「文化は遺伝する、文化的遺伝子をミームという」とし、それは言葉だと思いついたとし、「やまとことば」を介して現代に繋がっている、としている。
目次は、異常にながい。その中で、第2章、第1節の目次は次のようにある。ここに、縄文土器とそれを維持し続けた文化のすべてがある。
『第2章 縄文火焔士器は器を超え物語を伝えている
(1)縄文土器は日本オリジナル
縄文土器が世界で一番古い
最初から完成形をイメージしていた
縄文文化を象徴する縄文土器
容器の機能を捨ててまで自らの世界観を表現した
縄文デザインの面白さ
沖縄、対馬に行った縄文人も朝鮮半島には行っていない
縄文土器の価値は弥生土器とは桁違い
縄文土器の文様は 、世界観を表している
縄文土器はメッセージをつたえている』(目次より)
新石器時代の世界の状況を述べた後で、
『そして約1万5000年前、最初にして 最大級の歴史的画期が日本列島に訪れました。
それまで絶えて見ることのなかった土器の製作、使用が始まったのです。
土器の製作は、まずは ①適当な粘土を見つけ出し、②精選して素地を整え、③加える水を調節しながらこねて、④ねかす。 次いで、⑤ひとかたまりの素地で底部を作って器壁を立ち上げて、全体を成形する。そして⑥器面にデザイン(文様)を施し、⑦十分に乾燥。⑧燃料の薪を集めて着火し、⑨焼き上げる。
これらの作業に要する時日と労力は並大抵のものではありません。』(pp.17)
つまり、土器の大量生産は、近代工業にも似て、石器の製作とは革命的な差があるというわけである。この技術を、縄文人は世界のどの民族よりも、数千年前に確立した。しかも、完成品に対する、独特の高度なデザイン感覚をも盛り込んでいる。
さらに、土偶についても新たな見解を示している。
『縄文世界に初めて登場した最古の土偶が、ヒトには不可欠な頭や顔のない形態から出発
して頑なに中期まで維持し続けた不思議な理由もここに潜んでいます。 もし縄文人が、己が姿形を本気で表現したいのであれば、あの縄文土器の優れた作品を創造した造形力をもってすれば、全く造作ないはずです。しかし実際には、圧倒的多数の土偶にそれだけの潜在カの片鱗すら見せないのは特別な理由があったからにほかなりません。』(pp.121)
数千年にわたってつくられた土器も土偶も、本来の目的は初期のものに存在するはずである。
『縄文人が表現したかった精霊
ところで各種の動物像には頭から尻尾の先までの全体の形態によって初めて種類を特定できるという性格があります。それと人像は明らかに違います。
岡本太郎が喝破するように、ヒトを表現する場合には、頭のてっぺんから足のつま先までの全体形を必要とせず、目鼻口で顔を描きさえすれば、たちまち誰しもヒトと判断できるという妙味があります。その肝心要の顔を最初の土偶につけなかったことは、極めて重要です。そこにこそ、土偶はヒトなのではないことの積極的な主張を見るのです。』(pp.122)
最後には、「はじめに」で述べられた言語、すなわち古代から伝わる日本語について、かなり詳しく述べられている。
『日本語はいろいろな点で興味深い特徴を持っていますが、その中で注目すべきものが、オノマトぺ 。擬音語・擬声語・擬態語のことです。
じいつと見つめると、川が 「さらさら」流れる。風が「そよそよ」吹く。これらはみんな擬音語です。擬声語というのは「テッペンカケタカ」(ホトトギス)とか「ツクツクホウシ」(ツクツクボウシ)とか「ブッポウソウ」(コノハズク)とか、鳥や昆虫の声とを重ねて表現しているものです。擬態語というのは「じいつと」見るとか、そういうものです。』(pp.132)
『本当にもう「日本語はものすごくバラエティに富んでいます。またそれを、いくらでも変化させることができるのです。「もの悲しい」「うら寂しい」と言って、みんなちゃんと、その情感が分かるのです。それは自然との共感共鳴の中から生み出されてきたものです。』(pp.135)
この書のように、縄文文化に関して、土偶の目的を明示し、そこから「やまとことば」に言及した著作はないと思う。そのことが、第1人者によって書かれたことは、喜ばしいことに思える。
自然の恵みをそのまま利用するという作戦を1万年以上も実践しつづけてきた歴史の事実は、これからの地球が最優先で取り組まなければならないことを示唆している。