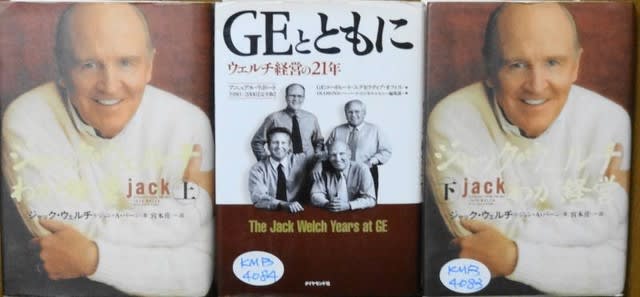TITLE: 「古代のインド―ヤマト文化圏(その2)」 KMM3333,34
このシリーズはメタエンジニアリングで「文化の文明化」を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
清川理一郎の古代インド説 ③of4
書籍名;「薬師如来 謎の古代史」[1997]
著者;清川理一郎 発行所;彩社流 発行日;1997.3.5
初回作成年月日;H29.5.15 最終改定日;
引用先;文化の文明化のプロセス Converging
副題を「仏の素顔とインドの魔族」として、現代の仏教の複雑性と、特にインドの仏教以前の神々との関係を探索している。
仏教の経典は、他の宗教に比べて格段に多い。それは何故か。私は、特に仏教に詳しいわけではないのだけれども、彼の説には、なるほどそういった見方もありそうだ、との印象を持った。現地・現物でその場で思考範囲をできるだけ広げてその根源を考える態度は、その場考学流のメタエンジニアリングとまったく同じである。
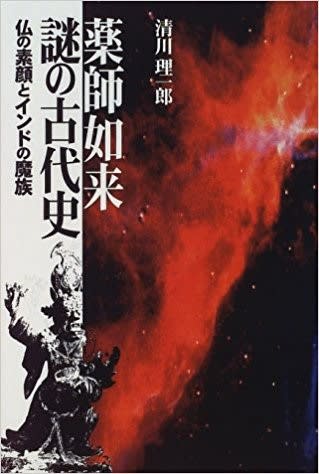
先ずは、総論から。
『仏教の経典の数はきわめて多い。そして、釈尊の直接の教えといわれる金口・直説とされる経典が非常に多いのである。経典類は一括して大経蔵とか一切経とか呼ばれているが、そのなかには教えを記した経典のほかに教団の規律を定めたものと、教えを解釈した論書も含まれる。
いわゆる経・律・論の三蔵である。』(pp.22)
経典の由来につぃては、
『文字はシャカの時代よりも千年以上前にすでに存在していた。ただ崇高な教えは文字に写すことはできないということで、口から口へと伝えられたのである。バラモン教の経典についても、このことはいえる。シャカ滅後、経典編集会議(結集)が何回か開かれるようになるが、しばらくの間は、やはり暗記しているものを口で言い合い、確かめあって解散したので、文字に写すことはしなかった。』(pp.23)
この経過から考えると、文字を使わない文化の方が賢い文化と云える場合もあることを思わせる。プラトンの、「正しいこととは、論じ合うことだ」の言葉を思い出す。
文字文化が印刷技術の進化により一方的に発達すると、印刷されたものは正しいという文化が育つ可能性がある。
その後、多くの国家や文字言語が発達したのちに、多くの文字で経典が書かれ始めたので、当然の結果として、多くの経典が生まれた。また、仏像についても無仏時代を経た後、特にアレキサンダーの東進の後で、仏像を作りだしたので、ギリシャ風などの色々な様式が同時代に現れた。
日本各地には、神仏習合の影響の結果、古い神社と薬師如来信仰が集まっている地域がいくつかあるという。その中の一つに越後の弥彦山周辺がある。
『仏教の霊地になる以前の弥彦の地に、仏教の・・・』(pp.44)ではじまり、今は無人になっている周辺の寺々の説明が続く。
それらには、『薬師寺の南側にある湯(くすり)神社は石薬師明神を祀るヤクシブツ信仰の神社であり、巨石信仰と蛇神信仰を持つ。野積の妻戸神社は弥彦神の妃神おヨネを祀る神社で、巨石信仰と蛇の信仰を持つ。』のように、不思議と古代の信仰対象が保たれていることが多い。
そして、「ヤクシブツ信仰圏」なるものを想定しており、そこに集まる諸仏についての系譜を纏めている。
『この系譜には、これまで弥彦の神仏習合の諸仏にみなかった仏が登場する。つまり、吉祥天、鬼子母神、夜叉(薬叉)などである。
系譜上の諸仏の本地はみな外道の時代からヤクシブツの本地とつながりがあり、ヤクシブツ信仰圏の系譜を構成している。また薬師十二神将の一つの金毘羅は夜叉大将の一つで、その前身はインダス河の「わに」といわれる。これを海神として祀ったのが四国の金毘羅宮(琴平神社)である。』(pp.51)
つまり、ヤクシブツ信仰圏にある神社は、ヤクシブツ信仰の原態、つまり外道につながる原形をそのまま残している、という。
そこから、古代インドの「魔族」の説明に移る。
『古代インドの魔族について述べる理由は、これまでみたように、今の私たちの周りに存在する仏の中にたくさんの魔族の出目を持つ仏が居るからである。』(pp.80)
『仏の原態が魔族につながる代表例は、前章で述べた外道時代に魔王だったヤクシャ出身のクベーラ(ビシャモン)である。一方、このクベーラはクビラ(金毘羅)に名称を変えて四国の金毘羅宮の祭神にもなっている。そしてクビラは「わに」の神格化ともいわれる。また、先にみた吉祥天は、ヤクシャ出身の夫(ビシャモン=クベーラ)と母(鬼子母神=ハーリーティ)の双方とも魔族とされる眷属を持った女神信仰出身の仏であった。つまり吉祥天の血筋は、魔族の系譜であった。』(pp.80)
『魔族を大きく分けると三つに分類できる。それはアスラとラクシャス、そしてブートに代表される悪霊群である。先ずアスラの中には、ヤクシャとヴリトラがいる。アスラは神々に敵対する魔族であった。(中略)ラクシャスは、アスラが神々に敵対する存在であったのに対して人間におそいかかる悪鬼とされる。(中略)ブードに代表される悪霊群は、事故、自殺、死刑、毒蛇などが原因の死によって出現するブートと呼ばれる死霊や、・・・様々な死霊や悪霊のことである。』(pp82)
『この分類の最初のアスラを構成する主たる実態はヤクシャである。外道(ヤクシャ)から仏教(大乗仏教)に入り諸仏になったケースは極めて多い。また、分類の二つ目のラクシャスも仏となるが、ヤクシャとラクシャスは外道において性質が異なる魔族である。』(pp.82)
最後に、「ヤクシブツ(薬師如来)の出目(原像)は古代バラモン教の魔族・ヴァルナ神だった」として、次のことを記している。
『中国でのヤクシブツ信仰は、道教的色彩が濃いものとなり南北朝の時代のとくに南朝に「続命法」の中心となって広められた。では、インドにおけるヤクシブツ信仰はどうであったのだろうか。じつは、インドにはヤクシブツが信仰されたことを示す積極的な資料や、ヤクシブツの彫像や画像などが存在しないのである。このことはヤクシブツをめぐる最大の謎である。多くの専門家は古代インドにおけるヤクシブツ信仰を否定的に考えている。私は、この謎を解く鍵はヤクシブツの外道における出目にあると考える。』(pp.114)
つまり、インドではヤクシブツが、その自目まで遡った信仰として残されているというわけなのであろう。古代の魔族としての扱いが続いているというわけなのだろう。
最後に、文化の波状理論にもどる。
『二つの文化(民族固有と民族間共通の文化)は、民族の移動、戦争などによって他に伝播する。伝播した文化が民族間共通の文化の場合は、相手の文化も同じなので、相手の文化を吸収したり吸収されたりする文化の融合はスムーズに行われる。
しかし、固有の文化の場合は、注目すべき分化現象が生ずる。それは、固有文化の中で固有性が非常に強い部分、つまり固有の文化の本質を形成しその文化の“核”となる部分は、伝播した後も極めて長い間変わらないで残存することである。文化伝播の理論の一つ、波状理論とは、文化の固有性が非常に強い部分の文化伝播についての理論である。』(pp.119)
清川理一郎の古代インド説 ④of4 KMB3333
書籍名;「猿田彦と秦氏の謎」[2003] 著者;清川理一郎
発行所;彩社流 発行日;2003.2.10
初回作成年月日;H29.5.15 最終改定日;
引用先;文化の文明化のプロセス Converging
副題を「伊勢大神・ホツマツタエ・ダビデの影」として、猿田彦が秦氏の元祖で、かつての出雲神族の最高神であり、伊勢大神でもあったが、日本書紀の編纂の頃には、その呪術性を天皇家に独占されて、道祖神にまで落とされた経緯、さらに秦氏の先祖を古代イスラエルに求めている。このストーリーはホツマツタエの話として、一時は偽書扱いを受けたが、今では評価が二分されていると思う。超古代の日本と古代ユダヤの繋がりは、多くの時とところで挙げられている。この一連のストーリーについても数冊の著書があるが、氏は改めて各国の古文書の内容から、これを肉付けしている。その集大成ともいえるのではないだろうか。

『サルタヒコノオオカミは日本の神武天皇朝以前に存在した日本古代のウガヤ王朝の時代、海の向こうから日本に渡来した外来神である。サルタヒコは数代にわたる神系譜を持つ神であり、わが国先住民族の出雲王朝の神々(国つ神)の祖先神として崇められ、またその最高神として信仰を集めてきた。
日本各地に分布するサルタヒコ大神を祀る神社は多い。その神格像は時空を超えて複雑であり、多様性に富んでいる。そして一方、サルタヒコはオープンでおおらかな神であるから、当時の一般の民衆に支えられた信仰のすそ野は極めて広く、いくつもの時代をとおして重層的なひろがりをみせてきた。』(pp.2)
『記紀(日本書記と古事記)の描写は、サルタヒコを岐の神、クナトの神、街の神などと呼ばれる道祖神や塞の神にまで格下げし、かつては国つ神・出雲神族の最高神だった、サルタヒコ大神の威光ある原像は描かれていないのである。つまり、記紀は、サルタヒコの真の姿を抹殺したうえ、正史の光のあたらない闇の中に葬ってしまっているのだ。』(pp.2)
『日本各地に鎮座する2000余社もあるサルタヒコを祀る神社の、主祭神・サルタヒコの真お姿を理解していただきたいのである。』(pp.3)
第1章では、サルタヒコの源郷をチベットの羌族に求め、更にその元を古代ユダヤ教徒の一民族としている。
第2章では、サルタヒコ信仰の多様性の例として、伏見稲荷、水尾神社、椿大神社を挙げている。
第3章では、伊勢神宮で真夜中に行われる祭祀から、おおもとの神が男であり、伊勢大神と称されているとしている。
第5章では、4世紀に大挙渡来した秦氏について述べ、猿田彦がその王であったとしている。
第6章では、日本各地に存在する秦氏の痕跡について、例証している。
第7章では、古代オリエントの地で出土した古代文書から、サルタヒコとダビデとの関連性を推定している。
第8章では、伊勢神宮に伝わる古代ユダヤの神跡について詳細に述べている。有名な、八咫鏡の裏面の画像も表示している。
以下は、各章から興味ある部分のみを抜き書きした。
『ヌナカワヒメとオオナムチとの間に生まれた神をタケミナカタ命としている。タケミナカタノミコトは信州諏訪の出雲系の諏訪大社をはじめ、全国の諏訪神社の祭神である。いずれにせよヌナカワヒメは、出雲系の有名な神々の大母神だったのだ。』(pp.31)
この有名は話と、まったく同じ話が中国最古の歴史書である「穆天子伝」(前430~225の魏の時代に成立)にある、西方の地の「西王母」の話を挙げている。彼女もまた、古代の玉を算出する地の女王だった。
『羌の字は、「羊」の字の下に「人」の字を加えて「羌」とするように、羌族は根っからの遊牧民であった。羌族の歴史は古く、中国の殷代(紀元前十五~十一世紀)の遺物として出土した甲骨文の文字から判断すると、殷の王の祭祀に臨んで、犠牲者として祭壇に捧げられたのが、羌族の人間だったと考えられるのだ。』(pp.36)
つまり、羌族は殷の民族とは敵対する民族であった。ところが、民族としての力は強く、春秋・戦国時代を生き抜いて、ついには秦国を建設する。
『中国の古代国家、周(西周)が東遷したのち(前770年)、西周の都があった陝西省の地に羌を基層民族とする国家が成立した。この国こそが、後の秦の始皇帝の国家統一(前221年)を経て滅亡(前110年)までつづいた秦国である。』(pp.38)
羌族は、彼らの聖数を「六」とする「六祖観念」を秦国に持ち込んだのだが、この観念は古代ユダヤから持ち込まれたとしている。
『鈴鹿市の椿ガ岳の麓に広がる、うっそうとした杉木立のなかに、主祭神・サルタヒコを祀る椿大神社が鎮座する。椿大神社は全国二千余社あるサルタヒコ神社の総本宮であり、古来、伊勢国一の宮として崇拝されてきた。』(pp.50)
伏見稲荷大社については、このように記している。かつての御神体である、おやま「稲荷山」の頂上には数基の古墳がある。
『山頂にある古、墳の年代は古くその古墳はおおよそ先住民の首長や有力者の墳墓と考えられるのである。また山麓の円墳の年代は、秦氏が移住した後の時期とも符合するので、秦氏一族の墳墓とみられている。
私は、山頂の古墳の主である先住民こそサルタヒコの神族の人たちと考える。サルタヒコは稲荷神社にとって古層の地主神なのだ。』(pp.76)
また、「イナリ」の名の根源は別のところにあるとして、
『キリストの頭上にかけられたINRIの意味を多くのユダヤ人が知っていたことだ』(pp176)としている。『処刑された十字架上のキリストの頭上に掲げられた“INRI”が転訛して「INARI」になったものと考える。』(pp.182)
『原始キリスト教徒はキリスト教のシンボルを“魚”とみていた。したがって伏見稲荷社の名が、「INARI」だったり、宮司の名の多くが“魚”に因むものだったりすることなどは、原始キリスト教徒が創始した伏見稲荷大社は、古代キリスト教色が極めて濃かったことの証なのである。』(pp.183)
先日、私はこの伏見稲荷を参拝したのだが、参詣者の大多数が西欧人で、恐らくはキリスト教徒と思われたのだが、これは偶然なのであろうか。いずれにせよ、伏見大社の参道には、「外国人参詣者連続日本一」の多くの旗がはためていた。
また、日本独特の真言密教については、次の記述がある。
『空海は唐に行く前から景教に強い関心を持っていたと思われる。それは、空海の出身地の香川県・讃岐は、原始キリスト教徒の秦氏が多く住んでおり、また空海の師であった仏教僧の勤操も、元の名を秦氏といった。(中略)空海が向かった長安には当時すでに、景教の教会が四つあった。空海がいた場所は景教の教会のすぐ近くだった。空海は景浄という景教僧と接触したと伝えられている。』(pp.284)
『私が残念に思うのは、真言宗の総本山には景教をめぐってこれまでみたような決定的な資料や証拠が残っているにもかかわらず、日本のアカデミズムが密教と景教の関係をなぜもっとはやくディスクローズしなかったかである。』(pp.286)
以上の4冊を読んで感じたことは、仏教の正式な伝来以前の日本列島は、多くの民族による国家が乱立していたのだが、インドから南方を通じて伝わった文化圏に属する民族の力が強かったようだ。それを記紀の編集によって、ひとつのストーリーにまとめ上げた大和朝廷の政治手腕には驚かされる。しかし、あちこちに「文化の核」が残されており、その繋がりは徐々に明らかになってゆくのだろうということだった。
4冊に示されたストーリーをすべて正しいと断定することはできないのだが、同時に、すべてを否定することもできない。最近は、日本書記と古事記の内容の真否について多くの著書が発行されている。また、そのような古代から伝わる歴史書は、すべて勝利を得た側が、自らの政権に都合の良いように書き残したものだ、との考え方が有力なっている。やはり、「文字の文化を文明とする」という文明論は、全体最適の眼から見るとおかしなところがあるようだ。SNSなどの発達により、新たな文明の定義が生まれることを期待している。
このシリーズはメタエンジニアリングで「文化の文明化」を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
清川理一郎の古代インド説 ③of4
書籍名;「薬師如来 謎の古代史」[1997]
著者;清川理一郎 発行所;彩社流 発行日;1997.3.5
初回作成年月日;H29.5.15 最終改定日;
引用先;文化の文明化のプロセス Converging
副題を「仏の素顔とインドの魔族」として、現代の仏教の複雑性と、特にインドの仏教以前の神々との関係を探索している。
仏教の経典は、他の宗教に比べて格段に多い。それは何故か。私は、特に仏教に詳しいわけではないのだけれども、彼の説には、なるほどそういった見方もありそうだ、との印象を持った。現地・現物でその場で思考範囲をできるだけ広げてその根源を考える態度は、その場考学流のメタエンジニアリングとまったく同じである。
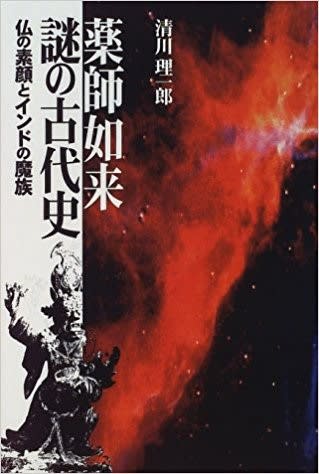
先ずは、総論から。
『仏教の経典の数はきわめて多い。そして、釈尊の直接の教えといわれる金口・直説とされる経典が非常に多いのである。経典類は一括して大経蔵とか一切経とか呼ばれているが、そのなかには教えを記した経典のほかに教団の規律を定めたものと、教えを解釈した論書も含まれる。
いわゆる経・律・論の三蔵である。』(pp.22)
経典の由来につぃては、
『文字はシャカの時代よりも千年以上前にすでに存在していた。ただ崇高な教えは文字に写すことはできないということで、口から口へと伝えられたのである。バラモン教の経典についても、このことはいえる。シャカ滅後、経典編集会議(結集)が何回か開かれるようになるが、しばらくの間は、やはり暗記しているものを口で言い合い、確かめあって解散したので、文字に写すことはしなかった。』(pp.23)
この経過から考えると、文字を使わない文化の方が賢い文化と云える場合もあることを思わせる。プラトンの、「正しいこととは、論じ合うことだ」の言葉を思い出す。
文字文化が印刷技術の進化により一方的に発達すると、印刷されたものは正しいという文化が育つ可能性がある。
その後、多くの国家や文字言語が発達したのちに、多くの文字で経典が書かれ始めたので、当然の結果として、多くの経典が生まれた。また、仏像についても無仏時代を経た後、特にアレキサンダーの東進の後で、仏像を作りだしたので、ギリシャ風などの色々な様式が同時代に現れた。
日本各地には、神仏習合の影響の結果、古い神社と薬師如来信仰が集まっている地域がいくつかあるという。その中の一つに越後の弥彦山周辺がある。
『仏教の霊地になる以前の弥彦の地に、仏教の・・・』(pp.44)ではじまり、今は無人になっている周辺の寺々の説明が続く。
それらには、『薬師寺の南側にある湯(くすり)神社は石薬師明神を祀るヤクシブツ信仰の神社であり、巨石信仰と蛇神信仰を持つ。野積の妻戸神社は弥彦神の妃神おヨネを祀る神社で、巨石信仰と蛇の信仰を持つ。』のように、不思議と古代の信仰対象が保たれていることが多い。
そして、「ヤクシブツ信仰圏」なるものを想定しており、そこに集まる諸仏についての系譜を纏めている。
『この系譜には、これまで弥彦の神仏習合の諸仏にみなかった仏が登場する。つまり、吉祥天、鬼子母神、夜叉(薬叉)などである。
系譜上の諸仏の本地はみな外道の時代からヤクシブツの本地とつながりがあり、ヤクシブツ信仰圏の系譜を構成している。また薬師十二神将の一つの金毘羅は夜叉大将の一つで、その前身はインダス河の「わに」といわれる。これを海神として祀ったのが四国の金毘羅宮(琴平神社)である。』(pp.51)
つまり、ヤクシブツ信仰圏にある神社は、ヤクシブツ信仰の原態、つまり外道につながる原形をそのまま残している、という。
そこから、古代インドの「魔族」の説明に移る。
『古代インドの魔族について述べる理由は、これまでみたように、今の私たちの周りに存在する仏の中にたくさんの魔族の出目を持つ仏が居るからである。』(pp.80)
『仏の原態が魔族につながる代表例は、前章で述べた外道時代に魔王だったヤクシャ出身のクベーラ(ビシャモン)である。一方、このクベーラはクビラ(金毘羅)に名称を変えて四国の金毘羅宮の祭神にもなっている。そしてクビラは「わに」の神格化ともいわれる。また、先にみた吉祥天は、ヤクシャ出身の夫(ビシャモン=クベーラ)と母(鬼子母神=ハーリーティ)の双方とも魔族とされる眷属を持った女神信仰出身の仏であった。つまり吉祥天の血筋は、魔族の系譜であった。』(pp.80)
『魔族を大きく分けると三つに分類できる。それはアスラとラクシャス、そしてブートに代表される悪霊群である。先ずアスラの中には、ヤクシャとヴリトラがいる。アスラは神々に敵対する魔族であった。(中略)ラクシャスは、アスラが神々に敵対する存在であったのに対して人間におそいかかる悪鬼とされる。(中略)ブードに代表される悪霊群は、事故、自殺、死刑、毒蛇などが原因の死によって出現するブートと呼ばれる死霊や、・・・様々な死霊や悪霊のことである。』(pp82)
『この分類の最初のアスラを構成する主たる実態はヤクシャである。外道(ヤクシャ)から仏教(大乗仏教)に入り諸仏になったケースは極めて多い。また、分類の二つ目のラクシャスも仏となるが、ヤクシャとラクシャスは外道において性質が異なる魔族である。』(pp.82)
最後に、「ヤクシブツ(薬師如来)の出目(原像)は古代バラモン教の魔族・ヴァルナ神だった」として、次のことを記している。
『中国でのヤクシブツ信仰は、道教的色彩が濃いものとなり南北朝の時代のとくに南朝に「続命法」の中心となって広められた。では、インドにおけるヤクシブツ信仰はどうであったのだろうか。じつは、インドにはヤクシブツが信仰されたことを示す積極的な資料や、ヤクシブツの彫像や画像などが存在しないのである。このことはヤクシブツをめぐる最大の謎である。多くの専門家は古代インドにおけるヤクシブツ信仰を否定的に考えている。私は、この謎を解く鍵はヤクシブツの外道における出目にあると考える。』(pp.114)
つまり、インドではヤクシブツが、その自目まで遡った信仰として残されているというわけなのであろう。古代の魔族としての扱いが続いているというわけなのだろう。
最後に、文化の波状理論にもどる。
『二つの文化(民族固有と民族間共通の文化)は、民族の移動、戦争などによって他に伝播する。伝播した文化が民族間共通の文化の場合は、相手の文化も同じなので、相手の文化を吸収したり吸収されたりする文化の融合はスムーズに行われる。
しかし、固有の文化の場合は、注目すべき分化現象が生ずる。それは、固有文化の中で固有性が非常に強い部分、つまり固有の文化の本質を形成しその文化の“核”となる部分は、伝播した後も極めて長い間変わらないで残存することである。文化伝播の理論の一つ、波状理論とは、文化の固有性が非常に強い部分の文化伝播についての理論である。』(pp.119)
清川理一郎の古代インド説 ④of4 KMB3333
書籍名;「猿田彦と秦氏の謎」[2003] 著者;清川理一郎
発行所;彩社流 発行日;2003.2.10
初回作成年月日;H29.5.15 最終改定日;
引用先;文化の文明化のプロセス Converging
副題を「伊勢大神・ホツマツタエ・ダビデの影」として、猿田彦が秦氏の元祖で、かつての出雲神族の最高神であり、伊勢大神でもあったが、日本書紀の編纂の頃には、その呪術性を天皇家に独占されて、道祖神にまで落とされた経緯、さらに秦氏の先祖を古代イスラエルに求めている。このストーリーはホツマツタエの話として、一時は偽書扱いを受けたが、今では評価が二分されていると思う。超古代の日本と古代ユダヤの繋がりは、多くの時とところで挙げられている。この一連のストーリーについても数冊の著書があるが、氏は改めて各国の古文書の内容から、これを肉付けしている。その集大成ともいえるのではないだろうか。

『サルタヒコノオオカミは日本の神武天皇朝以前に存在した日本古代のウガヤ王朝の時代、海の向こうから日本に渡来した外来神である。サルタヒコは数代にわたる神系譜を持つ神であり、わが国先住民族の出雲王朝の神々(国つ神)の祖先神として崇められ、またその最高神として信仰を集めてきた。
日本各地に分布するサルタヒコ大神を祀る神社は多い。その神格像は時空を超えて複雑であり、多様性に富んでいる。そして一方、サルタヒコはオープンでおおらかな神であるから、当時の一般の民衆に支えられた信仰のすそ野は極めて広く、いくつもの時代をとおして重層的なひろがりをみせてきた。』(pp.2)
『記紀(日本書記と古事記)の描写は、サルタヒコを岐の神、クナトの神、街の神などと呼ばれる道祖神や塞の神にまで格下げし、かつては国つ神・出雲神族の最高神だった、サルタヒコ大神の威光ある原像は描かれていないのである。つまり、記紀は、サルタヒコの真の姿を抹殺したうえ、正史の光のあたらない闇の中に葬ってしまっているのだ。』(pp.2)
『日本各地に鎮座する2000余社もあるサルタヒコを祀る神社の、主祭神・サルタヒコの真お姿を理解していただきたいのである。』(pp.3)
第1章では、サルタヒコの源郷をチベットの羌族に求め、更にその元を古代ユダヤ教徒の一民族としている。
第2章では、サルタヒコ信仰の多様性の例として、伏見稲荷、水尾神社、椿大神社を挙げている。
第3章では、伊勢神宮で真夜中に行われる祭祀から、おおもとの神が男であり、伊勢大神と称されているとしている。
第5章では、4世紀に大挙渡来した秦氏について述べ、猿田彦がその王であったとしている。
第6章では、日本各地に存在する秦氏の痕跡について、例証している。
第7章では、古代オリエントの地で出土した古代文書から、サルタヒコとダビデとの関連性を推定している。
第8章では、伊勢神宮に伝わる古代ユダヤの神跡について詳細に述べている。有名な、八咫鏡の裏面の画像も表示している。
以下は、各章から興味ある部分のみを抜き書きした。
『ヌナカワヒメとオオナムチとの間に生まれた神をタケミナカタ命としている。タケミナカタノミコトは信州諏訪の出雲系の諏訪大社をはじめ、全国の諏訪神社の祭神である。いずれにせよヌナカワヒメは、出雲系の有名な神々の大母神だったのだ。』(pp.31)
この有名は話と、まったく同じ話が中国最古の歴史書である「穆天子伝」(前430~225の魏の時代に成立)にある、西方の地の「西王母」の話を挙げている。彼女もまた、古代の玉を算出する地の女王だった。
『羌の字は、「羊」の字の下に「人」の字を加えて「羌」とするように、羌族は根っからの遊牧民であった。羌族の歴史は古く、中国の殷代(紀元前十五~十一世紀)の遺物として出土した甲骨文の文字から判断すると、殷の王の祭祀に臨んで、犠牲者として祭壇に捧げられたのが、羌族の人間だったと考えられるのだ。』(pp.36)
つまり、羌族は殷の民族とは敵対する民族であった。ところが、民族としての力は強く、春秋・戦国時代を生き抜いて、ついには秦国を建設する。
『中国の古代国家、周(西周)が東遷したのち(前770年)、西周の都があった陝西省の地に羌を基層民族とする国家が成立した。この国こそが、後の秦の始皇帝の国家統一(前221年)を経て滅亡(前110年)までつづいた秦国である。』(pp.38)
羌族は、彼らの聖数を「六」とする「六祖観念」を秦国に持ち込んだのだが、この観念は古代ユダヤから持ち込まれたとしている。
『鈴鹿市の椿ガ岳の麓に広がる、うっそうとした杉木立のなかに、主祭神・サルタヒコを祀る椿大神社が鎮座する。椿大神社は全国二千余社あるサルタヒコ神社の総本宮であり、古来、伊勢国一の宮として崇拝されてきた。』(pp.50)
伏見稲荷大社については、このように記している。かつての御神体である、おやま「稲荷山」の頂上には数基の古墳がある。
『山頂にある古、墳の年代は古くその古墳はおおよそ先住民の首長や有力者の墳墓と考えられるのである。また山麓の円墳の年代は、秦氏が移住した後の時期とも符合するので、秦氏一族の墳墓とみられている。
私は、山頂の古墳の主である先住民こそサルタヒコの神族の人たちと考える。サルタヒコは稲荷神社にとって古層の地主神なのだ。』(pp.76)
また、「イナリ」の名の根源は別のところにあるとして、
『キリストの頭上にかけられたINRIの意味を多くのユダヤ人が知っていたことだ』(pp176)としている。『処刑された十字架上のキリストの頭上に掲げられた“INRI”が転訛して「INARI」になったものと考える。』(pp.182)
『原始キリスト教徒はキリスト教のシンボルを“魚”とみていた。したがって伏見稲荷社の名が、「INARI」だったり、宮司の名の多くが“魚”に因むものだったりすることなどは、原始キリスト教徒が創始した伏見稲荷大社は、古代キリスト教色が極めて濃かったことの証なのである。』(pp.183)
先日、私はこの伏見稲荷を参拝したのだが、参詣者の大多数が西欧人で、恐らくはキリスト教徒と思われたのだが、これは偶然なのであろうか。いずれにせよ、伏見大社の参道には、「外国人参詣者連続日本一」の多くの旗がはためていた。
また、日本独特の真言密教については、次の記述がある。
『空海は唐に行く前から景教に強い関心を持っていたと思われる。それは、空海の出身地の香川県・讃岐は、原始キリスト教徒の秦氏が多く住んでおり、また空海の師であった仏教僧の勤操も、元の名を秦氏といった。(中略)空海が向かった長安には当時すでに、景教の教会が四つあった。空海がいた場所は景教の教会のすぐ近くだった。空海は景浄という景教僧と接触したと伝えられている。』(pp.284)
『私が残念に思うのは、真言宗の総本山には景教をめぐってこれまでみたような決定的な資料や証拠が残っているにもかかわらず、日本のアカデミズムが密教と景教の関係をなぜもっとはやくディスクローズしなかったかである。』(pp.286)
以上の4冊を読んで感じたことは、仏教の正式な伝来以前の日本列島は、多くの民族による国家が乱立していたのだが、インドから南方を通じて伝わった文化圏に属する民族の力が強かったようだ。それを記紀の編集によって、ひとつのストーリーにまとめ上げた大和朝廷の政治手腕には驚かされる。しかし、あちこちに「文化の核」が残されており、その繋がりは徐々に明らかになってゆくのだろうということだった。
4冊に示されたストーリーをすべて正しいと断定することはできないのだが、同時に、すべてを否定することもできない。最近は、日本書記と古事記の内容の真否について多くの著書が発行されている。また、そのような古代から伝わる歴史書は、すべて勝利を得た側が、自らの政権に都合の良いように書き残したものだ、との考え方が有力なっている。やはり、「文字の文化を文明とする」という文明論は、全体最適の眼から見るとおかしなところがあるようだ。SNSなどの発達により、新たな文明の定義が生まれることを期待している。