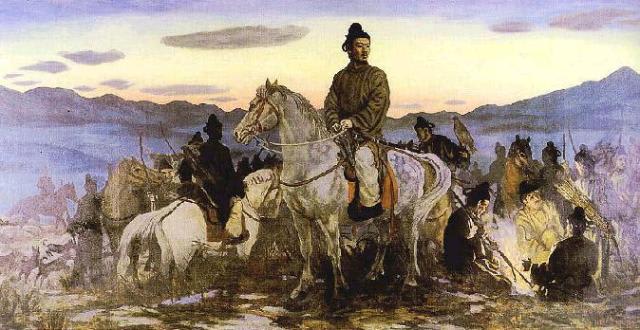ずっしりと重く安定感があり、渋くて縄文的なデザインが良く似合う陶器で大好きだ。
丹波立杭焼の歴史は古く、鎌倉時代に発祥し瀬戸、常滑、信楽、備前、越前と共に日本六古窯の一つに数えられています。


 (陶器の写真はWebより拝借しました)
(陶器の写真はWebより拝借しました)
丹後半島の帰りには時間がなく寄れなかったので、篠山市の「丹波焼・立杭 陶の郷」へ改めて出直すことにした。10月20日から陶器まつりが開催されるようで、土曜日なのに今日はガラガラだった。57軒の窯元の作品を購入できる『窯元横丁』では、2周もして、迷いに迷ってやっとお気に入りの皿・鉢など4点を購入した。


「陶の郷」近くの山麓には傾斜を利用して47mの登り窯が現存する。窯に火が入ると迫力があるだろうと感じさせる長大さだ。1300度で60時間も焼成する、かなりの木材が必要になる。


最近探訪した丹後や越では、製鉄技術を持った集団が弥生時代から活躍していた。製鉄も鉄を溶かすのに大量の木材が必要で、ひいては森林破壊につながる。弥生時代に大勢の渡来人が渡ってきた。その理由の一つに、朝鮮半島の森林破壊が進んで、燃料としての木材が枯渇したため、製鉄技術を持った集団が森林を求めて渡って来たとも言われている。出雲、諏訪、丹後、越など日本海の古代国などがそうだ。特に丹後や越は、半島からの鉄の材料や製品等を大和へ輸送する流通経路として最重要地域であった。だから大和政権後も大きな古墳やガラスの腕輪など、鉄による武器や農具の売買により裕福になった部族が存在していた訳だ。この地域の歴史が素戔嗚尊(出雲)やアメノヒボコ(丹波)、ツヌガアラシト(敦賀)、タケミナカタノミコト(諏訪)らの神話となって語られているのだろう。
古代の焼き物須恵器は、『日本書紀』には百済などからの渡来人が製作したとある一方、垂仁天皇(垂仁3年)の時代に新羅王子天日矛(アメノヒボコ)とその従者として須恵器の工人がやってきたとも記されている。
そろそろお腹がスエキなので、昼飯はタチグイにするか!
丹波立杭焼の歴史は古く、鎌倉時代に発祥し瀬戸、常滑、信楽、備前、越前と共に日本六古窯の一つに数えられています。


 (陶器の写真はWebより拝借しました)
(陶器の写真はWebより拝借しました)丹後半島の帰りには時間がなく寄れなかったので、篠山市の「丹波焼・立杭 陶の郷」へ改めて出直すことにした。10月20日から陶器まつりが開催されるようで、土曜日なのに今日はガラガラだった。57軒の窯元の作品を購入できる『窯元横丁』では、2周もして、迷いに迷ってやっとお気に入りの皿・鉢など4点を購入した。


「陶の郷」近くの山麓には傾斜を利用して47mの登り窯が現存する。窯に火が入ると迫力があるだろうと感じさせる長大さだ。1300度で60時間も焼成する、かなりの木材が必要になる。


最近探訪した丹後や越では、製鉄技術を持った集団が弥生時代から活躍していた。製鉄も鉄を溶かすのに大量の木材が必要で、ひいては森林破壊につながる。弥生時代に大勢の渡来人が渡ってきた。その理由の一つに、朝鮮半島の森林破壊が進んで、燃料としての木材が枯渇したため、製鉄技術を持った集団が森林を求めて渡って来たとも言われている。出雲、諏訪、丹後、越など日本海の古代国などがそうだ。特に丹後や越は、半島からの鉄の材料や製品等を大和へ輸送する流通経路として最重要地域であった。だから大和政権後も大きな古墳やガラスの腕輪など、鉄による武器や農具の売買により裕福になった部族が存在していた訳だ。この地域の歴史が素戔嗚尊(出雲)やアメノヒボコ(丹波)、ツヌガアラシト(敦賀)、タケミナカタノミコト(諏訪)らの神話となって語られているのだろう。
古代の焼き物須恵器は、『日本書紀』には百済などからの渡来人が製作したとある一方、垂仁天皇(垂仁3年)の時代に新羅王子天日矛(アメノヒボコ)とその従者として須恵器の工人がやってきたとも記されている。
そろそろお腹がスエキなので、昼飯はタチグイにするか!