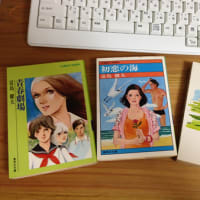映画・ドラマ化と、富島作品の中で一番有名なのではないだろうか。
17歳で孤児となった玲子が、妻を亡くした子持ちの吉川と知り合い、結婚する話。
映画もDVDで見たが、そのことは別に記すとして、
この原作は恋愛うんぬんではなく、「女の幸せ」とは何かを描いているものだと思った。
玲子は、死んだ母に恥じないよう、“強く正しく”生きようとする少女だ。
そして、『のぶ子の悲しみ』のように悲劇的でなく、玲子は幸せをつかむ。
その象徴が“結婚”であり、“愛する人との性の結びつき”なのだ。
さて、ここからだ。
「ぼくはきみをすぐれた芸術品にしようと思っている。
性は高度な芸術活動だし、きみは正常な自然なままの素材としてぼくの前にあらわれた。
男には多くの生きがいがある。(中略)
無垢な姿と心で嫁いできた妻をすばらしい女として完成させるのも、大きなよろこびなんだ」
玲子は高校生、妻、母の三役をこなすことを余儀なくされる。
玲子は吉川が酔って帰ってきた翌日の朝食に気を使い、服の染み抜きは怠らず、
同僚が遊びに来る日にはきちんと髪を結う。
それは“愛する人”に尽くしているということだけではない。
“妻として恥ずかしくないように”という思い、それは夫に対してだけではなく、世間に対してもだ。
そして、夫婦の絆を強めているのが“性”である。
玲子は吉川と幾夜をともにしながら性のよろこびを開花させられる。
「性は独立したものではないということよ。それはあたしのすべてに関係する行為なの。
文字どおり、あたしはあの人を愛し、あの人はあたしを愛してくれる。その象徴的な行為なのよ」
セックスは愛があれば当然の行為であり、そこに愛のすばらしさがある、
という作者のメッセージは何の疑いもなく受け止めてきた。
しかし、この作品を読みすすめるうちに、
それって、そのよろこび…それ“だけ”を指して女の幸せだといいたかったの?と思ってしまった。
物語の中でも、玲子は「封建的だ」「女は解放されるべきなのに」という批判を受けるが、
古いおんなでけっこうよ。もしそれがあたしのしあわせになるならば。
あたしの愛する人がそんなあたしでいいというなら、それでいいんだわ。
人間は究極はじぶんとじぶんが個人として愛し合っているひとたちだけでいきてゆくものだということを、あたしは知っている。
世界数十億の人の重みよりも、あたしにとって夫は重い。
その夫に尽くし、その夫のために気を配ることこそ、あたしの真実なのだ。
それはわかるんだ。
それは人を愛する心の根本だ。
でも“犠牲”が愛のすべてか?
玲子がまゆみの死んだ母(吉川の前妻)に似ているという設定も、なんだか男性の都合のような気がしてしまう。
女の幸せは男で決まる。
出産後も女性が社会で働く時代、みんなが“自己実現”にやっきになっている時代、
玲子の幸せは“不幸”ともとらえられよう。
逆に作品中では、30前にして独身の由起子が「婚期を逃す」と哀れまれている。
現代に不幸な女性がどれだけいることか(自分も含めて!)。
時代は変わる。幸せの定義も変わる。
男性上位に対する女性のマゾヒズムには理解があると思っていた(?)私だが、
意外にもこの作品にはアナクロニズムを感じてしまった。
今の若い子がこの作品を読んだらどう思うだろうか。
(自分も結婚したらまた読み直します)
映画『おさな妻』につづく
2010年6月11日読了
(集英社文庫 コバルトシリーズ 初版:昭和54年4月)
17歳で孤児となった玲子が、妻を亡くした子持ちの吉川と知り合い、結婚する話。
映画もDVDで見たが、そのことは別に記すとして、
この原作は恋愛うんぬんではなく、「女の幸せ」とは何かを描いているものだと思った。
玲子は、死んだ母に恥じないよう、“強く正しく”生きようとする少女だ。
そして、『のぶ子の悲しみ』のように悲劇的でなく、玲子は幸せをつかむ。
その象徴が“結婚”であり、“愛する人との性の結びつき”なのだ。
さて、ここからだ。
「ぼくはきみをすぐれた芸術品にしようと思っている。
性は高度な芸術活動だし、きみは正常な自然なままの素材としてぼくの前にあらわれた。
男には多くの生きがいがある。(中略)
無垢な姿と心で嫁いできた妻をすばらしい女として完成させるのも、大きなよろこびなんだ」
玲子は高校生、妻、母の三役をこなすことを余儀なくされる。
玲子は吉川が酔って帰ってきた翌日の朝食に気を使い、服の染み抜きは怠らず、
同僚が遊びに来る日にはきちんと髪を結う。
それは“愛する人”に尽くしているということだけではない。
“妻として恥ずかしくないように”という思い、それは夫に対してだけではなく、世間に対してもだ。
そして、夫婦の絆を強めているのが“性”である。
玲子は吉川と幾夜をともにしながら性のよろこびを開花させられる。
「性は独立したものではないということよ。それはあたしのすべてに関係する行為なの。
文字どおり、あたしはあの人を愛し、あの人はあたしを愛してくれる。その象徴的な行為なのよ」
セックスは愛があれば当然の行為であり、そこに愛のすばらしさがある、
という作者のメッセージは何の疑いもなく受け止めてきた。
しかし、この作品を読みすすめるうちに、
それって、そのよろこび…それ“だけ”を指して女の幸せだといいたかったの?と思ってしまった。
物語の中でも、玲子は「封建的だ」「女は解放されるべきなのに」という批判を受けるが、
古いおんなでけっこうよ。もしそれがあたしのしあわせになるならば。
あたしの愛する人がそんなあたしでいいというなら、それでいいんだわ。
人間は究極はじぶんとじぶんが個人として愛し合っているひとたちだけでいきてゆくものだということを、あたしは知っている。
世界数十億の人の重みよりも、あたしにとって夫は重い。
その夫に尽くし、その夫のために気を配ることこそ、あたしの真実なのだ。
それはわかるんだ。
それは人を愛する心の根本だ。
でも“犠牲”が愛のすべてか?
玲子がまゆみの死んだ母(吉川の前妻)に似ているという設定も、なんだか男性の都合のような気がしてしまう。
女の幸せは男で決まる。
出産後も女性が社会で働く時代、みんなが“自己実現”にやっきになっている時代、
玲子の幸せは“不幸”ともとらえられよう。
逆に作品中では、30前にして独身の由起子が「婚期を逃す」と哀れまれている。
現代に不幸な女性がどれだけいることか(自分も含めて!)。
時代は変わる。幸せの定義も変わる。
男性上位に対する女性のマゾヒズムには理解があると思っていた(?)私だが、
意外にもこの作品にはアナクロニズムを感じてしまった。
今の若い子がこの作品を読んだらどう思うだろうか。
(自分も結婚したらまた読み直します)
映画『おさな妻』につづく
2010年6月11日読了
(集英社文庫 コバルトシリーズ 初版:昭和54年4月)