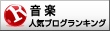SHY - TELEPHONE(1987発表作品)
ちょっと前に、ブラジルの名ヴォーカル、アンドレ・マトスのことをとりあげましたが、
最近、またも辛い情報を入手したので、このバンドを今回取り上げます。
SHY(シャイ)のヴォーカルで有名な、トニー・ミルズが末期がんの中、新作のソロアルバム「BEYOND THE LAW」を発表しました。
何ともすさまじい話です。あのクイーンのフレディ・マーキュリーもエイズと戦いながら、スタジオ・レコーディングをしていたという話がありますが、やはり辛い話です。トニーにとって、これが最後の作品となるという情報もあります。
SHYとはイギリスのメロディアス・ハード・ロックバンドで、1980年代に活躍したバンドです(結果的には21世紀までバンドは存続。リーダーのスティーブ・ハリスというギタリストが脳腫瘍で2011年に死去したためバンド活動は停止。スティーブも早過ぎる他界でした。)。
その時のヴォーカルがトニーなのです。
ちなみに、トニーは1990年にバンドを脱退したあと、1999年に再加入、2006年に再脱退しています。
SHYはハードロック&メタルファンならご存知の方が多いでしょうが、ヒット作がないために、ヒットチャート主義の洋楽ファンは知らないかもしれません。
でも、ポップなサウンドとハイトーン・ヴォーカルは一般の洋楽ファンの耳にも耐えられるだけのものがあると思います。
興味を持った方はSHYを聴いてみてください。
そして、トニー・ミルズというヴォーカリストの生きざまに触れてみていただけたら、幸いです。
動画の「テレフォン」は1987発表の曲ですが、2013年のスティーブ・ハリス追悼コンサート時に撮影されたようです。
Shy - Skydiving
これは21世紀になってから発表された曲です。まるでジャーニーみたいです。ジャーニーのファンに聴かせたい。
Tony Mills - Beyond The Law
2019年発表の6枚目のソロ作品からのリーダートラックです。闘病中とは思えない歌唱です。
Shy - Telephone
この曲のスタジオ作品もアップします。メンバーが若い!トニーの凄まじいハイトーンが聴きどころ。亡きスティーブ・ハリスのギター・ソロも実にセンスがいい。名ギタリストだったんですね。