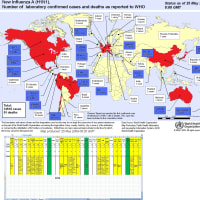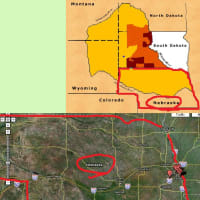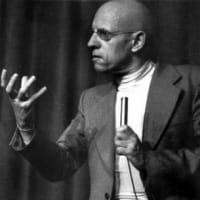映画「ラストマン・スタンディング」は黒澤明監督の用心棒だったからだと思うが、ラスト・エンペラー、ラスト・オブ・モヒカンなど、何かの「最後」を描いた映画は数知れずある。そしてこの度ひょんな事からラスト・サムライを鑑賞する機会を得た事はまさに奇遇と言わざるを得ない。
外国人の作った日本文化や日本国に関する映画やTVで満足した事がない上に、ハリウッド映画独特のステレオタイプの誇張に嫌悪感を抱いている私は、硫黄島からの手紙などハリウッドへ積極的に進出されている渡辺謙氏の最近の活動をアンビヴァレンツを持って眺めていたので、この度ラストサムライが手元にやってきて少々複雑な気持ちだったのだ。
総じて言えば映画としては面白い部分と面白くない部分とが混じっていたと言うのが正直な感想。面白くない部分は山ほどある。武士の生き方が原作者・監督そして最も大切なことだが、主役のトム・クルーズにどれだけ理解してもらえたのであろうか?理解するとは勿論知的理解などではない。何年もの蓄積、つまり伝統の中に入り込んで武士道を感じ取り生きる事でのみ体感される何かを彼らが感得したかどうか、そういう事を気にしていた。日本家屋に住み、古い箪笥や畳の部屋を味わい、時折着物に触れ、また剣道やその他の武道のもつ武の精神を少しでも尊ぶ心を持ち合わせているかどうか、それが気になっているのだ。クエンティン・タランティーノの方がコミカルだが妙に日本を理解しているような気がする。
一見すると西郷隆盛氏を思わせるようなKATSUMOTOと言う武士が、アナクロニズムの権化として描かれているのが失礼千万である。西郷さんの薩摩軍とて小火器で武装する程の柔軟性は持ち合わせていた筈である。そして旧士族に対する警察官か新政府軍人の扱いの酷さが目に余る。威張っているところを見ると警察官にも見える。警察官なら旧士族である。同じ武士としてKATSUMOTO率いる侍軍団を平時にはもっと丁重に扱う筈だし、新政府軍であればもともと数年前まではたかだか農民や商人である。あれほど旧士族に対して威張らないのではないか。
また江戸時代の鎖国日本を西部開拓時代のアメリカ原住民と比較してアナロジーを立てるところがあるが、賛否両論あるにせよ江戸のインフラ整備や教育システムと文盲率などはアメリカ原住民とは全く異なっていた筈である。霊性や生活技術と哲学的知恵と言う点でアメリカ原住民が深いものを持っていた事もわかるが、もっと違った側面、例えば文明と言う観点では江戸とステレオタイプなアメリカ原住民とではおそらく違いがあるだろう。これを一緒くたにして西欧文明が手を差し伸べて近代化したと言うプロットで映画を作ったのであれば、こんな塵芥映画は断固として国外追放しようではないか。江戸文化を形作る程に市民の教養・教育が無ければ明治維新は成功しなかったのであるから。少なくとも欧州では屋外で排泄をし、手づかみで食べていた頃に本邦では箸があり、汲み取りによる肥えの再利用がシステムとして完備されていたのであるから。
最後の突撃ではトム・クルーズも死すべきであった。それでこその侍であるのだが、死期を逃したのみならず、己は抜け駆けして駆け落ちを試みるような素振りを見せるなどは言語道断である。ハリウッド的ハッピーエンドで味付けをされ、日本の婦女子を生き残った白人似非サムライが迎えに行く・・・となんとも私の中の尊皇攘夷の意識を見事に駆り立ててくれた映画であった。
映画「GLORY」では奴隷であった黒人たちを集めた初の黒人部隊を率いる白人将校の奮闘記が描かれていたが、これに酷似しているのは偶然なのか意図的なのか。意図的であるとしたら、言わねばなるまい。「我々は戦争に負けたのであって、奴隷になったのではない。」(白州次郎翁)
最後に。映画を届けてくれたアイヌの友人に感謝します。こういう映画を見ると戦後60年がまだ清算されていないような気になります。ラコタ共和国は独立宣言をしたのに、我々は精神文化、つまり魂まで旧敵国=戦勝国に売り渡してしまったのでしょうかね?
外国人の作った日本文化や日本国に関する映画やTVで満足した事がない上に、ハリウッド映画独特のステレオタイプの誇張に嫌悪感を抱いている私は、硫黄島からの手紙などハリウッドへ積極的に進出されている渡辺謙氏の最近の活動をアンビヴァレンツを持って眺めていたので、この度ラストサムライが手元にやってきて少々複雑な気持ちだったのだ。
総じて言えば映画としては面白い部分と面白くない部分とが混じっていたと言うのが正直な感想。面白くない部分は山ほどある。武士の生き方が原作者・監督そして最も大切なことだが、主役のトム・クルーズにどれだけ理解してもらえたのであろうか?理解するとは勿論知的理解などではない。何年もの蓄積、つまり伝統の中に入り込んで武士道を感じ取り生きる事でのみ体感される何かを彼らが感得したかどうか、そういう事を気にしていた。日本家屋に住み、古い箪笥や畳の部屋を味わい、時折着物に触れ、また剣道やその他の武道のもつ武の精神を少しでも尊ぶ心を持ち合わせているかどうか、それが気になっているのだ。クエンティン・タランティーノの方がコミカルだが妙に日本を理解しているような気がする。
一見すると西郷隆盛氏を思わせるようなKATSUMOTOと言う武士が、アナクロニズムの権化として描かれているのが失礼千万である。西郷さんの薩摩軍とて小火器で武装する程の柔軟性は持ち合わせていた筈である。そして旧士族に対する警察官か新政府軍人の扱いの酷さが目に余る。威張っているところを見ると警察官にも見える。警察官なら旧士族である。同じ武士としてKATSUMOTO率いる侍軍団を平時にはもっと丁重に扱う筈だし、新政府軍であればもともと数年前まではたかだか農民や商人である。あれほど旧士族に対して威張らないのではないか。
また江戸時代の鎖国日本を西部開拓時代のアメリカ原住民と比較してアナロジーを立てるところがあるが、賛否両論あるにせよ江戸のインフラ整備や教育システムと文盲率などはアメリカ原住民とは全く異なっていた筈である。霊性や生活技術と哲学的知恵と言う点でアメリカ原住民が深いものを持っていた事もわかるが、もっと違った側面、例えば文明と言う観点では江戸とステレオタイプなアメリカ原住民とではおそらく違いがあるだろう。これを一緒くたにして西欧文明が手を差し伸べて近代化したと言うプロットで映画を作ったのであれば、こんな塵芥映画は断固として国外追放しようではないか。江戸文化を形作る程に市民の教養・教育が無ければ明治維新は成功しなかったのであるから。少なくとも欧州では屋外で排泄をし、手づかみで食べていた頃に本邦では箸があり、汲み取りによる肥えの再利用がシステムとして完備されていたのであるから。
最後の突撃ではトム・クルーズも死すべきであった。それでこその侍であるのだが、死期を逃したのみならず、己は抜け駆けして駆け落ちを試みるような素振りを見せるなどは言語道断である。ハリウッド的ハッピーエンドで味付けをされ、日本の婦女子を生き残った白人似非サムライが迎えに行く・・・となんとも私の中の尊皇攘夷の意識を見事に駆り立ててくれた映画であった。
映画「GLORY」では奴隷であった黒人たちを集めた初の黒人部隊を率いる白人将校の奮闘記が描かれていたが、これに酷似しているのは偶然なのか意図的なのか。意図的であるとしたら、言わねばなるまい。「我々は戦争に負けたのであって、奴隷になったのではない。」(白州次郎翁)
最後に。映画を届けてくれたアイヌの友人に感謝します。こういう映画を見ると戦後60年がまだ清算されていないような気になります。ラコタ共和国は独立宣言をしたのに、我々は精神文化、つまり魂まで旧敵国=戦勝国に売り渡してしまったのでしょうかね?