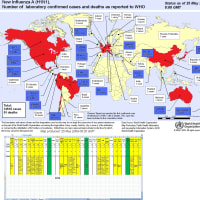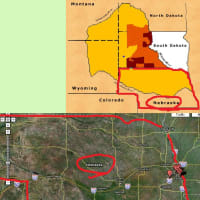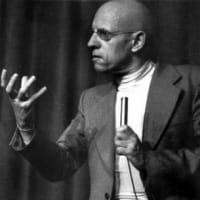「天皇の政治利用」と言う問題が持ち上がってきたが、色々と考えなければならない点があると思っていた。天皇の存在は「日本」と言う国と切り離せないからである。そしてこの日本と言う国を成り立たせるのに必要不可欠な存在が天皇であって、国の運営である政治との微妙な関係について少し思索を巡らせねばならない、そんな気がしていたのである。
「幕府」に対して「朝廷」があり、「天皇」は「征夷大将軍」の任命を行えた。中には執権として天皇を文字通り動かして「政治利用」しようとした輩が居なかった訳ではないが、ヘゲモニー争いの中で権力の座に就く者は「天皇」の存在を必要とした。「天皇」なくして「政治的権力者」はあり得なかったのである。つまり「日本の政治」と「天皇」とは歴史的に「交差しない」が、「切り離す事も出来ない」微妙な距離感なのである。両者が交差すると「親政」や「大日本帝国政府」となり、うまくいかないのだ。
これは「朝廷と幕府」でもよいし「宮中と府中」でも「国事と国務」でもよい。言葉は変わってもこの両者の関係性をまず捉えた上で「天皇と政治」と言う関係を考えていかないと、日本の国柄を無視した暴論が出現するのである。
何よりも政治は本来「政事」であった。これは「まつりごと」であるから「祭事」でもある。ここに「祭祀王」としての「天皇」の本領があるように思う。「俗」ではなく「聖」の部分から、人知ではどうにもならぬ「目に見えない世界」に対して「祈り」を捧げ、「国安かれ、民安かれ」と祈り続けておられるのだ。ここまで掘り下げて初めて、「日本」における「政治」と言うものの意味が見えて来る。「POLITICS」では独立した「POLISの市民」による「人知」が主体の統治体制かも知れないが、日本の「政治」は「POLITICS」とは異なるのだ。「THEOCRACY」に近い体制と言っても良いのではないか。
この辺り、「天皇の政治利用」と言う言葉が「日本の歴史」における「政治史」を誤解させて、「近代西洋民主主義の枠組み」に無理やり日本と言う国の国柄=「国体」を当てはめようとしているかのようにすら見える。議会制民主主義を担う議会と、天皇・皇室とを完全に切り離してスウェーデン式の「国体」に変革しようとでも言うのであろうか。自然に積み重ねられ培われてきたものは、人知で考えてこしらえたものより数段に強い。
「THEOCRACY」的な要素に支えられながら「国事と国務」とが「交差もせず、切り離されもせず」微妙な関係性の上に成り立っているのが「日本の国柄=国体」なのだろう。こう考えると「天皇の政治利用」と言う言葉自体が陰謀的ですらある。「天皇陛下の存在を有難く頂戴して初めて政治が成り立ち続けてきた」のであるから「利用」などとは不遜な発言に過ぎない。まるで「天皇」と「政治」とが全く相容れない別物のような物言いである。伝統的な家庭で言えば、「お父さん」と「お母さん」は個人同士だが、「家庭」としては一体化した存在である。「お父さん」は「お母さん」の実務的決定に対して承認をし、これに権威を与える。「お母さん」が家計を切り盛りしながらも、「お父さん」の堂々たる存在に安心感を覚える・・・こんなところではないか。これが「お父さんのお母さんによる政治利用」と言う事があれば「家庭崩壊」である。伝統的家庭では「お母さん」は「お父さん」を「利用する」立場には無いからである。役割を分担しながら「権威」に一応の価値と重きを置いてきたのが伝統的家庭であり、国家だろう。
これを真っ向から捉え、理解されていると思われるのが亀井金融相の発言だ。長くなるが引用したい。「首相は国会の指名だけで就任できない。天皇陛下から任命されて初めて首相になる。最高裁長官も陛下の任命だ(憲法6条)。国事行為(憲法7条)は多岐にわたる。閣僚は天皇陛下の認証で国務大臣となる。副大臣や検事総長、大使ら認証官も同じだ。法律、政令、条約の公布、国会の召集、衆院の解散、総選挙の公示、勲章の授与も国事行為だ。すべて陛下の御署名と御押印が欠かせない。海外からの賓客とのご会見、各国大使の信任状奉呈式など外交行事も多い。天皇陛下によって政府や国会の決定に正統性と重みが付与される。重責を託された首相らは襟を正し職務に励むよう自覚を促される。政治家の権力行使よりも高い次元で、陛下は国を統治されている。」これはおそらく「日本の政治」が「日本国憲法」に始まるのではなく「律令制度」から不断の体制である事を理解された人間の発言だろう。元来が野蛮人である西洋人の知的・肉体的な闘争の後に勝ち取られたような「民主主義」とは幾重にも色合いが異なる。
<識者の声>
#1(初代内閣安全保障室長・佐々淳行)
【正論】15日付の朝刊各紙は、第1面で大々的に≪小沢-羽毛田≫論争をとりあげていた。天皇陛下の習近平中国国家副主席との「特例」会見が、「天皇の政治利用」につながるかどうかが論点である。筆者は、これは民主党の小沢一郎幹事長と鳩山由紀夫内閣の「天皇の政治利用」だと断ずる。羽毛田信吾宮内庁長官は、国家行政組織法で授権された国家公務員としての任務、すなわち、天皇陛下のご健康を気遣い、一視同仁、政治外交上の中立性を守るべき天皇をお守りする任務を遂行した人物で、記者会見で一党の幹事長に、怒りに任せて公然と辞表を出せといわれる筋合いはない。以下、政治利用と断ずる、その理由を列挙したい。
1、まず一政党の幹事長に宮内庁長官の罷免権はない。いかに役人嫌いであるからといって、天皇の信任を受けている同長官への悪口雑言は、天皇に対しても非礼である。宮内庁長官の任免は、天皇と内閣総理大臣のなすべきことであり、一政党の幹事長が記者会見でいうことではない。
≪「国事行為」の理解に誤り≫
2、小沢幹事長は記者団に「憲法、読んだこと、あるのか」と礼を失する発言をした。確かに、日本国憲法第7条「天皇の国事行為」の項には、「天皇は内閣の助言と承認により、国民のため左の国事に関する行為を行う」とあり、憲法改正、国会の召集、衆議院解散など10項目が限定列挙されている。外交に関しては第8項「批准書や外交文書の認証」と第9項「外国の大使及び公使の接受」だが、要人との会見は明記されていない。
今回の習副主席はもとよりオバマ米大統領をはじめ外国の元首、首相などと天皇との会見は「国事行為」ではなく皇室外交の国際礼譲であり、さらにその助言役は宮内庁の羽毛田長官である。今回の会談を「内閣の方針」による「国事行為」ということこそ、不勉強による誤りである。
3、「1カ月ルールは誰が決めた。法律に書いてあるか」「内閣の決定したことに反対なら辞表を出してから、ものを言え」という小沢幹事長の羽毛田氏非難も多分、国民はその傲慢(ごうまん)で高圧的なもの言いぶりに反感を抱いたと思う。宮内庁への全国各地からの羽毛田氏支持の声はFAX、電話など1日で1千件を超したという。
4、最も妥当性を欠くのは、「天皇の体調がすぐれないなら、優位性の低い行事はお休みになればよい」という発言だが、鳩山総理もこれを支持したという。その大小の決定をするのも内閣なのか。では問うが、中国は大国だからルールに反してもよいが、小国なら接受しなくてもよいのか。身体障害者施設や老人・児童施設への行幸(ぎょうこう)は、大きいことなのか、小さいことなのか。
両陛下の国民をおもいやる優しい心からみれば、また皇室のため、内閣のためにも「大きなこと」ではないのか。この発言も、大小、強弱を問わず何事も公平にという両陛下の大御心(みこころ)にそわぬものと心得る。この点、国会開会式に「もっと思いが入ったお言葉を」といった岡田克也外相の発言にも、天皇の政治利用の下心を感じさせられた。
≪対米関係にも悪影響≫
5、習副主席が天皇に会うことは東アジアの平和と繁栄のために良いこと、と筆者も思う。だが、そんな大きな外交日程がなぜルール通り1カ月前に決められなかったのか。そこに、600人を率いて行われた小沢訪中とのパッケージ・バーター外交ではないかとの疑念を禁じ得ない。
中国が天皇を政治外交に利用したいと考えていることは、江沢民前政権以来、明々白々である。そこへ大訪中団を率いて訪れ、国賓並みの歓迎を受け、このパッケージ外交で迎合したのではないだろうか。報道によれば、小沢幹事長は「解放軍の総司令官だ」と自己紹介したという。自民党から「解放」したというつもりなのだろうが、アメリカはそうは思わない。アメリカの占領からの解放ととり、不快感を強めるだろう。
143人の現役議員全員に、1人1秒足らず、胡錦濤主席と握手させ、写真を撮らせる演出は、まさに宗主国に恭順する近隣国の“朝貢の図”で、誇りある日本人の正視に耐えない。そうすると、先月中旬、学習院大学ホールで上演された中国人民解放軍総政治部歌舞団のオペラを、お忍びで皇太子殿下が観劇したのも、このパッケージの一部だったのかとかんぐりたくなる。総監督の人気オペラ歌手は習副主席の妻だからだ。
小沢氏の記者会見は、いい気分で凱旋(がいせん)した日本で小役人が反抗したことへの怒りの表れと思うが、
天皇を戴(いただ)くのは日本の2千年の政治の知恵であり、世界に比類のない国体である。平時は「権威」として政治に関与せず、民族の存亡にかかわる重大な時に、国民統合の象徴としてお力を発揮していただく
というのが筆者の見解だ。ゆめゆめ一内閣の外交、ましてや党利党略に乱用することは許してはならない。
#2/佐藤優の眼光紙背:第64回
日本の国家体制の根幹に影響を与えうる深刻な出来事が生じた。
12月11日、羽毛田信吾宮内庁長官が、天皇陛下と中国の習近平(シー・チンピン)国家副主席の会見が決まった経緯に関して、<今回、外務省を通じて内々に宮内庁の窓口に打診をされてきたのは1カ月を切った段階でしたから、ルールに照らし、お断りをした。その後、官房長官から、ルールは理解するが日中関係の重要性にかんがみてぜひお願いするという要請があり、私としては、政治的に重要な国だとかにかかわらずやってきたのだからぜひルールを尊重していただきたいと申し上げました。/その後、再度、官房長官から、総理の指示を受けての要請という前提でお話がありました。そうなると、宮内庁も内閣の一翼をしめる政府機関である以上、総理の補佐役である官房長官の指示には従うべき立場。大変異例なことではありますが陛下にお願いした。が、こういったことは二度とあってほしくないというのが私の切なる願いです。>(12月12日asahi.com)と述べた。
その後、天皇陛下を政治利用したという世論の激しい非難が、鳩山由紀夫総理と小沢一郎民主党幹事長に対して向けられている。筆者は、日本は中国に対して過剰サービスをするうべきではないと考える。従って、習近平氏に対しても、もう少し淡々とした対応をとった方がいいと思う。ただし、日本外務省の中国専門家は異なる判断をしたのであろう。今回、生じた問題は、この中国要人の処遇を巡る問題とは位相を異にするところにあると筆者は考える。
そもそも羽毛田長官がいう1カ月ルールなどというものが、どのような根拠によって定められたものなのだろうか? 宮内庁官僚が定めたものではないのか? 天皇陛下との会見は、外交儀礼上、きわめて重要だ。急に組み込まれる外交日程はいくらでもある。公式晩餐会ならば、事前の準備や案内もあるので、突然、日程を組み込むことができないのは当然だ。しかし、会見について1カ月ルールを定め、外交の手足を縛ること自体がきわめて政治的行為であることに羽毛田氏は気づいていないようだ。
羽毛田宮内庁長官が、尊皇のまこと心をもって天皇陛下をお守りしているのかどうかということが問われているのだ。習近平氏の会見を受けるべきでないと羽毛田長官が職業的良心に基づいて考えるならば、「私はそのようなお願いをすることはできません。どうしてもというならば、私を解任してください」と言って頑張るべきだ。そして、解任されても、言い訳をせずに静かに去っていくべきと思う。身を挺して、天皇陛下が政治の嵐に巻き込まれないようにすることが宮内庁職員の仕事ではないか。羽毛田長官が経緯説明という名目で記者会見を行ったことによって、天皇陛下が政治問題に巻き込まれてしまったというのが真相だ。
14日、<民主党の小沢一郎幹事長が、宮内庁の羽毛田信吾長官の発言を「辞表を出してから言うべき」と批判した>(12月14日産経新聞電子版)が、当然のことと思う。羽毛田氏は、選挙で選ばれた政治家ではなく、内閣によって任命された官僚だ。鈴木宗男衆議院外務委員長が<私は陛下のご了解を戴いたのにもかかわらず、その日程のやり取りを表沙汰にした羽毛田宮内庁長官は尊皇精神に欠けていると言いたい。陛下のご健康、ご体調を軽々に平場で口に出すのはいかがなものか>(12月1日付ブログ「ムネオの日記」)と述べているが、その通りと思う。
小沢氏の対応に問題があると考えるならば、国民は次の選挙で、小沢氏並びに同氏と考え方を同じくする民主党の議員を落選させるという形で、影響を行使することができる。これに対して、羽毛田宮内庁長官をはじめとする官僚は、身分保障がなされているので、国民の力によって排除することはできない。南北朝時代、北畠親房、楠木正成など南朝の忠臣は身を挺して後醍醐天皇をお守りした。この精神で宮内庁職員は天皇陛下をお守りすべきと思う。(2009年12月15日脱稿)
「幕府」に対して「朝廷」があり、「天皇」は「征夷大将軍」の任命を行えた。中には執権として天皇を文字通り動かして「政治利用」しようとした輩が居なかった訳ではないが、ヘゲモニー争いの中で権力の座に就く者は「天皇」の存在を必要とした。「天皇」なくして「政治的権力者」はあり得なかったのである。つまり「日本の政治」と「天皇」とは歴史的に「交差しない」が、「切り離す事も出来ない」微妙な距離感なのである。両者が交差すると「親政」や「大日本帝国政府」となり、うまくいかないのだ。
これは「朝廷と幕府」でもよいし「宮中と府中」でも「国事と国務」でもよい。言葉は変わってもこの両者の関係性をまず捉えた上で「天皇と政治」と言う関係を考えていかないと、日本の国柄を無視した暴論が出現するのである。
何よりも政治は本来「政事」であった。これは「まつりごと」であるから「祭事」でもある。ここに「祭祀王」としての「天皇」の本領があるように思う。「俗」ではなく「聖」の部分から、人知ではどうにもならぬ「目に見えない世界」に対して「祈り」を捧げ、「国安かれ、民安かれ」と祈り続けておられるのだ。ここまで掘り下げて初めて、「日本」における「政治」と言うものの意味が見えて来る。「POLITICS」では独立した「POLISの市民」による「人知」が主体の統治体制かも知れないが、日本の「政治」は「POLITICS」とは異なるのだ。「THEOCRACY」に近い体制と言っても良いのではないか。
この辺り、「天皇の政治利用」と言う言葉が「日本の歴史」における「政治史」を誤解させて、「近代西洋民主主義の枠組み」に無理やり日本と言う国の国柄=「国体」を当てはめようとしているかのようにすら見える。議会制民主主義を担う議会と、天皇・皇室とを完全に切り離してスウェーデン式の「国体」に変革しようとでも言うのであろうか。自然に積み重ねられ培われてきたものは、人知で考えてこしらえたものより数段に強い。
「THEOCRACY」的な要素に支えられながら「国事と国務」とが「交差もせず、切り離されもせず」微妙な関係性の上に成り立っているのが「日本の国柄=国体」なのだろう。こう考えると「天皇の政治利用」と言う言葉自体が陰謀的ですらある。「天皇陛下の存在を有難く頂戴して初めて政治が成り立ち続けてきた」のであるから「利用」などとは不遜な発言に過ぎない。まるで「天皇」と「政治」とが全く相容れない別物のような物言いである。伝統的な家庭で言えば、「お父さん」と「お母さん」は個人同士だが、「家庭」としては一体化した存在である。「お父さん」は「お母さん」の実務的決定に対して承認をし、これに権威を与える。「お母さん」が家計を切り盛りしながらも、「お父さん」の堂々たる存在に安心感を覚える・・・こんなところではないか。これが「お父さんのお母さんによる政治利用」と言う事があれば「家庭崩壊」である。伝統的家庭では「お母さん」は「お父さん」を「利用する」立場には無いからである。役割を分担しながら「権威」に一応の価値と重きを置いてきたのが伝統的家庭であり、国家だろう。
これを真っ向から捉え、理解されていると思われるのが亀井金融相の発言だ。長くなるが引用したい。「首相は国会の指名だけで就任できない。天皇陛下から任命されて初めて首相になる。最高裁長官も陛下の任命だ(憲法6条)。国事行為(憲法7条)は多岐にわたる。閣僚は天皇陛下の認証で国務大臣となる。副大臣や検事総長、大使ら認証官も同じだ。法律、政令、条約の公布、国会の召集、衆院の解散、総選挙の公示、勲章の授与も国事行為だ。すべて陛下の御署名と御押印が欠かせない。海外からの賓客とのご会見、各国大使の信任状奉呈式など外交行事も多い。天皇陛下によって政府や国会の決定に正統性と重みが付与される。重責を託された首相らは襟を正し職務に励むよう自覚を促される。政治家の権力行使よりも高い次元で、陛下は国を統治されている。」これはおそらく「日本の政治」が「日本国憲法」に始まるのではなく「律令制度」から不断の体制である事を理解された人間の発言だろう。元来が野蛮人である西洋人の知的・肉体的な闘争の後に勝ち取られたような「民主主義」とは幾重にも色合いが異なる。
<識者の声>
#1(初代内閣安全保障室長・佐々淳行)
【正論】15日付の朝刊各紙は、第1面で大々的に≪小沢-羽毛田≫論争をとりあげていた。天皇陛下の習近平中国国家副主席との「特例」会見が、「天皇の政治利用」につながるかどうかが論点である。筆者は、これは民主党の小沢一郎幹事長と鳩山由紀夫内閣の「天皇の政治利用」だと断ずる。羽毛田信吾宮内庁長官は、国家行政組織法で授権された国家公務員としての任務、すなわち、天皇陛下のご健康を気遣い、一視同仁、政治外交上の中立性を守るべき天皇をお守りする任務を遂行した人物で、記者会見で一党の幹事長に、怒りに任せて公然と辞表を出せといわれる筋合いはない。以下、政治利用と断ずる、その理由を列挙したい。
1、まず一政党の幹事長に宮内庁長官の罷免権はない。いかに役人嫌いであるからといって、天皇の信任を受けている同長官への悪口雑言は、天皇に対しても非礼である。宮内庁長官の任免は、天皇と内閣総理大臣のなすべきことであり、一政党の幹事長が記者会見でいうことではない。
≪「国事行為」の理解に誤り≫
2、小沢幹事長は記者団に「憲法、読んだこと、あるのか」と礼を失する発言をした。確かに、日本国憲法第7条「天皇の国事行為」の項には、「天皇は内閣の助言と承認により、国民のため左の国事に関する行為を行う」とあり、憲法改正、国会の召集、衆議院解散など10項目が限定列挙されている。外交に関しては第8項「批准書や外交文書の認証」と第9項「外国の大使及び公使の接受」だが、要人との会見は明記されていない。
今回の習副主席はもとよりオバマ米大統領をはじめ外国の元首、首相などと天皇との会見は「国事行為」ではなく皇室外交の国際礼譲であり、さらにその助言役は宮内庁の羽毛田長官である。今回の会談を「内閣の方針」による「国事行為」ということこそ、不勉強による誤りである。
3、「1カ月ルールは誰が決めた。法律に書いてあるか」「内閣の決定したことに反対なら辞表を出してから、ものを言え」という小沢幹事長の羽毛田氏非難も多分、国民はその傲慢(ごうまん)で高圧的なもの言いぶりに反感を抱いたと思う。宮内庁への全国各地からの羽毛田氏支持の声はFAX、電話など1日で1千件を超したという。
4、最も妥当性を欠くのは、「天皇の体調がすぐれないなら、優位性の低い行事はお休みになればよい」という発言だが、鳩山総理もこれを支持したという。その大小の決定をするのも内閣なのか。では問うが、中国は大国だからルールに反してもよいが、小国なら接受しなくてもよいのか。身体障害者施設や老人・児童施設への行幸(ぎょうこう)は、大きいことなのか、小さいことなのか。
両陛下の国民をおもいやる優しい心からみれば、また皇室のため、内閣のためにも「大きなこと」ではないのか。この発言も、大小、強弱を問わず何事も公平にという両陛下の大御心(みこころ)にそわぬものと心得る。この点、国会開会式に「もっと思いが入ったお言葉を」といった岡田克也外相の発言にも、天皇の政治利用の下心を感じさせられた。
≪対米関係にも悪影響≫
5、習副主席が天皇に会うことは東アジアの平和と繁栄のために良いこと、と筆者も思う。だが、そんな大きな外交日程がなぜルール通り1カ月前に決められなかったのか。そこに、600人を率いて行われた小沢訪中とのパッケージ・バーター外交ではないかとの疑念を禁じ得ない。
中国が天皇を政治外交に利用したいと考えていることは、江沢民前政権以来、明々白々である。そこへ大訪中団を率いて訪れ、国賓並みの歓迎を受け、このパッケージ外交で迎合したのではないだろうか。報道によれば、小沢幹事長は「解放軍の総司令官だ」と自己紹介したという。自民党から「解放」したというつもりなのだろうが、アメリカはそうは思わない。アメリカの占領からの解放ととり、不快感を強めるだろう。
143人の現役議員全員に、1人1秒足らず、胡錦濤主席と握手させ、写真を撮らせる演出は、まさに宗主国に恭順する近隣国の“朝貢の図”で、誇りある日本人の正視に耐えない。そうすると、先月中旬、学習院大学ホールで上演された中国人民解放軍総政治部歌舞団のオペラを、お忍びで皇太子殿下が観劇したのも、このパッケージの一部だったのかとかんぐりたくなる。総監督の人気オペラ歌手は習副主席の妻だからだ。
小沢氏の記者会見は、いい気分で凱旋(がいせん)した日本で小役人が反抗したことへの怒りの表れと思うが、
天皇を戴(いただ)くのは日本の2千年の政治の知恵であり、世界に比類のない国体である。平時は「権威」として政治に関与せず、民族の存亡にかかわる重大な時に、国民統合の象徴としてお力を発揮していただく
というのが筆者の見解だ。ゆめゆめ一内閣の外交、ましてや党利党略に乱用することは許してはならない。
#2/佐藤優の眼光紙背:第64回
日本の国家体制の根幹に影響を与えうる深刻な出来事が生じた。
12月11日、羽毛田信吾宮内庁長官が、天皇陛下と中国の習近平(シー・チンピン)国家副主席の会見が決まった経緯に関して、<今回、外務省を通じて内々に宮内庁の窓口に打診をされてきたのは1カ月を切った段階でしたから、ルールに照らし、お断りをした。その後、官房長官から、ルールは理解するが日中関係の重要性にかんがみてぜひお願いするという要請があり、私としては、政治的に重要な国だとかにかかわらずやってきたのだからぜひルールを尊重していただきたいと申し上げました。/その後、再度、官房長官から、総理の指示を受けての要請という前提でお話がありました。そうなると、宮内庁も内閣の一翼をしめる政府機関である以上、総理の補佐役である官房長官の指示には従うべき立場。大変異例なことではありますが陛下にお願いした。が、こういったことは二度とあってほしくないというのが私の切なる願いです。>(12月12日asahi.com)と述べた。
その後、天皇陛下を政治利用したという世論の激しい非難が、鳩山由紀夫総理と小沢一郎民主党幹事長に対して向けられている。筆者は、日本は中国に対して過剰サービスをするうべきではないと考える。従って、習近平氏に対しても、もう少し淡々とした対応をとった方がいいと思う。ただし、日本外務省の中国専門家は異なる判断をしたのであろう。今回、生じた問題は、この中国要人の処遇を巡る問題とは位相を異にするところにあると筆者は考える。
そもそも羽毛田長官がいう1カ月ルールなどというものが、どのような根拠によって定められたものなのだろうか? 宮内庁官僚が定めたものではないのか? 天皇陛下との会見は、外交儀礼上、きわめて重要だ。急に組み込まれる外交日程はいくらでもある。公式晩餐会ならば、事前の準備や案内もあるので、突然、日程を組み込むことができないのは当然だ。しかし、会見について1カ月ルールを定め、外交の手足を縛ること自体がきわめて政治的行為であることに羽毛田氏は気づいていないようだ。
羽毛田宮内庁長官が、尊皇のまこと心をもって天皇陛下をお守りしているのかどうかということが問われているのだ。習近平氏の会見を受けるべきでないと羽毛田長官が職業的良心に基づいて考えるならば、「私はそのようなお願いをすることはできません。どうしてもというならば、私を解任してください」と言って頑張るべきだ。そして、解任されても、言い訳をせずに静かに去っていくべきと思う。身を挺して、天皇陛下が政治の嵐に巻き込まれないようにすることが宮内庁職員の仕事ではないか。羽毛田長官が経緯説明という名目で記者会見を行ったことによって、天皇陛下が政治問題に巻き込まれてしまったというのが真相だ。
14日、<民主党の小沢一郎幹事長が、宮内庁の羽毛田信吾長官の発言を「辞表を出してから言うべき」と批判した>(12月14日産経新聞電子版)が、当然のことと思う。羽毛田氏は、選挙で選ばれた政治家ではなく、内閣によって任命された官僚だ。鈴木宗男衆議院外務委員長が<私は陛下のご了解を戴いたのにもかかわらず、その日程のやり取りを表沙汰にした羽毛田宮内庁長官は尊皇精神に欠けていると言いたい。陛下のご健康、ご体調を軽々に平場で口に出すのはいかがなものか>(12月1日付ブログ「ムネオの日記」)と述べているが、その通りと思う。
小沢氏の対応に問題があると考えるならば、国民は次の選挙で、小沢氏並びに同氏と考え方を同じくする民主党の議員を落選させるという形で、影響を行使することができる。これに対して、羽毛田宮内庁長官をはじめとする官僚は、身分保障がなされているので、国民の力によって排除することはできない。南北朝時代、北畠親房、楠木正成など南朝の忠臣は身を挺して後醍醐天皇をお守りした。この精神で宮内庁職員は天皇陛下をお守りすべきと思う。(2009年12月15日脱稿)