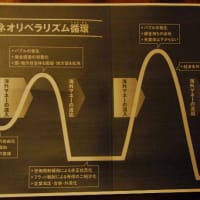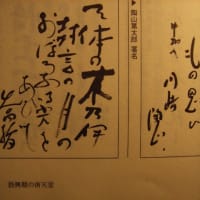その1では1955年の転換が冷戦構造の顕在化に関係していると述べた。今回のその2では1970年の戦後第二の転換について解説する。
ここらの大熊さんの分析は優れていると思う。私は勿論不勉強なのだが、こうした捉え方をしている読物は私は初めてだ。だからご自分でこの記事を読むことを勧めます。60年安保のあと、中核、革マル、社青同、同解放派、再建ブント、・・・と沢山の新左翼セクトが出来ました、と大熊さん、ええ、私もこの辺りまではこの眼で見ました。これらセクトは既成左翼政党には飽き足らず、激しい街頭デモを繰り返し、消耗して行き、既成左翼政党も急速に影響力を失いました。
1970年7月には華青闘、華僑青年闘争委員会と言う在日華僑青年の団体、批判され新左翼諸派は大きな衝撃を受ける。戦争責任や在日、環境保護、ジェンダーと言った問題が出始めたのはこの事が切っ掛けで、それらが出揃ったのは70年後半の転換期から、と言うのが大熊さんの分析です。
更に分析を進めて、「新しい社会運動」の可能性と限界について外国の例、緑の党、も含めて、議論しています。そしてマジョリティーに訴える言葉を失った左派、塩辛い左翼、と述べています。
この項つづく・・・。
ここらの大熊さんの分析は優れていると思う。私は勿論不勉強なのだが、こうした捉え方をしている読物は私は初めてだ。だからご自分でこの記事を読むことを勧めます。60年安保のあと、中核、革マル、社青同、同解放派、再建ブント、・・・と沢山の新左翼セクトが出来ました、と大熊さん、ええ、私もこの辺りまではこの眼で見ました。これらセクトは既成左翼政党には飽き足らず、激しい街頭デモを繰り返し、消耗して行き、既成左翼政党も急速に影響力を失いました。
1970年7月には華青闘、華僑青年闘争委員会と言う在日華僑青年の団体、批判され新左翼諸派は大きな衝撃を受ける。戦争責任や在日、環境保護、ジェンダーと言った問題が出始めたのはこの事が切っ掛けで、それらが出揃ったのは70年後半の転換期から、と言うのが大熊さんの分析です。
更に分析を進めて、「新しい社会運動」の可能性と限界について外国の例、緑の党、も含めて、議論しています。そしてマジョリティーに訴える言葉を失った左派、塩辛い左翼、と述べています。
この項つづく・・・。