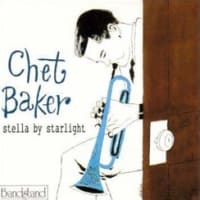J.R.モンテローズは熱烈なファンを持つサックス奏者だ。
彼はちょっと歪んだテナーを豪快に吹く白人である。
だけど私は彼の良さが今ひとつよくわからない。私自身がまだまだだと思う。
このアルバムは、ブルーノートをコレクションしている時に手に入れた一枚である。
だから当時は中身の良さが十分わかった上で購入したわけではない。
ブルーノートの音、そのものが欲しかっただけなのだ。
以前はブルーノートを聴いてさえいれば、正統なジャズに浸っているという実感があった。
それはヨーロッパジャズのような透き通る音ではない。
むせかえるような狭い空間に押し込められた猥雑な音だった。
一言でいえばブルーノートは、最も「人間くさい」音の塊だったのだ。
これが多くのジャズファンを惹きつけた最大の魅力であり、貫禄であった。
このアルバムもそんな雰囲気がたっぷり味わえる。
何せ脇を固めているのが、当時ファンキーブームの主役であったホレス・シルバー(p)初め、アイラ・サリヴァン(tp)、ウィルバー・ウェア(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)という布陣だ。
ブンブン唸りを上げるウィルバー・ウェアのベース、全員を発憤させるフィリー・ジョーのドラミングが特にすばらしい。
J.R.モンテローズもこんな面々に囲まれて、初のリーダー作として記念すべき吹奏を行っている。
「ここは一発、俺なりに堂々と吹いてやろう」
彼のそんな意気込みが全編に渡って感じられるのだ。
但し、冒頭にも書いたが私は彼のサックスがよくわからない。
ソニー・ロリンズのようでもあれば、ハンク・モブレーのようでもある。
まだまだだね~、というベテランリスナーの声が聞こえてきそうだが、そのへんはご容赦願いたい。
ただはっきりしているのは、名盤揃いの1500番台にあって、最もブルーノートらしい一枚であることは確かだ。
でもブルーノートには、なぜこの1枚しか彼のリーダー作がないのだろうか。
だから余計にわからなくなるのだ。