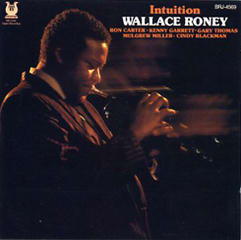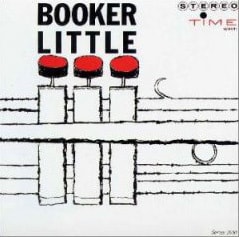とうとうCDでの再発となった。
まさにファン垂涎の的、チェット・ベイカーの「イン・ヨーロッパ」である。
中身は「イン・パリ」でもお馴染みだったが、やっぱりこのジャケットでないと魅力も半減するというものだ。
パンナムの権利問題で、絶対に再発は不可能といわれていただけに、この紙ジャケを手にすると万感胸に迫るものがある。
この喜びはコレクターにしかわからないだろう。
レコードを持っていてもなお、CDもほしくなる。これはそんな作品なのだ。
この写真を撮ったのは、もちろんウィリアム・クラクストンだ。
彼は昨年10月に80歳で惜しくもこの世を去ったが、この人もまたジャズ史に輝かしい足跡を残した名カメラマンだった。
ウエストコーストジャズのイメージを作ったのは明らかに彼である。
彼がひとたびシャッターを切ると、そこには生き生きとしたジャズメンの輝きや当時の世相が写し出されていた。
特にチェット・ベイカーのアルバムにいい写真が多いが、この他にも先日ご紹介した「リー・コニッツ with ウォーン・マーシュ」や、「オリジナル・ジェリー・マリガン・カルテット」、ソニー・ロリンズの「ウェイ・アウト・ウェスト」などは傑作中の傑作といえる。
そういえばジョン・ルイスの「グランド・エンカウンター」に写っている少女は、この 「イン・ヨーロッパ」で抱き合っている女性と同一人物なのだとクラクストン自身が話していたのを思い出す。
コレクターというものは、こういった些細な話をまるで宝物のように大事にする人種なのである。
このアルバムは1曲目の「Summertime」が有名だが、私は3曲目の「Tenderly」が大好きである。
いかにもチェット・ベイカーらしく、切々とトランペットを歌うように吹く。
ただアルバム全体を通してアンニュイなムードが続くので、この雰囲気を楽しめる人でないとお薦めしない。
とはいってもやっぱりこのジャケットだ。
中身の善し悪しはともかく、一ジャズファンとして、これだけで手に入れたくなるという感覚を大切にしたいと思うのである。