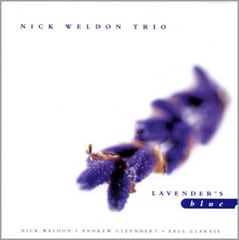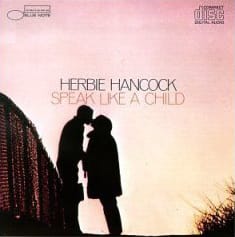ジョー・サンプルと聞いて違和感を覚えてはいけない。
確かに彼はフュージョン界の大物スターであり、泣く子も黙るクルセイダースのリーダーだ。
ストレート・アヘッドなジャズピアノを弾いている姿はあまり見たことがないかもしれない。
しかしボブ・ジェームス同様、一度弾かせたらこれがなかなかのものなのだ。
ジョー・サンプルは数年前に東京ブルーノートで生のステージを観た。
その時はエレキピアノだったので少々がっかりしたが、彼が放つ雰囲気(オーラ?)はこちらにも充分伝わってきた。
ステージ上のパフォーマンスも一流で、客を喜ばせるツボを知っている人だと感じた。
今度はぜひこうしたストレート・アヘッドなピアノトリオを生で聴きたいと思っている。
彼の弾くピアノには独特のフレーズがある。
私はマイケル・フランクスのヒット曲である「アントニオの歌」での間奏が一番彼らしいフレーズだと思っている。私は未だにあのフレーズが頭から離れない。知らない人がいたらぜひ一度聴いてみてほしい。
この時のフレーズがこのアルバムの中にも時々飛び出してきて私を嬉しくさせる。
ジョー・サンプルはもともと高域の音を巧みに転がす人だが、こういったフレーズによってより親近感を覚える人なのだ。
リズム・セクションの二人がこれまたいい。
レイ・ブラウンとシェリー・マンという超大物だ。この二人に囲まれて幸せこの上なしといったサンプルの演奏が続く。
ダイレクト・カッティング録音というのも発売当時はずいぶん話題になったものだ。
味わい深い一作である。