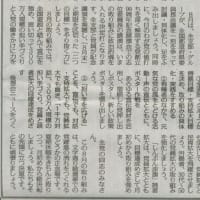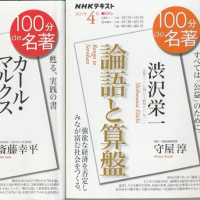憲法9条を使わなければ、国際紛争の火種を消すことはできない!
憲法9条を使わないことは憲法9条否定に加担することになる!
安倍式ゴマカシ・スリカエ積極的平和主義に憲法9条を対置すべきだ!
以下の朝日の社説を読んで、9条を使った平和の枠組みを提起すること、安倍首相のデタラメを論破することはできないことが改めて浮き彫りになりましたので、記事にすることにしました。ま、このことは朝日だけのことではありません。日本の全ての新聞・テレビが陥っていることです。では検証してみます。
朝日新聞 安保法制の与党協議/立ち止まって考えること 2015/3/9 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
朝日新聞 与党安保協議/なんでもありですか 2015/3/1 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
1.「国民の理解を得る努力を抜きに、拙速に進めるべきではない」論。
これは国民の理解を得る努力をすれば、オッケーということです。この場合、「国民の理解を得る」とはどういう状態を言うのでしょうか。曖昧です。これが既成事実化を許している最大の要因です。
2.「武力行使の新3要件などを定めた昨年の閣議決定のタイトル」「『切れ目のない』は『歯止めのない』につながりかねない。あいまいな安保法制を成立させれば、将来に禍根を残す」論。
朝日はこのように言っていますが、では何故閣議決定の撤回を求めないのか!ここに最大のゴマカシがあります。憲法9条を「歯止め」にしない歴史が閣議決定を創りだしている、容認させているのに、朝日は全く気付いていません。ここに日本の思想・思潮があります。この不当性・反動性に誰も気づいていません!ボタンを掛け違ってきたことを容認しているのです。「脅威」で思考停止に陥っているのです。いや、判っているのかも知れません。以下、朝日の閣議決定に対する見解をご覧ください。ゴマカシ・スリカエの歴史が浮き彫りです。
集団的自衛権の容認/この暴挙を超えて 2014/7/2 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
戦後日本が70年近くかけて築いてきた民主主義が、こうもあっさり踏みにじられるものか。安倍首相が検討を表明してからわずかひと月半。集団的自衛権の行使を認める閣議決定までの経緯を振り返ると、そう思わざるを得ない。法治国家としてとるべき憲法改正の手続きを省き、結論ありきの内輪の議論で押し切った過程は、目を疑うばかりだ。…9条と安全保障の現実との溝が、もはや放置できないほど深まったというなら、国民合意をつくった上で埋めていく。それが政治の役割だ。その手続きは憲法96条に明記されている。…自民党の憲法改正草案とその解説には「公益及び公の秩序」が人権を制約することもありうると書いてある。多くの学者や法律家らが、個人の権利より国益が優先されることになると懸念する点だ。極端な解釈変更が許されるなら、基本的人権すら有名無実にされかねない。個人の多様な価値観を認め、権力を縛る憲法が、その本質を失う。…集団的自衛権の行使とは、他国への武力攻撃に対し自衛隊が武力で反撃することだ。それは、自衛隊が「自衛」隊ではなくなることを意味する。くしくもきのう創設60年を迎えたその歴史を通じても、最も大きな変化だ。…解釈は変更されても、9条は憲法の中に生きている。閣議決定がされても、自衛隊法はじめ関連法の改正や新たな法制定がない限り、自衛隊に新たな任務を課すことはできない。議論の主舞台は、いまさらではあるが、国会に移る。ここでは与党協議で見られたような玉虫色の決着は許されない。この政権の暴挙を、はね返すことができるかどうか。国会論戦に臨む野党ばかりではない。草の根の異議申し立てやメディアも含めた、日本の民主主義そのものが、いま、ここから問われる。(引用ここまで)
集団的自衛権/解釈改憲の矛盾あらわ 2014/7/16 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
ならば、自衛隊員の生命の危険が高まることを国民にきちんと説明すべきだ――。こうした切実な問いに、首相は全く答えようとはしなかった。安全保障環境の変化や新3要件の説明を繰り返すばかりで、議論はかみ合いようもない。 一連の安全保障政策の見直しは、日本人だけの生命にかかわる問題ではない。集団的自衛権の行使や多国籍軍への後方支援の拡大は、世界の様々な紛争に日本が軍事的な関与を強めるということだ。紛争当事国の国民の生命や生活に、日本も責任を負わざるを得なくなることを意味する。いまの日本に、それだけの覚悟はあるのか。問題の射程は広く深い。衆参1日ずつですむわけがない。さらなる閉会中審査を含め、徹底した国会論議が不可欠だ。(引用ここまで)
安保論議/「明白な危険」は明白か 2014/10/7 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial2.html
憲法解釈が変わった今、関連する様々な政府の見解や答弁も変わるのか、あるいは変わらないのか。細かく吟味し直されなければならない。(引用ここまで)
日米防衛指針/拡大解釈が過ぎないか 2014/10/9 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
安保条約の基本は、米国の対日防衛義務と、日本の基地提供にある。周辺事態は、安保条約の枠組みや憲法の歯止めと実際の防衛協力との整合性をとるぎりぎりの仕掛けだった。中間報告に書かれた中身が実現すれば、国会の承認が必要な条約の改正に匹敵する大転換と言える。安倍政権は憲法改正を避けて解釈を変更したうえ、ガイドラインの見直しで日米同盟を大きく変質させようとしている。(引用ここまで)
秘密法施行/「丁寧に説明」はどこへ 2014/10/12 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
何が秘密に当たるのかがわからない。秘密の範囲が恣意的に、際限なく広げられる危険性がある。しかも半永久的に公開されないかもしれない――。…先日の衆院予算委員会では、集団的自衛権行使を判断する根拠となった情報が特定秘密に指定され、国会に開示されない懸念などが指摘された。 首相は「行政機関が特定秘密提供を拒む場合には、公文書管理監にその理由を疎明しなければならないので、提供されない場合は極めて限られる」と答えた。それは「あり得る」ということなのか。だとすれば具体的にはどのようなケースが想定されるのかを聞きたいが、議論はそれ以上深まらなかった。ただすべきことはまだ多くある。国会ではギリギリまで議論を重ねてほしい。(引用ここまで)
(衆院選)安倍政権の安保政策/「異次元」の転換を問う 2014/12/1 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
なにより大きな転換は、憲法9条の解釈を変えた7月の閣議決定である。歴代内閣は一貫して「集団的自衛権の行使は認められない」としてきたが、安倍内閣はその一線を越えた。…安倍政権が次々と安全保障政策を転換してゆくなか、国会での審議はあまりに乏しく、そのことについて首相が国民の信を問おうとすることもなかった。首相は「アベノミクス解散」と言うが、安保政策についても、ようやく有権者が判断する機会がやってくる。…安倍政権が進めてきた安保政策をこのまま維持するのか、それとも立ち止まって再考するのか。自衛隊は閣議決定だけでは動かない。今後の法制論議を見すえて、どんな国会の姿を描くのかが問われる。(引用ここまで)
(衆院選)秘密法施行/「不特定」の危うさ 2014/12/10 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
何が秘密か、わからない。「特定秘密」は特定できず、行政の恣意的(しいてき)な判断の余地を残している。それを監視すること自体、難しい。危うさを抱えたままの施行である。…多くの国民の懸念や反対を押しきって施行にこぎ着けた安倍政権が言いたいのは、要するに「政権を信用してほしい」ということだろう。その言い分を、うのみにするわけにはいかない。…ちょうど1年前、安倍政権は数を頼みに特定秘密保護法を成立させた。そして衆院選さなかの施行となった。世論を二分したこの法律がいま、改めて問われるべきだ。(引用ここまで)
憲法と自民党/改正ありきの本末転倒 2015/2/6 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
これが国の最高法規を改めるのにふさわしいやり方なのだろうか。社会や国際情勢の変化に伴い、憲法を変えるほうが国民の利益にかなうということはありえるだろう。そのときは国会で正面から論じ、国民投票に問えばよい。内容よりも改正のやりやすさを優先しようという運び方は、自主憲法制定を党是に掲げる自民党にとっては自然なことなのかもしれないが、本末転倒だと言わざるをえない。…過激派組織「イスラム国」による人質事件はあまりに痛ましかった。しかし、再発防止などの対策を日本の平和主義の根幹である9条の改正に結びつける議論は、短絡に過ぎる。改憲をめぐり安倍首相や自民党の視線の先には、9条改正という本丸がある。かつて首相は憲法改正へのハードルを低くするための96条改正論を唱えたが、世論の反対を受けいまは封印している。環境権創設などの議論を、本丸への新たな助走路として持ち出すべきではない。(引用ここまで)
与党安保協議/無理筋を押し通すな 2015/2/15 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
閣議決定は、自衛隊とともに行動する「米軍部隊の武器等」を防護できる考えを盛り込んでいた。だが政府はオーストラリア軍を念頭に、米軍以外にも対象を広げる方針である。そうなると、あの閣議決定は一体何だったのか、という疑問がふくらむ。公明党から慎重論が出たのは当然だろう。これを認めるのなら、閣議決定の見直しが必要ではないか。与党協議をへて閣議決定したはずなのに、今も法案化をめぐって与党内に溝が残る。このこと自体、閣議決定の中身が生煮えだったことを物語る。…もともと周辺事態法は、海外での武力行使はしないという一線を引いた法律である。とすると、集団的自衛権の行使との兼ね合いはどうなるのか。武力行使への一線を越えるなら、大きな変質と言わざるをえない。政府・自民党の論議から見えてくるのは、自衛隊をすばやく派遣するため、政府の裁量を大きくする考え方だ。国会の関与が不十分なまま、いかようにも解釈可能な法律のもとで、政府の一存で自衛隊を動かす恐れがぬぐえない。根底には、憲法と国会を軽んずる発想がひそんでいないか。そのときの都合で簡単に解釈を拡大するのでは、原則がないも同然だ。安保法制への国民の信頼は得られまい。筋の通らぬ話を与党だけで押し通してはならない。(引用ここまで)
与党安保協議/歯止めはどこへ行った 2015/2/21 6:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
法制定時、「周辺」という考え方について丁寧に説明するよう法案を修正した経緯もある。国民の幅広い理解を得るための措置だった。これを度外視するのは、当時の国会の議論を軽視することにならないか。政府が矢継ぎ早に投げかける提案は、これにとどまらない。自衛隊の支援対象は米軍以外にも広げ、これまで認めてこなかった武器・弾薬の提供や、発進準備中の航空機への給油なども想定している。…周辺事態法の地理的制約も、国会の関与も、国連決議も、政府をしばる要素は外していこうという動きである。集団的自衛権の行使を容認し、自衛隊の活動範囲を広げる昨年7月の閣議決定を、与党だけの協議でさらにゆるめようというのか。政府は「あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする安全保障法制」をめざすという。だがその結果、歯止めのない法案になってしまうなら、国民の理解は得られまい。(引用ここまで)
自衛隊の統制/抑制が生み出す信頼 2015/2/25 4:00
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
自衛隊はこれまで抑制的な姿勢に徹してきたからこそ、幅広い国民の信頼を受けている。制服組の矜持(きょうじ)として、そのことを忘れるべきではあるまい。政治の責任はきわめて重い。集団的自衛権の行使を認めた閣議決定を受け、新たな安全保障法制が焦点となる今国会は、文民統制を洗練させる機会でもある。国会の関与を含め、自衛隊を統制する確かな方策を講じなければならない。(引用ここまで)
愛国者の邪論 どうだったでしょうか。朝日が、いや日本の新聞・テレビ・政党が、最初のボタンを掛け違ってかけていけば、どのようなことが起こるか、明らかではないでしょうか。上記の社説はそのことを示しています。一つひとつのことは、一見すると批判しているようですが、最大の特徴は、社説の最後の部分に象徴的です。ズルズルと安倍首相のペースにはまり込んでしまっていることが浮き彫りになります。
このことは憲法9条を造ってから、警察予備隊以後の歴史が示しています。このことを、踏まえてリセットすることを訴えたいと思います。今こそ9条を使え!です。
長くなしましたので、中断します。つづく