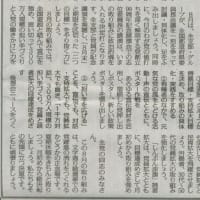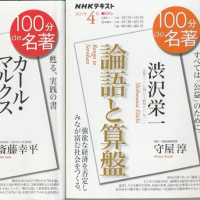そもそも憲法9条が呼びかけている行為は何か!
集団的自衛権/法的安定性は確保されている
読売新聞/2015/7/31 2:00
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150730-OYT1T50212.html
安全保障関連法案は、法的安定性や、過去の政府見解との論理的整合性を十分に確保している。政府は、この点を繰り返し丁寧に説明し、国民の理解を広げねばならない。
十分に確保しているならば、何故繰り返し丁寧に説明しなければならないのか。
参院特別委員会の法案審議が本格化してきた。民主党は、礒崎陽輔首相補佐官の「法的安定性は関係ない」との発言を問題視し、礒崎氏の更迭などを求めている。礒崎氏の発言は、集団的自衛権の行使の限定容認について説明する中で出たものだ。政府見解と相いれず、失言なのは間違いない。政府・与党幹部は、もっと緊張感を持つべきである。
そもそも「集団的自衛権の行使の限定容認について説明する中で」「政府見解と相いれ」ない「失言」がでてくるのは何故か!
安倍首相は、礒崎氏の発言は不適切だとの見解を示しつつ、「安全保障環境の変化を十分に踏まえる必要があるとの認識を示した」と一定の理解も示した。時代の要請に応じて、可能な範囲内で憲法解釈を見直すことは大切だ。
「安全保障環境の変化」「時代の要請に応じて、可能な範囲内で憲法解釈を見直すことは大切だ」ということそのものが問題であるということが、読売も安倍首相派も、全く判っていません。以下、国際安全保障の環境変化が著しい72年見解までの「変化」を一覧してみました。
1947年5月 憲法施行
1950年8月 警察予備隊
1952年4月 サンフランシスコ条約・日米安保条約
1952年7月 保安隊
1954年6月 自衛隊
1959年3月 伊達判決
1959年12月 砂川最高裁判決
1960年6月 日米安保条約
1964年8月 トンキン湾事件
1965年2月 北爆開始
1967年12月 非核三原則
1972年5月 沖縄施政権返還
1972年9月 日中共同声明
1972年10月 集団的自衛権と憲法との関係
北朝鮮は、日本を射程に収める数百発の弾道ミサイルを配備し、核開発を進める。中国も、東シナ海で領海侵入やガス田施設建設、南シナ海でも大規模埋め立てなどの現状変更を試みている。特に、大量破壊兵器とミサイル技術の進展と拡散は、日本にとって深刻な脅威である。この現状に対応するには、集団的自衛権行使の限定容認や、自衛隊と米軍の防衛協力の拡充を通じた抑止力の強化が欠かせない。
北朝鮮の側から視れば、日米の「抑止力」強化は、「危機」そのものですが、読売は、そのことを全くスルーしています。自分のことだけです。これでは外交になりません。対話になりません。問答無用です。
そもそも北朝鮮の数百発の弾道ミサイルは事実か。核開発の実行程度はどれくらいなのか。中国についても、中国側の主張は、正当行為としています。安倍政権は、どのレベルを「不当」としているのか、全く噛み合っていません。ゴマカシです。「大量破壊兵器とミサイル技術の進展」論は、イラクの時に、その誤りは証明されてしまいました。そのことの総括すらしていません。出てくる言葉は「日本にとって深刻な脅威」という言葉だけです。根拠は全く示されていません。
従って、このことが「集団的自衛権行使の限定容認や、自衛隊と米軍の防衛協力の拡充を通じた抑止力の強化が欠かせない」という結論になるのは、全く問題と言わなければなりません。
スリカエ・ゴマカシ・デタラメです。
弾道ミサイル発射を警戒中の米軍艦船が攻撃されるケースは、まさに日本の存立が脅かされる事態であり、集団的自衛権の行使を可能にしておく必要がある。
そもそも「警戒中」という設定そのものが身勝手です。どこを、何のために「警戒」しているのか、全く説明していません。「危機」「脅威」「北朝鮮は不良」ということを前提にしているのです。思考停止も甚だしいと言わなければなりません。
一方で、安保法案は、存立危機事態や必要最小限の武力行使といった厳格な要件を定めることで、過去の最高裁判決や政府見解の基本的な論理を踏襲している。
「厳格な要件を定めることで」ということそのものがゴマカシです。これらの要件は皆抽象的仮想妄想です。
本来、抑止力向上の観点では、昨年5月に有識者会議が提言した全面的な行使の容認が望ましかった。だが、これを退け、限定容認にとどめたのは、法的安定性を重視したためにほかならない。
読売新聞 集団的自衛権/日本存立へ行使「限定容認」せよ 2014/5/16 2:00
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20140515-OYT1T50136.html
報告書は、あらゆる集団的自衛権の行使を認める新解釈と、国家の存立にとって必要最小限の集団的自衛権に限って認める「限定容認論」を併記した。戦闘行動を伴う国連の集団安全保障措置への参加も可能としている。これに対し、安倍首相は、集団的自衛権の全面行使や集団安全保障への全面参加は従来の憲法解釈と論理的に整合しないとして、採用できないと明言した。一方で、「限定容認論」に基づき、与党との調整を進める方針を示した。首相が有識者会議の提言の一部を直ちに否定するのは異例だが、解釈変更に慎重な公明党に配慮した政治的判断と評価できる。集団的自衛権の全面行使が可能になれば、有事における政府の選択肢が増えるのは確かである。ただ、従来の解釈との整合性を保ち、法的な安定性を確保することは法治国家として不可欠だ。海外での戦争参加を認めるかのような誤解を払拭し、幅広い与野党や国民の合意を形成するためにも限定容認論が現実的である。(引用ここまで)
そもそも、憲法9条と現実には様々な乖離(かいり)がある。多くの憲法学者が自衛隊の存在や国際平和協力活動を「違憲」と決めつける。長年の国会での安全保障論議や、自衛隊の国内外での実績と評価を無視した硬直的な主張である。国会では、もっと現実を直視した議論が求められよう。
「憲法9条と現実には様々な乖離」論の場合の「現実」とは何か。「長年の国会での安全保障論議」「自衛隊の国内外での実績と評価」のことを言うのか、全く明らかにしていません。
自衛隊の国内の「実績」は、災害救助です。これは、将来自衛隊の災害救助隊化を暗示しています。もう一つは、海外の「実績」です。これは、憲法9条が歯止めになっていたことを黙殺することはできません。自民党政権は、一貫してアメリカの要請を受けて武力行使に途を開きたかった!しかし、国民の憲法9条を守れ!の声と国会内の共産党などの追及を受けて、曖昧にしたまま「派兵」ではなく「派遣」だということで、「国際貢献」という触れ込みで、海外に「派遣」していたのです。
国民は、こうした自衛隊の活動を「評価」しているのであって、戦争をするための自衛隊を「評価」「応援」しているのではありません。
自衛隊·防衛問題に関する世論調査 -内閣府 http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-bouei/
このことを黙殺して自衛隊の国内外での実績と評価を無視した硬直的な主張である。国会では、もっと現実を直視した議論が求められよう」などということは、ウソで固めた暴論と言わなければなりません。
そもそも読売は、裁判所が、自衛隊違憲論の判断を回避してきたことをどう評価するのでしょうか。
憲法9条訴訟判決一覧 http://tamutamu2011.kuronowish.com/kyuujyouhanketuitirann.htm
名古屋高裁イラク派兵違憲判決確定に対する政府の見解 ... - 防衛省 http://www.mod.go.jp/j/presiding/touben/169kai/san/tou141.html
戦後自民党政権は、既成事実のみを積み重ねをくり返すことで、あたかも「合憲」であるかのようにスリカエ・ゴマカシ・デタラメを謀ってきたのではないでしょうか。
そのような既成事実化の積み重ねの中で、構築したのが「専守防衛」論です。しかし、それでも「集団的自衛権行使違憲」論に立っていたのです。
しかしこの枠組みを打ち破って「集団的自衛権の限定的行使合憲」論に踏み込んだのが安倍首相です。この安倍首相に対して、「自衛隊合憲」論に立つ憲法学者や内閣法制局長官経験者たちから「集団的自衛権行使違憲」論からの批判が噴き出しているのです。
しかし、この批判に、まともに応えていないばかりか、「国際安全保障環境の変化」を口実に、「法的安定性」を否定する主張が出てきて、違憲の安保法制を正当化し採決を強行しようとしているのが、現在の状況ではないでしょうか。
愛国者の邪論は「自衛隊違憲」論の立場に立ちます。しかし、現段階においては、集団的自衛権行使合憲論に立つ安倍派に真っ向対決するのは当然のことですが、同時に「自衛隊合憲」論の立場から「集団的自衛権違憲」論の立場とも、自衛隊の海外派兵に反対するという点においては完全に一致しているのです。そこで、再度強調しておきます。
憲法9条は、「国際紛争を解決する手段」として、
国家による戦争、武力行使、武力による威嚇は永久に放棄したのです。
だから、戦力は保持しないし、戦争の権限である交戦権は否認したのです。
では「国際紛争を解決する」ためには、どんな手段を使うか、です。それは
「自国のことのみ専念するのではなく、他国を無視しない」という「普遍的」「政治道徳の法則」を使って、すなわち「対話と交流」、「非軍事的手段」=「平和的手段」を使って、しかも多様に発展させた外交努力を不断に行うと言っているのです。
このことを、戦後自民党政府は、どれだけ確信的に実行してきたか、そのことが問われているのです。
「憲法9条と現実には様々な乖離」は、憲法9条を形骸化させ、憲法9条を活かして来なかった自民党政権に問題があるということです。
参院特別委には、衆院では審議に加われなかった少数6会派も参加している。次世代の党と新党改革は安保法案に前向きだ。より多角的な質疑を展開してほしい。2015年07月31日01時38分 Copyright©TheYomiuriShimbun(引用ここまで)