
例によって図書館から借りてきた本で、『花森安治の青春』という本を読んだ。
著者は馬場マコトという人だが私の知っているい人ではない。
花森安治といえば、「暮らしの手帖」の編集をしていた人だということは常識としては知っていた。
この本はその花森安治の自伝であるが、実によく書けている。
花森安治という人は「暮らしの手帖」を出版し続けるにあたって、広告を一切取らずに、本の売り上げだけでその本を出版し続けたということは立派なことだと思う。
ある意味では当然といえば当然であるが、この世の中はその当然のことが当然として通らないので、様々な事件に振り回されることに行き着く。
この「暮らしの手帖」は最初からかどうかは定かに知らないが、様々な商品テストをして、その結果を消費者に知らしめることをしていたので、企業から広告をとればその審査が公平性に欠けるという面があったからだとは思うが、それはそれで立派なことには間違いない。
様々な商品の商品テストをする目的は、この世の半分が女性であるからには、女性の役に立つというか、女性の視線に立って物を見る、という想いがそういう行動につながっているかのように描かれている。
しかし、結果的にはそれがメーカーのモノ作りの改善にも、フィードバックし寄与しているようで、それぞれのメーカーはこの「暮らしの手帖」の評価に答えるべく努力したに違いない。
そのことによって日本のモノ作りの評価が世界的に認知されたということにもなったと思われる。
だが、著者の関心はもう一歩踏み込んだ視点で、この花森安治という人物に食い込んでいる。
それは戦後の反体制、反政府に対する信念の強さがどこからきているのか掘り下げるべく彼の生い立ちにまで遡って言及している。
戦後の花森安治は反戦平和で一本筋を通しているが、それは彼の軍隊生活に起因していることは察してあまりあるものだが、「反戦平和を願う」ということは軍隊経験があろうがなかろうが普遍的なことではないかと思う。
我々は先の大戦で、東京をはじめとする都市の空襲や、広島・長崎の原爆投下、あるいは沖縄の悲惨な戦いを経験したが、そういう経験があろうがなかろうが、反戦平和というのは根源的な人間の希求ではなかろうか。
花森安治が軍隊生活の中で過酷な試練に直面したので反戦平和主義になったというのは、ただたんなる思い込に過ぎず、反戦平和は彼一人の占有物ではなく、万人共通の潜在的でなおかつ根源的希求でなければならない。
彼は戦後の具体的な反戦平和の活動には自ら進んで身を投ずることはなかったが、「平和と戦争とどちらが良いか」と問えば、「戦争が良い」という人間はいないわけで「平和が良い」と言うに決まっている。
この判り切ったことをさも重大事であるかのごとく言いふらすといことのは、極めて無責任な行為であって、彼ほどの学識経験に富んだもののすることではないと思う。
戦後の我々の反戦平和運動というのは、常に日本という井戸の中だけの運動であって、戦争というのは相手のある状況であるにも関わらず、自分達だけが一方的に「戦争反対」と言っても意味を成していない。
現にそれは戦後に限って言えば憲法ですでに規定されているわけで、それにもかかわらず日本という井戸の中で、「戦争反対」を叫び続けるということは、天に向かって唾を吐いているのと同じである。
そういうレベルの人々は、自分は戦争反対を叫ぶことで、自分の同胞に対して良い事をしていると思い違いをしているのだ。
その戦争反対というシュプレヒコールは、武力という力の行使をきちんと定義もせず、規定もせず、言葉に無条件反射しているだけで、パブロフの犬と同じ思考回路でしかなく、その裏には自分たちの選出した政治家に対する鬱積した気持の表れではないかと私は考える。
政治家が自分たちの思い描いている政治とかけ離れたことをしているので、それに対する反発が反政府、反体制、反戦という行動をとらせているのではないかと思う。
しかし、民主政治というのは直接民主政治というのはありえないわけで、大勢の中から自分たちの代表を選挙で選出して、その代議員により間接民主制でしか政治は回らないので、それは当然すべての人を納得させるものではない。
自分はこの人が適任だと思うのに、実際に選ばれたのは、自分の考えとは相いれないものが代議員に選出された、ということが常にあるわけで、そうなるとそんな政権に素直に従うのは御免だ、という気持ちになるのも至極当然なことである。
その気持ちを態度で表すとなると、どうしても反戦平和、反政府、反体制、反原発というフレーズになってしまうのである。
「政治が自分の思いとは掛け離れた方向に進んでしまうのではないか」という想いを抱く人は極めて政治に対して真剣に考えている人であって、有象無象の無知蒙昧な人間は、常日頃そういうことを考えているわけではない。
政治に対して真剣に考えているからこそ、現政権の政治家のすることなすことが、心配で心配で居ても立ってもおれない、という危惧は察してあまりあるが、だからと言って直接行動でそれを是正しようという発想は、社会の秩序を乱すことも論を待たない。
そういう想いを抱く人は、並みの人よりは政治的に敏感な感覚であり、純な気持ちを持っており、頭脳明晰で学業成績もきっと良いに違いなかろうが、世の中はそういう綺麗ごとで割り切れるものではなく、権謀術数が渦巻く伏魔殿のようななものだから、若者らしい純な心で眺めていては過誤を招くことになる。
問題は、政治的に早熟で、頭脳明晰、学術優秀な若者ならば、政治の実態を自分の目で確かめ、政治の理念と実態のずれを暴き出して、それを国民に開示して、少しでもより良き方向に引導すべきだと思う。
戦後の反戦平和運動の在り様を見ていると、当時の日本政府があたかも軍国主義に逆戻りするかのようなアピールをしていたが、こんなバカな話もないと思う。
日米安保条約を結ぶと日本が再び戦争に巻き込まれるという論調であったが、ならば日本国憲法の第9条をどう理解しているのかと言いたい。
この論理的矛盾を政治的に早熟で学識経験豊富な人たちが理解していないはずがない。
そんなことは充分理性では判っているが、ただ自分の思い描いた人が自分の思い描いた通りの政治をしていないので、そこに欲求不満が鬱積したということだと思う。
この本の中には花森安治の本人には直接関わりのない事例が記されていたので、これは非常に興味ある部分であった。
それは1933年昭和8年の滝川事件で、その元凶が鳩山由紀夫の祖父にあたる鳩山一郎にあったというのだから実に興味ある歴史的事実といえる。
この鳩山家というのは日本の政治にとってはまさしくガンのような存在で、日本の国益を如何に損なったか計り知れないものがある。
これほど日本の国益を損ねた家系も珍しいのではなかろうか。
この滝川事件というのは、鳩山一郎が文部大臣の時に起きたわけで、彼に人を見る目があれば有り得ない事件であった。
彼が取り巻きの諫言に安易に乗ったが故の大騒動であったわけで、彼にモノの本質を見抜く眼力が備わっておれば、国を誤った道に嵌り込むような愚を起こさなかったと思う。
1930年昭和5年の統帥権干犯問題も、1933年昭和8年の滝川事件も、鳩山一郎という愚鈍な政治家がその時その場に居なかったら、日本はまた違う軌跡を歩んでいたに違いない。
政治家として、政党政治家として、こういう立ち居振る舞いをしておれば、政治的に早熟で純で学術優秀な若者が世を憂う気持ちになるのは当然のことで、その中で最も過激なものがテロに走るということは充分にありうる。
その状況は戦前戦後を通じて変わっていないわけで、政治的に早熟であるが故にその本質に無知な若者が、ことを急いで過激な行動に出ることが絶えないのである。
鳩山一郎と鳩山由紀夫の愚は、自分を過信して、ことの本質を見抜く先見の明に疎く、自分の周りの状況がさっぱり理解出来ていなかったという点に尽きる。
周りから煽てられると嬉しくなってしまって、「豚も木に登る」という状況を呈しているわけで、豚が木に登ったところですぐに落ちることは判り切ったことであるが、本人はそれに気が付かずにいたということだ。
この滝川事件でも、その後1935年昭和10年に起きた美濃部達吉博士の『天皇機関説』の問題でも、明らかに日本の知識階層の個人的なイジメに他ならない。
イジメの口実として、その対象者が「共産主義者ではないか」という嫌疑でもって、自分たちの仲間から排除しようという浄化作用があったわけで、この部分の解明というか、是正は極めて難しいと思う。
というのは、「滝川教授の講演がマルキストに偏っている」という思い込みをイジメた側は「日本にとっては良い事だ」と勘違いしているわけで、「それはただたんなる思い違いで、そんなことはありませんよ」ということをその人たちに分からせることは多分無理なことだと思う。
ここで組織のトップがきちんとしたプリンシプルでもって明確に公明正大な判断を下して、それを実行せしめれば価値観が悪い方のスパイラルに嵌り込むことはなかったが、この部分でトップにきちんとした信念がなかったものだから、声の大きい方にすり寄ったわけだ。
この二つの事件を子細に分析すれば、明らかに今学校現場で起きているイジメの構造と瓜二つなわけで、根も葉もないイジメの本質を探り出せない学校当局が右往左往している図でしかない。
日本を万世一統の誇り高き国家にすべく、日本から天皇制を批判する共産主義者を追い出そうとする思考は、当時の人々の共感を持たらしたことは充分考えられるが、それをより一生懸命に推進しようと頑張る人の存在がはなはだ困るわけで、滝川教授や美濃部教授を排斥しようとした人は、個人的な恨みでイジメたわけではなく、より良い日本にするために共産主義と思しき人たちを排除しようとしたに違いない。
ここで問われるべきは、国民は自分の祖国にどこまで殉ずるか、ということだと思う。
花森安治が東大を出ながら二等兵で招集されたということも、彼の国家に対する殉じ方の一例であったわけで、彼よりも要領のいい人間ならば、合法的に二等兵よりは楽な階級になり得たのに、彼はその部分で胡乱であったということだ。
その経験がトラウマとなって戦後は一貫して反戦平和に殉じたということは、それはそれで結構な事であるが、それとは別の次元で、主権国家の国民は国家存亡の危機になったらどういう態度を取ればいいのだろう。
我々の場合、憲法で戦争放棄を謳っているので、理論的には何一つ抵抗することなく、されるままでいるというのが素直な憲法解釈である。
反戦平和を唱える人、憲法改正に反対する人は、我々の祖国は外国から何をされても、されるままで何一つ抵抗してはならない、という立場を堅持しようとているが、果たしてそれでいいのであろうか。
戦後の花森安治は「それで良い」とはっきりと言い切っている節があるが、本当にそうであろうか。
こういう平和主義者の人たちは、「こちらから戦争を仕掛けなければ相手は決してそれを吹っ掛けてくることはない」と信じ切っているが、果たしてそんな甘い思考でいていいものだろうか。
今、この平和な日本に一人の人間が存在するということは、地球規模での生存競争の中に巻き込まれて適者生存の自然の法則に中で たまたま生かされているにすぎないのである。
だが、今の日本人の発想からすると、「自己の意思で生を得ているのだから、それに対峙するものは排除して、自分は正々堂々と胸を張って生きるのだ」という考え方である。
自分は他者によって生かされているという謙虚な発想には至っていないわけで、自分の欲望に立ち向かうものは全て悪しき者として排除する思考が働く。
だから祖国に殉じるという思考には至らないわけで、祖国は自分にとって欲するものを全部与えてくれる存在で、それを叶えてくれないものならば意味をなさない、という考え方だと思う。
だけれども、普通に常識のあるものならば、打ち出の小槌のように、願えば何でも叶えてくれる社会など有るわけない事は自明のことである。
ふんだんに社会保障を出し、ふんだんに生活保護を出し、ふんだんに学費を免除すれば、社会の活性化が削がれることは自明のことではないか。
北朝鮮のロケットが日本の上空を飛んいるのに、指を咥えて眺めていればいい、というのであれば日米安保もいらないし、沖縄の普天間基地もいらないが、自分の国ぐらいは自分で守りたいという普通の常識があれば、どこかで我慢して、どこかで耐えねばならないことも有り得るはずだ。
その時に、反政府、反体制の態度をあからさまに表明すれば、自分たちの仲間、いわゆる向こう3軒両隣の地域住民としての同胞が腹を立てることは必定だと思う。
この時に真面目に自分の祖国を思う者こそ、率先して自分たちと歩調を合わせようとしない同胞を密告し、糾弾しようとするわけで、結果としてそれが草の根の軍国主義になってしまうのである。
ところが戦後の平和運動というのは、そういう運動が戦後の憲法、戦後の法律で許される環境になったが故に、政治的に尖鋭な思考を持った人がお祭り騒ぎを演じたというわけだ。
御釈迦様の掌の上で、孫悟空が大暴れする図と同じで、それが出来る環境だからこそ、革命ゴッコにうち興じれたというわけだ。
問題は、この革命ゴッコであって、彼らはその時点でゴッコなどという安易な考えではなく、真剣に相手、敵を殺すことを考えていたわけで、その部分を甘く見てはならない。
全学連でも、全共闘でも、核丸でも、中核でも、ブントでも彼らの敵、いわゆる官憲、たとえば警察官や公安を真剣に殺すことを考えていたわけで、それは戦前の青年将校の立ち居振る舞いと全く同じ軌跡を歩んでいる。
「政治の腐敗を正す」という論理の組み立てからして同じ思考回路を辿っているわけで、こういう若者の無軌道で秩序を欠いた行動を褒めるバカな知識人の存在があるわけで、知識人がこういう無軌道な若者を煽てるものだから、日本が良くなるわけが無いではないか。
自分の祖国が余所の国と戦争するともなれば、戦争の理由や原因の如何を問わず、先ずは祖国に殉じる気持ちが無ければ近代国家の国民たりえないのではなかろうか。
戦争の原因や理由が如何なるものであろうとも、その国の為政者、最高責任者としては武力でもってしても事を解決しようと決断したわけで、その決断には国民たるもの従わざるを得ない。
自分の国の為政者の決断に従わないのであれば、当然何らかのペナルテイーが課せられても致しかたないわけで、その場合、自分の国から殺されるか敵に殺されるかの二者択一を迫られることになる。
国の要求する義務に応えるべく兵役についても、その中で行われる軍の制裁、兵隊同士のリンチは、国民に課せられた義務とはまた次元の異なる話で、何故に我々の軍隊ではこういう新兵イジメが蔓延したのであろう。
戦前の日本の軍隊は、それこそ1銭5厘のハガキでいくらでも集められたので、仲間内で一人二人殺しても全体には何の影響もない、という想いであったのだろうか。
しかし、兵、下士官というのは、どこの国の軍隊でも最下層の人間の集団であって、口で言っても理解できない人間の集まりということはあったと思う。
この本の主人公、花森安治のように東大を出て二等兵というのも珍しいケースで、普通は教育のあるものはそれなりのポストになるが、後は有象無象の無頼者という感があったに違いない。
少なくともアメリカやソ連や中国では、兵や下士官の位置づけは、無頼漢、与太者、流れ者という価値観で見られていたので、その中では鉄拳こそがルールであったと思われる。
ところが日本では制度として兵役に就くので、平時ならば普通の善良な市民であるべき人が、心を鬼にして人殺しをしなければならず、そのことを考えると普通の感情を持った人間ではそれが出来ないので、その鬱積がこういう無意味な仲間内のイジメという形の制裁になって組織の中に温存されたのでははなかろうか。
著者は馬場マコトという人だが私の知っているい人ではない。
花森安治といえば、「暮らしの手帖」の編集をしていた人だということは常識としては知っていた。
この本はその花森安治の自伝であるが、実によく書けている。
花森安治という人は「暮らしの手帖」を出版し続けるにあたって、広告を一切取らずに、本の売り上げだけでその本を出版し続けたということは立派なことだと思う。
ある意味では当然といえば当然であるが、この世の中はその当然のことが当然として通らないので、様々な事件に振り回されることに行き着く。
この「暮らしの手帖」は最初からかどうかは定かに知らないが、様々な商品テストをして、その結果を消費者に知らしめることをしていたので、企業から広告をとればその審査が公平性に欠けるという面があったからだとは思うが、それはそれで立派なことには間違いない。
様々な商品の商品テストをする目的は、この世の半分が女性であるからには、女性の役に立つというか、女性の視線に立って物を見る、という想いがそういう行動につながっているかのように描かれている。
しかし、結果的にはそれがメーカーのモノ作りの改善にも、フィードバックし寄与しているようで、それぞれのメーカーはこの「暮らしの手帖」の評価に答えるべく努力したに違いない。
そのことによって日本のモノ作りの評価が世界的に認知されたということにもなったと思われる。
だが、著者の関心はもう一歩踏み込んだ視点で、この花森安治という人物に食い込んでいる。
それは戦後の反体制、反政府に対する信念の強さがどこからきているのか掘り下げるべく彼の生い立ちにまで遡って言及している。
戦後の花森安治は反戦平和で一本筋を通しているが、それは彼の軍隊生活に起因していることは察してあまりあるものだが、「反戦平和を願う」ということは軍隊経験があろうがなかろうが普遍的なことではないかと思う。
我々は先の大戦で、東京をはじめとする都市の空襲や、広島・長崎の原爆投下、あるいは沖縄の悲惨な戦いを経験したが、そういう経験があろうがなかろうが、反戦平和というのは根源的な人間の希求ではなかろうか。
花森安治が軍隊生活の中で過酷な試練に直面したので反戦平和主義になったというのは、ただたんなる思い込に過ぎず、反戦平和は彼一人の占有物ではなく、万人共通の潜在的でなおかつ根源的希求でなければならない。
彼は戦後の具体的な反戦平和の活動には自ら進んで身を投ずることはなかったが、「平和と戦争とどちらが良いか」と問えば、「戦争が良い」という人間はいないわけで「平和が良い」と言うに決まっている。
この判り切ったことをさも重大事であるかのごとく言いふらすといことのは、極めて無責任な行為であって、彼ほどの学識経験に富んだもののすることではないと思う。
戦後の我々の反戦平和運動というのは、常に日本という井戸の中だけの運動であって、戦争というのは相手のある状況であるにも関わらず、自分達だけが一方的に「戦争反対」と言っても意味を成していない。
現にそれは戦後に限って言えば憲法ですでに規定されているわけで、それにもかかわらず日本という井戸の中で、「戦争反対」を叫び続けるということは、天に向かって唾を吐いているのと同じである。
そういうレベルの人々は、自分は戦争反対を叫ぶことで、自分の同胞に対して良い事をしていると思い違いをしているのだ。
その戦争反対というシュプレヒコールは、武力という力の行使をきちんと定義もせず、規定もせず、言葉に無条件反射しているだけで、パブロフの犬と同じ思考回路でしかなく、その裏には自分たちの選出した政治家に対する鬱積した気持の表れではないかと私は考える。
政治家が自分たちの思い描いている政治とかけ離れたことをしているので、それに対する反発が反政府、反体制、反戦という行動をとらせているのではないかと思う。
しかし、民主政治というのは直接民主政治というのはありえないわけで、大勢の中から自分たちの代表を選挙で選出して、その代議員により間接民主制でしか政治は回らないので、それは当然すべての人を納得させるものではない。
自分はこの人が適任だと思うのに、実際に選ばれたのは、自分の考えとは相いれないものが代議員に選出された、ということが常にあるわけで、そうなるとそんな政権に素直に従うのは御免だ、という気持ちになるのも至極当然なことである。
その気持ちを態度で表すとなると、どうしても反戦平和、反政府、反体制、反原発というフレーズになってしまうのである。
「政治が自分の思いとは掛け離れた方向に進んでしまうのではないか」という想いを抱く人は極めて政治に対して真剣に考えている人であって、有象無象の無知蒙昧な人間は、常日頃そういうことを考えているわけではない。
政治に対して真剣に考えているからこそ、現政権の政治家のすることなすことが、心配で心配で居ても立ってもおれない、という危惧は察してあまりあるが、だからと言って直接行動でそれを是正しようという発想は、社会の秩序を乱すことも論を待たない。
そういう想いを抱く人は、並みの人よりは政治的に敏感な感覚であり、純な気持ちを持っており、頭脳明晰で学業成績もきっと良いに違いなかろうが、世の中はそういう綺麗ごとで割り切れるものではなく、権謀術数が渦巻く伏魔殿のようななものだから、若者らしい純な心で眺めていては過誤を招くことになる。
問題は、政治的に早熟で、頭脳明晰、学術優秀な若者ならば、政治の実態を自分の目で確かめ、政治の理念と実態のずれを暴き出して、それを国民に開示して、少しでもより良き方向に引導すべきだと思う。
戦後の反戦平和運動の在り様を見ていると、当時の日本政府があたかも軍国主義に逆戻りするかのようなアピールをしていたが、こんなバカな話もないと思う。
日米安保条約を結ぶと日本が再び戦争に巻き込まれるという論調であったが、ならば日本国憲法の第9条をどう理解しているのかと言いたい。
この論理的矛盾を政治的に早熟で学識経験豊富な人たちが理解していないはずがない。
そんなことは充分理性では判っているが、ただ自分の思い描いた人が自分の思い描いた通りの政治をしていないので、そこに欲求不満が鬱積したということだと思う。
この本の中には花森安治の本人には直接関わりのない事例が記されていたので、これは非常に興味ある部分であった。
それは1933年昭和8年の滝川事件で、その元凶が鳩山由紀夫の祖父にあたる鳩山一郎にあったというのだから実に興味ある歴史的事実といえる。
この鳩山家というのは日本の政治にとってはまさしくガンのような存在で、日本の国益を如何に損なったか計り知れないものがある。
これほど日本の国益を損ねた家系も珍しいのではなかろうか。
この滝川事件というのは、鳩山一郎が文部大臣の時に起きたわけで、彼に人を見る目があれば有り得ない事件であった。
彼が取り巻きの諫言に安易に乗ったが故の大騒動であったわけで、彼にモノの本質を見抜く眼力が備わっておれば、国を誤った道に嵌り込むような愚を起こさなかったと思う。
1930年昭和5年の統帥権干犯問題も、1933年昭和8年の滝川事件も、鳩山一郎という愚鈍な政治家がその時その場に居なかったら、日本はまた違う軌跡を歩んでいたに違いない。
政治家として、政党政治家として、こういう立ち居振る舞いをしておれば、政治的に早熟で純で学術優秀な若者が世を憂う気持ちになるのは当然のことで、その中で最も過激なものがテロに走るということは充分にありうる。
その状況は戦前戦後を通じて変わっていないわけで、政治的に早熟であるが故にその本質に無知な若者が、ことを急いで過激な行動に出ることが絶えないのである。
鳩山一郎と鳩山由紀夫の愚は、自分を過信して、ことの本質を見抜く先見の明に疎く、自分の周りの状況がさっぱり理解出来ていなかったという点に尽きる。
周りから煽てられると嬉しくなってしまって、「豚も木に登る」という状況を呈しているわけで、豚が木に登ったところですぐに落ちることは判り切ったことであるが、本人はそれに気が付かずにいたということだ。
この滝川事件でも、その後1935年昭和10年に起きた美濃部達吉博士の『天皇機関説』の問題でも、明らかに日本の知識階層の個人的なイジメに他ならない。
イジメの口実として、その対象者が「共産主義者ではないか」という嫌疑でもって、自分たちの仲間から排除しようという浄化作用があったわけで、この部分の解明というか、是正は極めて難しいと思う。
というのは、「滝川教授の講演がマルキストに偏っている」という思い込みをイジメた側は「日本にとっては良い事だ」と勘違いしているわけで、「それはただたんなる思い違いで、そんなことはありませんよ」ということをその人たちに分からせることは多分無理なことだと思う。
ここで組織のトップがきちんとしたプリンシプルでもって明確に公明正大な判断を下して、それを実行せしめれば価値観が悪い方のスパイラルに嵌り込むことはなかったが、この部分でトップにきちんとした信念がなかったものだから、声の大きい方にすり寄ったわけだ。
この二つの事件を子細に分析すれば、明らかに今学校現場で起きているイジメの構造と瓜二つなわけで、根も葉もないイジメの本質を探り出せない学校当局が右往左往している図でしかない。
日本を万世一統の誇り高き国家にすべく、日本から天皇制を批判する共産主義者を追い出そうとする思考は、当時の人々の共感を持たらしたことは充分考えられるが、それをより一生懸命に推進しようと頑張る人の存在がはなはだ困るわけで、滝川教授や美濃部教授を排斥しようとした人は、個人的な恨みでイジメたわけではなく、より良い日本にするために共産主義と思しき人たちを排除しようとしたに違いない。
ここで問われるべきは、国民は自分の祖国にどこまで殉ずるか、ということだと思う。
花森安治が東大を出ながら二等兵で招集されたということも、彼の国家に対する殉じ方の一例であったわけで、彼よりも要領のいい人間ならば、合法的に二等兵よりは楽な階級になり得たのに、彼はその部分で胡乱であったということだ。
その経験がトラウマとなって戦後は一貫して反戦平和に殉じたということは、それはそれで結構な事であるが、それとは別の次元で、主権国家の国民は国家存亡の危機になったらどういう態度を取ればいいのだろう。
我々の場合、憲法で戦争放棄を謳っているので、理論的には何一つ抵抗することなく、されるままでいるというのが素直な憲法解釈である。
反戦平和を唱える人、憲法改正に反対する人は、我々の祖国は外国から何をされても、されるままで何一つ抵抗してはならない、という立場を堅持しようとているが、果たしてそれでいいのであろうか。
戦後の花森安治は「それで良い」とはっきりと言い切っている節があるが、本当にそうであろうか。
こういう平和主義者の人たちは、「こちらから戦争を仕掛けなければ相手は決してそれを吹っ掛けてくることはない」と信じ切っているが、果たしてそんな甘い思考でいていいものだろうか。
今、この平和な日本に一人の人間が存在するということは、地球規模での生存競争の中に巻き込まれて適者生存の自然の法則に中で たまたま生かされているにすぎないのである。
だが、今の日本人の発想からすると、「自己の意思で生を得ているのだから、それに対峙するものは排除して、自分は正々堂々と胸を張って生きるのだ」という考え方である。
自分は他者によって生かされているという謙虚な発想には至っていないわけで、自分の欲望に立ち向かうものは全て悪しき者として排除する思考が働く。
だから祖国に殉じるという思考には至らないわけで、祖国は自分にとって欲するものを全部与えてくれる存在で、それを叶えてくれないものならば意味をなさない、という考え方だと思う。
だけれども、普通に常識のあるものならば、打ち出の小槌のように、願えば何でも叶えてくれる社会など有るわけない事は自明のことである。
ふんだんに社会保障を出し、ふんだんに生活保護を出し、ふんだんに学費を免除すれば、社会の活性化が削がれることは自明のことではないか。
北朝鮮のロケットが日本の上空を飛んいるのに、指を咥えて眺めていればいい、というのであれば日米安保もいらないし、沖縄の普天間基地もいらないが、自分の国ぐらいは自分で守りたいという普通の常識があれば、どこかで我慢して、どこかで耐えねばならないことも有り得るはずだ。
その時に、反政府、反体制の態度をあからさまに表明すれば、自分たちの仲間、いわゆる向こう3軒両隣の地域住民としての同胞が腹を立てることは必定だと思う。
この時に真面目に自分の祖国を思う者こそ、率先して自分たちと歩調を合わせようとしない同胞を密告し、糾弾しようとするわけで、結果としてそれが草の根の軍国主義になってしまうのである。
ところが戦後の平和運動というのは、そういう運動が戦後の憲法、戦後の法律で許される環境になったが故に、政治的に尖鋭な思考を持った人がお祭り騒ぎを演じたというわけだ。
御釈迦様の掌の上で、孫悟空が大暴れする図と同じで、それが出来る環境だからこそ、革命ゴッコにうち興じれたというわけだ。
問題は、この革命ゴッコであって、彼らはその時点でゴッコなどという安易な考えではなく、真剣に相手、敵を殺すことを考えていたわけで、その部分を甘く見てはならない。
全学連でも、全共闘でも、核丸でも、中核でも、ブントでも彼らの敵、いわゆる官憲、たとえば警察官や公安を真剣に殺すことを考えていたわけで、それは戦前の青年将校の立ち居振る舞いと全く同じ軌跡を歩んでいる。
「政治の腐敗を正す」という論理の組み立てからして同じ思考回路を辿っているわけで、こういう若者の無軌道で秩序を欠いた行動を褒めるバカな知識人の存在があるわけで、知識人がこういう無軌道な若者を煽てるものだから、日本が良くなるわけが無いではないか。
自分の祖国が余所の国と戦争するともなれば、戦争の理由や原因の如何を問わず、先ずは祖国に殉じる気持ちが無ければ近代国家の国民たりえないのではなかろうか。
戦争の原因や理由が如何なるものであろうとも、その国の為政者、最高責任者としては武力でもってしても事を解決しようと決断したわけで、その決断には国民たるもの従わざるを得ない。
自分の国の為政者の決断に従わないのであれば、当然何らかのペナルテイーが課せられても致しかたないわけで、その場合、自分の国から殺されるか敵に殺されるかの二者択一を迫られることになる。
国の要求する義務に応えるべく兵役についても、その中で行われる軍の制裁、兵隊同士のリンチは、国民に課せられた義務とはまた次元の異なる話で、何故に我々の軍隊ではこういう新兵イジメが蔓延したのであろう。
戦前の日本の軍隊は、それこそ1銭5厘のハガキでいくらでも集められたので、仲間内で一人二人殺しても全体には何の影響もない、という想いであったのだろうか。
しかし、兵、下士官というのは、どこの国の軍隊でも最下層の人間の集団であって、口で言っても理解できない人間の集まりということはあったと思う。
この本の主人公、花森安治のように東大を出て二等兵というのも珍しいケースで、普通は教育のあるものはそれなりのポストになるが、後は有象無象の無頼者という感があったに違いない。
少なくともアメリカやソ連や中国では、兵や下士官の位置づけは、無頼漢、与太者、流れ者という価値観で見られていたので、その中では鉄拳こそがルールであったと思われる。
ところが日本では制度として兵役に就くので、平時ならば普通の善良な市民であるべき人が、心を鬼にして人殺しをしなければならず、そのことを考えると普通の感情を持った人間ではそれが出来ないので、その鬱積がこういう無意味な仲間内のイジメという形の制裁になって組織の中に温存されたのでははなかろうか。










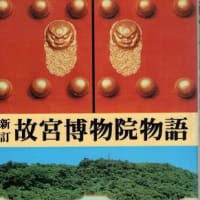




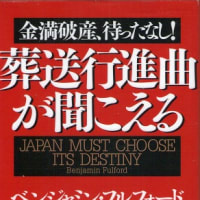

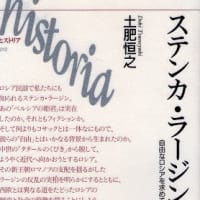
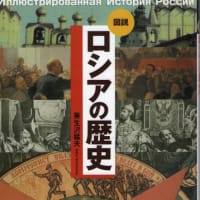

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます