
例によって図書館から借りてきた本で、「老いの流儀」という本を読んだ。
著者は吉本隆明。
私は無学にしてこの人のことをよく知らなかった。
で、この文章をしたためるにあたり、インターネットで検索してみると、戦後の日本の思想界を華麗に泳ぎ切った人物ということがわかった。
戦時中は軍国少年、戦後はマルクス主義者、その後は新左翼の大御所という地位と名誉を経て、並みの世間に迎合する文化人として今日に至ったというのが彼の経歴らしい。
人間の生育の過程で、その人の考え方が変遷するのは、ある程度はごく自然の成り行きというか、正常な生育過程といえる。
子どもの時から考え方が何ら変わらないというのでは、進歩がないということと同じで、普通の人間ならば年を経るにしたがいものの考え方が変遷して当然である。
今、後期高齢者と呼ばれている大部分の老人ならば、その全てがこういう精神的な変遷を経ていると思う。
その中で、ただ彼のみが戦後の大思想家と言われているのは一体どういうことなのであろう。
私に言わしめれば、彼の生き様というのは、その時代時代の潮流に見事に便乗して、常に時代の波頭に立って旗振り役を演じていたということではないかと考える。
戦時中という時代状況の中では、彼自身子供であったため、世間に順応せざるを得なかったが、子どもの域を脱し成人してからの彼は、時代の波を切り裂いて進む船の舳先に立って、押し寄せる波を切り裂く役目を担っていたわけで、そのことによって彼は常に時代の寵児としてもてはやされていたのではなかろうか。
人間の社会というのは、言い方を変えれば人間という種の群れなわけで、その群れは体制のいかんを問わずリーダーを擁立し、そのリーダーのもとに右往左往するのが生き物としての人間の自然に姿だと思う。
群れと群れも、離合集散するのも世の習いで、その時、その場の利害得失によって流動的にならざるを得ないのも自然の摂理だと思う。
ところが成人した後の彼の生き方というのは、常に群れのリーダーに反抗し、抵抗し、足を引っ張り、リーダーの行き先を妨害する行為であったわけだ。
民主的な社会では、為政者、統治者、行政の行為を監視して、その行く先や手段方法に対して反論し、警鐘を鳴らすことが許され、またそのことによって進路が是正されることも大いに大事であるが、お互いに人間である以上、双方ともに失敗とか見当違いとか、見込み違いというものを内包することも当然のことだ。
われわれの国が戦争に負けたのは、明らかに為政者の政策の失敗であったことは歴然としているが、ならば60年安保で反体制側が敗北したことに対して、吉本隆明氏らそれをフォローした陣営は、どういう責任をとったのかと問い直さなければならない。
戦争敗北の失敗を、我々は我々の手で総括しなかったのと同様、安保闘争の敗北に対しても、彼らは目に見える形で総括をしていないのではなかろうか。
こういう文化人、進歩的文化人は、言論によって無知蒙昧な大衆を煽るだけ煽って、失敗したらしたで、その総括はうやむやのまま矛先を変えただけではなかろうか。
私にとってまことに不可解なことは、戦時中の軍国少年が、戦後は見事な平和主義者に成り替わったことだ。
平和主義者であることがそのまま反体制陣営ということは一体どういうことなのであろう。
ここから敷衍される論理からすれば、体制側は全部、戦争屋でなければならないことになってしまうが、現実には「平和、平和」と騒ぎ立てながら暴力をふるったのは、平和主義者の側であって、これは一体どう解釈したらいいのであろう。
平和を説くものが暴力をふるう、これをどう説明したらいいのであろう。
これは彼のみの話ではなく、今の老人、高齢者、戦前生まれの人たちは、すべからこの経緯を経ているわけで、平和を口にしながら一方では暴力を是認しているが、これが我々の民族の本質なのだろうか。
人間が生きるという状況の中で、主義主張、思想というのはかくも無力ということなのであろうか。
まるで原始の人間と同じで、人間は生物学的な生の維持に対しては、思想、思考というのは何の足しにもならないということなのであろうか。
だとすると、吉本隆明が戦後、思想家としてもてはやされたということをどういう風にみればいいのであろう。
戦時中に、体制側からさんざん煮え湯を飲まされた反動として、怨嗟の気持ちで以ってその重しが取り除かれたように、体制に反抗するということであったのであろうか。
戦時中の治安維持法もとでパンドラの箱に押し込められていたものが、その蓋が取れたとたんに、浦島太郎が玉手箱を開け時に出た煙のように、共産主義という怪物が世間に蔓延したということは一体どういうことなのであろう。
あの戦時中にも潜在的な隠れ共産主義者が日本中に潜んでいたということなのであろうか。
私はそうではないと思う。
これは日本の民衆がヒラメのように、常に天下の行く末、その時々の空気、時世、時流というものを上目使いに見ていて、言ってもいい時期、やってもいい時期、暴れてもいい時期、潮目、タイミングに合わせて行動を起こしているものと思う。
その代表選手が、彼、吉本隆明であったんではないかと考える。
しかし、戦後日本の代表的な思想家でも、死は免れないようで、それが眼前に迫ると、それなりに我が身の振り方が気にかかるようになったに違いない。
この本は、対談を活字化したものらしく、書物としては読みやすいが、著作としては練られたものではない。
彼が、著作として、練って練って、推敲に推敲を重ねて書いたものならば、私ごとき者は恐らく読め切れないであろう。
こ難しい単語や語彙の羅列で、私の軽薄な知識ではおそらくついていけないものと思う。
そういう彼も、今後の老人介護の問題について、「最良の方策は年金を多くして、個人がそれぞれに介護する人を雇うシステムが最良だ」と述べているが、そういう理念や理想を口で言うのは一番簡単なことで、それを如何に実現するかで行政も政府も思い悩んでいるではないか。
文化人の無責任なところは、理想論を口では言うが、それを実現する方策を自らは語らず、その実践の責任をすべて行政に追いかぶせて、自分は口先で良い子ぶっているところである。
理想論というのは何も文化人から言われなくとも、市井の大衆にも十分にわかっているが、それを実現しようとすると、「ああ言えばこういう、こう言えばああいう」というわけで、議論百出して結果としては一歩も前進しないところが問題である。
私自身も老いの領域に入っているが、人間が不老長寿を願うというのは、もうそろそろ考え直す時期に来ていると思う。
長生きが目出度いなどという概念を変える時期に来ていると思う。
人間の平均寿命は、年々伸びているわけで、私の子どものころは定年は55歳であったし、織田信長の時代ならば人生50年であったわけで、人間の寿命というはそのあたりが適当ではないかと思う。
姨捨物語もそれをオーバーした時の話であって、それが様々な要因で長生きできるようになったけれども、そのことは必ずしも人間の幸福にはなっていないと思う。
そもそも人間が幸・不幸を認識するのは、自分自身の思い込みにすぎないわけで、それに尺度があるわけではなく、自分が幸福だと思えれば目出度いことだし、不幸だと感じれば、他に視点を向ければ慰めはいくらでもあるわけで、各人各様の考え方にすぎない。
今まで生きてきた人間は、如何なる死にざまを選択しようとも、それが各人の考え方であって、それに一律に幸福感を授けようとしても無理な話だと思う。
この世には老醜という言葉がある。
人間にも賞味期限があるように思うが、この賞味期限の切れた人間には老醜が漂う。
老人は赤ん坊に帰るという言い方もあり、二度わらしという言い方もあるが、ここまで生きてはならないと思う。
賞味期限のあるうちに生を全うしておくべきだと思う。
問題は、功なり、名をなし、財産も作り、もうこの世に仕残したことはない、と思っている人も大勢いると思うが、そういう人が「これで十分納得したからもうこの世から去りたい、人生の幕を下ろしたい」と、本人が思っていてもなかなかそれが許されないことである。
それが許されないので、結局のところ、老醜を曝してまで生き続けなければならない、ということになる。
これこそ惨い人生だと思う。本人にとって残酷な余生だと思う。
本人が十分自分の人生に納得したといっても、周囲がそれを許さない。
私の父は90歳で天寿を全うしたが、最後はオムツの世話になった。
ところが息子の私は親父のオムツの交換だけはどうしてもできなかった。
息子の私が父のそれをしてはあまりにも父が可哀そうに思えてどうしても出来なかった。
自分の子供や孫のときは何の抵抗もなくできたが、父のときはどうしてもできなかった。
それをしてしまっては、今までの父親としての尊厳が瓦解してしまうような気がして、父が可哀そうに思えて、それだけは人にやってもらった。
自分が父の立場になっても、オムツの交換だけは肉親にやってもらいたくないし、他人でも嫌だ。
人はこうまでして生きなければならないものだろうか。
私はそうではないと思う。人としての賞味期限のあるうちに、堂々と、この世と訣別することが可能な世の中に意識改革すべきだと思う。
不老長寿だとか長生きが価値を持つ時代ではないと思う。
死にたくないという人間に死ねというわけではない。
生きたくないという人間の希望を素直に受け入れるだけのことで、これこそ生きる権利と表裏をなすものだと思う。
賞味期限の切れた人間というと、人間の尊厳を蔑にする思考のように思われるが、現実の問題として、死にたい死にたいと思いつつ、口に出して公言しながら生きている老人も一杯いるはずだ。
それでも自死をせずに生きているということは、自死する勇気がないだけのことで、本心は死にたいというのが本音ではないかと思う。
いくら本人が口で言ったからといって、周りが本人の意思を尊重して、その通りのことをしたとしたら殺人となり、当人が罰せられるわけで、この時に何故本人の希望をかなえてやると罰せられるのかを考え直さなければならないと思う。
これは人類の長寿願望、不老長寿を崇めたてまつる倫理感に依拠する普遍的な思考で、死に至らしめる行為を遺棄するのは、太古から連綿と引き継がれた人類の普遍的な願望に反する行為だからだろうと思う。
ところがその時代の人類は、せいぜい50年程度しか生きなかったわけで、老醜を晒すまで生き延びる人が少なかったから、長寿が羨望されたのである。
本来ならば50歳前後で死ぬべき人が、60になっても70になっても80になっても死なないとなれば当然、老醜、痴ほう、寝たきり、下の世話、介護の問題が浮上してくるわけで、それは負の社会基盤整備ということになる。
すればするほど、励めば励むほど泥沼にはまり込んで抜け出れなくなってしまう。
文化的な人々は知識があるが故に、人類が太古から引きずっているその規範から脱却できないでいるものと考える。
姨捨信仰のように、賞味期限が切れたと自覚したものが、自死の道を選択しようとうすると、古代からの倫理念に束縛された周囲の人間は、他人の生の幕引きに手を貸していいかどうか分からなくなるのである。
どんな姿形であろうとも、生きたいという人に死を勧めるわけではない。
生きたくないという人を、無理に生きさせて、生き恥を晒すような老醜を強いてもいいかどうかを問うているのである。
芸能人で、「死ぬまで現役」などと言いながらよぼよぼの姿で登場する人がいるが、立ち居振る舞いに支障をきたすような姿で人前に出るものではないと思う。
特に芸人ならばこそ、自分の立ち居振る舞いも十分にできなければ、芸人としても賞味権限が切れているわけで、綺麗さっぱり引退してこそ、その人の尊厳が維持できると思う。
本人はいくら頑張っているつもりでも、金払って芸を見に来るお客にとってはたまったものではない。
けれども周囲も引退を勧めないわけで、これもある意味で無責任なことで、本人が老醜を晒していることを本人に気付かせることも親切であり、ある種の愛情だと思う。
綺麗に身を引くということは、人間の生き様として極めて重要なことだと思う。
芸能界から引退することもその一つであるが、社会から身を引くときにも、綺麗な身の引き方と、未練がましい汚い身の引き方があると思う。
人間の生き様という意味では、老醜という極端な事例でなくとも、60代70代となって、組織のそれなりの要職にありながら、獄につながれる人間の醜さも十分に考えなければならないと思う。
汚職、贈収賄、公金横領というような経済事犯では、いい歳のオッサンが刑事罰を食らっているが、彼らは子供や孫の前にどういう面下げて出るのか人ごとながら心配でならない。
老いの美学、死に際の美学というものもあると思う。
著者は吉本隆明。
私は無学にしてこの人のことをよく知らなかった。
で、この文章をしたためるにあたり、インターネットで検索してみると、戦後の日本の思想界を華麗に泳ぎ切った人物ということがわかった。
戦時中は軍国少年、戦後はマルクス主義者、その後は新左翼の大御所という地位と名誉を経て、並みの世間に迎合する文化人として今日に至ったというのが彼の経歴らしい。
人間の生育の過程で、その人の考え方が変遷するのは、ある程度はごく自然の成り行きというか、正常な生育過程といえる。
子どもの時から考え方が何ら変わらないというのでは、進歩がないということと同じで、普通の人間ならば年を経るにしたがいものの考え方が変遷して当然である。
今、後期高齢者と呼ばれている大部分の老人ならば、その全てがこういう精神的な変遷を経ていると思う。
その中で、ただ彼のみが戦後の大思想家と言われているのは一体どういうことなのであろう。
私に言わしめれば、彼の生き様というのは、その時代時代の潮流に見事に便乗して、常に時代の波頭に立って旗振り役を演じていたということではないかと考える。
戦時中という時代状況の中では、彼自身子供であったため、世間に順応せざるを得なかったが、子どもの域を脱し成人してからの彼は、時代の波を切り裂いて進む船の舳先に立って、押し寄せる波を切り裂く役目を担っていたわけで、そのことによって彼は常に時代の寵児としてもてはやされていたのではなかろうか。
人間の社会というのは、言い方を変えれば人間という種の群れなわけで、その群れは体制のいかんを問わずリーダーを擁立し、そのリーダーのもとに右往左往するのが生き物としての人間の自然に姿だと思う。
群れと群れも、離合集散するのも世の習いで、その時、その場の利害得失によって流動的にならざるを得ないのも自然の摂理だと思う。
ところが成人した後の彼の生き方というのは、常に群れのリーダーに反抗し、抵抗し、足を引っ張り、リーダーの行き先を妨害する行為であったわけだ。
民主的な社会では、為政者、統治者、行政の行為を監視して、その行く先や手段方法に対して反論し、警鐘を鳴らすことが許され、またそのことによって進路が是正されることも大いに大事であるが、お互いに人間である以上、双方ともに失敗とか見当違いとか、見込み違いというものを内包することも当然のことだ。
われわれの国が戦争に負けたのは、明らかに為政者の政策の失敗であったことは歴然としているが、ならば60年安保で反体制側が敗北したことに対して、吉本隆明氏らそれをフォローした陣営は、どういう責任をとったのかと問い直さなければならない。
戦争敗北の失敗を、我々は我々の手で総括しなかったのと同様、安保闘争の敗北に対しても、彼らは目に見える形で総括をしていないのではなかろうか。
こういう文化人、進歩的文化人は、言論によって無知蒙昧な大衆を煽るだけ煽って、失敗したらしたで、その総括はうやむやのまま矛先を変えただけではなかろうか。
私にとってまことに不可解なことは、戦時中の軍国少年が、戦後は見事な平和主義者に成り替わったことだ。
平和主義者であることがそのまま反体制陣営ということは一体どういうことなのであろう。
ここから敷衍される論理からすれば、体制側は全部、戦争屋でなければならないことになってしまうが、現実には「平和、平和」と騒ぎ立てながら暴力をふるったのは、平和主義者の側であって、これは一体どう解釈したらいいのであろう。
平和を説くものが暴力をふるう、これをどう説明したらいいのであろう。
これは彼のみの話ではなく、今の老人、高齢者、戦前生まれの人たちは、すべからこの経緯を経ているわけで、平和を口にしながら一方では暴力を是認しているが、これが我々の民族の本質なのだろうか。
人間が生きるという状況の中で、主義主張、思想というのはかくも無力ということなのであろうか。
まるで原始の人間と同じで、人間は生物学的な生の維持に対しては、思想、思考というのは何の足しにもならないということなのであろうか。
だとすると、吉本隆明が戦後、思想家としてもてはやされたということをどういう風にみればいいのであろう。
戦時中に、体制側からさんざん煮え湯を飲まされた反動として、怨嗟の気持ちで以ってその重しが取り除かれたように、体制に反抗するということであったのであろうか。
戦時中の治安維持法もとでパンドラの箱に押し込められていたものが、その蓋が取れたとたんに、浦島太郎が玉手箱を開け時に出た煙のように、共産主義という怪物が世間に蔓延したということは一体どういうことなのであろう。
あの戦時中にも潜在的な隠れ共産主義者が日本中に潜んでいたということなのであろうか。
私はそうではないと思う。
これは日本の民衆がヒラメのように、常に天下の行く末、その時々の空気、時世、時流というものを上目使いに見ていて、言ってもいい時期、やってもいい時期、暴れてもいい時期、潮目、タイミングに合わせて行動を起こしているものと思う。
その代表選手が、彼、吉本隆明であったんではないかと考える。
しかし、戦後日本の代表的な思想家でも、死は免れないようで、それが眼前に迫ると、それなりに我が身の振り方が気にかかるようになったに違いない。
この本は、対談を活字化したものらしく、書物としては読みやすいが、著作としては練られたものではない。
彼が、著作として、練って練って、推敲に推敲を重ねて書いたものならば、私ごとき者は恐らく読め切れないであろう。
こ難しい単語や語彙の羅列で、私の軽薄な知識ではおそらくついていけないものと思う。
そういう彼も、今後の老人介護の問題について、「最良の方策は年金を多くして、個人がそれぞれに介護する人を雇うシステムが最良だ」と述べているが、そういう理念や理想を口で言うのは一番簡単なことで、それを如何に実現するかで行政も政府も思い悩んでいるではないか。
文化人の無責任なところは、理想論を口では言うが、それを実現する方策を自らは語らず、その実践の責任をすべて行政に追いかぶせて、自分は口先で良い子ぶっているところである。
理想論というのは何も文化人から言われなくとも、市井の大衆にも十分にわかっているが、それを実現しようとすると、「ああ言えばこういう、こう言えばああいう」というわけで、議論百出して結果としては一歩も前進しないところが問題である。
私自身も老いの領域に入っているが、人間が不老長寿を願うというのは、もうそろそろ考え直す時期に来ていると思う。
長生きが目出度いなどという概念を変える時期に来ていると思う。
人間の平均寿命は、年々伸びているわけで、私の子どものころは定年は55歳であったし、織田信長の時代ならば人生50年であったわけで、人間の寿命というはそのあたりが適当ではないかと思う。
姨捨物語もそれをオーバーした時の話であって、それが様々な要因で長生きできるようになったけれども、そのことは必ずしも人間の幸福にはなっていないと思う。
そもそも人間が幸・不幸を認識するのは、自分自身の思い込みにすぎないわけで、それに尺度があるわけではなく、自分が幸福だと思えれば目出度いことだし、不幸だと感じれば、他に視点を向ければ慰めはいくらでもあるわけで、各人各様の考え方にすぎない。
今まで生きてきた人間は、如何なる死にざまを選択しようとも、それが各人の考え方であって、それに一律に幸福感を授けようとしても無理な話だと思う。
この世には老醜という言葉がある。
人間にも賞味期限があるように思うが、この賞味期限の切れた人間には老醜が漂う。
老人は赤ん坊に帰るという言い方もあり、二度わらしという言い方もあるが、ここまで生きてはならないと思う。
賞味期限のあるうちに生を全うしておくべきだと思う。
問題は、功なり、名をなし、財産も作り、もうこの世に仕残したことはない、と思っている人も大勢いると思うが、そういう人が「これで十分納得したからもうこの世から去りたい、人生の幕を下ろしたい」と、本人が思っていてもなかなかそれが許されないことである。
それが許されないので、結局のところ、老醜を曝してまで生き続けなければならない、ということになる。
これこそ惨い人生だと思う。本人にとって残酷な余生だと思う。
本人が十分自分の人生に納得したといっても、周囲がそれを許さない。
私の父は90歳で天寿を全うしたが、最後はオムツの世話になった。
ところが息子の私は親父のオムツの交換だけはどうしてもできなかった。
息子の私が父のそれをしてはあまりにも父が可哀そうに思えてどうしても出来なかった。
自分の子供や孫のときは何の抵抗もなくできたが、父のときはどうしてもできなかった。
それをしてしまっては、今までの父親としての尊厳が瓦解してしまうような気がして、父が可哀そうに思えて、それだけは人にやってもらった。
自分が父の立場になっても、オムツの交換だけは肉親にやってもらいたくないし、他人でも嫌だ。
人はこうまでして生きなければならないものだろうか。
私はそうではないと思う。人としての賞味期限のあるうちに、堂々と、この世と訣別することが可能な世の中に意識改革すべきだと思う。
不老長寿だとか長生きが価値を持つ時代ではないと思う。
死にたくないという人間に死ねというわけではない。
生きたくないという人間の希望を素直に受け入れるだけのことで、これこそ生きる権利と表裏をなすものだと思う。
賞味期限の切れた人間というと、人間の尊厳を蔑にする思考のように思われるが、現実の問題として、死にたい死にたいと思いつつ、口に出して公言しながら生きている老人も一杯いるはずだ。
それでも自死をせずに生きているということは、自死する勇気がないだけのことで、本心は死にたいというのが本音ではないかと思う。
いくら本人が口で言ったからといって、周りが本人の意思を尊重して、その通りのことをしたとしたら殺人となり、当人が罰せられるわけで、この時に何故本人の希望をかなえてやると罰せられるのかを考え直さなければならないと思う。
これは人類の長寿願望、不老長寿を崇めたてまつる倫理感に依拠する普遍的な思考で、死に至らしめる行為を遺棄するのは、太古から連綿と引き継がれた人類の普遍的な願望に反する行為だからだろうと思う。
ところがその時代の人類は、せいぜい50年程度しか生きなかったわけで、老醜を晒すまで生き延びる人が少なかったから、長寿が羨望されたのである。
本来ならば50歳前後で死ぬべき人が、60になっても70になっても80になっても死なないとなれば当然、老醜、痴ほう、寝たきり、下の世話、介護の問題が浮上してくるわけで、それは負の社会基盤整備ということになる。
すればするほど、励めば励むほど泥沼にはまり込んで抜け出れなくなってしまう。
文化的な人々は知識があるが故に、人類が太古から引きずっているその規範から脱却できないでいるものと考える。
姨捨信仰のように、賞味期限が切れたと自覚したものが、自死の道を選択しようとうすると、古代からの倫理念に束縛された周囲の人間は、他人の生の幕引きに手を貸していいかどうか分からなくなるのである。
どんな姿形であろうとも、生きたいという人に死を勧めるわけではない。
生きたくないという人を、無理に生きさせて、生き恥を晒すような老醜を強いてもいいかどうかを問うているのである。
芸能人で、「死ぬまで現役」などと言いながらよぼよぼの姿で登場する人がいるが、立ち居振る舞いに支障をきたすような姿で人前に出るものではないと思う。
特に芸人ならばこそ、自分の立ち居振る舞いも十分にできなければ、芸人としても賞味権限が切れているわけで、綺麗さっぱり引退してこそ、その人の尊厳が維持できると思う。
本人はいくら頑張っているつもりでも、金払って芸を見に来るお客にとってはたまったものではない。
けれども周囲も引退を勧めないわけで、これもある意味で無責任なことで、本人が老醜を晒していることを本人に気付かせることも親切であり、ある種の愛情だと思う。
綺麗に身を引くということは、人間の生き様として極めて重要なことだと思う。
芸能界から引退することもその一つであるが、社会から身を引くときにも、綺麗な身の引き方と、未練がましい汚い身の引き方があると思う。
人間の生き様という意味では、老醜という極端な事例でなくとも、60代70代となって、組織のそれなりの要職にありながら、獄につながれる人間の醜さも十分に考えなければならないと思う。
汚職、贈収賄、公金横領というような経済事犯では、いい歳のオッサンが刑事罰を食らっているが、彼らは子供や孫の前にどういう面下げて出るのか人ごとながら心配でならない。
老いの美学、死に際の美学というものもあると思う。










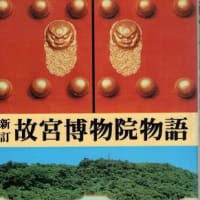




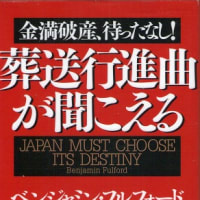

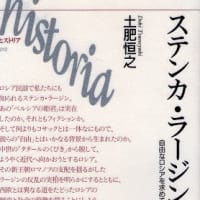
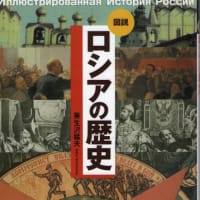

その違いは、人生に希望と目標を持って生きてきたかだと思います。希望と目標を持っている人は、いつまでも若々しいのです。
老いには個人差があるので、年齢で線引きすることは不合理ですね。
「死ぬまで現役」というのが本当は理想ですが、そのためにはその時まで健康なな体を維持しなければならない。
ところが、これがきわめて難しい。
いくら夢と希望を持っていても、運によってそれが阻まれることが往々にしてある。
天命には素直に従うほかないようだ。