文久3年(1863)に英国人ピアソン夫人がこの地に近い居留地97番地にドレス・メーカーを開店した。これが、横浜の洋裁業の始まりと云われている。とあったので、「日本百科全書」編集著者 秋葉隆によれば、次のように記述されていたので、投稿いたします。
日本に西洋の衣服が入ってきたのは16世紀で、戦国時代の武将など特権階級にあった者が、ポルトガル人やスペイン人の南蛮服をまた、江戸の鎖国時代には長崎の出島に在留していたオランダ人の紅毛服を愛用した。
安政5年(1858)には、横浜商会内に軍服や既製服を輸入する商会がつくられた。その2年後の万延1年(1860)日米修好通商条約批准交換使節団に随行した通詞、「中浜万次郎」が、ウイルソン会社製の手回しミシンを咸臨丸で持ち帰った。これが我国におけるミシンの第1号であろう。
翌年の文久2年(1862)に宣教師夫人「ブラウン」より、「沢野辰五郎」らがミシンの使用方法や婦人服の裁縫技術を習っている。同年、服装の簡素化を図る幕府の服制改革が行われ、慶応2年(1866)には、調練用に着物式軍装の戎服(じゅうふく)(筒袖陣羽織、陣(じん)股式(こしき))が採用された。
これより前の元治1年(1864)に「沼間守一」は、イギリス軍州征伐の兵が着用した軍服を作っている。また、「中兵万次郎」の持ち帰ったミシンを買い取った東京・芝の洋服屋、「植村久五郎」は軍服の調製にあたった。
慶応3年(1867)ドイツのロスモンド・ウィルマン商会やラダージ・オエルケ商会と云う注文仕立てのテーラーが、既製服の輸入を始めた。一方、ドレスメーカーのミセス・ピールソンは衣料商と帽子の製造を始めた。翌年、幕府の手で開成所が開設される。この開設所で、ミシンの技術の教授と仕立物の注文を受ける旨の「西洋新式縫物器機伝習並びに仕立て物之事」と題する広告記事が「中外新聞」1号に掲載され、ミシンの発達と裁縫界に一大転機がもたらされた。
明治元年(1868)西洋人によりテーラーやドレスメーカーが開かれた。これらは主として、前者は、香港から進出してきたイギリス人や上海に支店を持つラダージ・オエルケ商会系のドイツ人、後者は、滞日西洋夫人の経営の店が多い。横浜のほか、長崎や神戸にも西洋人が開業していたが、渡来した中国人の洋裁技術者の開業した店の数は、西洋人のそれをしのいだ。明治4年(1871)に慶応義塾内に仕立て局が設けられ、後に丸善洋服部に変わった。
明治3年(1870)に軍服が制定され、陸海軍服が洋式になったほか、官公吏、警察官、郵便配達夫、鉄道員の制服は、すべて洋式になり、明治5年(1872)太政官布告が発せられ、男子の礼服は、衣冠を祭服とするほかは洋装化することとなった。
明治6年(1873)我国初めての洋服裁縫書「改服裁縫初心伝」(勝山力松著)発行されたが、これには礼服(燕尾服)平服(フロックコート)達(だる)摩服(まふく)(詰め襟)背広の裁ち方が詳しく述べられている。明治11年(1878)に原田次郎訳「西洋裁縫教授書」が出版され、採寸、製図、グラージュ尺(比例尺)とインチ尺の図引法、補正など解説が載っていた。
明治18年(1885)皇后宮思召書により洋装が奨励された。翌年に宮廷婦人服が洋装化し、一時的な洋装模倣時代になったが、極端な西欧化への移行に対する非難によって長くは続かなかった。しかし、明治21年(1888)には、大家松之助編訳、「男女西洋服裁縫独案内」なる本が出ており、このころ、最初の服装雑誌も刊行されている。
その後、日清、日露戦争となり、大量の軍服の制作の必要に迫られ、洋裁技術の進歩とミシンの普及を促し、明治後期には、来日西洋人の増加、日本人の洋服着用の流行から洋服業も発展し、西洋人、中国人、日本人の洋服屋は横浜に集中していた。
明治39年(1906)にシンガー裁縫院が設立されると次第に洋裁学校が設立されるようになって、女学校の教科書にも洋裁が取り上げられ、大正中期の生活改善運動や大正デモクラシー思想の影響で、洋服は女子学生の制服、運動着、職業、職業婦人の服、子供服、肌着にまで及んで、大正11年(1923)の関東大震災、昭和7年(1932)の白木屋の大火などを契機にして洋装化が普及した。
一方、すでに洋装のモガ、モボが出現しており、学校の制服やバスガールの制服などにも洋服が採用され、更に、女性の社会進出に伴う職業婦人の増加が洋装化に拍車をかけた。
関東大震災後は、横浜の西洋人の洋服屋は帰国し、中国人、日本人の洋服屋は、東京や神戸へ分散して行ったが、その後、東京が洋服業の中心となった。
すでに、大正10年(1922)に文化裁縫学院(1936年文化服装学院と改称)が、大正14年(1926)には、ドレスメーカー女学院が設立されていた。と記述されていた。

(日本洋裁業発祥顕彰碑に面する通り)

(日本洋裁業発祥顕彰碑)

(あん板)

(ビルの一角を陣取る碑)
日本に西洋の衣服が入ってきたのは16世紀で、戦国時代の武将など特権階級にあった者が、ポルトガル人やスペイン人の南蛮服をまた、江戸の鎖国時代には長崎の出島に在留していたオランダ人の紅毛服を愛用した。
安政5年(1858)には、横浜商会内に軍服や既製服を輸入する商会がつくられた。その2年後の万延1年(1860)日米修好通商条約批准交換使節団に随行した通詞、「中浜万次郎」が、ウイルソン会社製の手回しミシンを咸臨丸で持ち帰った。これが我国におけるミシンの第1号であろう。
翌年の文久2年(1862)に宣教師夫人「ブラウン」より、「沢野辰五郎」らがミシンの使用方法や婦人服の裁縫技術を習っている。同年、服装の簡素化を図る幕府の服制改革が行われ、慶応2年(1866)には、調練用に着物式軍装の戎服(じゅうふく)(筒袖陣羽織、陣(じん)股式(こしき))が採用された。
これより前の元治1年(1864)に「沼間守一」は、イギリス軍州征伐の兵が着用した軍服を作っている。また、「中兵万次郎」の持ち帰ったミシンを買い取った東京・芝の洋服屋、「植村久五郎」は軍服の調製にあたった。
慶応3年(1867)ドイツのロスモンド・ウィルマン商会やラダージ・オエルケ商会と云う注文仕立てのテーラーが、既製服の輸入を始めた。一方、ドレスメーカーのミセス・ピールソンは衣料商と帽子の製造を始めた。翌年、幕府の手で開成所が開設される。この開設所で、ミシンの技術の教授と仕立物の注文を受ける旨の「西洋新式縫物器機伝習並びに仕立て物之事」と題する広告記事が「中外新聞」1号に掲載され、ミシンの発達と裁縫界に一大転機がもたらされた。
明治元年(1868)西洋人によりテーラーやドレスメーカーが開かれた。これらは主として、前者は、香港から進出してきたイギリス人や上海に支店を持つラダージ・オエルケ商会系のドイツ人、後者は、滞日西洋夫人の経営の店が多い。横浜のほか、長崎や神戸にも西洋人が開業していたが、渡来した中国人の洋裁技術者の開業した店の数は、西洋人のそれをしのいだ。明治4年(1871)に慶応義塾内に仕立て局が設けられ、後に丸善洋服部に変わった。
明治3年(1870)に軍服が制定され、陸海軍服が洋式になったほか、官公吏、警察官、郵便配達夫、鉄道員の制服は、すべて洋式になり、明治5年(1872)太政官布告が発せられ、男子の礼服は、衣冠を祭服とするほかは洋装化することとなった。
明治6年(1873)我国初めての洋服裁縫書「改服裁縫初心伝」(勝山力松著)発行されたが、これには礼服(燕尾服)平服(フロックコート)達(だる)摩服(まふく)(詰め襟)背広の裁ち方が詳しく述べられている。明治11年(1878)に原田次郎訳「西洋裁縫教授書」が出版され、採寸、製図、グラージュ尺(比例尺)とインチ尺の図引法、補正など解説が載っていた。
明治18年(1885)皇后宮思召書により洋装が奨励された。翌年に宮廷婦人服が洋装化し、一時的な洋装模倣時代になったが、極端な西欧化への移行に対する非難によって長くは続かなかった。しかし、明治21年(1888)には、大家松之助編訳、「男女西洋服裁縫独案内」なる本が出ており、このころ、最初の服装雑誌も刊行されている。
その後、日清、日露戦争となり、大量の軍服の制作の必要に迫られ、洋裁技術の進歩とミシンの普及を促し、明治後期には、来日西洋人の増加、日本人の洋服着用の流行から洋服業も発展し、西洋人、中国人、日本人の洋服屋は横浜に集中していた。
明治39年(1906)にシンガー裁縫院が設立されると次第に洋裁学校が設立されるようになって、女学校の教科書にも洋裁が取り上げられ、大正中期の生活改善運動や大正デモクラシー思想の影響で、洋服は女子学生の制服、運動着、職業、職業婦人の服、子供服、肌着にまで及んで、大正11年(1923)の関東大震災、昭和7年(1932)の白木屋の大火などを契機にして洋装化が普及した。
一方、すでに洋装のモガ、モボが出現しており、学校の制服やバスガールの制服などにも洋服が採用され、更に、女性の社会進出に伴う職業婦人の増加が洋装化に拍車をかけた。
関東大震災後は、横浜の西洋人の洋服屋は帰国し、中国人、日本人の洋服屋は、東京や神戸へ分散して行ったが、その後、東京が洋服業の中心となった。
すでに、大正10年(1922)に文化裁縫学院(1936年文化服装学院と改称)が、大正14年(1926)には、ドレスメーカー女学院が設立されていた。と記述されていた。

(日本洋裁業発祥顕彰碑に面する通り)

(日本洋裁業発祥顕彰碑)

(あん板)

(ビルの一角を陣取る碑)













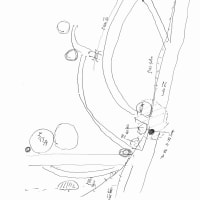






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます