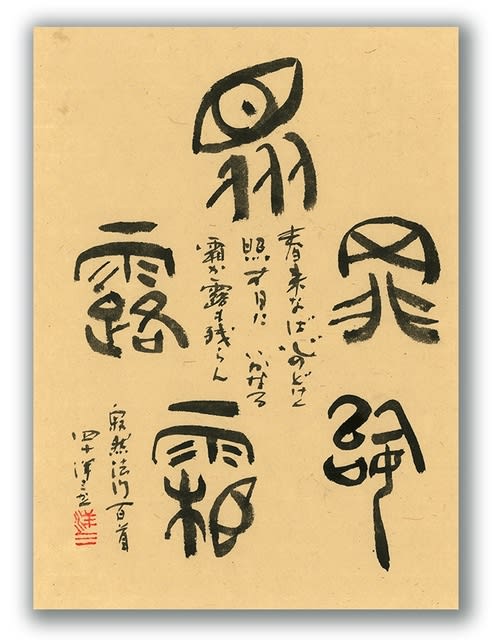日本近代文学の森へ (186) 志賀直哉『暗夜行路』 73 「快」と「不快」 「前篇第二 十二」 その2

2021.2.26
転居して、気持ちが変わったのだろうか、謙作は「仕事」をしようと考える。もちろん小説を書くのが「仕事」である。
謙作の気分はいくらか変った。彼はこの機をはずさず仕事をしようと考えた。尾の道でかかっていた長いものにはちょっと手がつかなかったから、彼は栄花の事を書く事にした。
実際会えばどうだかわからなかった。が、離れていて考えると彼は心から栄花に同情出来た。それには、一方不確かな感じもあった。会ってどうだか知れない人間に対し、離れているがために同情出来るのだという事は仕事の上からも面白い事ではなかった。
しかし実際会えば、そして第三者よりも何かの意味で近づけば、それでも自分は現在の栄花に対し同情が持てるかどうか、彼は甚だ心もとなかった。元々書こうと思う動機が同情──お栄が少しも同情なしに何かいったのに対する腹立にあっただけにこの事は拘泥しないではいられなかった。彼はある時栄花に会って見てもいいと思った。しかし妙に億劫な気もし、なかなか実行は出来そうもなかった。
そして彼は自分が栄花に会った場合を想像して見て、栄花がどういう調子で自分に対するか? そうなる前の栄花を知る自分に対し、栄花も多少その頃の気持を呼び起すであろうか? それとも、そう見せかけ、その頃をなつかしむような風を見せ、心は現在を少しも動かない、そういう荒んだ調子であるか? 何方(どっち)とも想像出来た。しかし何れにしろ、彼はそういう絶望的な栄花にやはり同情出来そうに思えた。絶望的な境地から栄花を救う、こういう気持も彼には起った。児(こ)殺し、それから数々の何か罪、そういうものを総て懺悔し悔改めた栄花。が、それを考えて見て、彼はやはり妙に空ろな栄花しか考えられなかった。もし自分が栄花に会う場合、こういう風に、いわゆる基督信徒根性で簡単にこんな望みを起すとすれば、それは余り感心出来ない事だと考えた。
本統に一人の人が救われるという事は容易な事ではないと思った。
やっぱりなんだか根に持ってる。お栄が、栄花のことに「同情」を持たなかったことが、謙作は気にくわないのだ。
栄花の噂を聞いて、お栄は「ひどい女もあるものね。」と言っただけなのだが、謙作は「悪いのは栄花ではない」と言ってやりたかった。だから、噂だけではなくて、実際に栄花にあってつきあってみたら、自分がそれでも栄花に同情し続けることができるのだろうかと考えるのである。同情しつづけて、更に栄花を救うことができるか? そこまで考えて、謙作は、オレにはまだそんな「基督信徒根性」が残っているんだなと気づき、それを「余り感心出来ない事」だと考える。
謙作がキリスト教を捨てたのは、結局のところそのあまりに厳しい性へ戒律が原因だった。ごく簡単にいえば、遊女と遊ぶか、信仰を守るかの二者択一になってしまったのだ。この辺が、明治期のプロテスタントのネックだったのではなかろうか。そんな二者択一で信仰が考えられたら、キリスト教が持っている深い「思想」を理解する以前に「棄教」になってしまうのは目に見えている。
謙作が、栄花という「不幸な遊女」を救いたいと思うことを「基督信徒根性」だと考えてしまうのは、やはり、謙作が、つまりは志賀直哉が、キリスト教の思想を深く理解していないことの反映としか思えない。
だから、「本統に一人の人が救われるという事は容易な事ではないと思った。」という謙作の感慨には、残念ながら、真実味がない。「救われる」ということはどういうことなのかについて、ちっとも考えが深まっていないように思えるからだ。
この後に、「蝮のお政」のことがでてくる。お政は、京都の八坂神社の下の寄席で、自身の一代記を芝居にしていたというのである。そのお政を芝居小屋の入り口で見かける。
丁度電燈の下で謙作はその顔をよく見る事が出来た。それは気六ヶしそうな、非常に憂鬱な顔だった。心が楽しむ事の決してないような顔だった。
彼は蝮のお政については何も知らなかった。長い刑期を神妙にして、そして悔改めた事を認められ、何かの機会に出獄して、そして、今は生活のために一座を組織し、旅から旅と自身の過去の罪を売物に、芝居をして廻っている。──これだけの事が考えられるのであった。
そしてこれだけでも彼はその時見たお政の顔つきからその心持を察するには十二分だった。それが妙にはっきり映って来た。彼は淋しい、いやな気持になった。彼はお政のした悪い事をしらなかったし、それに何の同情も持てなかったが、それでもそういう悪事を働きつつあった時の心の状態に比し、今が、よりいい状態だとはいえない気がして、変に淋しい不快(いや)な気持になった。それは何れもいい状態でないに違いない。しかしお政自身の心として何方(どっち)がより幸福な状態であるかを想像すると、悪事を働きつつあった頃の生々した張りのある心の上の一種の幸福は今は全く彼女から消え去ったに違いないと思わないわけに行かなかった。そして、その代りに今何があるか。自身の罪を芝居にして廻っている。それは全く芝居に違いなかった。懺悔でも何でも要するに芝居に違いなかった。しかも見物はそれが当の人物である所に何らかの実感を期待するだけに一層彼女には苦しい偽善が必要となるに違いなかった。こういう生活が彼女をよくするはずはない。そして、一度罪を犯した者は悔改めてからも、たといお政ほど罪に露骨な関係を持った生活をしないまでも、きっとこういう心の不幸に苦しめられないものはないだろうと彼は思った。
お政は脊(せい)の高い男性的な強い顔をした女だった。若い頃は押出しの立派な女だったろうと思われる所がある。
謙作は今、栄花の事を書こうと思うと、かつて見たその女を憶い出さずにはいなかった。彼は現在の栄花を考え、気の毒なそして息苦しいような感じを持ちながら、しかいわゆる悔改めをしてお政のような女になる事を考えると一層それは暗い絶望的な不快(いや)な気持がされるのであった。本統の救いがあるならいい。が、真似事の危っかしい救いに会う位ならやはり「斃(たお)れて後やむ」それが栄花らしい、むしろ自然な事にも考えられるのであった。
彼は会いに行く機会を作る事が億劫だったので、そのまま書き出した。ある時彼は山本に会った時、その事を話すと、山本は、
「ああ、先日ネ、家内と牡丹を見に行く時、両国で船に乗ろうとして待っていると路次の口に立って此方(こっち)を見ているのが、どうも栄花じゃあないかと思った。やはりそうだったのだネ」といった。実際その路次に栄花の桃奴の家はあったのである。
「会って見る興味はないかい?」
「そうだネ、ない事もないが……」山本は言葉を濁し、乗気な風を見せなかった。
蝮のお政の「心の状態」は、悪事を働いていたときと、こうして懺悔の芝居をしているときとでは、どっちが「いい」のだろうかと謙作は考えるわけだが、不思議な思考回路である。
「悪事」を働いているときの、「生々した張りのある心の上の一種の幸福」とは何だろうか。道徳に反した恋をして、その結果相手を殺したとかそういう「悪事」が想定されるが、そしてそうした行為に「一種の幸福」感が伴うということはもちろんあるだろうが、その「心の状態」と、その後の「心の状態」を同じ平面にならべて、どっちがいいか? などと比べるのはナンセンスに過ぎはしないか。
「心の状態」はどうであれ、その行為が「悪」かどうかは、人間の生き方をかけた問題であるはずだ。「心の状態」など、それに付随して出てくる感情にすぎない。「いやな気」がしようと、正しいことはするし、「幸福」を感じようと、悪は避ける、これが人間の基本だろう。
しかし、そんなふうな常識的なことを言ってもしょうがない。志賀直哉にとっては「心の状態」こそが、すべての基準なのだ。
この引用部分に、「不快(いや)な」を初めとする感情を表す言葉がどれだけ出て来るかを詳しく見ると、ほんとうに驚く。ほとんどが、それだ。
栄花にしても、今のままでは「気の毒なそして息苦しいような感じ」がするけれど、だからといって生半可に救われるのも、「暗い絶望的な不快(いや)な気持」になる。だからいっそのこと、「斃(たお)れて後やむ」──つまりは死ぬまで今のままで突っ走る、それが「自然」だというわけである。なんという論理だろう。いやこれはもう論理ですらない。
栄花の人生について、謙作は考えているように見えながら、実は、何も考えていない。考えているのは、自分の「感じ」だけだ。自分が「不快」に感じるような生き方は認めたくないというだけのことで、そんなことは栄花にとってはどうでもいいことなのだ。
志賀直哉における「快・不快」は、志賀直哉論の要となるのだろうが、それにしても、改めてその凄まじさを目の当たりにして、呆れるほかはない。