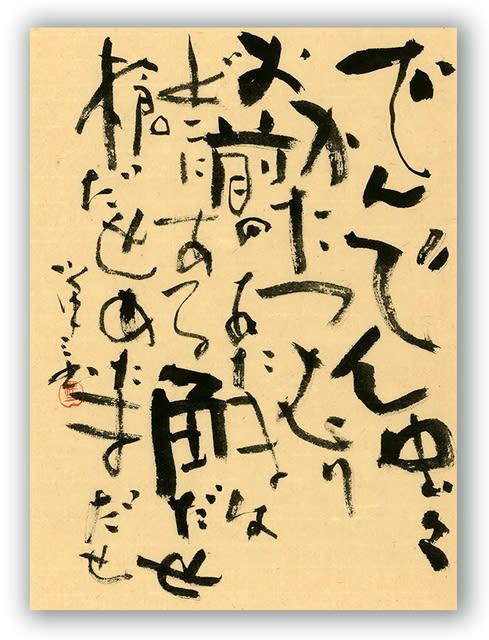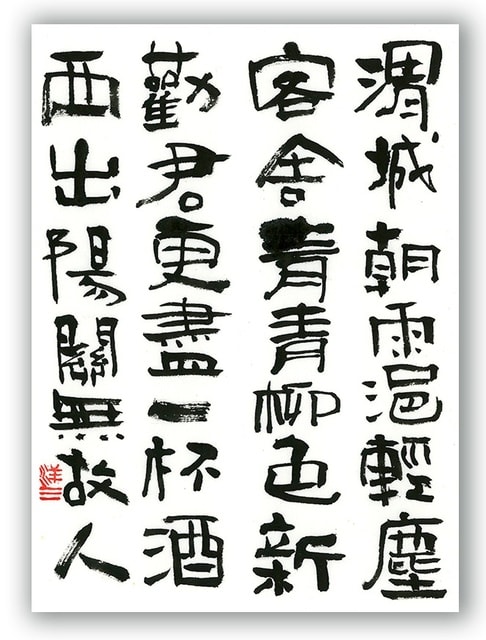日本近代文学の森へ (150) 志賀直哉『暗夜行路』 37 放蕩のゆくえ 「前篇第一 十一」その2

2020.4.26
遊郭の入口でしばし逡巡した謙作だったが、とうとう意を決して入っていく。しかし「中でのこと」はまったく書かれずに、次の行は、いきなりこんなふうに書かれる。
二時間ほどして彼は往きとは全く異った気持で曲輪を出て来た。自身でも不思議なほど気安い気持だった。悔ゆるというような気持は全くなかった。
ここまでの道のりの描写の長さからすると、実にあっけないことだが、案外こんな感じがリアルというものかもしれない。
そして、その後に、「中でのこと」が振り返ってこんなふうに描かれる。
女は醜い女だった。青白くて、平ったい顔の、丁度裏店(うらだな)のかみさんのような女だった。実に鈍く善良な女だった。彼はもう二度とその女を見たいとは思わなかったが、何かで、これからも好意を示したい気が切(しき)りにした。為替で寄附金をしてもいいと考えた。女は一人の客ごとに雇主から五銭ずつを受取るのだという事を彼は聞いた。
実にザラザラした印象を残す文章である。いきなり「醜い女だった」と書いてしまうそのなんともいえない残忍さ。そう、どうしても「残忍さ」を感じてしまうのだ。相手をした遊女を、ひとりに人間としてきちんと認識していない。どんな容貌であろうと、そこに生身の人間を感じとる感性が作家ならあってしかるべきと思うのは、ないものねだりなのだろうか。
「醜い女」で「裏店のかみさんのような女」で、「二度と見たいとは思わなかった」けれど、でも、その女の境遇に同情して「寄附してもいい」と考える謙作。それはこんな女でも、自分は同じ人間としての同情心は持っているのだといわんばかりで、どうにもこうにも、始末におえない傲慢さである。
「放蕩」を始めたころの若い謙作の精神がこうした未成熟さをさらけ出しているのは、むしろ仕方のないことで、こうした人間観が、この後、小説全篇を通じてどう変わっていくのか、あるいは変わっていかないのかが、この小説の読み所だろう。
ところで、この「放蕩」は、意外な方向へ謙作を導いていく。それは今まで同居してきたお栄との関係である。お栄は、謙作の祖父の妾だった女で、謙作よりも20歳ほど年上のいわば母代わりのような女だったから、身の回りの世話をしてもらいながら同居してきても、それ以上の関係に移行する気遣いはなかったはずなのだ。それなのに、謙作の中に湧き上がり猛威を振るい始めた性欲は、その矛先をお栄に向けるという仕儀になってしまうのだ。
彼は放蕩を始めてから変にお栄を意識しだした。これは前からもない事ではなかったが、彼の時々した妙な想像は道徳堅固にしている彼に対し、お栄の方から誘惑して来る場合の想像であった。その想像では常に彼はお栄に説教する自分だった。そういう事が如何に恐ろしい罪であるか、そのために如何に二人の運命が狂い出すか、そんな事を諄々と説き聴かす真面目臭い青年になっていた。しかも、そういう想像をさす素振りがお栄の方にあったわけではなかったが、彼は時々そんな風な想像をした。
それがこの頃になって変って来た。夜中悪い精神の跳梁から寝つけなくなると、本を読んでも読んでいる字の意味を頭がまるで受つけなくなる。ただ淫蕩な悪い精神が内で傍若無人に働き、追い退けても追い退けても階下に寝ているお栄の姿が意識へ割り込んで来る。そういう時彼はいても起ってもいられない気持で、万一の空想に胸を轟かせながら、階下へ下りて行く。お栄の寝ている部屋の前を通って便所へ行く。彼の空想では前を通る時に不意に襖が開く。黙って彼はその暗い部屋に連れ込まれる。──が、実際は何事も起らない。彼は腹立たしいような落ちつかない気持になって二階へ還って来る。しかし、段々の途中まで来てまた立止る。降りて行こうとする気持、還ろうとするが彼の心で撃ち合う。彼は暗い中段に腰を下ろして、自分で自分をどうする事も出来なくなる。
その辺の謙作の葛藤はこのように詳細に描かれている。そのうえ、謙作がある夜に見た夢が、また異様な迫力をもって描かれ、凄みがある。
謙作が寝ているところへ宮本がやってきて、阪口が旅先で死んだという。なんでも、放蕩のすえに刺激を求めてとうとう「播磨」をやり(この「播磨」がどうすることを指すのかは、書かれていない。とにかく危険なのだそうだ。)その挙げ句死んだというのだ。謙作は便所に立つがそれも夢だった。(夢から覚めたと思ったら、まだ夢だっというのはぼくもよく見る夢だ。)その後の描写がなかなか凄い。
彼は便所へ立って行った。(それがまた夢だったのである)便所の窓が開いていて、戸外は静かな月夜だ。木の葉一つ動かない、しんとした夜景色で、広い庭には(彼の家の庭より、それはよほど広い庭だった)屋根の影が山形に<っきりと映っている。彼はふとその地面で何か動いたように思った。映った屋根の棟でそれが動いていた。彼は先刻、どーんという鈍い響で何かが自分の寝ている屋根の上へ飛び下りたような気がした事を憶い出した。
それは七、八歳の子供位の大きさで、頭だけが大きく、胴から下がつぼんだように小さくなった、恐しいよりはむしろ滑稽な感じのする魔物だった。それが全く声もなし、音もなしに、一人安っぼ<跳(おど)っている。彼から影を見られている事も知らずに、上を見、下を見、手を挙げ、足を挙げ、一人ではしゃいでいるが、動<ものはその影だけで夜は前にも書いたようにしっとりと月光の中に静まり返っていた。彼はこれが跳っている間、その棟の下にいる者は悪い淫蕩な精神に苦しめられるのだと思った。淫蕩な精神の本体がこんなにも安っぽいものだと思う事はかえって何となく彼を清々(すがすが)しい気持にした。そして今度は本統に眼を覚ました。