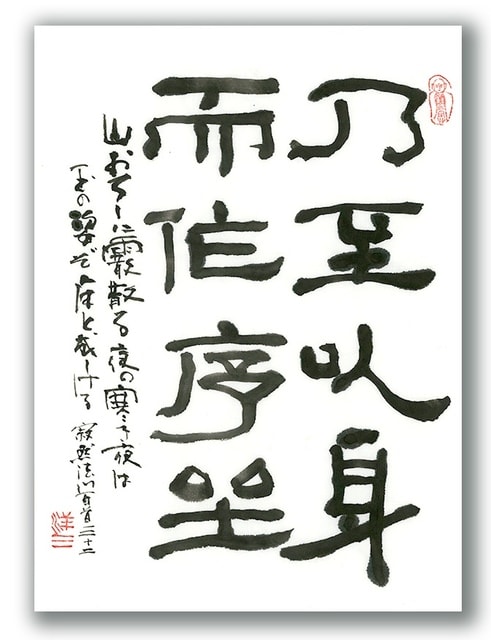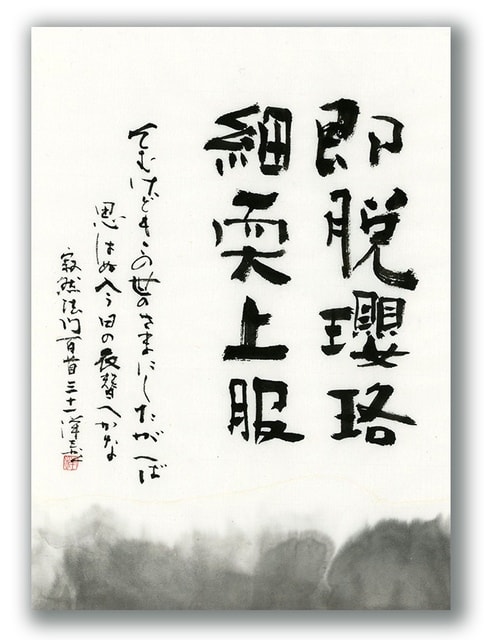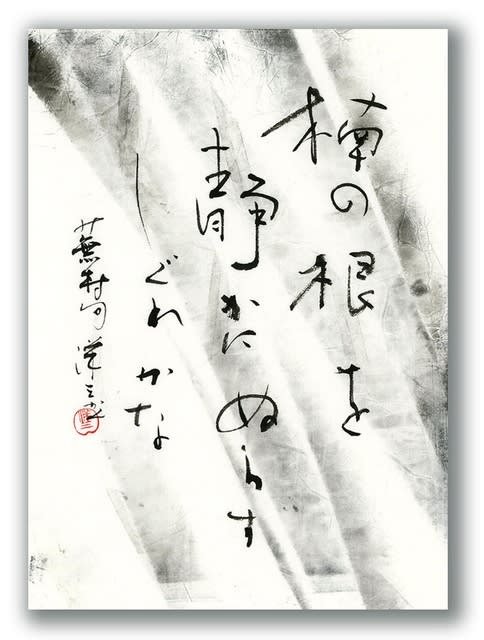日本近代文学の森へ (172) 志賀直哉『暗夜行路』 59 自由 「前篇第二 七」 その1

2020.10.14
気持にも身体(からだ)にも異常な疲労が来た。彼はもう何も考えられなかった。彼はそれから二時間ばかり、ぐっすりと眠った。
四時頃眼を覚ました。その時は気分も身体もほとんど日頃の彼になっていた。彼は顔を洗って、少時(しばらく)、縁へしゃがんで、ぼんやり前の景色を眺めていた。その内彼はお栄や信行が心配しているだろう事を想い出した。そして早速返事を出す事にした。
信行の手紙は、謙作の心を根底から揺るがすものだったが、それでも、2時間ほどぐっすり眠ると、謙作は自分をとりもどす。
お手紙拝見しました。一時はかなり参りました。日頃の自分を見失ったほどでした。しかし一卜寝入りして今はもうそれを取りもどしています。君がいいにくい事を打明けて下さった事は本統にありがた<思いました。
母上の事、今は何も書きたくありません。しかしそういう事の母上にあったというのは何より淋しい気をさす事でした。もっともそれで母上を責める気は毛頭ありません。僕には母上がこの上なく不幸な人だったという事きり今は考えられません。
父上に対しては、多分、この事を知ったがために僕は一層父上に感謝しなければならぬのだろうという気が漠然しています。実際父上がこれまで僕にして下さった事は普通の人間には出来ない事だったに違いありません。それを感謝しなければならぬと思っています。そして父上がこの事から受けられた永いお苦みに就いても想像はつきます。随分恐しい事だったに違いありません。ただ僕としては、これから先、父上とどういう関係をとるか、これを疑問にしています。父上に御苦痛を与える事なしに、やはり今度を機会として、無理のない処まで関係をはっきり落ちつける方がいいように考えます。
しかし君との関係は別です。それから出来る事なら、咲子や妙子との関係も別だといいたい気が実に強くしています。
とりもどしたとは言っても、すでに以前の自分ではないはずだ。何かが決定的に変わったはずである。しかし、謙作の手紙を読み進めると、この衝撃は、根底から謙作を変えるものではなかったという印象が深い。
まず、兄に対して。この事実を打ち明けてくれた信行にはただただ感謝の気持ちが綴られている。一片の恨みも妬みもない。父や母への思いは複雑極まるが、兄信行や、妹咲子、妙子への思いはまったく別だと言い切る。まっすぐな謙作の気持ちが伝わってくる。
母に対してはどうか。母については「何も書きたくありません」とまず断りながら、それでも、「そういう事の母上にあった」ことは自分を「淋しい気をさす事」であったという。「そういう事の母上にあった」という書き方は、その事実が母の責任ではないという謙作の認識を示している。だから、「母上を責める気は毛頭ありません」ということになる。それはいわば事故だったのであって、母が行為の主体として行ったわけではない、ということだ。そしてその母は、「母上がこの上なく不幸な人だった」としか考えられないというのだ。
これは謙作が実際にそう感じたということではなくて、そのように事態を理性的に「処理」した、ということだろう。そうすることで、「日頃の彼」を辛うじて保ったということだ。しかし、この事実をほんとうに受け止め、ほんとうの現実を謙作が生きるには、まだそうとうの時間が必要のはずだ。
一方父に対してはどうだろう。ここでも、理性的な処理は行われている。こうした事実があったにもかかわらず、自分を育ててくれたということに対して父には「感謝しなければならぬと思っています」という。「感謝している」ではなくて「感謝しなければならぬと思っています」なのだ。これも理性的な判断だが、感情的にはそんなに簡単ではない。
感謝しているからといって、父との関係がどうなるかは「疑問」だというのだ。「父上に御苦痛を与える事なしに、やはり今度を機会として、無理のない処まで関係をはっきり落ちつける方がいいように考えます。」という回りくどい表現からは、この後の父との関係の難しさが滲みでている。
自分に就いては、どうか余り心配しないで頂きます。一時は随分まいりましたし、今後もまいる事があるかも知れません。しかし回避かも知れませんが、自分がそういう風にして生れた人間だという事を余り大きく考えまいと思っています。いやです。それは恐しい事かも知れません。しかしそれは僕の知った事ではありません。僕には関係のない事がらです。責任の持ちようのない事です。そう考えます。そう考えるより仕方ありません。そしてそれが正当な考え方だと思います。
自分については、まずはこのようにして、自我の崩壊を「回避」したといえるだろう。自分の出生にまつわることを「余り大きく考えまい」とする、そして、「僕の知ったことではない」「僕には関係のない事柄」「責任の持ちようのない事」、そう「考える」ことで、その重大事からの打撃を「回避」したわけである。けれども、それで済む問題ではもちろんなかった。
この後、謙作は、愛子とのことであれほど悩んだのも、「断られる原因を知ることが出来なかった」からだと言い、今度も、愛子の時のように原因が分からず断られたら今よりもっと悩んだだろうと書き、次のように続ける。
どうか僕の事は心配しないで頂きます。僕は知ったがために一層仕事に対する執着を強くする事が出来ます。それが僕にとって唯一の血路です。其処に頼って打克つより仕方ありません。それが一挙両得の道です。(中略)
それから創作に自家の事の出る事、心配されるお気持、同感出来ます。それは何かの形で出ない事はないかも知れません。しかし不愉快な結果を生ずる事には出来るだけ注意します。
この衝撃的な事実を「知った」ことは、かえって自分の仕事への執着を強くするだろう、それが自分にとっての「唯一の血路」だ、そして、そのことでこのことに「打ち克つ」以外に自分の生きる道はない、というのだ。
作家として生きるということは、自分に起きるあらゆることを糧としなければならない、またそうすることで作家として成長できるというこの言葉は、また志賀直哉自身の決意でもあろう。しかも、このことを謙作が小説に書いて世間に知らしめることを危惧する兄に対して、その気持ちは分かるが、自分が作家である以上、「何かの形で出ない事はないかも知れません」と釘をさし、「不愉快な結果を生ずる事には出来るだけ注意します」と、曖昧な形でしか約束をしないところも、謙作の「作家根性」は坐っているというべきだろう。
肝心のお栄との結婚については、手紙の最後に次のように書く。
お栄さんも余り心配しないよう願います。
それからお栄さんの事はもう少し考えさして頂きます。しかしお栄さんに《はっきり》断る意志あれば止むを得ませんが、僕としてはもう一度、申出をするか、このまま断念するか、この事もう少し考えたく思います。
(《 》は傍点)
ここはちょっと意外だ。実の父たる祖父の妾であるお栄との結婚となれば、信行でなくとも、やはり思いとどまるというのが普通だろう。だから、「お栄さんとの結婚はきっぱり諦めます。」という文面になるだろうと予測していたら、これが意外に粘り強い。ことここに及んでも、諦めないのだ。お栄が「はっきり」断らないのなら、もう一度申し出てみるかもしれないという。ここまでお栄に執着するのは何故なのか。よく分からないが、やはり、謙作はお栄に生みの母を見ているのだろう。
書き終ると、彼は完全に今は自分を取りもどしたように感じた。彼は立って柱に懸けておいた手鏡を取って、自分の顔を見た。少し青い顔をしていたが、其処には日頃の自分がいた。充奮からむしろ生き生きした顔だった。何という事なし彼は微笑した。そして「いよいよ俺は独りだ」と思った。彼には自由ないい気持が起った。
手紙を書いたことで、謙作は「完全に今は自分を取りもどしたように感じた。」という。衝撃の事実を告げる手紙を読んでから、たった2時間寝ただけなのに、もう「完全に」立ち直っている。それどころか、鏡には「充奮からむしろ生き生きした顔」がうつっている。そして「いよいよ俺は独りだ」と思い、「自由ないい気持」が心に起こるのだ。
明らかに早すぎる立ち直りだ。普通だったらそうはならない。びっくりして、ヤケになり、酒場に飛び込んで浴びるほど酒を飲んで暴れ、二日酔いに苦しんだあげく、女郎屋に出向き、さんざん放蕩を尽くすが、それでも気持ちは収まらない、なんてところが相場だろう。まあ、それが「普通」かどうかは知らないが、それにしても、この謙作の「立ち直り」は不自然だし、それはやはり一時的な「回避」の結果であろう。
しかしまたこうも思うのだ。人は、とんでもない状況に突き落とされると、かえって意識が高揚し、それまでにない「自由」を感じるものなのかもしれない、と。
謙作の場合は、「いよいよ俺は独りだ」という感慨は、しかし、ひとえに父が実の父ではないということを知ったことから来るのだろう。実に父たる祖父はすでにこの世にいない。(どうもこの小説中にこの祖父の死は描かれていないが、おそららく死んでいるだろう。)もちろん、生みの母はとうに亡い。自分の「両親」を亡くした人間が感じる「自由」。ぼくはまだそれを知らないが、いったいどんな味のする「自由」なのだろうか。