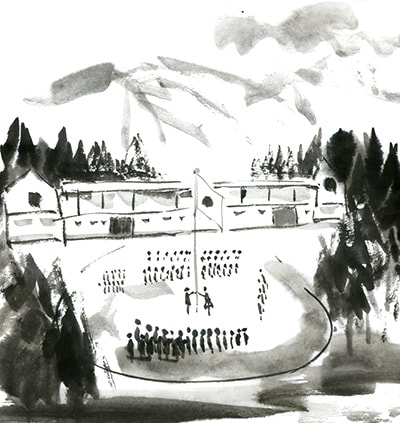86 「手応え」

2016.6.2
岩波書店の「図書」の最新号に、原田宗典の「手応え」というエッセイが載っていた。その中にこんな記述があった。
私は女房に話しかけた。
「ある時ね、晩年の中川一政にある人が率直に尋ねたんだそうだ。先生の絵は三日で完成するものもあれば、十年かかっても完成しない絵もありますよね。一体、何で判断するんですか? 何がどうなったら、先生の絵は完成するのですか?」
「ふんふん……そしたら?」
「中川先生はね、ちょっと間を置いてから「手応えだよ」とだけ答えたのだそうだ。」
「手応え……?」
「そう、手応えだよ。君にはちょっと分からないかもしれないけど、ぼくには分かる。いいものが書けた時、確かにそういう手応えがあるんだ。それはもう手応えと呼ぶしかないような感覚なんだ。」
「ふうん……」
女房は不思議そうな顔をしていたが、私はその「手応え」という言葉自体にちょっとした興奮を覚えた。インターネットやスマホの普及で、世の中は既に「手応えのない」時代に突入している──今、本当に必要とされているのは、中川一政の言う「手応え」なのではなかろうか。
いいなと思ったことがひとつ、ダメじゃんと思ったことが二つある。
いいなと思ったのは、この中川一政の言葉自体である。
中川一政の絵にぼくはそれほど親しんでいるわけでもないが、それでも、その絵や書には割合おおく接してきたような気がする。どこか素朴な味わいのある絵、それにもまして、「稚拙」の感のある書。どこで「完成」を判断するのかと聞きたくなるのももっともなことだ。それに対して、「手応え」だと答えたというわけだが、何度も耳にしてきた当たり前の「手応え」という言葉に、原田氏と同様に「ちょっと興奮」したわけである。
確かにそういう瞬間がある。写真を撮る時など、とにかく「数打ちゃ当たる」とばかりに闇雲に撮るから、同じような写真ばかりがゴマンとできる。その中から、どれを選ぶかが大問題。そこでも「手応え」のようなものが感じられる。「あ、これかな?」ぐらいだけど。そして、その写真をどう「現像」するかが更に大きな問題となる。コントラストをどうするか、色調をどこまでいじるか、トリミングはどうするか、数え切れない問題があって、追求していくとキリがない。けれども、どこかでふと手がとまることがある。「あ、これ、いいかも。」って思える瞬間でやめる。それが「手応え」なのかもしれない。
そんなことを考えているうちに、ふと、学校で古文を教えていた時に扱った「今昔物語」の文章が思い出された。これは栄光学園独自で作成している「中学生の古典」に収録されている話で、題は中学生向きに「馬盗人」としているが、本題は「源頼信朝臣男頼義射殺馬盗人語〈源頼信朝臣(あそむ)の男頼義、馬盗人を射殺す語(こと)〉」(巻第二十五・本朝世俗)である。
ある夜、源頼信のところに東の国から馬が届いた。当時は馬は大変価値の高いものだから、馬泥棒が東の国から盗む機会をねらってついてきたのだが、とうとうその機会を逸して、頼信の家に来てしまった。馬が親のところに来たと聞いた息子の頼義が、その馬を欲しくてたまらずに、雨の降るのもいとわずに親の家を訪ねるが、朝になったら見せてやるから、気に入ったらお前にやると言われ、その夜は、親子で同じ部屋に寝る。泥棒は、雨の夜をもっけの幸いに、まんまと馬を盗み出して逃げて行く。それに気づいた親子だが、親は息子に「おいドロボウだ!」とか言わずに、弓矢を持って馬で追う。息子は息子で「おとうさん、ドロボウだよ!」とも言わずに、やっぱり父の後を追う。そのうちに、親子が思った通りに逃げ道を逃げた泥棒が、「ここまで来れば大丈夫」とばかり、馬の歩みを遅くしてのんびり川の浅瀬を歩ませていると、それに追いついた親が、その水音を聞いて、息子が付いてきていることも確かめてもいないのに「アレを射よ。」と言う。すべてが真っ暗闇の中である。要するに、武士の親子は、何にも言わなくても、気持ちが通じているということなのだ。
さて、その真っ暗闇の中で、どのくらい先にいるのかも見えない泥棒にむかって、ただ水音だけをたよりに矢を射ったわけだが、その部分の記述がこうなっているのである。(長くてスミマセン)
暗ければ、頼義がありしも知らぬに、頼信、「射よ、かれや。」と言ひける言もいまだ果てぬに、弓の音すなり。尻答えぬと聞くに合はせて、馬の走りて行く鐙(あぶみ)の、人も乗らぬ音にてからからと聞こえければ、
念のために口語訳しておくと、「あたりが真っ暗なので、頼信は息子の頼義がそこにいるということもわからないのに、頼信は「あれを射よ。」と言ったその言葉も終わらぬうちに(頼義のひく)弓の音がした。手応えがあったと聞くと同時に、馬が人の乗っていない鐙をからからと音を立てるのが聞こえたので、」ということになる。
実に見事な描写でほれぼれするのだが、それはともかくここに出てくる「尻答えぬ」が、思い出されたというわけなのだ。
「尻答えぬ」について、「中学生の古典」には、「手応えがあった。命中した音がした。「尻」は矢尻で、命中した時、矢尻が微妙な手応えのある響きを発するのである。」と脚注があるのだが、この脚注は「微妙な響き」としたほうがいいだろう。
さて、その「微妙な響き」とは、どんな響きなのだろうか。盗人(註2)に命中して矢尻の羽(註1)が微妙に空気を震わせるのだろうか。それはまさに、「微妙」そのものであって、それが人の耳に聞こえるはずもない。聞こえるはずもないけれど、何か感ずる、その「微妙な」感じ、感覚。そして、その「響き」は、直前に弓をはなったこの手に、手の筋肉に、ひいてはその手を動かした神経に、脳に、ぴったりと「連動」している。それこそが「手応え」ではないのか。
あるいは高浜虚子の「金亀虫(こがねむし) 擲つ(なげう)闇の深さかな」も思い出される。ここでは「手応えのなさ」がかえって深い闇の「手応え」を感じさせる不思議な世界がひろがる。
いずれにしても、中川一政が感じた「手応え」、原田宗典が感じた「手応え」、それらもみなこうした「手応え」の世界に通じるだろう。
国語辞典では「手応え」を「ものを打ったり突いたり切ったりした時などに、手にかえってくる感覚。」(「日本国語大辞典」)としているが、この、今昔物語の武士のように、矢を射ったときにも感じる「手応え」は、ぼくらの日常や芸術活動の中での「手応え」を、鮮明にイメージ化しているように思えるのだ。
以上で、「いいなと思ったこと」については終わり。
「ダメじゃん」と思ったことについては短く書いておく。そのひとつは、「君にはちょっと分からないかもしれないけど、ぼくには分かる。」というところ。作家ではない(たぶん)妻にむかって、「芸術家じゃない君には分からないかもしれない」というような言いぐさは、思い上がっている。何も作家だけが特別なわけじゃない。家事をしていても、育児をしていても、会社で仕事をしていても、「手応え」はある。「妻」が怒らなかったのが不思議である。
もうひとつは、この引用部分の後半全部。「インターネット」や「スマホ」をやり玉にあげておけば、一般大衆の共感を得られるものと思い込んでいる人が多すぎる。特にオジサン世代から高齢者に多いが、せめて作家を名乗る人間は、こうした安易な「まとめ」に陥るのを警戒すべきだろう。
(註1)
このエッセイを書いた直後、都内某所へ電車で向かう途中、古い友人から「今日のエッセイの中に「矢尻の羽が」っていう表現があったけど、どういうこと? 矢尻って、矢が物に突き刺さる先端のことだと思ってたけど、違う意味があるのかな。」というメール(厳密に言うと、フェイスブックのメッセージ)が来た。そういえば、「矢尻」というのは、彼の言うとおり、「先端」のことだった。「日本国語大辞典」によれば、「矢の先端についていて、対象物に突き刺さる部分。縄文時代以来用いられ、材質により石鏃、骨鏃、鉄鏃、銅鏃、竹鏃という。形態上からは、尖根(とがりね)、平根(ひらね)、三角鏃などがみられる。やさき。矢の根。矢の実。」となっている。
「矢尻」を、ぼくは、「矢の先端」ではなく、「矢羽根の方」つまり「矢の後ろ」と勘違いしていたというわけだ。(まあ、どっちが「前」でどっちが「後」かってこともそれはそれで問題だけど。)それは確かに「勘違い」なのだが、なぜ「矢の先端」を「尻」というのだろうかという疑問がすぐに続いて出た。負け惜しみではないけれど、「尻」というのは、どう考えても「後ろ」を指すのではあるまいか。だから、「矢尻」を「矢羽根のついた後ろの方」だと勘違いしてしまったのではなかろうか、などとウジウジ考えていた。
それはそれとして、「矢尻」が「先端」なら、「矢尻がたてる微妙な響き」というのは、厳密に言えば、「先端」が、盗人の体に突き刺さる「プスッ」だか「ブスッ」だかいう音ということになる。何だか味気ない話である。それより、ぼくの「勘違い」から生じた「盗人に命中して矢尻の羽が微妙に空気を震わせるのだろうか。」といった「響き」の方が味わい深いものがあるのではないか、などと考えたが、まあ、これはやっぱり負け惜しみには違いない。
けれども、シツコイようだが、暗闇の中を飛んでいった矢が、盗人に命中してたった音があったとして、それは、厳密に「矢の先端」から発する音か、「矢羽根の方」から発する音かなど区別のつくものではなかろう。したがって、「矢尻の羽」という言い方は誤りだが、その音、「微妙な響き」は、「矢全体」から発せられたと考えることもできるというものだ。
などと、電車の中でとつおいつ考えていたわけだが、ふと、この「尻」は「後」のことではないか、と思った。日本語の「しり」は、「尻」でもあり「後」でもある。語源は同じだ。「今昔物語」では「尻」の文字を使っているが、「尻答えぬ」というのは、「矢を放った後、なんか当たったという感じが確かにして」という意味だと解釈したらどうだろうか。その「当たった!」という「感じ」は、矢の方からかすかに伝わってきた「微妙な響き」であっても一向に差し支えないし、その「音」が「矢尻」がたてようが、「矢羽根」がたてようが、そんな厳密な区別はいらなくなる。
そんなことを思いついて、件の友人に、「しり、は、尻ではなくて、後ととる方がいいかも。」とiPhoneでメールした。「なるほど、そういうことか。そういえば「後」は「しり」と読ませることもあるよね。了解。」と友人が返してきた。
「手応えあり」である。
(註2)
最初に書いたとき、この「盗人」が「馬」としていた。その「勘違い」に気づかず、(註1)でも、「馬に当たった」を連呼してしまったわけだが、当たったのは「馬」じゃないでしょという指摘が別の知人からあったので訂正。まったく、馬に当たっちゃったら「手応えあり」どころの騒ぎではないわけである。