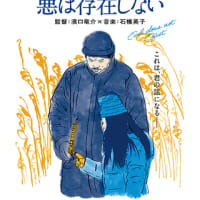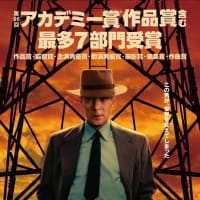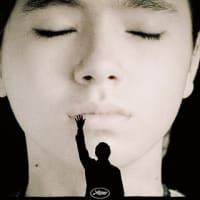これも『古今和歌集』に収められている、六歌仙のひとり在原業平の和歌です。『伊勢物語』の「東下り」で登場する和歌ですので、すでに知っている和歌ですね。さまざまなテクニックを使っていて整理しにくいのですが、知っている和歌だからこそ理解しやすいと思います。
【品詞分解】
からころも 枕詞
着 カ行上一段活用「きる」の連用形
つつ 接続助詞
なれ ラ行下二段活用「なる」連用形
に 完了の助動詞「ぬ」の連用形
し 過去の助動詞「き」の連体形
つま 名詞
し 強調の副助詞
あれ ラ行変格活用「あり」の已然形
ば 順接確定条件の接続助詞
はるばる 副詞
来 カ行変格活用「く」の連用形
ぬる 完了の助動詞「ぬ」の連体形
旅 名詞
を 格助詞
し 強調の副助詞
ぞ 強調の係助詞
思ふ ハ行四段活用「おもふ」の連体形
【現代語訳】
(何度も着て身になじんだ)唐衣のように、(長年なれ親しんだ)妻が(都に)いるので、(その妻を残したまま)はるばる来てしまった旅(のわびしさ)を、しみじみと思うことです。
【和歌の技法】
〈折句〉
㋕ら衣 ㋖つつなれにし ㋡ましあれば ㋩るばる来ぬる ㋟びをしぞ思ふ
五七五七七の各冒頭の音が「かきつはた」になっています。伊勢物語でも「かきつばた」の五文字を句の上に据えて詠むように依頼されていたのを思い出してください。このような歌の技法を折り句といいます。
〈枕詞〉
「唐衣」は「着」にかかる枕詞。枕詞は五音です。
〈序詞〉
「唐衣着つつ」は、「なれ」を導く序詞。序詞は枕詞と同じようにある語句を導き出しますが、五音を超えます。
〈掛詞〉
掛詞というのは二つの意味がある言葉です。ダジャレのような用法ですね。
・「なれ 」 「着慣れる」またはなじんで柔らかくなるを意味する「萎る」と「馴れ親しむ」の「なれる」を掛けた言葉
・「つま」 都に残してきた「妻」と衣の裾を意味する「褄」を掛けた言葉
・「はるばる」 着物を張るを意味する「張る張る」と「遥々」を掛けた言葉
・「き」 「来」と「着」を掛けた言葉
〈縁語〉
縁語というのは関連する言葉のことです。ここでは「なれ」、「つま」、「はる、「き」は「唐衣」の縁語になっています。
【文法】
「にし」
・完了の助動詞「つ」、「ぬ」と過去の助動詞「き」「けり」はよく一緒に使われます。
てき (「つ」の連用形+「き」)
てけり(「つ」の連用形+「けり」)
にき (「ぬ」の連用形+「き」)
にけり(「つ」の連用形+「けり」)
のパターンで出てきます。「て」と「に」が一音なので、品詞分解で見つけにくいのでパターンで覚えておくと便利です。
このパターンで「てき」や「にき」の「き」は過去の助動詞「き」なので、活用によっては「てし」「てしか」、「にし」「にしか」という形で出てくることがあります。この「し」にも気を付けてください。
〈強意の副助詞「し」〉
強意の副助詞「し」は、語の後についてその後を強調する役割があります。現代語にはないので、私たちには感覚的にわかりにくい単語です。逆にこの「し」がないほうが現代人には意味がとりやすくなります。例えば
「妻しあれば」
は、
「妻あれば」
のほうが意味が取りやすい。
このように見分けます。