心配、気づかい。それこそ、ぼくが求めてやまないものだったと思う。温かくて揺るぎなく、変わることのない気づかい。リビアでは血と涙が流され、痣だらけの、ズボンに小便のしみをつけた男があふれ、人々は貧困に苦しみ安らぎを求めているというのに、ぼくという子供はばかみたいに、気づかってもらうことを切望していた。そして、当時はそういう言葉では考えていなかったが、ぼくの自己憐憫は腐敗して自己嫌悪に変わっていた。
 |
リビアの小さな赤い実 |
|
ヒシャーム・マタール 著 金原瑞人/野沢佳織 訳 |
|
| ポプラ社 |
1979年、リビアの首都トリポリの通称クワの木通りに住む、少年スライマーンは9才。パパは仕事でしょっちゅう外国に行くため家を空け、ママはそのたびに心が不安定になり、「薬」を飲んでいる。そんなある日、外国に行っているはずのパパを町で見かける。その一週間前に、隣人のラシードさんが反逆者として逮捕される。そして、彼の家にもパパを探しに男たちがやってきて、父は姿を消す。
物語は大人になったスライマーンが当時を語る形式になっています。
14歳の時、親の決めた結婚に反発しながらも従うしかなく、すぐに離縁されるよう、それを飲めば子供が出来なくなるという薬を飲んだのだが、効かずにスライマーンを妊娠した母は、彼を愛しながらも、父に対して心を開いていない。
思い出の中の風景は美しいのに、そこでは日常に暴力が存在している。
少年は両親が大好きなのに、パパは不在で、ママは心を病んでいる。
自分がいない間、ママを守れと父に言われ、大人の男になろうともがくが、その方向はどこかゆがんでいる。
「アラブの春」の前のリビア・トリポリの日常生活が描かれていてとても興味深かったものの、少年の気持ちや行動に、共感できるところがなく、なかかな入り込めないところがありました。
けれど、ふと原題が、「IN THE COUNTRY OF MEN」ということに気づいて、ちょっと本への向き合い方がわかった気がしました。
とはいえ、読み終わっても消化不良のままですが・・・。
スライマーンの素直な9歳の少年としての姿と、時々垣間見せる残虐性というのを結びつけるものが何なのか、理解できないのです。
ただ、著者のプロフィールを読むと、スライマーンが彼の分身であることは確実で、ある意味で、本書は”私小説”なのかもしれません。
私小説と言えば、少し前に、車谷長吉の”塩壷の匙”を再読したのですが、主人公の残虐性が常に内面から(=主観的に)描かれているところが、本書と似ているかも・・・。戦前や戦後の社会の状況について私なりの理解があるので、主人公の気持ちをまだ自分の内面に照らし合わせながら少しは消化することができましたが、それでも違和感が残りました。
リビアについても、イスラム世界についても何も知らない私が、スライマーンを理解することが出来なくても仕方ないかもしれません。でも、分からないものは分からないまま、とりあえず飲み込んでおくことで、例えば中東で繰り返される紛争、暴力のニュースを見る目が少し変わったと思います。
だから、わかりやすい作品より、この後、自分の中で発酵してくれそうで、やっぱり読んでよかったと思った一冊でした。
![]() いよいよ梅雨入り
いよいよ梅雨入り
人気ブログランキングへ















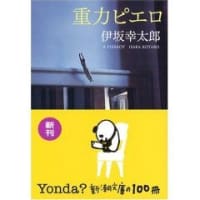



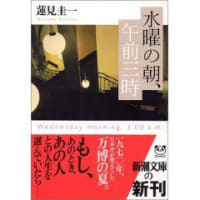

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます