
光市母子殺人事件の裁判が終結してから、十日ほどしか経っていないのだが、もう過去のニュースと言う気がする。これで本村さんもやっと静かな生活に戻れるのだと、安どする半面、死刑囚となった元少年の心理と言うか、心の闇の深さに何か釈然としない思いが澱んでいた。そんな時、ある雑誌に掲載された作家門田氏のドキュメントを読んだ。門田氏は「なぜ君は絶望と闘えたのか―本村洋の3300日」を執筆。元少年とも拘置所で面会。その時の様子や元少年の言葉を雑誌で記述していた。すでに30歳となるこの元少年の言葉には、拭っても拭いきれない人間の業を感じた。
事件は日本の裁判制度や法制度に多くの疑問を突き付け、数々の新しい扉を開いたという点で歴史に残る事件裁判であった。諸々のことはすべて新聞などで詳細に報道されているのでここで繰り返す必要はないであろう。
注目したのは、元少年が門田氏に伝えた幾つかの言葉である。
「胸のつかえがおりました」「僕は生きている限り償い続けたい」「僕は死刑に値すると思っています」
この面会は、最高裁から広島高裁に差し戻しされ、2008年4月に広島高裁で死刑と言う判決が下された直後のことであった。門田氏は元少年のこれらの言葉にかなり衝撃を受けていた。
たしかに、それまでに伝えられている言動とはかなり違ってみえる。だが、はたしてこの言葉は額面通りに受け取れるのだろうか。その疑問は彼のその後の行動と言葉につながっているようだ。広島高裁の判決を不服として上告。その理由を次のように述べている。
「判決に不満だったからではなく、判決文に不服だったからです」さらに、
「裁判官に裁いてほしくはないんです。僕は本村さんに裁いてほしいのです」
私には元少年の心の闇の一端をのぞいたような気がした。
差し戻し判決が下った時点で、死刑になるということは予測されていた。それからの二年間で元少年はかなり追い込まれたはず(これは門田氏も指摘していた)。元少年は初めて自分の死について向き合うことになったのかも。当然、心境も激変したに違いない。一審二審の無期刑はかなり強いものに見えていたからだ。
審議差し戻し後、彼の新たな弁護団は「殺意はなかった。偶然の事故だった」と荒唐無稽な弁護に変更する(それまでの証言は嘘とした)。これが、死刑廃止論の弁護団のねつ造だと、世論の反発を呼んだ。門田氏によれば、この証言は元少年が最初から言っていた事で、それを弁護側が採用して法廷に持ち込んだもの。最初の弁護団はあまりにも荒唐無稽で弁護にならないとして採用しなかった、と言うのが真実らしい。
こんな小学生並みの言い訳が一般社会では通用しないのは当たり前。母に甘えるために見知らぬ家に上がり込み、勢いで首を絞めるわけがない。リボンを結ぶつもりが赤ちゃんの首を絞めてしまったなど、言い訳にもならない。それほど幼い頭しかなかったとは言える。これほど精神的に幼い人間だから、死刑は何とか避けてほしい、というのが弁護団の願いだったのだろう。
しかしながら予測通りの死刑判決。やっぱり、という思いが、次の展開へ必死の工作となり、反省と悔いの心の吐露であったのでは、と思わざるを得ない。すべて自己保身とは言わないが、手前勝手な精神構造が垣間見える。
この身勝手さこそ元少年のすべてであった。そう考えると、「胸のつかえがおりた」などと言う言葉は、口先だけのものに聞こえてくる。「生きてる限り、償いたい」という言葉も、次への可能性を求める言葉にしか聞こえてこない。それが上告と言う行動に現れたのでは。これは私個人の解釈であり、短絡的な判断というそしりは免れないことを承知で言いたい。
判決文に不服と言うのも実に手前勝手だ。ないものねだりの特性を感じさせる。本村さんに裁いてほしい、というのも同じ。本村さんにとってこれほど迷惑な話はないだろう。母に甘えるために近寄ったという幻想物語と同じ構図ではないのか。自分は死刑で当然だと思うが、罪を償うことは死刑だけではないと思う、とも語っていた。では生きてどんな償いができるというのだろうか。そんな疑問さえ浮かぶ。言葉が重いようで実に軽い。
もし本当に反省しているなら、死んだ方がいいと思っているなら、上告の必要はない。さらに本村さんを苦しめる必要はなかった。判決文の内容など、自分勝手の不満でしかない。本村さんに分かって欲しいというのも詭弁に聞こえてしまう。
元少年はたしかに家庭に恵まれず、虐待の中で幼少時代を過ごしたという不幸は十分に理解する。そのために自分勝手な精神構造で物事を構築するということも、逆によく分かった。私の中の澱みが蠢いた。
死刑という刑罰は安易に使えないほど重い。またそれを宣言する裁判官の心だって穏やかではないだろう。死刑が確定した死刑囚の思いがどんなものであるか、経験のないものには語ることができない。だが、どんな死刑囚でもその場に直面した時、初めて自分の罪と正面から向き合うであろうことは、想像できる。
元少年もまた死刑という現実に追い込まれて初めて自分の罪を見つめたはず。そして今、人間として初めて自分の生を考えているに違いない。それは今までとは比べ物にならないほど濃い時間となっているのではないだろうか。残りの生という、わずかの時間に、すばらしい人間に生まれ変わる可能性だってある。だからと言って死刑を免れていいということにはならない。罪は罪だから。いくら反省してもそれはそれなのだ。「殺人の罪」はそれほど重いということだ。自分の「生」に気づくということも、死刑の中に課せられた「罰」の一つとも言えるだろう。
死刑廃止が文明社会を表わす基準であるかのような論がある。死刑がない社会が先進であるかのように言う。欧米を見ろと説く輩もいる。人を裁く権利は人間にはない、死刑は国家による報復だ、などなど。全く頓珍漢な論だ。欧米のどこが先進と言えるのか。アングロサクソンとアボリジニを比べると、砂漠で生きる知恵や文明ははるかにアボリジニの方が上だ。死刑廃止がそれほどの文明であるとは思えない。死刑制度があるということも、極めてまっとうな文明であると、私は思う。
















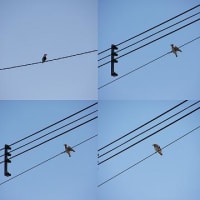


で、10代の特攻隊員たちが、お国のために命を捧げることに繋がった…。彼らはオトナだったのか?子供だったのか?
江戸時代の武家男子は、14歳ぐらいで元服をしたといわれます。14歳になると社会が成人として認めたことになります。でも現代は、成人として認められるのは20歳、少し遅くはないでしょうか?そのためにピーターパン症候群が激増してる。ここに多くの問題が潜んでるように思います。人間、早くオトナになったほうがいい。そして、やるべきことをやったら、動物のように早くこの世を退散したほうがいい。だから、18歳
成人、選挙権賦与には大賛成です。
本ブログの趣旨と離れてごめんなさい!
今進められている18歳の成人も大賛成です。選挙権もいいと思います。いまどき、18歳で酒の飲めないやつはほとんど一生飲めない人です。
年金も18歳から納めればいい。
デズモンド・モリスは「マンウォッチング」だった。
お詫びして訂正します。
最近、こういう間違いが結構あります。アブナイ、なぁ。