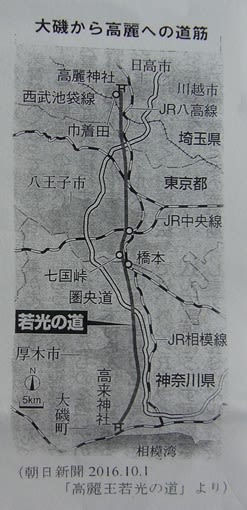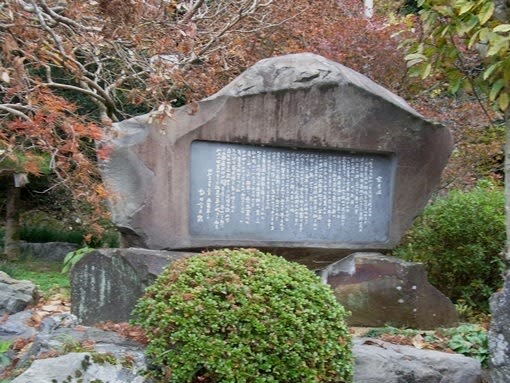日本民家園とその周辺
晴天に恵まれ春の空とは思えない様な
どこまでも青い綺麗な空の下、
川崎市立日本民家園とその周辺を歩いてきました(3月17日)
廣福寺の境内に入る。辛夷が見頃でした。

廣福寺
鎌倉幕府の御家人 稲毛重成の創建と云われている。

枡形山を登り始める~

枡形城址。
標高83,9m 枡形山の頂上に着いた。
源 頼朝の側近だった稲毛重成が築城した枡形城址です。

早速展望台に昇った

展望台からの眺望は素晴らしかった。

スカイツリー、東京タワー、レインボーブリッチまで良く見えた。


生田緑地の丘陵斜面の道を暫らく降りて日本民家園に向かう。
大きい玉石の階段は誠に歩き難かった。

日本民家園が見えてくる。
全国各地から代表的な民家を集めて移築したもの24棟程が集められていた。
沢山 民家の写真を撮ったのですが何棟かを投稿します。

見るからに豪華な木造二階建て建築の原家の住宅。
同じ川崎市内にあった明治期後半の民家です。

完成までに22年の歳月を費やしたと云う立派な住宅でした。

原家を過ぎるとその先は江戸期の古民家が続きます。
この鈴木家住宅は福島県にあった。
19世紀初期馬宿・馬方が泊まる宿で
馬を繋ぐ事が出来る土間があった。

江向家住宅。
越中五箇山、合掌造りの住宅で豪雪にも耐えられる様に
屋根の傾斜は急勾配で作られています。

合掌造りで有名な集落、飛騨白川郷にあった山下家の住宅です。
ここの1階はそば処になっている。ここで昼食におそばを食べた。

作田家住宅
千葉九十九里の漁村にあった。
17世紀後期の網本の家で手前と奥の二棟が合体した造りになっている。
分棟型と呼ばれている。

広瀬家
山梨県塩山市にあった17世紀末期のもので
屋根に二面の傾斜を持つシンプルなデザインの切妻造。

広瀬家の炉辺では薪がくべられ、
古い生活用具も配置されていて暮らしの姿が浮かんできた。

船越の舞台(重要有形民俗文化財)

野外の観客席

日本民家園の西門から出園、暫らく歩いて木の門(枡形門)に辿り着いた。

枡形山城址で一休みしてから帰りは生田緑地の急勾配を只管降りた。
段差の高い階段を降りるのに凄く難儀をしました。
想定外でしたが みんなで助け合って降りたのも いい思い出になります。
来月4月は勝沼ぶどうの丘周辺です。どんな景色に出会えるか楽しみです。