
8月に入って、新型コロナ禍が再び慌ただしくなってきました。そのうち県外に行けなくなりそうな勢いなので、今のうちにということで半日休暇を取り、温泉巡りに出発。行先は群馬県を選択し、できるだけ山奥にしようということで、旧六合村(現中之条町)の温泉に向かうことにしました。
まずはこんな時だから人が少ないだろうと期待し、有名な尻焼温泉の川の湯の様子を見に行きましたがそれなりに人がいたので、目的地を京塚温泉 しゃくなげ露天風呂に変更。露天風呂の鍵を借りるために「喜久豆腐店」に向かいました。京塚温泉 しゃくなげ露天風呂は、現地に人がいないため、近くの「喜久豆腐店」「宿くじら屋」等で料金500円を支払い鍵を借りるというシステム。近くと言っても歩くと遠いので、露天風呂に着く前に鍵を借りていく必要があります。
無事に鍵を借りて、喜久豆腐店から露天風呂までは車で2~3分ほど。白砂川に架かる橋を渡ってすぐ左折し、介護施設脇の未舗装道路を進むと、戦国時代の砦のような手作り感満載の施設が目に入ります。隣にはプレハブ小屋がありますが、それは地元民専用の内湯とのこと。

入口の扉前にユーモラスな顔をしたチケット入れがあるのでそこにチケットを入れ、鍵を開けて中に入ると、いきなり大きめの露天風呂と白砂川の対岸の崖が目に飛び込んできました。川側には塀がないので視界を遮るものがなく、屋根もないので開放感が半端ない。見えるのが崖のみ(立ち上がれば白砂川の流れも見える)なので絶景とまでは言えないけれど、この開放感はなかなかないでしょう。(過去の情報を調べた限りでは一度浴槽にかかる屋根が設置されたはずなのですが・・・。一応今でも脱衣スペースの上には屋根がかけられています。)

さて肝心の温泉については、浴槽は結構広いです。利用するであろう想定人数を考えれば無駄に広いかな(この日は終始独泉)。情報では浴槽がヌルヌルするという評価が多かったですが、この日はそれがなく快適でした。掃除した直後だったのかも知れません。
お湯(源泉)は塩ビ管からドボドボと投入されており、その隣ではホースから水も投入されていました。ただ投入量は源泉の方が圧倒的に多め。そしてもちろんかけ流しで消毒もされていないでしょう。温泉の使用法の掲示がないですが、加水のみのかけ流しと思われます。

湯の質は、無色透明(ちらほらと茶褐色の湯の花が舞う)、微硫黄・鉄臭、微渋・鉄味。渋味は源泉よりホースから注がれる水の方が渋かったので、その影響かも知れません。際立った特徴はない湯だけれども、仄かに湯の香が香ってくる湯は温泉らしさを感じさせてくれます。泉質はカルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉で、源泉は「花敷温泉 川端の湯」となっています。花敷温泉はすぐ近くにある一軒宿の温泉地ですが、その宿とは源泉が異なるようです。
そして湯の中を見ると細かい気泡が舞っており、体への泡付きがあります。その泡付きのためか、若干ツルスベ感が感じられました。源泉が滝のように注がれていてそこで泡が発生していましたが、離れた湯尻でも気泡が舞っていたので、源泉由来の気泡でしょう。それだけ湯が新鮮ということですね。
湯温は若干ぬるめの設定で、真夏の炎天下でも長めに浸かっていられました。適当にホースで加水しているようで絶妙な湯加減であす。それに屋根がないと言っても脱衣スペースの屋根から伸びた影が一部湯船にかかっていたので、直射日光も避けられました。温泉入浴に関しては、開放感と相まって十分に満足できるものでした。
だが、しかし、です。しばらくのんびりと湯浴みを楽しんでいたところ、アカウシアブという大型のアブの攻撃を受ける羽目に。何度追い払っても向かってくるその獰猛さには恐れ入りました。あまりのしつこさに負け退散。鍵を借りる際に豆腐店の女将さんからアブのことを言われていたのですが、まさかこれほどとは・・・。
そんなことがあり残念な最後になってしまったけれども、温泉自体は素晴らしいものであり、記憶に残る入浴となりました。温泉マニアなら気に入る人が多いでしょう(ただし女性には厳しいかも)。春か秋であれば、アブも出ないだろうし新緑や紅葉を楽しみながら湯に浸かれるので、より楽しめるのではないかと思います。
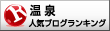
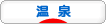
まずはこんな時だから人が少ないだろうと期待し、有名な尻焼温泉の川の湯の様子を見に行きましたがそれなりに人がいたので、目的地を京塚温泉 しゃくなげ露天風呂に変更。露天風呂の鍵を借りるために「喜久豆腐店」に向かいました。京塚温泉 しゃくなげ露天風呂は、現地に人がいないため、近くの「喜久豆腐店」「宿くじら屋」等で料金500円を支払い鍵を借りるというシステム。近くと言っても歩くと遠いので、露天風呂に着く前に鍵を借りていく必要があります。
無事に鍵を借りて、喜久豆腐店から露天風呂までは車で2~3分ほど。白砂川に架かる橋を渡ってすぐ左折し、介護施設脇の未舗装道路を進むと、戦国時代の砦のような手作り感満載の施設が目に入ります。隣にはプレハブ小屋がありますが、それは地元民専用の内湯とのこと。

入口の扉前にユーモラスな顔をしたチケット入れがあるのでそこにチケットを入れ、鍵を開けて中に入ると、いきなり大きめの露天風呂と白砂川の対岸の崖が目に飛び込んできました。川側には塀がないので視界を遮るものがなく、屋根もないので開放感が半端ない。見えるのが崖のみ(立ち上がれば白砂川の流れも見える)なので絶景とまでは言えないけれど、この開放感はなかなかないでしょう。(過去の情報を調べた限りでは一度浴槽にかかる屋根が設置されたはずなのですが・・・。一応今でも脱衣スペースの上には屋根がかけられています。)

さて肝心の温泉については、浴槽は結構広いです。利用するであろう想定人数を考えれば無駄に広いかな(この日は終始独泉)。情報では浴槽がヌルヌルするという評価が多かったですが、この日はそれがなく快適でした。掃除した直後だったのかも知れません。
お湯(源泉)は塩ビ管からドボドボと投入されており、その隣ではホースから水も投入されていました。ただ投入量は源泉の方が圧倒的に多め。そしてもちろんかけ流しで消毒もされていないでしょう。温泉の使用法の掲示がないですが、加水のみのかけ流しと思われます。

湯の質は、無色透明(ちらほらと茶褐色の湯の花が舞う)、微硫黄・鉄臭、微渋・鉄味。渋味は源泉よりホースから注がれる水の方が渋かったので、その影響かも知れません。際立った特徴はない湯だけれども、仄かに湯の香が香ってくる湯は温泉らしさを感じさせてくれます。泉質はカルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉で、源泉は「花敷温泉 川端の湯」となっています。花敷温泉はすぐ近くにある一軒宿の温泉地ですが、その宿とは源泉が異なるようです。
そして湯の中を見ると細かい気泡が舞っており、体への泡付きがあります。その泡付きのためか、若干ツルスベ感が感じられました。源泉が滝のように注がれていてそこで泡が発生していましたが、離れた湯尻でも気泡が舞っていたので、源泉由来の気泡でしょう。それだけ湯が新鮮ということですね。
湯温は若干ぬるめの設定で、真夏の炎天下でも長めに浸かっていられました。適当にホースで加水しているようで絶妙な湯加減であす。それに屋根がないと言っても脱衣スペースの屋根から伸びた影が一部湯船にかかっていたので、直射日光も避けられました。温泉入浴に関しては、開放感と相まって十分に満足できるものでした。
だが、しかし、です。しばらくのんびりと湯浴みを楽しんでいたところ、アカウシアブという大型のアブの攻撃を受ける羽目に。何度追い払っても向かってくるその獰猛さには恐れ入りました。あまりのしつこさに負け退散。鍵を借りる際に豆腐店の女将さんからアブのことを言われていたのですが、まさかこれほどとは・・・。
そんなことがあり残念な最後になってしまったけれども、温泉自体は素晴らしいものであり、記憶に残る入浴となりました。温泉マニアなら気に入る人が多いでしょう(ただし女性には厳しいかも)。春か秋であれば、アブも出ないだろうし新緑や紅葉を楽しみながら湯に浸かれるので、より楽しめるのではないかと思います。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます