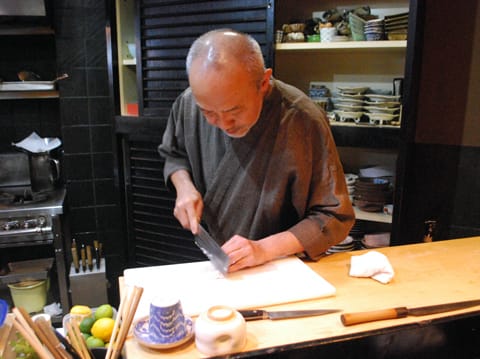今回は古事記全3巻のうち、「中つ巻」の後半をまとめることにしたい(9/21と10/6に学んだ部分)。これで古事記の2/3を学んだことになる。本題に入る前に、少し全体の構成をおさらいしておく。武光誠著『図解雑学 古事記と日本書紀』(ナツメ社刊)の「『古事記』の構成」によると、
古事記は上・中・下の3巻で構成されている。上巻は「序」と神代の記事、中巻・下巻では皇室の系譜と継承がまとめられている。
●上巻では『古事記』のなりたちと神話を記述
『古事記』の上巻は、まず「序」文から始まる。序文は太安万侶の手によるもので、『古事記』完成時に記された。
「序」に続く、上巻での神代の記述は、1つのまとまりを持った神話の体を
なしている。『日本書紀』が多くの異伝を併記して公的な史書らしい体裁を
整えているのと比べると、より物語的であるともいえる。また、『日本書紀』と比べて、大国主命を中心とした出雲神話を重点的に紹介している点も特徴である。
●中・下巻は天皇家の系譜と伝承を記述
中巻では初代神武天皇から15代応神天皇までの記事、下巻では16代仁徳天皇から33代推古天皇までの記事が載っている。中巻と下巻の区分けについては、「仁徳天皇が半人半神の時代と人間の時代との境目こあたる]という当時の考え方にもとづくものだとする説がある。確かに応神天皇以前のエピソードは神がかり的な内容力多いが、仁徳天皇以降のものになると、骨肉の争いや恋の悩みなど、人間らしい実録風の記事が増えている。
あるいは、中巻・下巻の区分けは、儒教の渡来をターニングポイントにしたのではないかという説もある。これは、儒教が渡来した時代を治めた応神天皇の代を中巻でしめくくり、儒教的聖帝である仁徳天皇を徳治の時代の始まりとして、下巻の冒頭に記述したのではないかというものである。
古事記の中つ巻は、奈良県民にとっては親しみやすい「神武東征説話」に始まる。前回ざっと説明したが、ここで『図説 地図とあらすじでわかる! 古事記と日本書記』(青春新書)を引用して振り返っておく。
神武東征―神の系譜に連なる御子の天下平定への道のり
●二二ギの孫たちの東征始まる
ウガヤフキアヘズとタマヨリビメの間に生まれた四人の子供のうち、長兄イツセと末弟、イハレビコは、天下平定を思い立ち、東征の旅に出た。白肩(しらかた)の津に上陸したイツセとイハレビコを待ち受けていたのは、登美の豪族ナガスネビコ(トミビコ)といい、天皇家の祖先が奈良盆地に侵攻した際の抵抗勢力の首長、または、縄文時代から祀られた手長足長の神であるといわれている。そのナガスネビコの抵抗は相当激しく、イハレビコの側にも大きな損害をもたらした。イツセが敵の矢を受けて負傷、木(きの)国まで来たところで無念の言葉を残して息を引き取ってしまうのだ。
●神の力を借りて大和の地へ
その後、弟イハレビコが中心となり、進車が再開される。その一行は、日の神の御子として、太陽に面かっで進撃するのはよくないということから、日を背にして戦おうという、イツセの死の直前になされた取り決めのため、海路南下し、熊野より再上陸を果たした。だがその熊野で妖気に当たり、一行は気を失って倒れてしまう。
一同が目覚めたのは、タカクラジという男が刀を持って現われた時であった。その男は、不思議な夢の話をした。それによると、自分の夢にアマテラスとタカミムスビが現われ、タケミカブチに子孫の手助けをするよう命じた。タケミカヅチは自分が降らずとも、国を平定した時の大刀があればイハレビコを助けることができると言って、タカクラジの倉の屋根に穴を空けてその大刀を降し入れようと言った。翌朝、目覚めると夢の通りにこの大刀があったので、こうして献上したのだという。タカクラジは神々の意向通りに刀を届けにきたのだった。
その後、タカミムスビは、八咫烏(やたがらす)を遣わしてイハレビコを先導させた。烏の誘うほうに進みながら、イハレビコは、阿陀の鵜飼の祖先をはじめ様々な人に出会う。この時、イハレビコは名前を問い、人々はこれに素直に応えているのだが、これは恭順の証で、イハレビコの支配を受け入れたことを意味している。一方で抵抗する者もいた。宇陀のエウカシは服従すると見せかけ、罠を施した屋敷にイハレビコを誘って殺そうと謀った。しかし、弟のオトウカシが兄の企みをイハレビコに知らせたため露見し、エウカシは、追い込まれて自分の仕掛けた罠にかかって死んだ。
忍坂では尾の生えた土雲、ヤソタケルが岩屋の中で待ち構えていた。イハレビコはヤソタケルヘの友好を装って、多くの配膳人にたくさんの料理を運ばせた。しかし配膳人たちは密かに刀を携えていたのである。そして、イハレビコの歌を合図に斬りかかり、油断したヤソタケルを打ち滅ぼしたのである。
こうして次々と荒ぶる神々を征伐・服従させ、敵を退けたイハレビコは、畝火(うねび)の白祷原(かしはら)宮から天下を治めた。初代天皇神武の誕生である。
おさらいは以上である。では、中つ巻後半のキーワードを拾ってみる。ヤマトタケルの逸話が感動的である。
景行天皇P115
Wikipediaによると《景行天皇は、『古事記』『日本書紀』に記される第12代天皇。和風諡号は大足彦忍代別天皇(おほたらしひこおしろわけのすめらみこと)・大帯日子淤斯呂和氣天皇(おほたらしひこおしろわけのすめらみこと 古事記)》《日本武尊(やまとたけるのみこと 倭建命)の父》。
《「タラシヒコ」という称号は12代景行・13代成務・14代仲哀の3天皇が持ち、時代が下って7世紀前半に在位したことが確実な34代舒明・35代皇極(37代斉明)の両天皇も同じ称号をもつことから、タラシヒコの称号は7世紀前半のものであるとして、12,13,14代の称号は後世の造作と考える説があり、景行天皇の実在性には疑問が出されている。記紀の記事は多くが日本武尊(やまとたける)の物語で占められ、残るのは帝紀部分のみになり史実性には疑いが持たれるものの、実在を仮定すれば、その年代は4世紀前半かと考えられている》。
《『古事記』によれば記録に残っている御子が21人、残らなかった御子が59人、合計80人も御子がいたことになっている》《都は纒向日代宮(まきむくのひしろのみや、現在の奈良県桜井市穴師か)》。相撲神社手前の道の脇に、「景行天皇纏向日代宮跡」道の脇に「景行天皇纏向日代宮(けいこうてんのうまきむくノひしろノみや)跡」という石碑が建っているそうだ。
倭建命(ヤマトタケルノミコト)P115
Wikipediaによると《諱(いみな)は小碓尊(命)(おうすのみこと)。第12代景行天皇の皇子・第14代仲哀天皇の父とされる。津田左右吉の説では、実際には4世紀から7世紀ごろの数人の大和(ヤマト)の英雄を統合した架空の人物とされる》《『日本書紀』、『先代旧事本紀』では日本武尊、『古事記』では倭建命》。
《西征 父の寵妃を奪った兄大碓命に対する父天皇の命令の解釈の行き違いから、小碓命は素手で兄をつまみ殺してしまう。そのことで小碓命は父に恐れられ、疎まれて、九州の熊襲建兄弟の討伐を命じられる。わずかな従者しか与えられなかった小碓命は、まず叔母の倭姫命が斎王を勤めていた伊勢へ赴き女性の衣装を授けられる。このとき彼は、いまだ少年の髪形を結う年頃であった》《九州に入った小碓命は、熊襲建の新室の宴に美少女に変装して忍び込み、宴たけなわの頃を狙ってまず兄建を斬り、続いて弟建に刃を突き立てた。誅伐された弟建は死に臨み、その武勇を嘆賞し、自らをヤマトヲグナと名乗る小碓命に譲って倭建(ヤマトタケル)の号を献じた》《その後、倭建命は出雲に入り、出雲建と親交を結ぶ。しかし、ある日、出雲建の太刀を偽物と交換した上で、太刀あわせを申し込み殺してしまう》。
《東征 西方の蛮族の討伐から帰るとすぐに、景行天皇は重ねて東方の蛮族の討伐を命じる。倭建命は再び倭姫命を訪ね、父天皇は自分に死ねと思っておられるのか、と嘆く。倭姫命は倭建命に伊勢神宮にあった神剣天叢雲剣(草薙剣)と袋とを与え、「危急の時にはこれを開けなさい」と言う》《倭建命はまず尾張国造家に入り、美夜受媛(宮簀媛)と婚約をして東国へ赴く》《相模の国で、国造に荒ぶる神がいると欺かれた倭建命は、野中で火攻めに遭ってしまう。そこで叔母から貰った袋を開けたところ、火打石が入っていたので、草薙剣(天叢雲剣)で草を掃い、迎え火を点けて逆に敵を焼き尽くしてしまう。それで、そこを焼遣(やきづ=焼津)という》。
《相模から上総に渡る際、走水の海(横須賀市)の神が波を起こして倭建命の船は進退窮まった。そこで、后の弟橘媛が自ら命に替わって入水すると、波は自ずから凪いだ。入水に当たって媛は火攻めに遭った時の夫倭建命の優しさを回想する歌を詠む。弟橘姫は、倭健命の思い出を胸に、幾重もの畳を波の上に引いて海に入るのである。七日後、姫の櫛が対岸に流れ着いたので、御陵を造って、櫛を収めた》。
《その後倭建命は、足柄坂(神奈川・静岡県境)の神を蒜(ひる=野生の葱・韮)で打ち殺し、東国を平定して、四阿嶺に立ち、そこから東国を望んで弟橘姫を思い出し、「吾妻はや」(わが妻よ……)と三度嘆いた。そこから東国をアヅマ(東・吾妻)と呼ぶようになったと言う。また甲斐国の酒折宮で連歌の発祥とされる「新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる」の歌を詠み、それに、「日々並べて(かがなべて) 夜には九夜 日には十日を」との下句を付けた火焚きの老人を東の国造に任じた。その後、科野(しなの=長野県)を経て、倭建命は尾張に入る》。
《素手で伊吹の神と対決しに行った倭建命の前に、白い大猪が現れる。倭建命はこれを神の使いだと無視をするが、実際は神自身の化身で、大氷雨を降らされ、命は失神してしまう。山を降りた倭建命は、居醒めの清水(山麓の関ヶ原町あるいは米原市の両説あり)で正気をやや取り戻すが、すでに病の身となっていた。弱った体で大和を目指して、当芸・杖衝坂・尾津・三重村(岐阜南部から三重北部)と進んで行く。ここでは地名起源説話を織り交ぜて、死に際の倭建命の心情を映し出す描写が続く。そして、能煩野(三重県亀山市〉に到った倭建命はついに「倭は国のまほろば……」以下の4首の国偲び歌を詠って亡くなるのである》。
《倭建命の死の知らせを聞いて、大和から訪れたのは后や御子たちであった。彼らは陵墓を築いてその周りで這い回り、歌を詠った。すると倭建命は八尋白智鳥となって飛んでゆくので、后たちはなお3首の歌を詠いながら、その後を追った。これらの歌は「大御葬歌」(天皇の葬儀に歌われる歌)となった》《白鳥は伊勢を出て、河内の国志幾に留まり、そこにも陵を造るが、やがてまたその地より天に翔り、行ってしまう》。
成務天皇P130
Wikipediaによると《『古事記』『日本書紀』に伝えられる第13代天皇(在位:成務天皇元年1月5日(131年2月19日) - 同60年6月11日(190年7月30日))。和風諡号は稚足彦尊(わかたらしひこのみこと)、若帯日子天皇(わかたらしひこのすめらのみこと、古事記)》《『記・紀』に載せる成務天皇の旧辞部分の記事は、他の天皇のそれに比して極端に文量が少なく、史実性には疑いが持たれているものの、実在を仮定すればその年代は4世紀半ばに当たると考えられている》。
《都は志賀高穴穂宮(しがのたかあなほのみや、現在の滋賀県大津市穴太)。 『古事記』に「若帯日子天皇、近つ淡海の志賀の高穴穂宮に坐しまして、天の下治らしめしき」とある。成務天皇を架空と見る立場からは、天智天皇の近江宮のモデルを過去に投影した創作とする》。御陵は《『古事記』に「沙紀之多他那美(たたなみ)」とある。現在、同陵は奈良県奈良市山陵町の佐紀石塚山古墳(前方後円墳・全長218m)に比定される。江戸時代まで度々盗掘の被害に遭った古墳の一で、犯人は流罪・磔などに処されたという》。
仲哀天皇P131
Wikipediaによると《『古事記』『日本書紀』に記される第14代天皇(在位:仲哀天皇元年1月11日(192年2月11日) - 同9年2月6日(200年3月8日))。足仲彦天皇(たらしなかつひこのすめらみこと)、帯中日子天皇(古事記)》《仲哀天皇は実在性の低い天皇の一人に挙げられているが、その最大の根拠は、彼が実在性の低い父(日本武尊)と妻(神功皇后)を持っている人物であり、この二人の存在および彼らにまつわる物語を史実として語るために創造され、記紀に挿入されたのが仲哀天皇であるというのが、仲哀天皇架空説である》。
《また、仲哀天皇の「タラシナカツヒコ(足仲彦・帯中日子)」という和風諡号から尊称の「タラシ」「ヒコ」を除くと、ナカツという名が残るが、これは抽象名詞であって固有名詞とは考えづらい(中大兄皇子のように、通常は普通名詞的な別名に使われる)。つまり、仲哀天皇の和風諡号は実名を元にした物ではなく、抽象的な普通名詞と言う事になる。さらに前述の通り、『日本書紀』では父の日本武尊の死後36年も経ってから生まれたことになる不自然さもあり、仲哀天皇架空説を支持する意見は少なくない》。
神功皇后P131
Wikipediaによると《仲哀天皇の皇后。『紀』では気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)・『記』では息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)・大帯比売命(おおたらしひめのみこと)・大足姫命皇后。父は開化天皇玄孫・息長宿禰王(おきながのすくねのみこ)で、母は天日矛裔・葛城高顙媛(かずらきのたかぬかひめ)。彦坐王の4世孫、応神天皇の母であり、この事から聖母(しょうも)とも呼ばれる》。
《『日本書紀』などによれば、201年から269年まで政事を執り行なった。夫の仲哀天皇の急死(200年)後、住吉大神の神託により、お腹に子供(のちの応神天皇)を妊娠したまま海を渡って朝鮮半島に出兵して新羅の国を攻めた。新羅は戦わずして降服して朝貢を誓い、高句麗・百済も朝貢を約したという(三韓征伐)。渡海の際は、お腹に月延石や鎮懐石と呼ばれる石を当ててさらしを巻き、冷やすことによって出産を遅らせたとされる》《神功皇后が三韓征伐の後に畿内に帰るとき、自分の皇子(応神天皇)には異母兄にあたる香坂皇子、忍熊皇子が畿内にて反乱を起こして戦いを挑んだが、神功皇后軍は武内宿禰や武振熊命の働きによりこれを平定したという》。
《江戸時代から実在の人物かどうか様々な論考があったが、明治から太平洋戦争敗戦までは学校教育の場では実在の人物として教えていた。現在では実在説と非実在説が並存している》《神功皇后を卑弥呼や台与と同じような巫女王であったとする見方もある。住吉三神とともに住吉大神の1柱として、また応神天皇とともに八幡三神の1柱として信仰されるようになる》。
建内宿禰(タケノウチノスクネ、武内宿禰)P132
世界大百科事典によると《大和朝廷初期の伝説上の人物》《孝元天皇の孫 (《古事記》) または曾孫 (《日本書紀》) で,景行朝初年,紀直 (きのあたい) の女を母として紀国で生まれたとされる。景行天皇の 51 年正月の宴に〈非常 (おもいのほか) に備へて〉門下に侍し忠誠を賞され,同年棟梁の臣となり,記によれば成務,仲哀,応神,仁徳 (紀では景行から仁徳) 朝の大臣をつとめたという。この間,仲哀死後に神功 (じんぐう) 皇后とともに神託を聞き,皇后の朝鮮出兵後は,応神即位のために忍熊王 (おしくまのみこ) の軍を破り,太子 (のちの応神) に従って気比 (けひ) 大神を拝し,即位へと導く。応神天皇 9 年,弟の甘美内 (うましうち) 宿衝に讒されるが,盟神探湯 (くかたち) に勝って潔白を示す。仁徳朝にも瑞祥に関連した二つの伝承がある》。
盟神探湯とは、釜で沸かした熱湯の中に手を入れさせ、正しい者は火傷せず、罪のある者は大火傷を負うとする古代の裁判法である。《この人物の物語はもちろん史実とはいえない。仁徳天皇以外はすべて実在しない天皇にかけて伝承が語られていること,忍熊王討伐の話が本来和邇 (わに) 氏の持っていた伝承であったことなどがその証となる。 《古事記》孝元天皇条にはその 7 人の男子が波多,巨勢 (こせ),蘇我,平群 (へぐり),損城,紀など 27 氏の祖となる系譜を伝える。過去に大臣となった伝承を持つ氏族,大和南西部を中心とした豪族を網羅したこの系譜もまた作為されたものであろう》。
《だが作為にもその目的がなければならない。これについては蘇我氏がその権勢を示すために,蘇我馬子をモデルとして 6 世紀末前後に作ったとする説, 藤原鎌足をモデルとして 7 世紀末に作られたとする説がある。後者は,系譜や物語にかかわる天皇がほとんど非実在者であること, 《風土記》に神功皇后の物語が多く,武内宿衝の記事は絶無なので,両者の結合は記紀成立時であること,文武天皇の宣命に鎌足と武内宿衝とを近侍の重臣として等視する事実のあることなどを根拠とする。しかし蘇我氏の祖先伝承はこれが唯一であることを考えると,ただちに後説にも従い得ない。皇室の姻族として損城氏を継いだ蘇我氏が,まず損城氏との血族系譜を作ったのが根幹となっていたはずであり,大臣としての武内宿衝像が成立するのは 7 世紀後半以後であろう》。皇国史観の下では忠臣の誉れが高く、明治から昭和初期にかけて、日本銀行券の肖像としても使われた。死亡年齢については、280歳、295歳、306歳、312歳、360歳などの諸説がある。
応神天皇P139
『古事記』には品陀和氣命(ホムダワケノミコト)として登場する。世界大百科事典によると《第 15 代に数えられる天皇。仲哀天皇の皇子,母は息長足姫 (おきながたらしひめ) (神功皇后)。諱 (いみな) は誉田別 (ほんだわけ)という》《《日本書紀》によると,仲哀天皇は西征のさなかに没し,皇后が三韓に遠征したさいにはすでに胎内にあり,遠征から帰ったのち,筑紫で生まれたという。中央にかえり,皇后の摂政のもとで,皇太子となり,皇后の没後,はじめて即位し,大和国高市郡軽島 (豊) 明宮に居した》。
《応神朝では,武内宿衝(たけうちのすくね) が前代からの勢力を保っているが,天皇にかかわる国内記事として,妃の兄媛 (吉備氏の祖御友別の妹) とともに吉備に幸し,御友別の兄弟子孫の功に報い,吉備国を 5 県に分かち,それぞれを封じたという。対外記事としては,百済から弓月君 (秦氏の祖),阿直岐 (あちき) (漢 (あや) 氏の祖),王仁 (わに) (河内書 (ふみ) 氏の祖) らが来朝したとあるなど,帰化人のはじめての渡来を記録している。そののち,天皇の皇子測道稚郎子 (うじのわきいらつこ) を日嗣 (太子) とし,大山守命に山川林野をつかさどらせ,大鷦鷯 (おおささぎ) 尊を太子の輔として,国事を分担させたという。治世 41 年にわたり,豊明宮 (一説に摂津の大隅宮) に没した》。
《母,神功皇后は天照大神と住吉大神の神託によって朝鮮半島を平定したと語られる巫女的性格の女性。天皇は,受胎後,母の半島平定中ずっと胎中にあり,帰国した北九州で誕生,後に空船 (むなぶね) に乗って難波に漂着する。その後重臣の武内宿衝に伴われて敦賀に禊 (みそぎ) し,気比 (けひ) 大神に名を賜って大和に帰り,母の献酒を受け,軽島の明宮 (あきらのみや) に即位する。この物語にみられる,漂流,海上来臨,みそぎ,成人,即位という展開は,神来臨を原型とした始祖神話譚の性格を濃厚に持つ。 《住吉大社神代記》が〈大神と密事 (むつびごと) あり〉と述べ,天皇を神の子とするのも,天皇の神秘的性格を示すものである。また祖父を東西平定の英雄,日本武尊とし,母を,新羅皇子の血統をひき,半島を平定した神功皇后としたのは,この天皇が日本および半島の生まれながらの君主であるという主張を示す。後に天皇と母は八幡信仰の中心に据えられていく》。
宇遲能和紀郎子(ウヂノワキイラツコ=菟道稚郎子)
Wikipediaによると《記紀に伝えられる古墳時代の皇族(王族)》《応神天皇の皇子で、母は和珥臣祖の日触使主(ひふれのおみ、比布礼能意富美)の女 ・宮主宅媛(みやぬしやかひめ、宮主矢河枝比売)である(ただし『先代旧事本紀』には、物部多遅麻連の女・山無媛とする)。同母妹に八田皇女・雌鳥皇女。父天皇の寵愛を受けて皇太子に立てられたものの、異母兄の大鷦鷯尊(おおさざきのみこと、後の仁徳天皇)に皇位を譲るべく自殺したという美談で知られる。百済から来朝した阿直岐・王仁を師に典籍を学んで通達し、父の天皇から寵愛された。応神天皇40年(309年)1月に皇太子となる》。
《翌年に天皇が崩じたが、太子は即位せず、大鷦鷯尊と互いに皇位を譲り合った。そのような中、異母兄の大山守皇子は自らが太子に立てなかったことを恨み、太子を殺そうと挙兵する。大鷦鷯尊はこれをいち早く察知し、大山守皇子はかえって太子の謀略に遭って殺された。この後、太子は菟道宮(京都府宇治市の宇治上神社が伝承地。『山城国風土記』逸文に桐原日桁宮)に住まい、大鷦鷯尊と皇位を譲り合うこと3年。永らくの空位が天下の煩いになると思い悩んだ太子は互譲に決着を期すべく、自ら果てた。尊は驚き悲しんで、難波から菟道宮に至り、遺体に招魂の術を施したところ、太子は蘇生し、妹の八田皇女を献ずる旨の遺言をして、再び薨じたという》。
大山守命(オオヤマモリノミコト)P139
応神天皇の皇子で、大雀命(オホサザキノミコト=のちの仁徳天皇)の異母兄。
Wikipediaによると《応神天皇40年1月、菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)の立太子の際、山川林野の管掌を任されたが、兄である自らが皇太子になれなかったことを恨んでいた。応神天皇の崩御後、密かに皇位を奪おうと謀り、皇太子を殺害するために数百の兵を挙げた。しかし、この謀は前もって大鷦鷯尊(おおさざきのみこと。後の仁徳天皇)と皇太子の察知するところとなり、菟道川(うじがわ)の渡河中に渡し守に扮する皇太子の計略によって船を転覆させられ、救援を請うも空しく水死した。遺骸は考羅済(かわらのわたり。現在の京都府京田辺市河原)で見つかり、那羅山に葬られたという(那羅山墓)。現在、この墓は奈良市法蓮町所在の円墳に比定され、宮内庁の管理下にある》。
以上、一気に中つ巻の終わりまで走ってしまった。何といっても中つ巻後半はヤマトタケルなので、かなりの字数を割いた。残るは下つ巻で、第16代仁徳天皇~第33代推古天皇までが紹介される。しかし、たとえば推古天皇は3行、第32代崇峻天皇に至ってはわずか2行なので、これまでのようなストーリー性は薄い。読者の皆さん、もう少しお付き合いください。