
奈良は清酒の発祥地である。山と渓谷社刊『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』の「清酒」(特産品)によると、
※トップ写真は、「第1回乾杯デジタルフォトコンテスト」(日本酒で乾杯推進会議)入賞作品
酒の歴史は古く、平城京から出土した木簡にも造酒のことが書かれている。長い間濁り酒だったが、室町時代に清酒が造られ、この上が無いと「無上酒」とまで呼ばれた。この清酒を造ったのが正暦寺(しょうりゃくじ=奈良市)。日本の清酒の起源はここから始まる。「菩提酛(ぼだいもと)」と呼ばれる酒母(しゅぼ)は奈良盆地の米、菩提山川の清らかで豊かな水によって生まれた。
戦国時代はかなりの量が造られ、武将たちは競って求めたという。武田勝頼を滅ぼした徳川家康を信長は「南都諸白(なんともろはく)」でもてなし、秀吉が吉野山で花見の宴を張った時も「南都諸白」。奈良正暦寺の僧房酒は天下一の酒として知られていった。近年、昔ながらの酒母造りが正暦寺で復活、「菩提もと」を使った地酒が造られている。
また、桜井市の大神神社では毎年「醸造安全祈願祭」(酒まつり)が営まれる。同神社のHPによると、
例年11月14日に、「酒の神様」「醸造の祖神」と仰がれるご神徳を称えて、新酒の「醸造安全祈願祭(酒まつり)」が行われます。特に14・16・17日には社頭で醸造元より奉納された四斗樽の鏡が開かれて参拝者に振る舞われ、境内一円がお酒の甘美な香りで満ち溢れます。前日13日の午前9時には、拝殿・祈祷殿向拝の大杉玉(直径1メートル60センチ、重さ150キロ)が緑の色も鮮やかな新しいものと取り替えられます。
奈良県下には多くの酒蔵(酒造会社)がある。奈良県の酒は、バラエティに富んでいるのが特徴だ。酒蔵も、他府県のように1か所に集中するのではなく、県下に広く分布している。春日大社、大神神社、橿原神宮など、神社に寄り添うような格好で酒蔵があることも奈良の特徴である。
日本酒の味を左右するのは、水である。奈良市は春日山原始林、生駒は生駒山、葛城は金剛葛城山、とそれぞれ伏流水に恵まれている。吉野は日本一水の豊富なところだし、大和高原には良質の地下水が湧き出る。だから各地で特徴のある日本酒が作られる。
フランスでは、各地でワインの新酒祭り(ヴァン ヌーボー)が行われる。ボジョレ・ヌーボー解禁日のお祭り騒ぎも、よく知られている。その影響で、日本でも、山梨や神戸や河内で、ワインの新酒祭りが行われる。
そこで提案である。毎年1~2月に、日本酒の「新酒祭り」を奈良県内で開催できないだろうか。「醸造安全祈願祭」のようなメーカーのための祭りではなく、美味しい新酒とそれに合う料理を楽しむイベントとして…。発案者は(ハンドルネーム)井伊和気右衛門さんだ。当ブログの「日本酒で乾杯!」という記事に、
此の神酒(みき)は我が神酒ならず 倭成す大物主の醸(か)みし神酒 幾久 幾久
(高橋邑の活日の歌『日本書紀』)
大和に酒の神、いい地酒、うまいものが揃いましたね。大物主の祝福で奈良のうまいものといい地酒がマリアージュ。でも、三輪の酒まつりは、酒蔵の醸造祈願祭。作る側のお祭です。お酒をいただく側のうまい料理とうまい酒のマリアージュを楽しめる新酒祭りがあればいいのになあ。きっと、ボジョレー騒ぎよりいいお祭りになるのに。
というコメントを投稿していただいたのである。これには私から《どこかに提案してみましょうか。黒滝村の牧場飼育の猪や、御所の合鴨を使った鍋料理と組み合わせて…。冬場の閑散期の良いイベントになりそうです》と返答させていただいた。

北海道では、北海道酒遊記「パ酒ポート(パシュポート)」というお酒(日本酒、ワイン、ビール)のスタンプラリー・イベントを実施しているそうだ。旅行会社にお勤めのMさんに教えていただいた。Facebookには、
飲んでますか?北海道のお酒。北海道各地では魅力的なお酒がたくさん造られてます。広い大地、澄んだ空気、絶えることのない雪清水…。北海道の恵みを凝縮し豊かな自然が育んだ日本酒、ワイン、ビールの数々。その酒造を巡りながら「観光」も「食」もお得に楽しみませんか?パ酒ポートで巡るちょっと大人のスタンプラリーいよいよスタート!スタンプを集めて、豪華賞品をゲット!
完走者には全種蔵書制覇認定書をプレゼント、めざせ道産酒マイスター!
そのほかにも…パ酒ポート4つのお得!
①全23か所の酒造所で必ず受けられる特典&割引あり!
②特約温泉施設30店舗でワンコイン(500円)入浴可!
③特約ガソリンスタンドでなんと5円/ℓ引き!
④特約飲食店や各施設で割引や特典など!

奈良市では、観光閑散期のイベントとして2010年2月から「なら瑠璃絵」をスタートさせた。2014年2月からは、「珠光茶会」という5日間の大茶会を開催する。どちらも悪くはないのだが、日本酒好きのワタクシとしては、寒い2月にはココアやお茶よりお酒を飲んで温まりたいし、美味しい小鍋もつつきたい。
大和肉鶏の水炊き、大和牛(やまとうし)のすき焼き、ヤマトポークの豚しゃぶ。牧場飼育の猪鍋(黒滝村)は臭味がないし、牛乳仕立ての飛鳥鍋は、文字通り飛鳥時代に明日香村で考案された鍋物である。ニューフェイスの倭鴨(やまとがも)の鴨鍋は、「第4回 鍋-1グランプリ」で優勝している。「○○うま酒祭り」「○○酒蔵バル」などのネーミングは、いかがだろう。○○のところには地名を入れ、「葛城うま酒祭り」「吉野酒蔵バル」のように…。
幸い奈良県下に酒蔵は広い地域に分布している。南部や東部の山間部にもいい酒蔵があるし、畜産物は美味しいし、新鮮な大和野菜も収穫できる。道具立てはすべて揃っているのである。さてこのアイデア、どこへ提案しに行ったものやら…。
※トップ写真は、「第1回乾杯デジタルフォトコンテスト」(日本酒で乾杯推進会議)入賞作品
酒の歴史は古く、平城京から出土した木簡にも造酒のことが書かれている。長い間濁り酒だったが、室町時代に清酒が造られ、この上が無いと「無上酒」とまで呼ばれた。この清酒を造ったのが正暦寺(しょうりゃくじ=奈良市)。日本の清酒の起源はここから始まる。「菩提酛(ぼだいもと)」と呼ばれる酒母(しゅぼ)は奈良盆地の米、菩提山川の清らかで豊かな水によって生まれた。
戦国時代はかなりの量が造られ、武将たちは競って求めたという。武田勝頼を滅ぼした徳川家康を信長は「南都諸白(なんともろはく)」でもてなし、秀吉が吉野山で花見の宴を張った時も「南都諸白」。奈良正暦寺の僧房酒は天下一の酒として知られていった。近年、昔ながらの酒母造りが正暦寺で復活、「菩提もと」を使った地酒が造られている。
また、桜井市の大神神社では毎年「醸造安全祈願祭」(酒まつり)が営まれる。同神社のHPによると、
例年11月14日に、「酒の神様」「醸造の祖神」と仰がれるご神徳を称えて、新酒の「醸造安全祈願祭(酒まつり)」が行われます。特に14・16・17日には社頭で醸造元より奉納された四斗樽の鏡が開かれて参拝者に振る舞われ、境内一円がお酒の甘美な香りで満ち溢れます。前日13日の午前9時には、拝殿・祈祷殿向拝の大杉玉(直径1メートル60センチ、重さ150キロ)が緑の色も鮮やかな新しいものと取り替えられます。
奈良県下には多くの酒蔵(酒造会社)がある。奈良県の酒は、バラエティに富んでいるのが特徴だ。酒蔵も、他府県のように1か所に集中するのではなく、県下に広く分布している。春日大社、大神神社、橿原神宮など、神社に寄り添うような格好で酒蔵があることも奈良の特徴である。
日本酒の味を左右するのは、水である。奈良市は春日山原始林、生駒は生駒山、葛城は金剛葛城山、とそれぞれ伏流水に恵まれている。吉野は日本一水の豊富なところだし、大和高原には良質の地下水が湧き出る。だから各地で特徴のある日本酒が作られる。
フランスでは、各地でワインの新酒祭り(ヴァン ヌーボー)が行われる。ボジョレ・ヌーボー解禁日のお祭り騒ぎも、よく知られている。その影響で、日本でも、山梨や神戸や河内で、ワインの新酒祭りが行われる。
そこで提案である。毎年1~2月に、日本酒の「新酒祭り」を奈良県内で開催できないだろうか。「醸造安全祈願祭」のようなメーカーのための祭りではなく、美味しい新酒とそれに合う料理を楽しむイベントとして…。発案者は(ハンドルネーム)井伊和気右衛門さんだ。当ブログの「日本酒で乾杯!」という記事に、
此の神酒(みき)は我が神酒ならず 倭成す大物主の醸(か)みし神酒 幾久 幾久
(高橋邑の活日の歌『日本書紀』)
大和に酒の神、いい地酒、うまいものが揃いましたね。大物主の祝福で奈良のうまいものといい地酒がマリアージュ。でも、三輪の酒まつりは、酒蔵の醸造祈願祭。作る側のお祭です。お酒をいただく側のうまい料理とうまい酒のマリアージュを楽しめる新酒祭りがあればいいのになあ。きっと、ボジョレー騒ぎよりいいお祭りになるのに。
というコメントを投稿していただいたのである。これには私から《どこかに提案してみましょうか。黒滝村の牧場飼育の猪や、御所の合鴨を使った鍋料理と組み合わせて…。冬場の閑散期の良いイベントになりそうです》と返答させていただいた。

北海道では、北海道酒遊記「パ酒ポート(パシュポート)」というお酒(日本酒、ワイン、ビール)のスタンプラリー・イベントを実施しているそうだ。旅行会社にお勤めのMさんに教えていただいた。Facebookには、
飲んでますか?北海道のお酒。北海道各地では魅力的なお酒がたくさん造られてます。広い大地、澄んだ空気、絶えることのない雪清水…。北海道の恵みを凝縮し豊かな自然が育んだ日本酒、ワイン、ビールの数々。その酒造を巡りながら「観光」も「食」もお得に楽しみませんか?パ酒ポートで巡るちょっと大人のスタンプラリーいよいよスタート!スタンプを集めて、豪華賞品をゲット!
完走者には全種蔵書制覇認定書をプレゼント、めざせ道産酒マイスター!
そのほかにも…パ酒ポート4つのお得!
①全23か所の酒造所で必ず受けられる特典&割引あり!
②特約温泉施設30店舗でワンコイン(500円)入浴可!
③特約ガソリンスタンドでなんと5円/ℓ引き!
④特約飲食店や各施設で割引や特典など!

奈良市では、観光閑散期のイベントとして2010年2月から「なら瑠璃絵」をスタートさせた。2014年2月からは、「珠光茶会」という5日間の大茶会を開催する。どちらも悪くはないのだが、日本酒好きのワタクシとしては、寒い2月にはココアやお茶よりお酒を飲んで温まりたいし、美味しい小鍋もつつきたい。
大和肉鶏の水炊き、大和牛(やまとうし)のすき焼き、ヤマトポークの豚しゃぶ。牧場飼育の猪鍋(黒滝村)は臭味がないし、牛乳仕立ての飛鳥鍋は、文字通り飛鳥時代に明日香村で考案された鍋物である。ニューフェイスの倭鴨(やまとがも)の鴨鍋は、「第4回 鍋-1グランプリ」で優勝している。「○○うま酒祭り」「○○酒蔵バル」などのネーミングは、いかがだろう。○○のところには地名を入れ、「葛城うま酒祭り」「吉野酒蔵バル」のように…。
幸い奈良県下に酒蔵は広い地域に分布している。南部や東部の山間部にもいい酒蔵があるし、畜産物は美味しいし、新鮮な大和野菜も収穫できる。道具立てはすべて揃っているのである。さてこのアイデア、どこへ提案しに行ったものやら…。










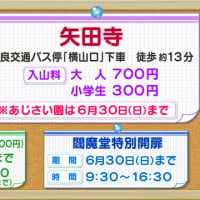















大和の酒祭りいいですね!私も最近は奈良の日本酒ばかり飲んでいます。鉄田様は、近鉄高天ビル地下にある「酒房 亜耶」さんをご存じでしょうか?
そちらのマスター田中さんが中心となり、来年春頃に奈良の地酒のイベントを企画していらっしゃるそうです。宜しければ一度、話を聞いてみて下さい。
これからも、楽しい記事を楽しみにしております。
なお、こちらにそぐわない投稿であれば削除して下さい。
> 「酒房 亜耶」さんをご存じでしょうか?そちらのマスター田中さんが中心
> となり、来年春頃に奈良の地酒のイベントを企画していらっしゃるそうです。
あのビルは「ほおずき」ばかりを訪ねていまして、「酒房 亜耶」は、前を通るだけでした。いちど訪ねてみます。ただあまり小規模なイベントでは、効果は得られないと思います。
2/24(月)午後、東京・日本橋三越前の奈良まほろば館で奈良酒のイベントをやります。私と酒販店の社長がお酒の講話をしたあと、とっておきの「奈良酒」の振る舞いをし、最後に180ml瓶入りのお酒をプレゼントします。あとは1階の売店で、お好みの奈良酒を買っていただきます。
これでテストマーケテイングしたあと、次のステップを考えたいと思っています。
> 1975年日本酒(米から作ったお酒、清酒のこと)消費量は170万KL、現在
> 60万KLと約3分の1、全国酒蔵数3200が今1584蔵と減っています。
はい。但し、吟醸酒や大吟醸は好調ですよ。安価な普通酒が減っているのです。
> 生産1位兵庫(灘)2位京都(伏見)で実に全国の半分を生産します。
この地域は普通酒(「白鶴まる」など)の生産量が多いので、統計上、そうなってしまうのです。
> 京都市で「日本酒で乾杯条例」が制定されましたが今年消費量が20%増しとか
京都の先見の明には、驚きます。和食の世界遺産登録も、京都の料理人さんのおかげです。奈良としては、ぜひこの波に乗りたいです。
私としては、最初は観光イベントというより、地元の者が楽しむお祭りで、毎年続けているうちに観光客も一緒になって楽しむ祭りに大きく成長していくのがいいんじゃないかと。
私がもし他府県のお祭りに行くとすれば、観光(客寄せ)イベントより、地元のお祭りに参加させてもらうほうが絶対いいと思うからです。
観光客相手のレストランより、地元民愛用の食堂へ行きたい心理ですかね。
地酒も食文化も、地元民が支えてこそですから。
もう一つ、単なる酒飲みや商業的なイベントじゃなくて、今年も人々とともに新酒を味わい、お互いの健康を祝い合えることを、お酒の神様大物主命に感謝できるお祭りになればいいなあと思います。
だから、大神神社の役割は欠かせません。それがあってこそ、奈良独自のお祭りになることですしね。
あちこちからいっぱいアイデアが出てきて、まとめるのは大変だろうと思いますが、こうやってあれこれ考えている時が一番楽しいですね。
> 記事にしてくださってありがとうございます。フェイス
> ブックの方の反響も大きくって、嬉しいです。
106人の「いいね!」と17件のコメントをいただきました。
> 観光客相手のレストランより、地元民愛用の食堂へ行きたい
> 心理ですかね。地酒も食文化も、地元民が支えてこそですから。
自然と地元から手が上がるのが理想ですが、動かないようなら、やはり仕掛けを考えなければいけません。奈良の人は、引っ込み思案ですから。
> お互いの健康を祝い合えることを、お酒の神様大物主命
> に感謝できるお祭りになればいいなあと思います。
いいですね。春日大社にも酒蔵があります。神社とタイアップするのが、「いかにも奈良らしい」ですね。
> こうやってあれこれ考えている時が一番楽しいですね。
その通り。私も講演の都度、この話を持ち出したいと思っています。
> 1月から2月にかけて、各藏元さんは仕込みの最中で
> 大変忙しいでしょう。本当に新酒が上がるのは秋です。
1~2月の観光閑散期の行事にしたいのです。秋は黙っていても観光客が来ますので。この辺りは、蔵元の意見も聞きたいと思います。
> 藏元見学といったイベントを外しても、楽しい企画になりそうです。
酒販店や神社をメインに据えるとか、蔵元の負担を軽くする方法が必要ですね。