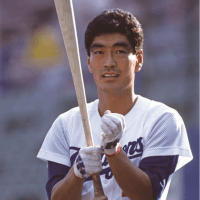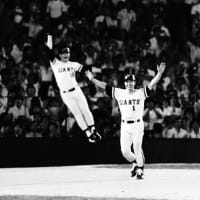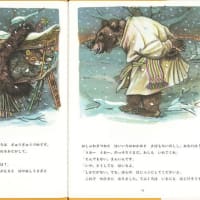5月17日 京都市交響楽団第700回定期演奏会を聴きに行く。
指揮 ピアノ ハインツ ホリガーさんで最初に
ホリガー エリス3つの夜の小品がピアノ独奏版そして管弦楽版と連続して演奏された。
今日は開演ぎりぎりに着席したのでこの曲が始まった時プログラムで曲目を確認する時間がなかった。
それで、まあいいや とにかく演奏を集中して聴いて後でプログラムを見ようと思ってその通りにした。
指揮者が出てきてステージ左手に置いてあるピアノに座って演奏し始めた。
「おや ピアノの弾き振りか?でもステージのあんなに左の奥からどうやってオーケストラを指揮するのだろう。これは見ものだぞ」と思っていたらピアノの演奏が終わると指揮者はちゃんと指揮台の方に行って指揮を始めたので またまた おや?となってしまった。
「あんなに左の方にあるピアノに座って演奏を始めたのはみんなをびっくりさせるための演出か」 と思った。
後でプロクラムを見て、同じ曲をピアノ版と管弦楽版で演奏してくださったとわかった。
次に演奏されたのが ホリガー 2つのリスト作品のトランスクリプション
「灰色の雲」「不運」
グレゴリオ聖歌「怒りの日」、もしくはその断片と思えるような旋律が管楽器を中心に出てきたのが印象的だったけど全体的なことは忘れてしまった。
次に武満徹の 夢窓 が演奏された。
演奏中、木管楽器の音がどこからでているのかわからない時間がしばらくあり落ち着かない気持ちだった。
ふと気づくと指揮者の左にフルート右にクラリネットがいた ああ、あそこだったのかと思った。
指揮者の右のクラリネットはどなたが演奏されているのかわからなかったけれど演奏が終わって正面を向いてあいさつされたとき ああ いつも正面を向いて演奏されている方だと初めてわかった。
横からのお姿を見ることが初めてだったので。
いつも正面からばかりだと横からだとわからないことがあるんだなと やはり人間と言うか僕の感覚と言うものはあてにならないものだなあとそのときつくづく思った。
コントラバスが左右に並んでいたので弦楽器の並びは目を凝らして見たはずなのにその弦楽器のど真ん中にいらっしゃる二人の木管奏者の方が最初は見えてなかったなんて。
僕の視力が矯正してもそれほどよくないこともあるし、あんなところに木管がいるはずがないという思い込みもあると思った。(通常はコンサートマスターやビオラの主席の方などがいらっしゃる場所なので)
次に
シューマンの交響曲第1番が演奏された。
シューマンの交響曲に関してドビュッシーのこんな言葉がある。
「ベートーヴェン以後、交響曲が無用となったことは実証済みであるように私には思われる。実際、シューマンの場合もメンデルスゾーンにあっても交響曲はすでに力が衰えた同一の形式のうやうやしい繰り返しでしかもうないではないか」と。
岩波文庫 ドシュッシー 音楽評論集 47ページより引用。
僕はシューマンの交響曲でアグレッシブなタイプの演奏を聴くときしばしばある意味ドビュッシーがここで書いていることは的を射ていると思うことがある。
しかし、この日の演奏は、そういうアグレッシブと言うタイプの演奏ではなかった。
力をいかに入れるかよりもむしろ力をいかに抜くか、そしていかにゆったり演奏するかを意識したタイプの演奏だった。
そのような演奏に接した時、シューマンがシューベルトの交響曲 グレイトの楽譜を発見した時に語ったとされる言葉 「天国的に長い」というものを思い出した。
そして思った 力を抜いて演奏するとシューマンの交響曲もシューベルトに劣らず天国的だと。
要するにシューマンそのものが天国的と言う感覚を心に持った人だからシューベルトの天国性にも気づくことができたのだと思った。
そりゃそうだよな、シューマンは「子供の情景」の作曲者なのだものと思った。
シューマンの交響曲は最近CDなどで聴く頻度も増えたけれど そういうことに気付くことができたのは目の前で繰り広げられる演奏がある意味、神々しさを感じさせてくれるタイプの演奏だったからだ。
本当にいくら作曲家が素晴らしいものを書いても演奏する人がいなければ音楽は音にならない。
そしてその演奏によって作曲家が書いたものがどういうものだったのか気づくことができる。
その役割と言うものを感じされてくれる本当に素晴らしい演奏でよかった。
それはともかく 一日 いちにち 無事にすごせますように それを第一に願っていきたい。