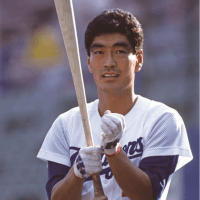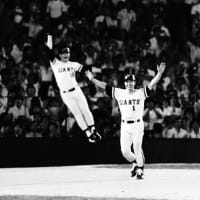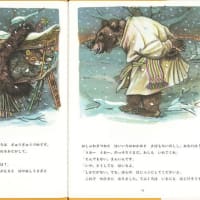6月27日名古屋フィルハーモニー交響楽団第97回名曲シリーズを聴きに行く。
指揮 ヨハンナ・マラングレさんで
シューベルト:イタリア風序曲第2番ハ長調 D 591
ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調 作品21
ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調 作品55『英雄』
の3曲が演奏された。
シューベルトはシューベルトらしい柔らかさと勢いのある音楽だなと思った。
ただ、最初のうちはシューベルトだなとは思っても特にイタリア風とも思わなかったけれど曲の終盤になってだんだん音が活発に動くようになってきた段階でようやく 「そうかイタリアか」と思った。
ベートーヴェンの交響曲二曲は あちらこちらと目移りして聴くよりも見るのに必死という感じだったのでどんな演奏だったかよく覚えていない。
夢中で見ているうちに終わってしまった。
でも 夢中になれるということは要するに素晴らしかったということだと思う。
断片的に覚えていることだけを記していく。
どれが交響曲一番でどれが交響曲三番の印象かも記憶があやふやになっているので 二曲を聴いた印象として書こうと思う。
第一番の第一楽章冒頭で弦のピチカートがはじけて木管を中心に不協和な音が響いた時に、まあ すごいなあと思った。
第三楽章ももっぱらショルティさんやハイティンクさん(この人はショルティさんよりは速いけど)を聴いてきた僕には十分速いテンポに思えた。
そして、プログラムにはメヌエットと書いてあるけれどこれだけ高速で快活 かつ力に満ちているとやはりもはやメヌエットではないなと思った。
プログラムの楽曲解説にも書いてあるように実質はスケルツォだと。
第一楽章の冒頭 第三楽章を聴いただけでもうベートーヴェンは古典派の枠は超えてしまっているように僕には思える。(専門家ではないのであくまで一素人の感想だけど)。
それで頭に浮かんだのが名フィルのサイトに書いてあった次のような記述
「ベートーベン
ドイツの作曲家。ハイドン,モーツァルトと並びウィーン古典派三巨匠と呼ばれるベートーベンは、先人二人の完成させた古典派様式を至上の高みにまで洗練させ、独自の様式を築き上げ、晩年には来たるべきロマン派時代の萌芽を思わせる作風まで示している。
――世界大百科事典(平凡社)より――」と。
これを読んだとき いやあ ベートーヴェンはハイドン モーツァルトと並ぶ古典派三巨匠ではないだろうと思った。(個人の感想です)
一楽章の冒頭の入り方、そして 三楽章が実質もはやメヌエットではないことだけをとりあげても、もう交響曲第一番の段階で古典派の枠を超えてしまっている。
それを考えたときまだ20歳代の頃にある図書館でいろんな百科事典でベートーヴェンと言う項目を読み比べたときのことを思い出した。
確かに僕がそのときに読んだいくつかの百科事典には名フィルの方が引用された百科事典のように ハイドン モーツァルトと並ぶ古典派3巨匠もしくはそれと同じ主旨の書き方がなされていたように記憶している。(もう40年前の話だからこの記憶に自信はないけど)
その中である百科事典はベートーヴェンの項目が「ベートーヴェンは古典派かロマン派かと論ずるのはナンセンスである」というような書き方がしてあった。
それを読んだとき この百科事典いいなあと思った。
どの百科事典だったかはもう忘れてしまったけど。
僕の印象ではベートーヴェンは古典派がそこに流れ込み またロマン派がそこから流れ出していく大きな湖のような存在(琵琶湖よりももっと大きい大陸の湖をイメージ)という感じだ。
ちなみにちょっとウィキペディアを見てみたら
「その(ベートーヴェンの)作品は古典派音楽の集大成かつロマン派音楽の先駆とされ、後世の音楽家たちに多大な影響を与えた」と書かれている。
この書き方が僕の印象ではかなり適切な書き方のような気がする。
でも名フィルのサイトでウィキペディアより引用とするわけにもいかないだろうし。
古典派3巨匠の一角ととらえようが古典派の集大成かつロマン派先駆ととらえようがそれは認識のものさしというかグループ分けの違いなので 別にどちらが正しいという問題ではないのだけれど、、、。
それに名フィルが引用した平凡社百科事典にも「独自の様式を築き上げ」とあるので、その「独自の様式」がつまり古典派の集大成と考えて読めば、ウィキペディアの記述と平凡社百科事典の記述は大差ないことになる。
さて、家に帰ってきてコンサートで配布されたプログラムの解説を読んでみると
交響曲第一番の第一主題とモーツァルトの交響曲第41番の第一主題の類似性が指摘されている。
そうか と思って二つの主題を心の中で歌ってみると確かにモーツァルト41番の主題の一つ一つの音に重みを加える形でリズムを変化させると交響曲第一番の主題になる。
なるほどそうかと納得してしまった。
ベートーヴェン一番第二楽章冒頭と モーツァルト40番第二楽章の主題の類似性も指摘されているのでこれも心の中歌ってみると特に1+6=7つ目の音まではリズムも音の登っていき方もそっくり、いやあ これまで50年気づかなかったなあと思った。
でも それを言うなら交響曲第3番の第一楽章で最初チェロで出てくるドーミドーソの音形はモーツァルトの交響曲第39番第一楽章で木管と弦が中心になって主題を提示した直後にトランペットが高らかに奏でる音形とまったく同じだし(ちょっとリズムと言うか音の長さのバランスが違うけど)。同じ変ホ長調だし、、、。
要するに ベートーヴェンはモーツァルトの最後の3つの交響曲をとても意識していたということか。と思ってしまう。
ブラームスの交響曲第一番がベートーヴェンの第九に似ているテーマなどのためベートーヴェンの交響曲第10番と呼んだ人がいるのに似てるなと思った。
歴史は繰り返すということか? よくわからないけど、、、。
演奏は前に書いたようにむしろ見ることに夢中になっていたのでよく中身は覚えてないけど、指揮者がそれほど体幹の強いタイプの方でないような気がしたのと 僕の席から見るとコンサートマスターがスッとした感じで目立っておられたせいで、そこを中心に弦楽器の前で弾いている方々や管楽器の奏者が引っ張っているように僕には思えた。
それはそれで見ごたえがあってよかった。
ベートーヴェンは同じ音形が管楽器の中で弦楽器の中でそして管弦相互でリレーされていく場面が多いので見ていて本当に楽しい。
見晴らしのいい席だったし。
バイオリンなど高音域の弦がなだらかな音を奏でるのをバックにチェロなど低音域の楽器が力のこもった音を刻んで行ったりするのも見ていて楽しかった。
あと、この日は割と弦楽器に目が行ったおかげで木管と弦楽器との掛け合いの場面などではバイオリンは木管と音域が近くて本当に掛け合いをする上での呼応性が高いなと思った。
時にはコンサートマスターがソロで木管と掛け合っておられるのではないかと思ってしまった場面もあった。
ただ、僕はそこまで詳しくないので違っているかもしれないけれどベートーヴェンの交響曲で弦楽器のソロってそんなに出てこないと思うのできっと僕の錯覚と思う。
あとこれも交響曲一番 三番を通しての感想なのだけれど曲の要所ではオーボエがしみじみと響くことが多いなと思った。
特に交響曲第三番の第四楽章の中間地点くらいでオーボエがこれまで進んできた音楽を回想するかのように味わい深くテーマをゆっくりと奏でるところが好き。あそこは音楽がフィニッシュに向かって盛り上がっていくのろしの役割も果たしているし、ベートーヴェンの慎重さ、周到さがよく感じられる箇所だし、、、。
きっとベートーヴェンは木管の中心はオーボエという感覚の人なんだろうと想像してしまった。
こういうのも家でCDラジカセで聴いていてもなかなか気づかないことなのでやはりコンサートにはいくべきだなと思う。
音を力強く刻むところで 短いとまでは言えなくても 少なくとも無駄に音を伸ばさないということが意識されてるな思う場面が特に弦楽器においてあって、それもなんだか聴いていて心地よかった。
いい演奏会でよかったなと思った。
気分がよくなった勢いでコンサートホールを出て名古屋でもちょっとディープな街の裏通りの方に行ってみたけど やはり金曜の夜は男でも一人だと怖い。
表通りに引き返して台湾か中国の人が営んでいる感じの中華料理店で食事して帰った。
それはともかく いちにち いちにち 無事に過ごせますように。