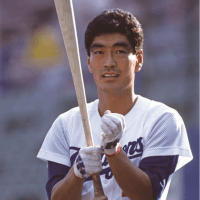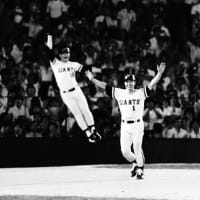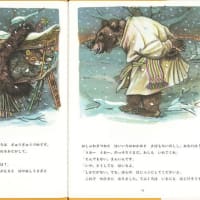5月16日名古屋フィルハーモニー第534回定期演奏会を聴きに行く。
指揮はジャン クロード カサドシュさん
最初にガーシュインのピアノ協奏曲へ調が演奏された。
ピアノ独奏 トーマス エンコさん。
3月の定期演奏会でガーシュインが演奏されたときは、僕の印象はジャズかクラシックか範疇のよくわからない音楽という感じだった。
この日の演奏は僕の印象だとジャズの要素が多分にあるクラシックと言う感じだった。
要するにガーシュインの音楽って演奏の仕方によってジャズの方にバイアスがかかったりクラシックの方にバイアスがかかったりということなのだと思う。
そして僕にとってはこの日のようにジャズの要素のあるクラシックという感じの演奏の方が安心して聴けるという思いはある。
やはり、クラシックを聴いてきた時間がながいから。
演奏で印象に残ったことは例えば大きな音が来ると予想されるようなところで意外と大きな音が来なかったということ。
力まないように注意することが演奏のなかで一つの大きな要素だったように思う。
たぶん力まないということに注意をはらっているんだろうなと思って指揮者に注目すると大きい音をオーケストラに要求するときは力強い動きと言うよりもむしろスッと流れるような素早い動きという感じだった。
この素早い動きが少し力を抜くことにつながっているような気がした。
ジャズの要素のあるクラシックなので演奏中もちろんラヴェルのことは心に浮かんだけれど音楽がドラマチックになるようなところではむしろラフマニノフが心に浮かんでくることが多かった。
ピアノの旋律に一瞬ラフマニノフのものがあったような気がするのだけれど そんなに知らない曲だし一瞬のことなので勘違いかもしれない。
ピアノも素早い音を出すときに正確で強いのだけれど軽々と弾いているように思えることが何度もありちょっとすごいなと思った。
ピアノの素早いリズムが同じテンションを保ちながら木管などにリレーされていくさまはちょっといい感じだった。
ピアノ独奏のトーマス エンコさんが即興をやりますと言ってアンコールを弾き始められた。
本当に即興と言う感じの演奏だったけれど途中、かなり強くバッハを感じる場面が何度かあった。
あとベートーヴェンを感じる場面もバッハほどではないけれどあった。
家に帰ってきてプログラムを見るとトーマス エンコさんはBACH MIRRORというCDを出しておられるとのことで、きっとそういうことなのかなと想像した。
想像なのでCDの中身のことは僕には全く分かりません。ごめんなさい。
20分の休憩をはさんで次にベルリーズの幻想交響曲作品14が演奏された。
この演奏も柔らかい感じで音が大きい所でもマックスまでいくのではなくちょっと余力があるという感じがなんともいいなと思いながら聴いていた。
テンポを上げて盛り上げることが可能な楽曲展開でもむしろテンポを落とすような場面も何度かあって、そのテンポ設定が優雅な演奏の展開に寄与していたと思う。
プログラムの楽曲解説にも1830年つまりベートーヴェンが亡くなってわずか3年しかたっていないのに革新的な曲という主旨のことが書いてある。
僕も作品が書かれた時代と言うことを考えると本当に素晴らしい音楽だなと思う。
例えば管楽器はもう後期ロマン派を思い浮かべることができるほどにステージいっぱいに並んでいる。
弦楽器もチェロ コントラバスなど低い弦楽器から バイオリン ビオラなど比較的高い弦楽器までまんべんなく活躍するという感じだ。
なので、弦楽器の見せ場では目が右から左、左から右へと首振り扇風機のように移動してしまった。
第二楽章の美しいメロディを聴いた時には本当に幻想交響曲という名前がぴったりというほどファンタジックだなと思った。
家でCDを聴くときはしばしば第三楽章はスキップしてしまう僕だけどコンサートで聴くと管楽器のかけあい、楽章後半の盛り上がりなどCDでは味わえない音楽の要素をいろいろ味わうことができてよかった。
音の出どころを目で追ってしまう癖のある僕だけれどこの第三楽章でオーボエと他の木管が掛け合いをしているときもう一つの楽器の音はどこから出ているのかついにわからずに終わってしまった。
マーラーの交響曲などのようにステージの袖奥で音を出している可能性も十分にあると思った。
4楽章 5楽章はかなり気分がハイな状態で聴いていたのでどんな演奏展開だったかもう忘れてしまったけれどいい演奏だった。
第五楽章の鐘の音もどこからでているのか最後までわからなかった。一瞬天井のスピーカーから音が出ているのかとスピーカーに注目したけれどどうもそうではないみたいだった。
ただ、感じとしては録音された音とも思えなかったのでこれもステージから見えないところで音を出していたのかもしれない。
でも あの鐘の音ってステージの上でトンカチみたいなものでたたくのを見ると一気に幻想の世界から現実世界に戻ってしまったようで興ざめと言うことが僕が過去に行ったコンサートでもしばしばあった。
なので、見えないところで音を出していたのはイメージ戦略というか聴き手の想像力を駆り立てるという意味では正解だったと思う。
僕の感想としては今までに生演奏で聴いた幻想交響曲の中では最も夢中になって聴ける演奏だったと思う。
それはともかく 一日 いちにち無事にすごせますように、それを第一に願っていきたい。