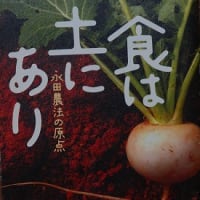農作業の合間に道草をやるのが習慣となっている。へたすると、道草のほうが長いことさえある。そんな近所の道草をやっている途中に、4mくらいの石垣の途中になにやら「ど根性雑草」が花を咲かせていた。

近づいてみると、それは「ハハコグサ」(キク科)だった。この群落の横の並びには小さな排水口がいくつかあった。そこから芽が出たというわけだが、ここだけなぜハハコグサ一家が進出したかが不可解だ。さすが、雑草軍団の生命力の面目躍如というところだ。
ハハコグサは、「春の七草」(セリ、ナズナ、ハコベ、スズナ=カブ、スズシロ=ダイコン、ホトケノザ=コオニタピラコ、ゴギョウ=ハハコグサ)として有力な食べ物だった。冬に不足がちな栄養素を取り入れるため古来から食べられていたが、中国の節句が導入、コラボされ、以来、「七草粥」として定着する。

いっぽう、ハハコグサはかつて「草餅」の主流だった。お餅のつなぎとしてその細かな毛が活かされて「母子餅」として3月の節句には欠かせない食べ物となった。しかし、母と子とをすりつぶす餅は縁起が悪いとされ、江戸から明治にかけて香りと色の鮮やかな「ヨモギ」の草餅に代わっていったらしい。

道草の帰りにわが家の境界を歩いたとき、ハハコグサの群落が一斉に花咲いていたのを偶然にも発見する。群落となるとなかなか壮観でもあった。
ハハコグサが「ゴギョウ」(御形)と言われるがその理由がよくわからなかった。本来は紙で作った「人型」に自分の罪を移してから川に流して穢れをはらうのだが、当時の「紙」は高価なものだった。その代わりとして、薬効と食材で身近なハハコグサが選ばれたというわけだ。ハハコグサを身体に撫でかけて罪を移し川に流して穢れをはらったという。庶民にとってハハコグサは身近な素材だったが、改めてハハコグサをリスペクトしたい気持ちになった。