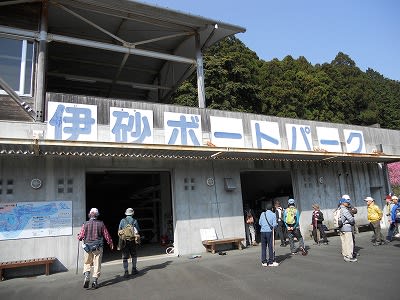ついさっきまで雨だった。
かつては銅山採鉱で繁栄していた天竜区龍山町を歩く。
つり橋の「峰の澤橋」を揺れながら渡ってみる。

天竜川は周囲の秋の山々を映し出す湖面となっていた。
案内は森林コーディネーターの新人4期生でこの辺の出身者がすべてを行う。
川向かいの国道は紅葉詣でで車の往来が頻繁だったが、反対側のここの裏街道は車があまり通らない。

道路の利用者は旧「峰の澤銅山」周辺に住む一部住民だけだという。
ハンターに出会った。
シカを追って川までシカを追い詰めたそうだが、逃げられたという。
ときには熊も出没することもあるという。

この時期で目立つ赤い実は、「ガマズミ」をはじめ、フユイチゴ・サネカズラ・ノイバラ・ナンテンも確認した。
以前この道は雑草や落石も多くて通行したくない道路であったが、今はきれいに整備されていた。
雨天模様で「散策会」参加者は十数名だったが案内人による地元情報がどんどん出てくる収穫があった。

さらには、雨を考慮してルート資料をビニールシートに入れて配布してくれた。
「スズメウリ」も散策会で初めて出会う。
きょうは雨プロで急遽歩くルートをここに変更したが、このように意外な見どころがあるのも発見だった。
この裏街道は日陰気味だったこともあってシダやコケが豊富で、石垣がびっしりそれで覆われた自然レイアウトが素晴らしい。


往来が少ないことも植物が豊富になった理由でもある。
忘れられた世界に貴重な輝きがある。
誰かが仕組んだバーチャルな消費世界にメディアも加担してしまっている。
そんな情報に洗脳された大衆は列を組んで群がってしまう。
やはり、自分の足元の宝を発見する視座を磨くのが大切だ。
そんなとき、ささやかな「森林散策会」の世界は貴重な場ではないかと、あらためて痛感する。
かつては銅山採鉱で繁栄していた天竜区龍山町を歩く。
つり橋の「峰の澤橋」を揺れながら渡ってみる。

天竜川は周囲の秋の山々を映し出す湖面となっていた。
案内は森林コーディネーターの新人4期生でこの辺の出身者がすべてを行う。
川向かいの国道は紅葉詣でで車の往来が頻繁だったが、反対側のここの裏街道は車があまり通らない。

道路の利用者は旧「峰の澤銅山」周辺に住む一部住民だけだという。
ハンターに出会った。
シカを追って川までシカを追い詰めたそうだが、逃げられたという。
ときには熊も出没することもあるという。

この時期で目立つ赤い実は、「ガマズミ」をはじめ、フユイチゴ・サネカズラ・ノイバラ・ナンテンも確認した。
以前この道は雑草や落石も多くて通行したくない道路であったが、今はきれいに整備されていた。
雨天模様で「散策会」参加者は十数名だったが案内人による地元情報がどんどん出てくる収穫があった。

さらには、雨を考慮してルート資料をビニールシートに入れて配布してくれた。
「スズメウリ」も散策会で初めて出会う。
きょうは雨プロで急遽歩くルートをここに変更したが、このように意外な見どころがあるのも発見だった。
この裏街道は日陰気味だったこともあってシダやコケが豊富で、石垣がびっしりそれで覆われた自然レイアウトが素晴らしい。


往来が少ないことも植物が豊富になった理由でもある。
忘れられた世界に貴重な輝きがある。
誰かが仕組んだバーチャルな消費世界にメディアも加担してしまっている。
そんな情報に洗脳された大衆は列を組んで群がってしまう。
やはり、自分の足元の宝を発見する視座を磨くのが大切だ。
そんなとき、ささやかな「森林散策会」の世界は貴重な場ではないかと、あらためて痛感する。