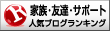ヨハネ14章
今日の朝は、この章を読んだ。
この章を読みながら、神様が非常に身近な方であることを覚えた。
確かに私自身直接神様を見たことはないし、夢や幻でも神様に会うという経験をしたことがない。
しかし、聖書の言葉が真実であるならば(という控えめな言い方をあえてするけれど)、本当に神様は私たちの身近な存在であると言える。
表現を変えれば、私たちは神様の大きな存在の中に入れられていると言った方が適切だろう。
また、神様が三位一体のお方であることは、より一層私たちに近い存在であることを意識させてくれる。
■ 御父と御子と御霊、そして私たちの一体性
16節
「わたし(御子)は父にお願いします。そうすれば、父はもうひとりの助け主(御霊)をあなたがたにお与えになります。その助け主がいつまでもあなたがたと、ともにおられるためにです。」
18節
「わたし(御子)は、あなたがたを捨てて孤児にはしません。わたしは、あなたがたのところに戻って来るのです。」
20節
「その日には、わたし(御子)が父におり、あなたがたがわたしにおり、わたしがあなたがたにおることが、あなたがたにわかります。」
23節
「だれでもわたし(御子)を愛する人は、わたしのことばを守ります。そうすれば、わたしの父はその人を愛し、わたしたちはその人のところに来て、その人とともに住みます。」
くり返して「神様は私たちと共にいてくださる方」というメッセージが示されている。
私たちは孤独ではない。
神様は私たちと共にいてくださる。
父なる神様、イエス様、聖霊様、感謝します。ハレルヤ!
今日の朝は、この章を読んだ。
この章を読みながら、神様が非常に身近な方であることを覚えた。
確かに私自身直接神様を見たことはないし、夢や幻でも神様に会うという経験をしたことがない。
しかし、聖書の言葉が真実であるならば(という控えめな言い方をあえてするけれど)、本当に神様は私たちの身近な存在であると言える。
表現を変えれば、私たちは神様の大きな存在の中に入れられていると言った方が適切だろう。
また、神様が三位一体のお方であることは、より一層私たちに近い存在であることを意識させてくれる。
■ 御父と御子と御霊、そして私たちの一体性
16節
「わたし(御子)は父にお願いします。そうすれば、父はもうひとりの助け主(御霊)をあなたがたにお与えになります。その助け主がいつまでもあなたがたと、ともにおられるためにです。」
18節
「わたし(御子)は、あなたがたを捨てて孤児にはしません。わたしは、あなたがたのところに戻って来るのです。」
20節
「その日には、わたし(御子)が父におり、あなたがたがわたしにおり、わたしがあなたがたにおることが、あなたがたにわかります。」
23節
「だれでもわたし(御子)を愛する人は、わたしのことばを守ります。そうすれば、わたしの父はその人を愛し、わたしたちはその人のところに来て、その人とともに住みます。」
くり返して「神様は私たちと共にいてくださる方」というメッセージが示されている。
私たちは孤独ではない。
神様は私たちと共にいてくださる。
父なる神様、イエス様、聖霊様、感謝します。ハレルヤ!
今日の午前中、教会にパーテーションが届いた。
教会の一角に置いて、掲示板代わりに使おうと考えた。
しばらく前から構想はあったのだが、ようやく購入に踏み切った。
前にKさんといっしょにリサイクルショップに行ってみたが、ちょうど良いものが見つからなかったので、アスクルで取り寄せた。

組み立ては簡単で、一人ですぐにできた。
早速、当初考えていた位置に置いてみた。
そして、8月に行なわれたタイ・ベトナムの伝道旅行の様子を伝える写真を貼った。
このパーテーションは、主にアジアでの伝道に関する情報提供に使おうと考えている。
この写真の中にある大きな扇子は、W先生の教会へのベトナムのお土産。
せっかく写真を撮るので、ついでに入れてみた。
教会の皆さんにアジアの諸国の教会やその活動に少しでも関心を持ってもらえるとうれしい。
一番下の段は、マガジンラックのようになっているので、貸し出し用のお薦めの本を入れて置くようにしたいと考えている。
教会の一角に置いて、掲示板代わりに使おうと考えた。
しばらく前から構想はあったのだが、ようやく購入に踏み切った。
前にKさんといっしょにリサイクルショップに行ってみたが、ちょうど良いものが見つからなかったので、アスクルで取り寄せた。

組み立ては簡単で、一人ですぐにできた。
早速、当初考えていた位置に置いてみた。
そして、8月に行なわれたタイ・ベトナムの伝道旅行の様子を伝える写真を貼った。
このパーテーションは、主にアジアでの伝道に関する情報提供に使おうと考えている。
この写真の中にある大きな扇子は、W先生の教会へのベトナムのお土産。
せっかく写真を撮るので、ついでに入れてみた。
教会の皆さんにアジアの諸国の教会やその活動に少しでも関心を持ってもらえるとうれしい。
一番下の段は、マガジンラックのようになっているので、貸し出し用のお薦めの本を入れて置くようにしたいと考えている。
昨日、実家の母から手紙が届いた。
家族の近況報告とともに、実家に送られてきた同窓会の案内が入っていた。
南部中学の同窓会。
10月8日の午後・・・無理かな。残念。
ホテル日航で行なうとのこと。
久しぶりに中学時代の友達に会ってみたいという気にはなったが、日程的に無理っぽい。
ちょうどこの日、福岡小学校では21世紀へのメッセージということで埋めておいた作文が開けられることになっているそうだ。
小学生の頃の自分が何を書いたのかもう忘れてしまったので、見てみたい気がする。
もうてっきり終わってしまって、処分されているかも、と思い込んでいたので、もしや手に入るのではと期待している。
豊橋市の市制100周年にちなんだイベントなのだが、ちょうどその年に豊橋にいないのは、なんとも間の悪い話。
家族の近況報告とともに、実家に送られてきた同窓会の案内が入っていた。
南部中学の同窓会。
10月8日の午後・・・無理かな。残念。
ホテル日航で行なうとのこと。
久しぶりに中学時代の友達に会ってみたいという気にはなったが、日程的に無理っぽい。
ちょうどこの日、福岡小学校では21世紀へのメッセージということで埋めておいた作文が開けられることになっているそうだ。
小学生の頃の自分が何を書いたのかもう忘れてしまったので、見てみたい気がする。
もうてっきり終わってしまって、処分されているかも、と思い込んでいたので、もしや手に入るのではと期待している。
豊橋市の市制100周年にちなんだイベントなのだが、ちょうどその年に豊橋にいないのは、なんとも間の悪い話。
ヨハネ 13:12-14
「イエスは、彼ら(十二弟子たち)の足を洗い終わり、上着を着けて、再び席に着いて、彼らに言われた。
『わたしがあなたがたに何をしたか、わかりますか。あなたがたはわたしを先生とも主とも呼んでいます。あなたがたがそう言うのはよい。わたしはそのような者だからです。それで、主であり師であるわたしが、あなたがたの足を洗ったのですから、あなたがたもまた互いに足を洗い合うべきです。』」
イエス様は十字架の死を迎える前夜、弟子たちの足を洗われた。
この時代の、この地域の文化を知らないと、足を洗うことの意味は分かりにくい。
当時、足を洗うのは奴隷の仕事だった。
だから、この場所で、イエス様がした行為は、弟子たちには奇妙に思われたに違いない。
単に師であるばかりではない、神の御子であられるお方が、なぜ弟子の足を洗われたのか、その時の弟子たちには理解できなかっただろう。
かつて、アメリカからいらっしゃったある講師が「Jesus Style」というテーマで話してくださったことを今でも覚えている。
すでに10年以上前のことだが、インパクトが強かったので忘れることができない。
イエス様のライフスタイルをいくつかのポイントにまとめて説明してくださった。
その時のメインのポイントが、「servant:しもべ」だった。
神であるお方が人として来てどんな生き方をしたか?
それは、しもべとして仕える、というものだった。
最初にあげた聖書箇所は、それを象徴するような出来事である。
そして、先の言葉に続いてイエス様はこのように言われた。
「『・・・あなたがたがこれらのことを知っているのなら、それを行うときに、あなたがたは祝福されるのです。』」(ヨハネ13:17)
イエス様が私に期待し、求めておられる生き方は、しもべとして仕えること。
教会行事として、この聖書箇所にちなんだ「洗足式」というものがあり、そ
の時には確かに私は教会員の方々の足を洗う。
しかし、本当に大事なのは、普段どれだけ尽くしているのかということだと思った。
私が働くようにと与えられた環境の中で、いかに他者に仕えていくかが問われていると感じた。
聖書を教えることにより、また教会の環境を整えることにより、また時間を割いて教会に集まる方々のために祈ることにより、仕えていきたい。
また私が話を聞くことで何かお役に立てるのであれば、いっしょにいて話を聞くようにしたい。
また神学校で勉強させて頂いているのも、自分の成長のためでありつつ、また周囲の方々のためでもあるということを忘れないようにしたい。
Jesus Styleに生きたい。
「イエスは、彼ら(十二弟子たち)の足を洗い終わり、上着を着けて、再び席に着いて、彼らに言われた。
『わたしがあなたがたに何をしたか、わかりますか。あなたがたはわたしを先生とも主とも呼んでいます。あなたがたがそう言うのはよい。わたしはそのような者だからです。それで、主であり師であるわたしが、あなたがたの足を洗ったのですから、あなたがたもまた互いに足を洗い合うべきです。』」
イエス様は十字架の死を迎える前夜、弟子たちの足を洗われた。
この時代の、この地域の文化を知らないと、足を洗うことの意味は分かりにくい。
当時、足を洗うのは奴隷の仕事だった。
だから、この場所で、イエス様がした行為は、弟子たちには奇妙に思われたに違いない。
単に師であるばかりではない、神の御子であられるお方が、なぜ弟子の足を洗われたのか、その時の弟子たちには理解できなかっただろう。
かつて、アメリカからいらっしゃったある講師が「Jesus Style」というテーマで話してくださったことを今でも覚えている。
すでに10年以上前のことだが、インパクトが強かったので忘れることができない。
イエス様のライフスタイルをいくつかのポイントにまとめて説明してくださった。
その時のメインのポイントが、「servant:しもべ」だった。
神であるお方が人として来てどんな生き方をしたか?
それは、しもべとして仕える、というものだった。
最初にあげた聖書箇所は、それを象徴するような出来事である。
そして、先の言葉に続いてイエス様はこのように言われた。
「『・・・あなたがたがこれらのことを知っているのなら、それを行うときに、あなたがたは祝福されるのです。』」(ヨハネ13:17)
イエス様が私に期待し、求めておられる生き方は、しもべとして仕えること。
教会行事として、この聖書箇所にちなんだ「洗足式」というものがあり、そ
の時には確かに私は教会員の方々の足を洗う。
しかし、本当に大事なのは、普段どれだけ尽くしているのかということだと思った。
私が働くようにと与えられた環境の中で、いかに他者に仕えていくかが問われていると感じた。
聖書を教えることにより、また教会の環境を整えることにより、また時間を割いて教会に集まる方々のために祈ることにより、仕えていきたい。
また私が話を聞くことで何かお役に立てるのであれば、いっしょにいて話を聞くようにしたい。
また神学校で勉強させて頂いているのも、自分の成長のためでありつつ、また周囲の方々のためでもあるということを忘れないようにしたい。
Jesus Styleに生きたい。