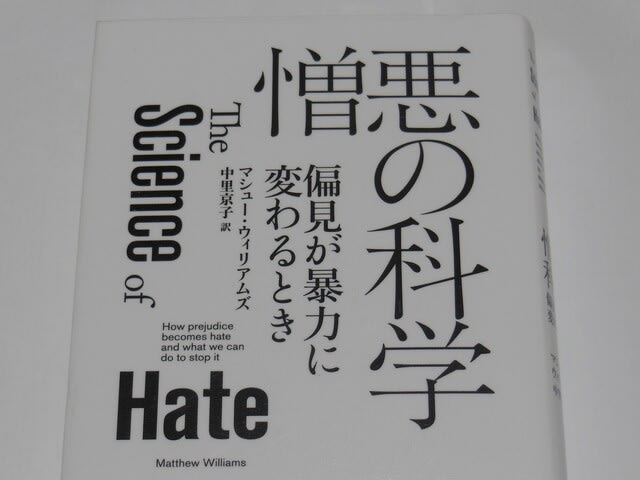人が人種・民族、性的嗜好(LGBTQ+)等によるヘイトクライムを犯すに至る原因について考察した本。
前半では脳スキャン等の実験や知見を紹介し脅威の認識や憎悪と脳の働き(活性化する部分等)を論じ、脳科学的な解説がなされていますが、これに関しては脳スキャンでわかるのは特定の部位の血流の増加であってそれが脳の具体的な働きや感情とどう結びついているのか等の評価判断には慎重であるべきという意見が研究者からなされ、著者も疑問を投げかけています(141ページ)。各種の心理学系の実験研究が紹介されていますが、その実験結果の解釈には検討の余地がありそうに思える点もあり、なによりも著者自身が度々、だからといって同様の状況に置かれた者が皆ヘイトクライムを犯すわけではないと指摘し、何が偏見を憎悪に変えヘイトクライムを犯すに至るのかが問題提起されます。憎悪を促進するものとして、価値観への脅威やトリガーとなる事件、宗教や過激な思想等が挙げられていますが、結局のところ偏見が憎悪に、暴力に変わる原因や、ティッピングポイント(大きな変化が一気に生じる転換点:350ページ)といった著者が提起した興味あるポイントを説明できているように感じられません。著者自身が最後の章で研究の限界について縷々述べているところです(353~359ページ)。実験研究の紹介と並行して、実際の事件について加害者の経歴や事件に至る経緯を多数紹介していて、読みでがありますが、そこは「科学」というよりはジャーナリズムの文章で、まさにそういう事例があったことは事実でも同じ境遇に置かれた他の人がヘイトクライムを犯すとは限らないものです。
ヘイトクライムの実例について多くのケースを知るという点では収穫がありましたが、タイトルから憎悪についての科学的な解明や、偏見が憎悪や暴力にエスカレートする原因や機構・機序の理解を期待すると、分厚い本を長時間かけて読んだ結果、今ひとつ釈然としない気持ちで終わると思います。
刑事裁判で5人の精神医から統合失調症と診断された被告人に対して、ノンフィクション作家が孤独な女性と偽って文通し「医者を騙した」と告白させ、その手紙が裁判の証拠とされて心神喪失が否定されて終身刑となったというケースが紹介されています(212~214ページ)。著者はそれに否定的な評価はまったくしていませんが、ずいぶんと野蛮なやり方がまかり通っているのだなと思います。
冒頭に、著者がジャーナリストを志して大学院入学を決めていたが犯罪学へと進路を変えることにつながった事件として、ゲイバーから出たところで3人の男に襲われて殴られ同性愛を詰られた経験を書いています(9~11ページ)。ここで著者は加害者の属性について3人の男であること以外は記載していません。私は、この本の趣旨、同性愛を理由に言いがかりをつけてきたことから考えるまでもなく襲撃者は白人だと受け止めました。著者はこの襲撃者について第4章に至って初めて黒人であったことを明らかにします(121ページ等)。しかし、その場面でも著者はそれまで襲撃者の人種を明らかにしなかった理由はまったく説明しませんので、あえて隠したとか読者を試そうという意識ではないようです。著者にとって、路上でいきなり言いがかりをつけて殴る人物は説明しなくても黒人ということなんでしょうか。あるいは私が、悪者は白人だという偏見を持っているということでしょうか。ちょっと悩んでしまいました。

原題:The Science of Hate : How prejudice becomes hate and what we can do to stop it
マシュー・ウィリアムズ 訳:中里京子
河出書房新社 2023年3月30日発行(原書は2021年)
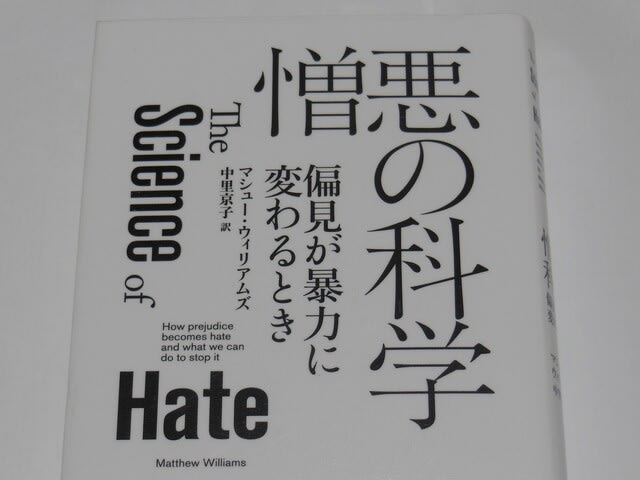
前半では脳スキャン等の実験や知見を紹介し脅威の認識や憎悪と脳の働き(活性化する部分等)を論じ、脳科学的な解説がなされていますが、これに関しては脳スキャンでわかるのは特定の部位の血流の増加であってそれが脳の具体的な働きや感情とどう結びついているのか等の評価判断には慎重であるべきという意見が研究者からなされ、著者も疑問を投げかけています(141ページ)。各種の心理学系の実験研究が紹介されていますが、その実験結果の解釈には検討の余地がありそうに思える点もあり、なによりも著者自身が度々、だからといって同様の状況に置かれた者が皆ヘイトクライムを犯すわけではないと指摘し、何が偏見を憎悪に変えヘイトクライムを犯すに至るのかが問題提起されます。憎悪を促進するものとして、価値観への脅威やトリガーとなる事件、宗教や過激な思想等が挙げられていますが、結局のところ偏見が憎悪に、暴力に変わる原因や、ティッピングポイント(大きな変化が一気に生じる転換点:350ページ)といった著者が提起した興味あるポイントを説明できているように感じられません。著者自身が最後の章で研究の限界について縷々述べているところです(353~359ページ)。実験研究の紹介と並行して、実際の事件について加害者の経歴や事件に至る経緯を多数紹介していて、読みでがありますが、そこは「科学」というよりはジャーナリズムの文章で、まさにそういう事例があったことは事実でも同じ境遇に置かれた他の人がヘイトクライムを犯すとは限らないものです。
ヘイトクライムの実例について多くのケースを知るという点では収穫がありましたが、タイトルから憎悪についての科学的な解明や、偏見が憎悪や暴力にエスカレートする原因や機構・機序の理解を期待すると、分厚い本を長時間かけて読んだ結果、今ひとつ釈然としない気持ちで終わると思います。
刑事裁判で5人の精神医から統合失調症と診断された被告人に対して、ノンフィクション作家が孤独な女性と偽って文通し「医者を騙した」と告白させ、その手紙が裁判の証拠とされて心神喪失が否定されて終身刑となったというケースが紹介されています(212~214ページ)。著者はそれに否定的な評価はまったくしていませんが、ずいぶんと野蛮なやり方がまかり通っているのだなと思います。
冒頭に、著者がジャーナリストを志して大学院入学を決めていたが犯罪学へと進路を変えることにつながった事件として、ゲイバーから出たところで3人の男に襲われて殴られ同性愛を詰られた経験を書いています(9~11ページ)。ここで著者は加害者の属性について3人の男であること以外は記載していません。私は、この本の趣旨、同性愛を理由に言いがかりをつけてきたことから考えるまでもなく襲撃者は白人だと受け止めました。著者はこの襲撃者について第4章に至って初めて黒人であったことを明らかにします(121ページ等)。しかし、その場面でも著者はそれまで襲撃者の人種を明らかにしなかった理由はまったく説明しませんので、あえて隠したとか読者を試そうという意識ではないようです。著者にとって、路上でいきなり言いがかりをつけて殴る人物は説明しなくても黒人ということなんでしょうか。あるいは私が、悪者は白人だという偏見を持っているということでしょうか。ちょっと悩んでしまいました。

原題:The Science of Hate : How prejudice becomes hate and what we can do to stop it
マシュー・ウィリアムズ 訳:中里京子
河出書房新社 2023年3月30日発行(原書は2021年)