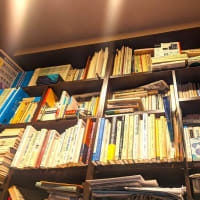なぜ自分は存在しているのか?
自分が存在していることの意味はなにか?
存在していることの根拠はなにか?
なぜ自分が存在していることを問題にするのか?
…
こういった疑問を持っている人は、是非マルティン・ハイデッガーに触れてみてほしいと思います。
コロナ禍で「何もすることがない!」「オンライン授業があーだこーだ」と言っている時間があったら、ハイデッガーの『存在と時間』を全部読み切っちゃってほしいですね。
で、本来的な大学生なら、その読み切った存在と時間を、英語、ドイツ語、フランス語等で再度読んでほしいですね。そのためには、外国語もしっかり学んでほしいですね。(むっちゃハードル高いですけど…)
僕もまた、この存在と時間を原文で読みたくて、ドイツ語を始めた人間の一人です。
もちろん、「なぜ僕が存在しているんだろう?」「なんのために生まれてきたのだろう?」ということを、LUNA SEAの歌から刺激されて、考えるようになり、突き詰めていった結果、ハイデッガーにぶち当たりました。
以下の文章もまた、ドイツの大学生向けのわかりやすい教科書の文章です。もちろん「わかりやすい」というのは、ドイツで勤勉な学生にとっての「わかりやすい」であって、日本の大学生には、(言語の違いもあって)ちんぷんかんぷんだと思います。
でも、コロナ禍で大学での学びが危うい中、ハイデッガーに触れ、存在と時間の世界に入り込み、「存在とは何か」について考えてみるっていうのも、悪くないと思います。
大学生って、本来、こういう本を読んで、あーだこーだと一人で考え込む時間を過ごす存在だったんじゃないかな、と。
こういう時期だからこそ、平均的な存在者であるDas Man(ダスマン)の世界を離れて、このハイデッガーの世界に入り込むのもいいんじゃないかなって思います💛
存在の意味-マルティン・ハイデッガー
バーデン州のメスキルヒ出身のマルティン・ハイデッガーは、1909年から1913年にかけて、ブライスガウのフライブルクで、哲学とカトリック神学を学んだ。1907年には既に、フランツ・ブレンターノの学位論文「アリストテレスにおける存在者の多様な意味について」(1862)を読んでいた。学生時代にハイデッガーに影響を与えたのが、彼の教理神学の教師だったカール・ブライヒの「存在について」という著作と、フッサールの「論理学研究」であった。ハイデッガーは、1913年、「心理学主義の判断についての学」で学位を取得した。彼の教授資格論文で、彼は「ドゥンス・スコトゥスのカテゴリー論と意味論」(1915年)を研究し、その教授資格論文のレクチャーでは、「歴史科学における時間概念」が取り上げられた。ハイデッガーは、さらにより徹底的に、超越論的哲学と生まれつつある現象学の基盤を反省するようになる。とりわけ世界(Welt)と生(Leben)という基本概念を反省するようになる。
ハイデッガーは、1920年、フッサールのアシスタントとなり、1923年にマールブルクの教授となる。最も活発で創造的だったこのマールブルク時代、神学者のルドルフ・ブルトマンとの協働に特徴づけられながら、ハンス-ゲオルク・ガダマー、カール・レーヴィット、ハンナ・アーレント、ハンス・ヨナスらが、ハイデッガーの下で学び、彼の卓越した存在論と解釈学の講義を聴いていた。それと並行して、ハイデッガーは、20世紀の主著の一つとなった「存在と時間」を書き上げた。この「存在と時間」は、1927年、「哲学と現象学研究のためのフッサール年報」に掲載され、この年報(そしてフッサール)に捧げられた。この時代にハイデッガーの助手だったガダマーは、「すぐさま、世界的な評判となった」、と語っている。ガダマーはまた、自分の師(=ハイデッガー)がいかにして、シュヴァルツヴァルトの自分の山小屋でしばしば深夜になるまでこの書物を書いていたかについても報告している。1928年、ハイデッガーは、フッサールの後継者としてフライブルクに招聘された(就任講演は「形而上学とは何か」、1929年)。ハイデッガーは、「存在と時間」に関連して、カントの超越論的哲学(先験的哲学)との批判的-再構成的な対決を深化させていった(「カントと形而上学の問題」、1929年)。それに次いで、ダボス(スイス)にて、新カント派のエルンスト・カッシーラとの有名な論争(ダボス討論)が行われた(*感性悟性二元論VS感性的理性一元論)。
ハイデッガーは、1933年、フライブルク大学の学長になる。彼は、「ドイツの大学の自己主張」という講演を行った。この講演で、彼は、学生たちに対して、「勤労奉仕」「国防奉仕」「知的奉仕」での活動を要請する。ハイデッガーは既にNSDAPに入党していた。彼の(ナチ党への)参加を理由に、ハイデッガーの教育活動は、1945年から1951年までの間、禁じられた。その間、ナチス時代の彼の諸活動を見ると、ある区分された(特殊な)見方が可能である。ハイデッガーは当初、ドイツのポジティブな発展の希望をナチズムと結びつけたが、その後、1944年まで、彼は自分の講義や研究を、ドイツの理想主義、ヘルダーリン、ニーチェへの強烈な論究に捧げていた。これらの論究は、ナチスのイデオロギーから批判的に距離を取ることとして理解することができる。1952年、ハイデッガーは、定年退職後、何度も、注目を集める講演や主催ゼミナールを行った。彼の思索の晩年は、これまでの哲学からの決別によって特徴づけられる。それを彼は、「ケーレ(転回)」と呼び、正確には、非常に早くから既にその決別の兆しはあった。彼の要望で彼の死後に公開されたが、1966年の「シュピーゲル」の企画インタビューでは、「神だけがただわれわれを救うことができる(Nur noch ein Gott kann uns retten)」という彼のラディカルで批判的な後期哲学を特徴づけるタイトルが掲げられた。
『存在と時間』は、何ゆえに突出した作品となったのか。ハイデッガーは、二つのラディカルな根源的な問いを打ち立てている。その一つが、存在の意味への問い-存在の意味の問い(Seinssinnfrage)である。この問いは、これまでの哲学の彼の解釈によれば、古代の哲学の起源以降、立てられていなかった、もしくは、間違って立てられてきた、あるいは、答えてこなかった、あるいは間違って答えられてきた問いである。続く二つ目の問いは、存在の根拠(起源)への問い(Seinsgrundfrage)である。すなわち、そもそもなぜ何ものかが在り、無ではないのか、という問いである。これは、ライプニッツやシェリングが打ち立てつつも、これまで一つの答えも出てこなかった問いである。この問いに直面したハイデッガーは、『存在と時間』の中で、伝統的な事物的存在論(Substanzontologie)の根本的な批判を行っている。彼は、イノベーティブな仕方で、真理問題を提示し、様式概念である事実性と可能性(アリストテレスの現実態=energeiaと可能態=dynamis)の古典的な分析を、人間の現存在分析の文脈の中に入れ込み、人間の実存へのまなざしの中で、古典的なカテゴリー論を変形させた。それに加えて言えば、『存在と時間』の中で、これまでのハイデッガーの研究のあらゆる方法と主題が凝縮され、新たに捉え返されている。とりわけ、分析の過程で変形され、新たに結合された五つの主要な層に区分することができよう。すなわち、第一に、プラトンとアリストテレスに代表される伝統的な「存在論」ならびに「形而上学」の層、第二に、カントと関連する「超越論的哲学(批判哲学)」の層、第三に、フッサールと関連する「現象学」の層、第四に、ジンメルとディルタイによって打ち立てられた「生の哲学と解釈学」の層、そして最後の第五に、パウロとキルケゴールに強い影響を受けている「実存的・宗教的ならびに神学的」な層である。
無論、これらの層はただ便宜的に、あとづけ的に区分できるだけに過ぎないが、これらの層を用いて、ハイデッガーは、ヨーロッパ哲学史と西洋理性史の主要なもろもろの観点を明確にテーマ化し、反省している。しかも、それをイノベーティブな仕方で行っている。ここで重要なのは、最初から、存在論と形而上学への再構築的な回帰(Rückbezug)が、伝承の批判的な解体(≪破壊≫)へと方向づけられている、という点である。というのも、これらのカテゴリーは、人間の生(現存在)の把握のためにはふさわしくないからである。また、ハイデッガーは、超越論的哲学を批判的に、破壊的に受け入れている。とりわけ『純粋理性批判』の形式主義の章でのカントの時間分析は、人間の生の時間性(の分析)には適していない。フッサールの現象学の受け入れは、方法的に、デ・ファクトに(事実として)、その意識哲学的な諸前提に対して向けられており、ハイデッガーに反して人間の世界-内-存在の先行的・忘我的な同一の熟考を試みた主体と客体の差異(Subjekt-Objekt-Differenz)に向いている。フッサールのデカルト主義に反して、『存在と時間』では、-現象学的方法(7節)のあらゆる明示的な評価に際して-実際に、基本的な批判と変形が加えられている。ジンメルとディルタイを経由してショーペンハウアーとニーチェへと立ち返る生の哲学と解釈学(了解の諸基盤への問い)の層は、イノベーティブに、キルケゴールの実存・弁証法の受け入れによって、また、アリストテレスの実践-分析の生産的なハイデッガーの習得によって、変形させられている。それゆえに、中心的な関心-構造(Sorge-Struktur:気遣い、)は、アリストテレスのオレキス(orexis:欲求)と関連して存立することになり、良心(Gewissen)の構造は、フロネーシスの構造と関連して存立することになる。
『存在と時間』の全般的な解釈の方向性は、生の哲学的な解釈学へと向いており、ハイデッガーの用法で言えば、「実存論的分析」へと向いている。この中で、ハイデッガーは、人間の実存の非本来的な様式と、その本来的な様式とを区別している。実存的-宗教的で神学的なもろもろの層は、本来的な実存様式へと向かっていく。すなわち、良心へ、責へ、不安と死へ、と。それらの分析が、『存在と時間』の中の大部分を占めている。ここでは、パウロ、ヨハネス、アウグスティヌス、ルター、キルケゴールが、この作品の基底を成している。
…
ハイデッガーの存在論は、かなり難しいです。
ドイツ人のわりと勉強好きな人に聴いても、「ハイデッガーは難しい💦」と言っています。
また、ドイツ人から、「ドイツ人の僕が読んでも難しいのに、日本人の君がそのハイデッガーの本を読むなんて…、信じられない」と何度か言われました(苦笑)。
「日本語の翻訳本がいくつもでているんだよ」と言っても、「彼の文章を翻訳することってできるの? ドイツ語としてもよく分からない文章なのに…」って言われるのみ…。
でも、日本人は、なぜかハイデッガーが大好きなんですよね。存在論も日本ではやっぱり人気だし、ハイデッガーの思想って、どこか日本的というかアジア的というか…。ただ、全く同じかと言われると、そこはやっぱり東西のバックグラウンドが違うわけで、、、。
先の見えない今だからこそ、「存在者の存在の意味」について考えてみるのも悪くないと思うし、ハイデッガーの思索は、ネット上で得られる知識とは全く次元の違うもので、人間(己)を深く理解する上で大きく役立つと僕は思っています。
『存在と時間』はamazonでもすぐに買えますよ~。
個人的にはこちらの中公クラシックスがオススメです。
『存在と時間』以外だと、、、
芸術や美やその真実については『芸術作品の根源』がいいですねー。
こちらもよく読まれています。
入門編としては、、、
この本が読みやすいですかね。
コロナ禍の大学時代を無駄にしないためにも、ハイデッガーに取り組むのは一つのいいアイデアだと思います!