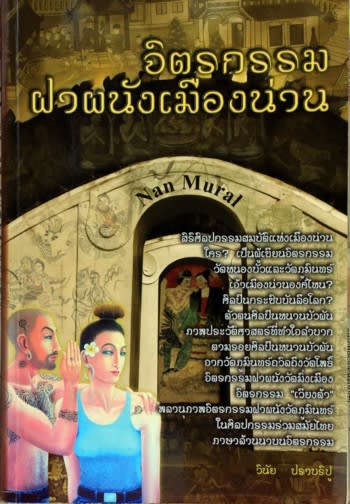ナビに導かれて、次に訪れたのは古刹「ワット・トン・レーン」です。
開基は1584年だと考えられています。
東向きの伽藍で、礼拝堂の壁は煉瓦積、寒さ除けで小さな窓になっています。屋根は急こう配の三層構造です。この建築様式は、タイ・ルーの故地シップソーン・パンナーの住宅と酷似しています。
特徴のあるナーガ屋根飾りです。
ご本尊にお参りです。
堂内にはタイ・ルーの人たちが奉納した幟が天井からたくさん下がっています。仏塔などの模様が織り込まれた幟を「トゥーン・ドック」、印刷された幟を「トゥーン・ターム」と呼びます。
トゥーンを織り、寺院へ奉納することは、輪廻を信じ、仏陀に敬意を払い、功徳を積むことだと考えられています。同様にトゥーンは、魂を天上に導き、弥勒菩薩に会見するための装置であると信じられています。
そのため、タイ・ルーの人々は生涯を通じて、寺院へトゥーンを奉納します。
この信念と信仰が、父母への感謝とトゥーンの功徳の象徴を表したタイ・ルーの神話「メー・カ・プアク」もしくは「タムナン・プラチャオ・ハー・トン」で語られます。
『5人の賢者(または、五仏)が白いカラスに五つの卵を授けます。
ある雨の日、白いカラスはエサを探しに巣を離れます。雨は激しく降り、卵は大雨で流されてしまいました。
流された卵は人間が見つけ出し、拾い上げられます。巣に戻った白いカラスは卵がないことに非常に悲しみます。嘆き悲しんだ白いカラスは、とうとう亡くなり天国へ昇ります。
五つの卵から生まれた五人は、若者に成長すると出家をし修行に励みます。
ある日、彼らは父母に功徳を捧げることを望みます。そこで、彼らの養育を助けてくれた人たちを象徴する幟を織ることにしました。
カクサンダ(拘留孫)は鶏、コーナーガマナ(倶那含牟尼)はナーガ、カッサパ(迦葉)はカメ、ゴータマ(釈迦牟尼)は雌牛の目、そしてメッテイヤ(弥勒菩薩)は服をかき混ぜるための櫂です。
彼らは織った幟を奉納するため寺院へ持っていきます。しかしながら、彼らの功徳は実の父母に届くことはできませんでした。
そこへ白いカラスが飛んできて、彼らにカラスの爪を模した芯のろうそくに火を点けるように言います。そうして彼らの功徳は達成されました。』
「メー・カ・プアック」または「五仏」は子供たちの世話をする人たちへの感謝を題材にしています。かってのタイ・ルーの習慣では、生みの親と育ての親は同じではないかも知れないようです。ワット・ノン・ブアの東側壁画でバラモンがチャンタラ・クマーラに話している運命も、生まれたての赤ん坊を母親ではない女性が世話している、タイ・ルーの特徴と習慣に関している、との解説があります。
カラスのかぎ爪の小さなろうそくカップ(パーン・プラティプ)に火を点ける習慣はイー・ペーンやローイ・クラトンを説明しています。また、トゥーンが人々と五仏が信仰で結ばれることを意味しています。
タイ・ルーの寺院には白いカラスの物語を描いた壁画もあるそうです。
■ナーン市街からプアまで67km、バンコクから累計で1023kmの走行となりました。